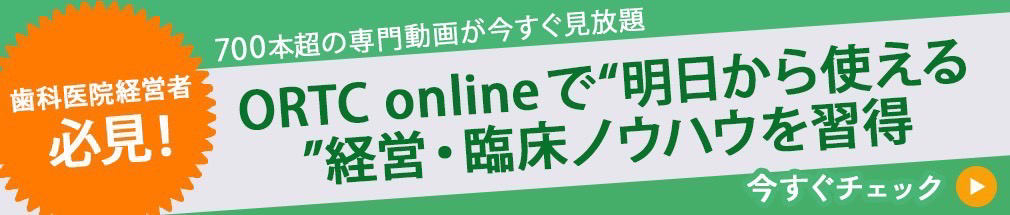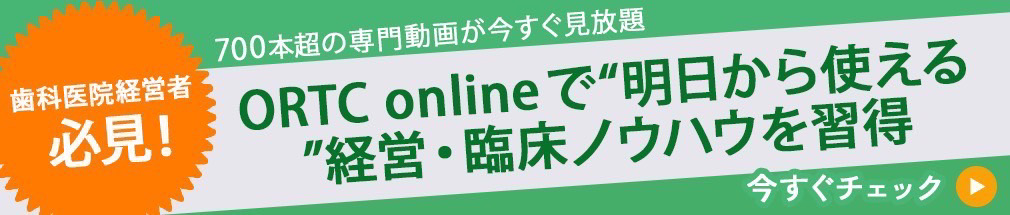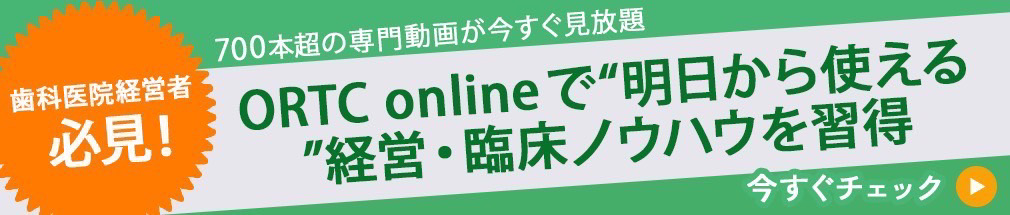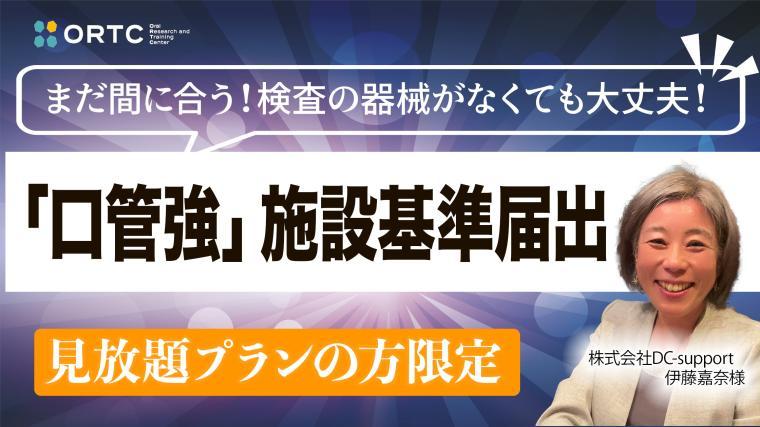歯科医院の事業承継で、こんな不安を感じていませんか?
「院長が交代するらしい…」と聞いて、新しい方針や診療スタイルに不安を感じ、スタッフの入れ替わりや、患者様からの信頼が揺らぐことに対する現場の戸惑いといったことなどです。
実はこれらの悩みは、「承継=経営者同士の交代」ではなく、スタッフ・患者様・地域にとっても大きな“転機”になるからこそ起きるものです。
本記事では、歯科医院の事業承継における現場の対応・患者様への配慮・よくあるトラブルの対処法について、現役歯科衛生士の視点からお伝えします。
承継は混乱ではなく、チームの結束と医院の進化のチャンスです。
現場で“今すぐできる”具体的な工夫を知ることで、あなたの医院をより良い方向へ導くヒントが見つかります。
歯科医院の事業承継とは?基本的な流れと手続き
歯科医院の事業承継とは、医院の運営や資産、スタッフ体制などを、新しい経営者に引き継ぐプロセスを指します。
単なる“引き継ぎ”ではなく、経営・財務・法的な手続きを含む複雑な移行であり、関係者全員にとっての転機です。
近年では、後継者不在や高齢化によって、医院を他者に譲渡する「第三者承継」や「M&A」も増加傾向にあります。
ここではまず、歯科医院の事業承継における「パターン」と「手続き・費用」の基本を押さえ、全体像を把握していきましょう。
歯科医院継承のパターンと流れ 歯科医院の承継には大きく分けて、以下の3つのパターンがあります。
親族内承継 院長の子や親族が引き継ぐケース。患者やスタッフの信頼が維持されやすい一方、世代交代の準備不足が問題になることも。 親族外承継 長年勤務した勤務医など、院長以外の内部スタッフへの承継。医院文化が継続されやすいメリットがあります。 第三者承継(M&A含む) 外部の歯科医師や法人へ譲渡するケース。医院の売却益が得られる一方、文化や方針の違いから現場で混乱が生じるリスクもあります。
継承方法としては「居抜き物件(設備・スタッフ込み)」としての譲渡も多く、M&A専門業者の介在によってマッチングが行われる例も増えています。
それぞれにメリット・デメリットがあるため、経営的視点だけでなく、 現場への影響や引き継ぎのしやすさ も考慮して検討する必要があるのです。
歯科医院継承の相場や手続きのリアル 事業承継にかかる金額はケースによって異なりますが、平均的な譲渡価格は2000万〜4000万円が相場と言われています。
この金額には、設備、内装、スタッフ、地域の患者様の基盤など、医院の“価値”全体が含まれています。
手続き面では、以下のような流れが一般的です。 1.承継計画の立案(現院長・後継者間の意向共有) 譲渡契約の締結(資産・負債の整理含む) 行政手続き(診療所開設届、保健医療機関指定届、新規指導など) スタッフ・患者への周知と体制づくり 新規指導は、後継者が保険医療機関として再申請を求められる場合があるため、制度理解とタイミング調整が非常に重要です。
福祉保健局や厚労省、業界ポータルサイトなどで最新の制度や注意点を事前に確認しておくと、スムーズな承継に繋がります。
歯科医院の継承でよくある失敗とその回避法
歯科医院の事業承継において、「手続きは完了したのに現場が回らない」「患者様が離れた」「スタッフが一斉に辞めた」そんな事例は決して珍しくありません。
その多くが、「現場への情報共有の不足」や「変化への説明不足」など、“伝えるべきことが伝わっていない”ことに起因します 。
ここでは、実際に現場で起こりやすいトラブルと、それを未然に防ぐための実践的な対策を紹介します。
スタッフへの情報共有と対応 事業承継が決まったとき、最初に影響を受けるのは現場のスタッフです。
「ある日突然の事業継承の発表」でスタッフの空気が一変し、 “聞かされていなかった”という事実だけで、不信感は一気に膨らみます。
情報は、「内容」以上に「伝えるタイミング」と「伝え方」が重要です。
理想は、承継が確定した時点で速やかに共有し、「新院長のプロフィール」「承継の理由」「今後の方針」を丁寧に説明することです。
また、説明会の場では質問の時間を確保し、「言いづらい不安」にも耳を傾ける姿勢が大切になります。
何も言わないことが一番のストレスです。
情報を出し惜しみをせず、オープンな対話の場を設けることで、“一緒に進む仲間”としての関係性を保ちましょう。
患者様への告知と不安対応 長年通院している患者様にとって、院長の交代は信頼のリセットに近い大きな出来事です。「大丈夫かな?」「今まで通り診てもらえる?」といった不安を抱くのは当然の反応です。
患者様対応では、「何が変わるのか」よりも「何が変わらないのか」を伝えることが重要です。
たとえば、「スタッフは変わらず対応します」「診療時間や治療方針は継続します」といった“安心材料”を明示することで、不安を和らげられます。
告知の方法は、受付での口頭説明、診療中の院長からの一言、院内掲示やお手紙など、複数のチャネルを使うと効果的です。
また、新院長が積極的にあいさつや会話を行うことで、「人として信頼できるか」の第一印象が良くなり、早期の関係構築に繋がります。
継承後のトラブルを回避する実践策 現場の混乱を防ぐには、「継承=一気に変える」ではなく「段階的に慣れていく」仕組みづくりがカギです。
そのために効果的なのが、事前の共有ミーティングやロールプレイングです。
たとえば、「診療の流れが変わる」「機器の使い方が変わる」といった場面では、事前に説明会を開き、スタッフからの意見や不安を吸い上げましょう。
また、「どの業務をいつから変更するのか」を明文化し、無理のない移行スケジュールを組むことがポイントです。
最も重要なのは、現場を巻き込むことです。
“知らない間に方針が変わっていた”という状況は、スタッフの離職や士気低下を招きます。
あくまで「急な変化」ではなく、「合意ある変化」であることが、継承後の安定した運営に直結します。
\詳しく学びたいなら/
歯科医院の事業承継で起こるスタッフ入れ替えと人材確保のポイント
事業承継において、 スタッフの入れ替わりは避けられない可能性がある現実 です。
新院長の方針や医院の雰囲気が変わることで、「今まで通り働けるか不安」と感じたスタッフが退職を選ぶケースは少なくありません。
一方で、承継後も医院の安定運営を継続するためには、人材の早期確保が必須です。
ここでは、スタッフの入れ替わりがもたらす影響と、新たな人材確保に向けた具体策を解説します。
スタッフの入れ替わりが起こりうる現実 実際の現場では、事業承継を機に長年勤めていたスタッフが退職することは珍しくありません。 信頼関係が深かった前院長が退くことで、“ついていく相手がいなくなった”と感じ、退職を決意するケースが多いです。
このような状況下で、退職するスタッフによる丁寧な引き継ぎがあるかないかで、医院の混乱度合いが大きく変わるでしょう。
業務マニュアルの整備や、口頭だけでなく文書による申し送りを行うことで、新体制へのスムーズな移行が可能になります。
また、 退職の意向が出た段階で、「引き止める」か「引き継ぎを前提に退職を見守る」か、院長と現場での判断軸を明確にしておくことも、チーム運営の混乱を防ぐ重要なポイントです。
新たな人材の早期確保と採用活動 スタッフが抜けることを前提に、あらかじめ採用活動をスタートさせることは、承継準備の中でも優先度が高い対応です。
採用活動の具体例としては、以下のとおりです。
・求人媒体や紹介会社への早期掲載 ・面接時に「医院のビジョン」や「承継に伴う変化点」を明示する説明 ・OJT(現場指導)を見越した教育担当の配置
このとき重要なのは、スキル重視だけではなく、「チームに馴染めるか」を基準に含めることです。
いくら経験豊富でも、既存のスタッフや歯科医院の文化に合わないと、早期退職のリスクが高まります。
「気配りのできる人柄」の新人がチームの雰囲気を柔らかく変え、結果として患者様の満足度向上にもつながります。
新体制の中で機能する“人”を選ぶためには、履歴書のスペックだけでなく、現場での“空気を読む力”や協調性にも注目した採用戦略が欠かせません。
歯科医院の事業承継後に求められるコミュニケーションと現場調整
事業承継は、歯科医院の「体制が変わる」だけで終わりではありません。
むしろ、承継後こそが“本当のスタート”になります。
院長が交代した直後の歯科医院では、診療方針のすり合わせや、スタッフ間の役割分担の再調整など、「目に見えない戸惑い」が現場に広がりやすい状態です。
だからこそ、 スタッフと院長との密なコミュニケーションと、日々の業務レベルでの情報の共有・調整が不可欠になります 。
承継後の混乱を最小限に抑え、スムーズな医院運営につなげるための実践ポイントを見ていきましょう。
新しい院長との連携とコミュニケーションの重要性 新体制の立ち上げ後、しばらくは“これまでのやり方”と“新しい方針”のギャップが生じることが多く、スタッフが現場での判断に迷う場面が増えがちです。
この時期に必要なのは、「分からないまま働く」のではなく、新しい院長としっかり連携しながら現場を整えていく姿勢になります。
大事なのは、以下のような情報を“スタッフ側から積極的に”伝えることです。
・その医院ならではの患者様の傾向や特徴 ・スタッフ一人ひとりの得意分野や強み ・導入済みの設備やツールの運用方法、現場の工夫
これらを共有することで、院長は医院の“地盤”を正しく理解しやすくなり、結果として無理のない改善や方針づくりが可能になります。
日々の会話や定例ミーティングはもちろん、「ちょっとした相談」や「雑談レベルの情報交換」こそが、現場の信頼関係を築く土台となります。
診療方針やルールの変更と現場への浸透 院長が変われば、診療方針やルールの見直しが行われることは自然な流れです。
例えば「保険診療の進め方」「自由診療の比率」「患者対応のトーン」などが変わると、スタッフがこれまでのやり方に迷いを感じることもあります。
ここで重要なのは、「変えること」自体が問題なのではなく、“なぜ変えるのか”を伝えるかどうかです。
現場が納得できないまま進められると、不信感や無言の反発が生まれ、連携ミスや雰囲気の悪化にもつながります。
方針変更の意図を明確に共有し、「患者さんにとってどう良くなるのか?」という視点で伝えることが、現場の理解と協力を得る鍵になります。
また、変更内容は口頭だけでなく文書や資料にまとめ、ミーティングや朝礼などで繰り返し共有することが大切です。
必要であれば、ロールプレイやシミュレーションを通じて、スタッフが新ルールを“体感”できるようにする工夫も効果的です。
\詳しく学びたいなら/
機器やシステムの導入・変更への対応 歯科医院の事業承継では、「新院長が自分のやり方を取り入れる」という形で、機器やシステムの導入・変更が行われることがよくあります。
予約システムや電子カルテの刷新、新しい滅菌器や診療ユニットの導入など、ハード・ソフト両面での変化が現場に影響を与えます。
こうした変化は、医院全体の効率化やサービス向上に繋がる一方で、スタッフにとっては“慣れたやり方が通じなくなる”という不安の種にもなり得ます。
この章では、スタッフの不安を軽減し、患者様にも安心して通っていただくための対応策を解説します。
新しい機器導入やシステム変更の可能性 新体制になった歯科医院では、「現場の見直し」の一環として、新たな機器やシステムが導入されることがあります。
これにより、 現場スタッフには新たな学びと適応が求められます。
導入された当初は「前の機械の方が楽だった」「新しい操作がわかりづらい」と感じるスタッフも少なくありません。
しかし、そのまま使い方を“自己流”で覚えてしまうと、効率が下がるだけでなく、診療や患者対応に支障が出ることもあります。
そのため、機器やシステムの導入時には、以下の準備と学びの時間が必要です。
・事前の研修会の実施 ・マニュアルや操作動画の配布 ・スタッフ全員が同じ理解レベルになるまでのフォロー体制の確保
また、実際に運用が始まった後には、「トラブルが起きたときにすぐ報告・共有できる仕組み」をつくることもポイントです。
LINEグループや共有ノート、チャットツールなどを活用し、小さな疑問も放置しないようにしましょう。
患者様への影響を考慮した事前テストと、導入後の迅速な患者様対応 機器やシステムの変更は、現場だけでなく患者様の体験にも直結します。
小さな違和感が、「歯科医院が変わってしまった」という印象につながることもあります。
そのため、患者様への影響を最小限に抑えるためには、以下の対応が有効だと考えられます。
・運用前の“事前テスト”やシミュレーションを行い、使い勝手や問題点を洗い出す ・スタッフ間でのロールプレイにより、患者様対応のトーンや流れを確認しておく ・導入初期は必ず補助者を配置し、不安があればすぐ対応できる体制を整える
さらに、変更点を伝える際には、「こう変わります」「ここが改善されました」といった前向きな説明を患者様に行うことで、納得感を持ってもらいやすくなります。
患者様の不安や混乱を最小限に抑えるためにも、“機器を使う私たちの準備”と“患者様への伝え方”はセットで考えることが大切です。
承継後の安定期とさらなる発展:チームワークと患者様満足度の向上
事業承継の初動を乗り越えると、歯科医院には徐々に「安定期」が訪れます。スタッフも新体制に慣れ、患者様からの信頼も少しずつ戻ってくる時期です。
しかし、この段階で気を緩めてしまうと、組織は停滞し、せっかくの変化が「現状維持」で終わってしまいます。
安定した今こそ、「さらに良い医院をつくるための土台づくり」が重要です。
この章では、チームワークの再構築と患者様満足度の向上に向けた実践ポイントをお伝えします。
チームワークの再構築とスタッフ間の協力体制 承継直後はどうしても「自分のことで精一杯」になりがちですが、安定期に入ったらこそ、チームとしての意識を高め直す時期です。
ここで効果的なのは、全スタッフで“共通の目標”を持つようにするなどの工夫が必要となってきます。小さな目標でも、医院全体の一体感は確実に変わります。
さらに、以下のような仕組みで協力し合える環境を育てることが大切です。
・月1回の定期ミーティングでの情報共有と意見交換 ・日常的なコミュニケーションを促す雑談タイムや昼休みの雰囲気作り ・「ありがとうカード」や「感謝を伝えるメモ」など、お互いを認め合う風土の醸成
組織として機能するためには、「忙しいから話せない」ではなく、忙しいときほど“話せる空気”をつくることが大切です。
患者様満足度の維持・向上への取り組み 歯科医院のさらなる発展に欠かせないのが、患者様からの“継続的な支持”を得ること=満足度の維持と向上です。
承継後しばらくは、「新しい院長、大丈夫かな?」「治療の方針は変わるのかな?」と不安に思っている患者様も少なくありません。
そこで重要になるのが、変化を感じさせない“安心感の提供”と、変化があるなら“理由の明示”です。
たとえば、次の事柄が挙げられます。
・既存患者様に対しては、これまでの診療内容や担当者をできる限り継続 ・少しの変化も、「より良くするための取り組み」として丁寧に説明 ・院内掲示やWebサイトで新しい院長の想い・診療スタイルを紹介 ・新患対応では、丁寧な初診カウンセリングや、安心感を与える接遇を重視
患者様は「治療がうまい」だけでなく、「ここなら通い続けたい」と思える理由を大切にしています。 スタッフ全員で、「治療+人間関係」で信頼される医院づくりを目指しましょう。
歯科医院承継後のブランディングと地域社会との連携
事業承継を経た歯科医院は、「院長が変わったから」ではなく、「この医院は、もっと信頼できる場所になった」と思ってもらうことが鍵です。
そのために重要なのが、“医院の顔”としてのブランディングと、地域とのつながりの再構築することにあります
「ただ引き継ぐ」だけではなく、“より地域に愛される医院へ進化する”という視点が求められます。
院長が変わるということは、医院の雰囲気や理念に“変化のきっかけ”が生まれるタイミングです。
これをチャンスと捉え、地域との関係性を再構築しながら、医院の魅力を改めて伝えることが、今後の成長につながります。
特に近年は、患者様がWebで医院を選ぶ時代です。
「新しい先生、どんな人?」「治療方針は変わった?」といった不安や関心に対し、積極的な情報発信と“想いの見える化”が必要になってきます。
承継が地域社会との関係性を再構築する機会であること 新しい院長にとって、地域との関係はゼロからのスタートに近いかもしれません。
だからこそ、地域活動への参加や対話の機会づくりが、信頼の第一歩となります。
たとえば、次の事柄が挙げられるでしょう。
・保育園や学校での歯みがき指導 ・地域の健康イベントへの協賛やブース出展 ・院内での無料相談会や見学会の開催 など
“医院の存在を知ってもらう場”を増やすことで、地域との接点が生まれ、自然と信頼が築かれていきます。
こうした活動と並行して、WebサイトやSNSでの情報発信も重要です。
院長の経歴や人柄、医院の雰囲気、診療へのこだわりなどを、写真や言葉で丁寧に伝えることで、患者様が安心して来院しやすくなります。
「何をしているか」ではなく「どんな想いでそれをやっているか」が伝わる発信こそが、“選ばれる医院”のブランディングの本質です。
まとめ 歯科医院の事業承継は、経営者同士の引き継ぎだけではなく、 現場で働く私たちにとっても、大きな転機 です。
新しい院長、新しいやり方、そして新しい空気、どんなに準備が整っていたとしても、不安や戸惑いをゼロにすることはできません。
スタッフ一人ひとりの力が集まれば、チームは強くなります。
そしてそのチーム力は、患者様の信頼や安心につながっていきます。
この記事では、承継時に現場で起きやすい問題や、それにどう向き合えばいいのかを、お伝えしました。
すぐにできること、ちょっと工夫すれば変わることが、きっとあったと思います。
「変わること」に不安もあると思います。
ですが、「変われる自分たちがいる」と信じられたら、その医院はもっと前に進めると思います。
この記事で、承継を“ただの変化”ではなく、“成長のチャンス”に変えるきっかけになれば嬉しいです。
\詳しく学びたいなら/
よくある質問 Q1. 歯科医院の事業承継は、スタッフにいつ伝えるのが適切ですか? A. 原則として、承継が確定したタイミングで速やかに伝えるのが理想です。遅れると不信感につながりやすく、離職やチーム崩壊のリスクもあります。具体的な移行スケジュールが定まっていなくても、現時点の状況と今後の見通しを共有する姿勢が大切です。
Q2. 院長が交代する際、患者さんにはどう伝えればよいですか?
A. 長年の患者様にとって、院長交代は不安材料になります。「何が変わるか」よりも、「何が変わらないか」を丁寧に伝えましょう。受付や診療室での口頭説明に加えて、院内掲示やリーフレットなどのツールも有効です。
Q3. 承継後にスタッフが大量に辞めることはありますか? A. 残念ながらあります。特に、情報共有やコミュニケーションが不足していると、現場の不安が膨らみ、連鎖的に退職者が出ることもあります。対策として、継承前後にミーティングや1on1面談を実施し、感情の整理と信頼構築を進めましょう。
Q4. 新しい機器やシステムを導入する際に現場が混乱しないか心配です。 A. 混乱を防ぐためには、導入前の研修と事前テストが不可欠です。特に、患者様対応に直結する機器は、実際の診療に入る前にスタッフが十分に操作に慣れておくことが大切です。
Q5. 新しい院長と現場スタッフの関係性がうまく築けるか不安です。 A. 最初はお互いに遠慮や違和感があるものです。日々の小さな会話や、定期的なミーティングでの対話を積み重ねることで、関係性は自然と深まっていきます。スタッフ側も受け身ではなく、「伝える・聞く」姿勢を大切にしましょう。
Q6. ブランディングやSNSは承継後すぐに始めても大丈夫ですか? A. はい、むしろ承継直後は医院の方針や雰囲気を地域に再認識してもらう好機です。ただし、いきなりすべてを変えるのではなく、これまでのイメージを尊重しつつ、新しい魅力を少しずつ伝えていくスタンスが安心感を与えます。
歯科衛生士ライター:原田
歯科医療の現場で役立つ実践的な知識を届けるORTC
ORTCは「笑顔の役に立つ」を理念に、歯科界の知識を共有する場を目指しています。歯科医療の現場で役立つ最新の知識と技術を提供することで、臨床と経営の両面からクリニックの成長を支援します。最先端の技術解説や経営戦略に特化した情報を集約し、歯科医療の現場での成果を最大化。自己成長を追求するためのコンテンツをぜひご活用ください。
無料会員登録 無料動画の視聴、有料動画のレンタルが可能です。歯科業界についてのオンライン・オフラインセミナーへの参加が可能となります。
ORTCPRIME 月額5500円 で、 ORTC内のすべての動画を見放題に。臨床の現場に役立つ最新の技術解説や、歯科医院経営の成功戦略を網羅した特別コンテンツをご利用いただけます。 歯科業界の方へ効率的に知識を深めていただける内容です。
ORTC動画一覧
ORTCセミナー一覧
まずは無料会員登録 こちらのリンクより会員登録ページへお進みください。
会員登録はこちら
ORTCPRIMEへのアップグレードも簡単! 登録後は「マイページ」から、ORTCPRIMEにいつでもアップグレード可能です。
 こちらの動画もおすすめです
こちらの動画もおすすめです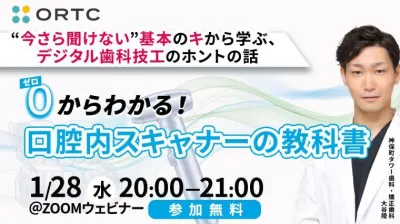 “今さら聞けない”基本のキから学ぶ、デジタル歯科技工のホントの話『ゼロからわかる、口腔内スキャナーの教科書』
“今さら聞けない”基本のキから学ぶ、デジタル歯科技工のホントの話『ゼロからわかる、口腔内スキャナーの教科書』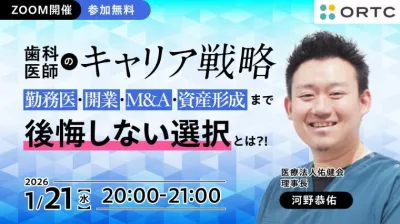 歯科医師のキャリア戦略 ― 勤務医・開業・M&A・資産形成まで、後悔しない選択とは ―
歯科医師のキャリア戦略 ― 勤務医・開業・M&A・資産形成まで、後悔しない選択とは ―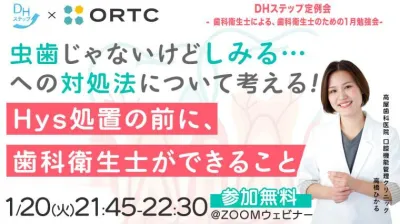 虫歯じゃないけどしみる…への対処法について考える Hys処置の前に、歯科衛生士ができること
虫歯じゃないけどしみる…への対処法について考える Hys処置の前に、歯科衛生士ができること 「TBIが変われば患者が変わる」 自費TBI成功マインド
「TBIが変われば患者が変わる」 自費TBI成功マインド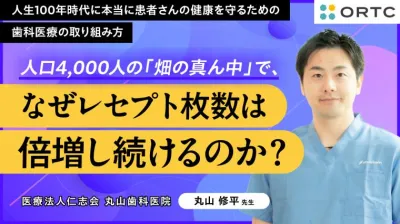 人口4,000人の「畑の真ん中」で、なぜレセプト枚数は倍増し続けるのか?
人口4,000人の「畑の真ん中」で、なぜレセプト枚数は倍増し続けるのか?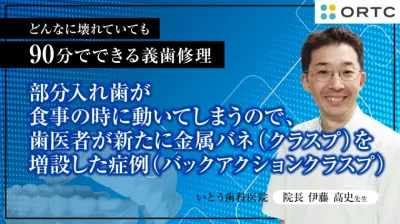 部分入れ歯が食事の時に動いてしまうので、歯医者が新たに金属バネ(クラスプ)を増設した症例(バックアクションクラスプ)
部分入れ歯が食事の時に動いてしまうので、歯医者が新たに金属バネ(クラスプ)を増設した症例(バックアクションクラスプ)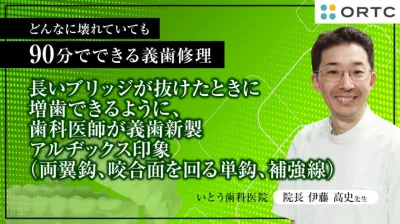 長いブリッジが抜けたときに増歯できるように、歯科医師が義歯新製 アルヂックス印象(両翼鈎、咬合面を回る単鈎、補強線)
長いブリッジが抜けたときに増歯できるように、歯科医師が義歯新製 アルヂックス印象(両翼鈎、咬合面を回る単鈎、補強線)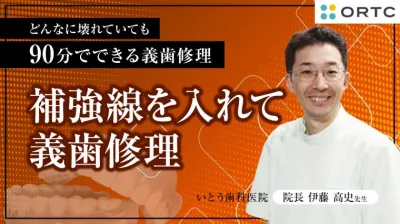 補強線を入れて義歯修理
補強線を入れて義歯修理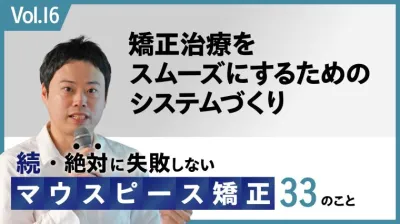 続・ 絶対に失敗しないMP矯正33の事 システムづくり
続・ 絶対に失敗しないMP矯正33の事 システムづくり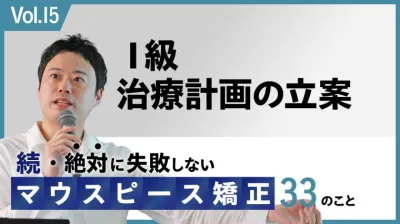 続・ 絶対に失敗しないMP矯正33の事 Ⅰ級 治療計画の立案
続・ 絶対に失敗しないMP矯正33の事 Ⅰ級 治療計画の立案