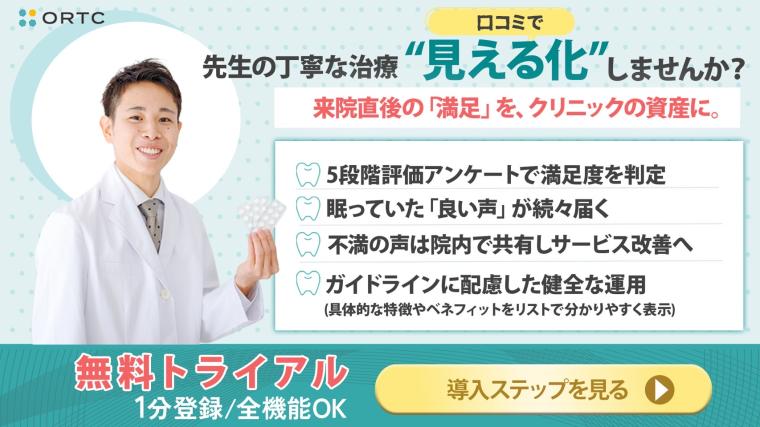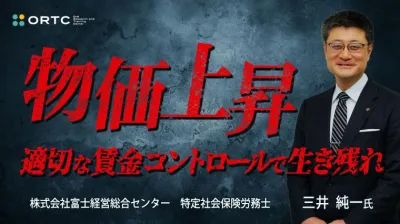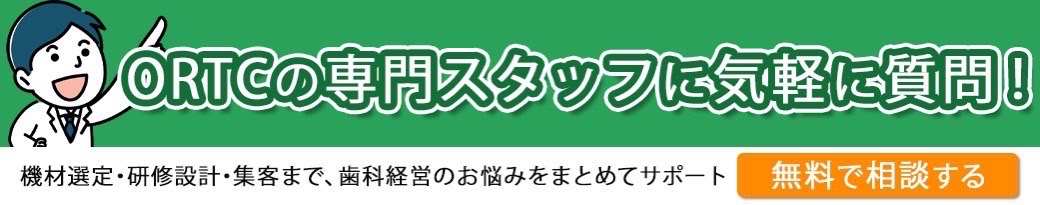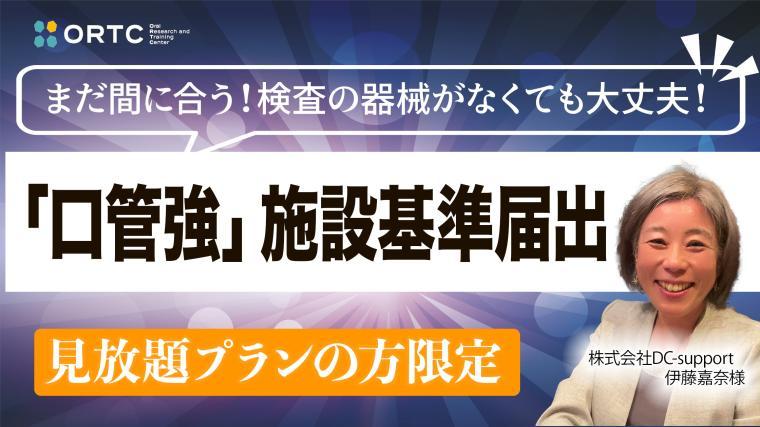歯科医院の賃上げ戦略 人材不足時代を生き抜くための経営の新常識
歯科経営
近年、歯科医院を取り巻く環境は大きく変化しています。
とくに深刻なのが歯科衛生士や歯科助手の人材不足です。日本歯科衛生士会の調査によると、歯科衛生士の有効求人倍率は全国平均で約2倍前後と、他業種に比べても高水準が続いています。こうした状況下で、経営者が最も頭を悩ませるのが「人材の採用と定着」。その中核にあるのが賃上げです。給与水準は、スタッフが医院を選ぶ際の第一条件であり、また長期的に働き続けてもらうための重要な要素となります。この記事では、歯科医院経営における賃上げを「コスト」ではなく「投資」と捉え、どのように取り組むべきかを具体的に解説します。
全国的な人材不足と賃上げ圧力の背景とは?

歯科業界における人材不足の背景には、以下の要因が考えられます。
- 歯科衛生士養成校の卒業生数の頭打ちと雇用のミスマッチ
年間の新規卒業生数は、ほぼ横ばいで推移しており、供給が増えていません。加えて、入学者数も減少傾向にあり、定員割れを起こしている養成校は増加傾向にあります。需要増に供給が追いついていない状況です。
(出典:一般財団口腔保険協会 歯科衛生士教育に関する現状調査の結果報告)
- 他業界との待遇格差
医療、介護業界全体で人材確保が課題となり、賃金引き上げや待遇改善が進む中、歯科は待遇で劣るケースが増加しています。求職者はより条件の良い職場を選ぶ傾向にあります。
- 働き方改革の影響
週休3日制やリモートワークが広がる中、従来型の勤務形態では歯科の魅力を打ち出しにくくなっています。また長時間労働や労働環境への厳しい視線が強まり、給与と労働条件の両立が求められています。
厚生労働省の賃金構造基本統計調査(2024年)によれば、歯科衛生士の平均給与は月額約27万円と上昇傾向にあります。しかし、都市部での初任給が30万円を提示している医院が多いのに対し、地方では10万円以上下回る医院もあり、地域格差があるのが現状です。その結果、資格を持っていても違う職種を選択するケースが増えています。賃上げを後回しにする医院は採用競争から取り残される危険性が高まっているのです。
(出典:賃金構造基本統計調査|厚生労働省)
賃上げがスタッフ定着やモチベーションに与える効果

賃上げは単なる「採用の武器」にとどまらず、定着率や職場全体の活性化にも直接作用します。
- 離職防止効果
同業他院との給与差は退職理由の上位に挙げられます。定期的な昇給は「長く働ける医院」という安心感を提供します。 - 自己評価とやりがい
賃金アップは「自分の努力が正しく評価されている」というシグナルとなり、業務へのモチベーションを高めます。 - チーム力の向上
適切な賃上げは院内の公平感を生み、スタッフ同士が協力し合う風土を醸成します。
実際、賃金テーブルを見直した医院では患者対応の質が向上し、リコール率が約15%改善したという報告もあります。
賃上げはスタッフの心理に直接働きかけ、経営成果にまで波及するのです。
株式会社富士経営総合センター 特定社会保険労務士
三井 純一
「物価上昇 適切な賃金コントロールで生き残れ」
「【今すぐ使える】人財管理における3つのポイントご紹介」
「昇給=コスト増」ではなく「投資」という発想が必要

賃上げを検討する際、多くの経営者が抱くのは「経営を圧迫するのでは」という不安です。しかし、賃上げを投資と位置付けることで長期的なリターンを得ることが可能です。
生産性向上との連動
- 診療効率化:アポイント管理や自動精算システムを導入し、スタッフの事務負担を軽減。
- 自費率アップ:ホワイトニングやインプラント説明を衛生士が担うことで、院長の診療時間を確保。
- リコール率改善:LINE連携による自動リマインドで来院率を強化。
例えば、スタッフ1人あたりの売上が月10万円向上すれば、年額で120万円の増収。賃上げ分を上回る成果を実現できるのです。
他院との差別化は「給与+福利厚生+教育制度」で決まる!
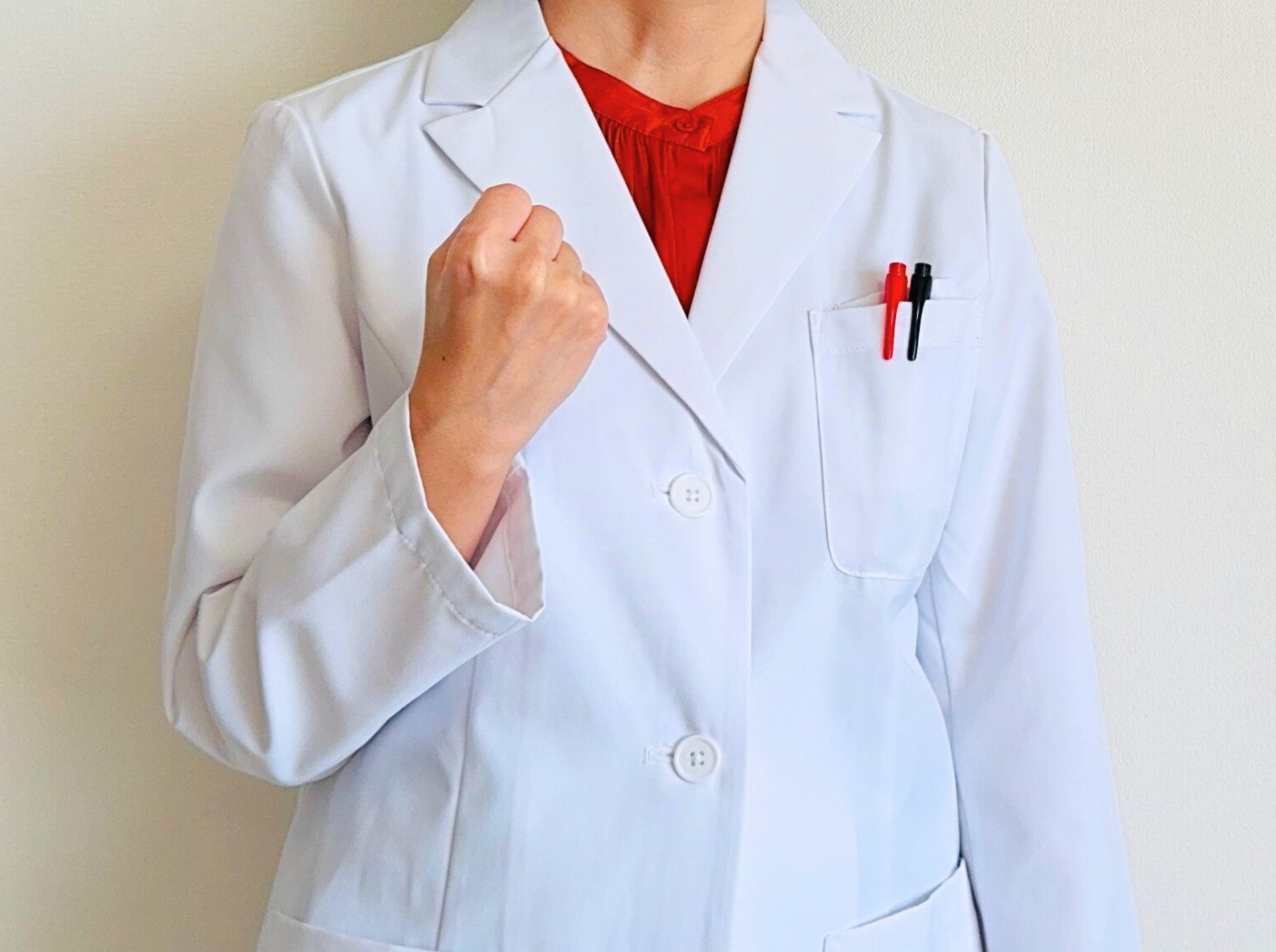
給与だけを上げても、同業他院が同水準に追随すれば差別化は難しくなります。重要なのは福利厚生や教育制度を組み合わせた総合的な魅力づくりです。
福利厚生の工夫
- 週休2.5日制、年間休日120日以上
- 週休3日制など時短勤務の選択制度の導入
- 産休・育休後の働き方の選択制
- 健康診断やワクチン接種の全額補助
教育・キャリア支援
- 外部セミナー参加費補助と代休取得
- 認定歯科衛生士取得支援と取得後の給与アップ
- キャリアランクに応じた給与テーブルの透明化
とくに、20〜40代の衛生士は「スキルアップできる職場」を重視する傾向があります。給与だけでなく成長実感とそれに見合った報酬を得られる環境を示すことが、長期定着につながります。また人生100年時代において、この先、50代以降の歯科衛生士の働き方も重要になってくるでしょう。豊富な臨床経験やコミュニケーション能力を生かすことで、医院経営の大きな戦力になり得るでしょう。
戦略的な賃上げを実現するためのステップ

賃上げを単なる給与の引き上げに終わらせず、医院経営を強化する施策として機能させるためには、計画的なステップが欠かせません。以下の流れを参考に、自院に最適な仕組みを整えましょう。
①現状分析
まずは現在の収支構造を正確に把握することから始めます。売上の推移、固定費、材料費、人件費率などを分析し、賃上げ余力を数値化します。地域の平均給与や他院の募集条件を調査し、自院の給与水準を客観的に比較することも重要です。特に歯科衛生士は地域差が大きいため、「競合医院よりどの程度上げる必要があるか」を定量的に把握することで、無理のない賃上げ幅を設定できます。
②賃上げの目的を明確化
単に「スタッフ確保のため」という理由だけではなく、離職率の改善・モチベーション向上・生産性アップなど、賃上げによって達成したい具体的なゴールを決めます。目的を明確にすることで、スタッフにも納得感を持ってもらいやすくなります。たとえば「年間リコール率を80%に引き上げる」「ホワイトニングの自費率を前年比20%増」など、医院の成長指標と連動させると効果的です。
③段階的な賃上げ計画
いきなり大幅な昇給を実施すると、経営リスクが高まります。複数年にわたる段階的な賃上げを設定し、売上目標の達成や生産性改善と連動させる方法が現実的です。例えば「1年目は基本給+5,000円、2年目は自費診療比率が目標値に達した場合にさらに+5,000円」というように、条件付きのステップアップを取り入れることで、スタッフのモチベーション維持にもつながります。
④評価制度とセットで運用
賃上げを公平に実施するためには、評価基準の明確化が不可欠です。勤続年数だけでなく、患者満足度、カウンセリング実績、研修参加などを評価項目に加えることで、成果に応じた昇給が可能になります。評価制度が曖昧なままだと、賃上げが不満の原因となり、逆に離職リスクを高めかねません。スタッフ面談を定期的に行い、評価の透明性を確保することも忘れないようにしましょう。
⑤収益改善策との連動
賃上げ分の原資を確保するためには、売上拡大や診療効率化を同時に進めることが重要です。具体的には、自費メニューの提案強化、予防プログラムの定期化、予約管理システムによる稼働率向上などが挙げられます。スタッフが新たな施策に積極的に関わることで、賃上げが医院の成長を後押しする好循環が生まれます。
⑥スタッフへの情報共有
賃上げの背景や計画をスタッフに共有することで、医院とスタッフが同じ目標に向かって動ける環境を整えます。経営者だけが数字を握るのではなく、「この施策が達成されれば来年度の昇給幅が広がる」と具体的に示すことで、経営改善がチーム全体の課題として意識されるようになります。
このように、現状分析から評価制度、収益改善策までを一貫したステップとして設計することで、賃上げは単なるコストではなく、医院の成長を促進する投資へと変わります。
賃上げを支える「収益モデル転換」とは?

持続的な賃上げを実現するには、従来型の保険診療依存から脱却し、収益モデルを根本から見直す発想が求められます。
自費診療の拡大
インプラント、ホワイトニング、マウスピース矯正など、自費率を高める治療はスタッフの専門性を活かす絶好の分野です。衛生士がカウンセリングを主導すれば、院長の診療効率も向上し、1人あたり売上の最大化につながります。
デジタル技術の導入
口腔内スキャナーやクラウド予約システム、AI自動診断補助などを取り入れることで診療効率を改善。同じ人員でより多くの患者を診る体制を整えることで、賃上げ原資を確保できます。
地域密着型サービス
訪問歯科や小児予防プログラムなど、地域ニーズに特化したサービス展開は競合との差別化を生み、安定的な患者層と収益を確保できます。
収益基盤を多角化することで、賃上げを「経費」ではなく成長戦略の一環として実施できるようになります。
まとめ
歯科医院における賃上げは、もはや選択肢ではなく必須の経営課題です。
- 全国的な人材不足により、給与水準は採用競争の分かれ目となる。
- 賃上げはスタッフ定着やモチベーション向上に直結し、医院全体のパフォーマンスを押し上げる。
- 「コスト増」ではなく投資と捉え、生産性向上や自費率アップと連動させることで利益拡大が可能。
- 福利厚生・教育制度との組み合わせが、他院との差別化を強化する。
- 収益モデル転換により、持続可能な賃上げが現実的になる。
経営者は「どのように賃上げを実現するか」を戦略的に設計することが、医院の未来を左右します。
最新の経営事例や具体的な実践方法は、歯科医療メディアORTCが開催するセミナーや特集記事でも紹介されています。自院に最適な賃上げ戦略を見つけ、採用力と経営の持続性を両立させましょう。
Q&A
Q1.診療報酬改定2025年の賃上げは?
A.2024年度の診療報酬改定で「医療従事者の給与改善」が重要論点の1つとなり、ベースアップ評価の創
歯科医療の現場で役立つ実践的な知識を届けるORTC

ORTCは「笑顔の役に立つ」を理念に、歯科界の知識を共有する場を目指しています。歯科医療の現場で役立つ最新の知識と技術を提供することで、臨床と経営の両面からクリニックの成長を支援します。最先端の技術解説や経営戦略に特化した情報を集約し、歯科医療の現場での成果を最大化。自己成長を追求するためのコンテンツをぜひご活用ください。
無料会員登録
無料動画の視聴、有料動画のレンタルが可能です。歯科業界についてのオンライン・オフラインセミナーへの参加が可能となります。
ORTCPRIME
月額5500円で、 ORTC内のすべての動画を見放題に。臨床の現場に役立つ最新の技術解説や、歯科医院経営の成功戦略を網羅した特別コンテンツをご利用いただけます。 歯科業界の方へ効率的に知識を深めていただける内容です。
まずは無料会員登録
こちらのリンクより会員登録ページへお進みください。
ORTCPRIMEへのアップグレードも簡単!
登録後は「マイページ」から、ORTCPRIMEにいつでもアップグレード可能です。