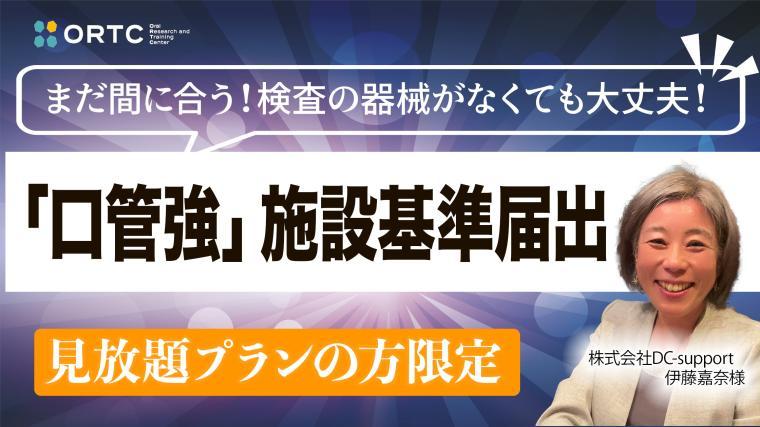歯科医院の診療においてレントゲン機器は欠かせない重要な設備です。しかし、高額な導入費用や維持費を考えると、投資判断は慎重に行う必要があります。
本記事では開業を目指す歯科医師や、すでに開業されている先生方に向けて、レントゲン機器の種類ごとの特徴、導入コストやランニングコスト、保険診療での算定方法、さらに患者説明のポイントまで詳しく解説していきます。
レントゲンの種類と特徴
歯科用レントゲンは「パノラマレントゲン」「デンタルレントゲン」「歯科用CT」の3種類に分けられ、それぞれに用途が異なります。
パノラマレントゲン
パノラマレントゲンは、歯科診療で広く使用されるレントゲン装置で、口腔内全体の状態を一枚の画像で確認できます。歯列、顎骨、顎関節、副鼻腔まで撮影できるため、虫歯や歯周病の診断、親知らずの埋伏状況、顎骨の異常や嚢胞、腫瘍の検査に役立ちます。一度の撮影で広範囲を確認できるので、患者の負担が少なく、治療計画を立てる際の基本的な検査として欠かせません。被曝量も比較的少なく、安全性が高いことも特徴です。
デンタルレントゲン
デンタルレントゲンとは、歯科治療で最も頻繁に用いられるレントゲン撮影になります。一度に1~3本程度の歯を鮮明かつ精密に撮影できるため、歯の根や歯周組織など細部の診断に適しています。主に虫歯の深さ、根管治療の経過や成功状況、歯根の先に生じる根尖病変、歯根破折などの確認に使用されます。
パノラマレントゲンに比べ撮影範囲は狭いですが、その分解像度が高く、細かい病変の早期発見に威力を発揮します。また、撮影時の被曝量が少なく、患者の安全性も高いため繰り返し撮影が可能で、治療経過の観察にも頻繁に使われます。
治療の正確性向上や診断精度の確保に欠かせない基本的な診断ツールです。患者への説明時には、「精密な治療を安全に進めるために欠かせない検査」と伝えると理解が得やすくなります。
歯科用CT
歯科用CT(コーンビームCT)は、歯科診療に特化した立体的なレントゲン撮影装置です。従来のパノラマやデンタルレントゲンでは捉えられない骨や歯の三次元的な構造を鮮明に映し出します。主にインプラント治療、親知らずの抜歯、根管治療の難症例や顎骨の病変診断に使用され、精密な治療計画に欠かせません。骨の厚みや歯根の位置関係が正確に把握でき、安全性が高まります。一方、被曝量はやや高めのため適切な使用が求められます。
導入コスト、維持費の具体的な内訳

レントゲン機器の導入には多額の初期費用とその後の維持費がかかります。ここでは具体的な費用相場を詳しく説明します。
パノラマ・CT・セファロについて
歯科用CTは特に高額で、スペックやメーカーによって価格が大きく異なるため、自院の診療内容や患者層に合わせて慎重な選択が必要です。
| 項目 | パノラマ(全顎撮影) | CT(歯科用コーンビームCT) | セファロ(側貌・頭部X線) |
|---|
| 撮影範囲 | 顎全体、歯列、鼻腔、顎関節まで | 顎・歯・骨などを立体的に(3D) | 頭部全体(側面や正面) |
| 画像の種類 | 2D(平面画像) | 3D(立体画像) | 2D(側貌や正貌) |
| 費用(保険点数) | 約1,000〜2,000点前後 | 約3,000〜5,000点前後 | 約1,000〜2,000点前後(矯正の場合は自費が多い) |
| 機器の価格帯 | 約300万〜600万円 | 約800万〜1,500万円以上 | パノラマと兼用なら+100万〜300万円ほど |
年間保守契約料は機器ごとに異なり、パノラマやCTの場合は約20万円前後が相場です。また、消耗品や定期的な部品交換も必要となります。
※メーカーによって費用も異なりますので、あくまでも目安としてお考えください。
本体機器が大きくなりますので、設置できるかどうかも重要なポイントになります。
| 項目 | パノラマ | CT(歯科用CBCT) | セファロ |
|---|
| 本体サイズ(目安) | 幅100〜130cm × 奥行100cm × 高さ200cm | 幅130〜180cm × 奥行120〜150cm × 高さ200cm以上 | パノラマ装置と一体型の場合、横幅が追加で30〜50cm必要 |
| 重量(目安) | 約100〜150kg | 約150〜250kg | 単体では存在せず、パノラマと組み合わせて設置 |
| 設置スペース(目安) | 約2m × 2m 以上 | 約2.5m × 2.5m 以上 | パノラマ+セファロ一体型なら2.5m以上の横幅が望ましい |
スペースが狭いと、患者導入時も大変になります。また、後から機器を買い替える場合などは、現状のスペースに入る大きさなのかは要確認をしないといけません。
また、パノラマやCTと合わせて、デンタルを同じレントゲン室に置く場合のスペースも考えていきましょう。狭いと、デンタル撮影しにくい位置にしか置けなくなるなんてことも考えられます。
デンタルレントゲンのCRとDRでのコストの違い
歯科医院でよく見るデジタルレントゲンには2種類あります。
CR:コンピューテッド・ラジオグラフィー
イメージングプレートと呼ばれるフィルムで撮影を行い、専用機械に通して読み取るタイプ
DR:ダイレクト・ラジオグラフィー
センサーが直結しており、撮影後すぐにパソコンに表示されるタイプ
この2つのコストについて比べてみます。
初期費用として、X線撮影装置本体の価格は大きな差はないでしょう。
デンタルレントゲン:約30〜80万円
ただ、その他の機器や設備の準備費用により、CR式よりもDR式の方が初期費用が1.5倍くらいかかると言えます。
ランニングコストは以下のようになります。
| 項目 | CR式 | DR式 |
|---|
| 消耗品費用 | イメージングプレート(IP)の交換費用:
約5,000円~15,000円/枚(耐用年数:約1~2年) | ほぼなし(センサー自体は高価だが、消耗品は少ない) |
| メンテナンス費用 | 読み取り機の定期保守契約:
年間約10万~20万円 | センサーおよびソフトウェアの保守契約:
年間約15万~25万円 |
| 電気代 | 機器の使用電力量に応じて発生(大きな差異はない) | 同左 |
| 総合的な維持費 | 年間約15万~35万円 | 年間約15万~30万円 |
個人的な見解や使用している感想として、
・長期的にみると、DR式の方が消耗品が少なく、撮影から現像までのスピードが早いため患者の回転率もいいと考えられます。コストのことを長期で考えるなら、DRだなと思います。
・CR式のイメージングプレートは、DR式のセンサーよりも口の中へ入れた時の不快感が少ないような気が致します。また、口が開きにくい患者や嘔吐反射がある患者にとっては、センサーは少し分厚く負担が大きいようにも感じました。
・歯科医師や歯科衛生士の使いやすさ的に、イメージングプレートの方が馴染みがあり、使いやすいと感じる人が多いなという印象です。正直、私も慣れるまでは、センサーの扱いが難しいと感じました。それに比べて、イメージングプレートは思い通りの撮影ができ、使いやすかったです。
CR式、DR式、それぞれの特徴を知り、コスト面も考え、選択していかなければなりません。歯科医院の中でも、大きな金額が動く機器になりますので、慎重に選択してください。
保険請求と患者負担金額

患者へのレントゲン撮影の説明は、「なぜ撮影が必要か」を明確に伝えることが重要です。まず、「目視だけではわからない歯や顎の内部の状況を、画像で詳しく確認するために撮影します」と説明します。次に具体的な目的を示し、「虫歯の進行状況や歯の根の状態、骨の厚みや顎関節の問題を正確に診断することで、より安全で精密な治療計画を立てられます」と伝えましょう。
また、安全性についても説明が必要です。「歯科用レントゲンは放射線量が極めて低く、日常生活で自然に受ける放射線量に比べてもごくわずかで、身体への影響は心配ありません」と伝えることで、患者の不安を和らげることができます。
さらに費用についても明確に伝えていきます。歯科医院経営ではレントゲン撮影の保険請求が収益に大きく影響します。「保険診療のため負担は少なく、3割負担でパノラマは約1,200円、デンタルは約170円、CTは約3,500円ほどです」と具体的に説明することで安心感が生まれます。
患者が納得して治療を受けられるよう、目的・安全性・費用の3点を丁寧かつ具体的に説明していくことを心がけていきます。
※費用・保険点数に関して
金額や保険点数は、あくまでも2024年時点での概算になります。診療報酬改定や地域差により変更する場合がございますので、ご注意ください。
導入時のポイント
機器導入時には診療効率と投資コストのバランスを見極める必要があります。
初期投資が高額でも、CTの導入によりインプラント治療など高度な治療が可能になり、長期的な収益増につながるケースもあります。逆に、一般診療中心ならパノラマとデンタルの組み合わせで効率的な運営が可能です。
導入検討時には以下のチェックリストを参考にしましょう。
- ・導入する機器が診療内容と一致しているか
- ・初期投資と維持費が許容範囲か
- ・保険診療で適切に算定可能か
- ・デジタル化による業務効率化と感染対策が十分か
また、開業時や設備更新時には自治体の補助金やリースを積極的に活用したり、地域の商工会議所などに相談し、補助金申請や税制優遇制度を利用したりすることでコスト削減が可能です。
1)融資について
日本政策金融公庫の融資では、新規開業や設備投資を支援するための融資鮮度があります。低金利で長期返済が可能です。また、担保がある場合など、状況に応じて、融資金額が上がったり、金利が下がったりします。
2)補助金・助成金について
・中小企業等事業再構築促進事業(ものづくり補助金)
歯科医院でも個人事業主や資本金が1億以下の医療法人が対象となります。(細かい条件がありますので、利用される場合には確認をお願いいたします。)
レントゲン機器も対象となり、½~⅔ の補助率で、最大上限が1,250万補助されます。この補助金のデメリットは、
・申請も大変
・採択されるため申請してももらえない可能性あり
・実績報告が必要
と、いろいろ大変そうではありますが、しっかりと事業計画を立てていらっしゃる歯科医院であれば大丈夫かと思います。
・地方自治体の助成金
地域によって、医療機器の導入に対する独自の助成金制度を設けている場合がございます。助成金なので、条件を満たせばもらえるお金になります。補助金よりも申請難易度低めで実績報告も必要ないことが多いです。地域によりますので、お住まいの地域で検索をしてみてください。
3)税制優遇措置について
・固定資産税の特例
一定の要件を満たす設備投資を行なった場合に、固定資産税の軽減措置を受けられる可能性があります。
・中小企業経営強化制度
生産性の向上に対する設備投資をした場合に、即時償却や税額控除を受けられる制度になります・
※補助金や税制優遇措置などは、年度や政策により変更になる場合がございます。お考えの際には、最新情報の確認や専門家への相談などおすすめいたします。
まとめ
歯科レントゲン機器は診療品質の向上と医院経営の安定化に不可欠です。機器選定では診療内容に適した装置を選び、コストと診療効率を十分に検討することが重要です。
個人的には、レントゲン室の大きさなどに合わせることも考えていただきたいポイントです。歯科衛生士として働いていて、小さいレントゲン室で患者との距離が近く仕事しにくいと感じることもありました。コストや設置スペース問題もあるのでしょうが、歯科医院のスタッフの仕事のしやすさも視野に入れるとより良い歯科医院作りにつながると思います。
また、保険点数の正しい理解と患者への明確な説明を徹底することで収益性を確保できます。補助金やリース制度の活用も視野に入れ、最適な運用を目指しましょう。
歯科衛生士ライター:原田
歯科医療の現場で役立つ実践的な知識を届けるORTC

ORTCは「笑顔の役に立つ」を理念に、歯科界の知識を共有する場を目指しています。歯科医療の現場で役立つ最新の知識と技術を提供することで、臨床と経営の両面からクリニックの成長を支援します。最先端の技術解説や経営戦略に特化した情報を集約し、歯科医療の現場での成果を最大化。自己成長を追求するためのコンテンツをぜひご活用ください。
無料会員登録
無料動画の視聴、有料動画のレンタルが可能です。歯科業界についてのオンライン・オフラインセミナーへの参加が可能となります。
ORTCPRIME
月額5500円で、 ORTC内のすべての動画を見放題に。臨床の現場に役立つ最新の技術解説や、歯科医院経営の成功戦略を網羅した特別コンテンツをご利用いただけます。 歯科業界の方へ効率的に知識を深めていただける内容です。
ORTC動画一覧
ORTCセミナー一覧
まずは無料会員登録
こちらのリンクより会員登録ページへお進みください。
会員登録はこちら
ORTCPRIMEへのアップグレードも簡単!
登録後は「マイページ」から、ORTCPRIMEにいつでもアップグレード可能です。
 こちらの動画もおすすめです
こちらの動画もおすすめです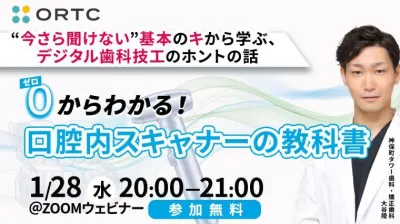 “今さら聞けない”基本のキから学ぶ、デジタル歯科技工のホントの話『ゼロからわかる、口腔内スキャナーの教科書』
“今さら聞けない”基本のキから学ぶ、デジタル歯科技工のホントの話『ゼロからわかる、口腔内スキャナーの教科書』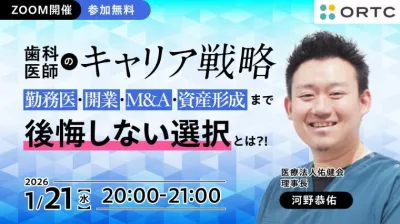 歯科医師のキャリア戦略 ― 勤務医・開業・M&A・資産形成まで、後悔しない選択とは ―
歯科医師のキャリア戦略 ― 勤務医・開業・M&A・資産形成まで、後悔しない選択とは ―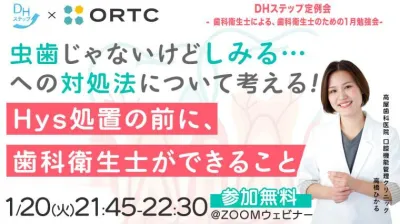 虫歯じゃないけどしみる…への対処法について考える Hys処置の前に、歯科衛生士ができること
虫歯じゃないけどしみる…への対処法について考える Hys処置の前に、歯科衛生士ができること 「TBIが変われば患者が変わる」 自費TBI成功マインド
「TBIが変われば患者が変わる」 自費TBI成功マインド 後継者不在、人材不足、競争激化を乗り切る! 歯科医院M&Aの基本と成功へのプロセス
後継者不在、人材不足、競争激化を乗り切る! 歯科医院M&Aの基本と成功へのプロセス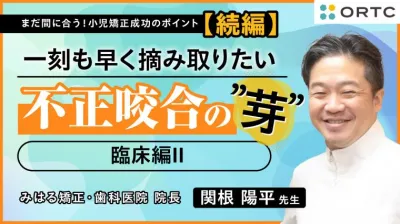 続・まだ間に合う!小児矯正のポイント 〜一刻も早く摘み取りたい 不正咬合の”芽”~ 臨床編Ⅱ
続・まだ間に合う!小児矯正のポイント 〜一刻も早く摘み取りたい 不正咬合の”芽”~ 臨床編Ⅱ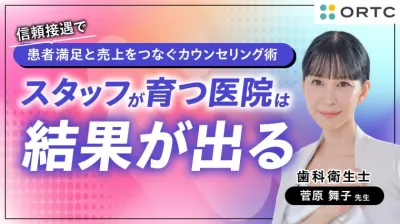 信頼接遇で患者満足と売上をつなぐカウンセリング術 〜スタッフが育つ医院は結果が出る〜
信頼接遇で患者満足と売上をつなぐカウンセリング術 〜スタッフが育つ医院は結果が出る〜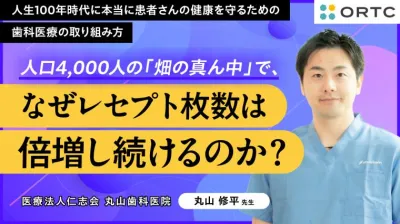 人口4,000人の「畑の真ん中」で、なぜレセプト枚数は倍増し続けるのか?
人口4,000人の「畑の真ん中」で、なぜレセプト枚数は倍増し続けるのか?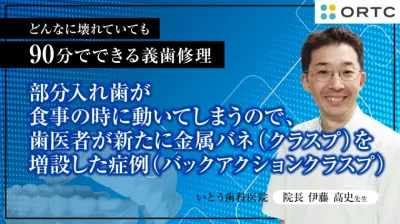 部分入れ歯が食事の時に動いてしまうので、歯医者が新たに金属バネ(クラスプ)を増設した症例(バックアクションクラスプ)
部分入れ歯が食事の時に動いてしまうので、歯医者が新たに金属バネ(クラスプ)を増設した症例(バックアクションクラスプ)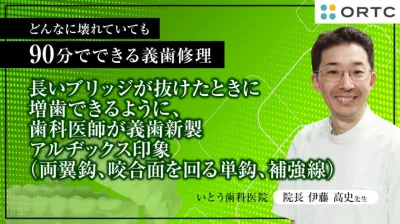 長いブリッジが抜けたときに増歯できるように、歯科医師が義歯新製 アルヂックス印象(両翼鈎、咬合面を回る単鈎、補強線)
長いブリッジが抜けたときに増歯できるように、歯科医師が義歯新製 アルヂックス印象(両翼鈎、咬合面を回る単鈎、補強線)