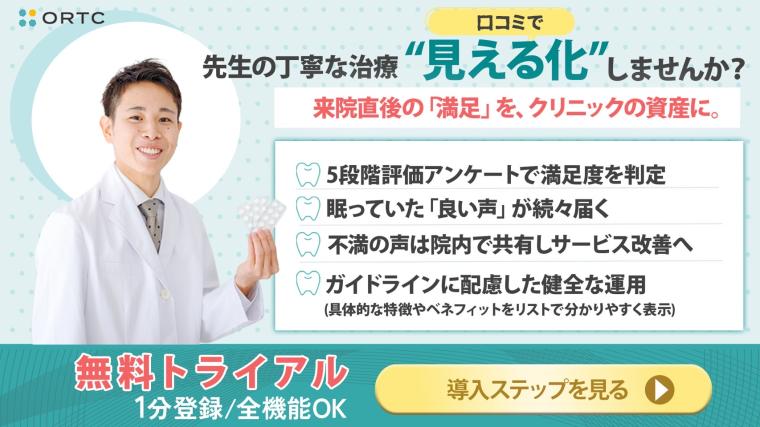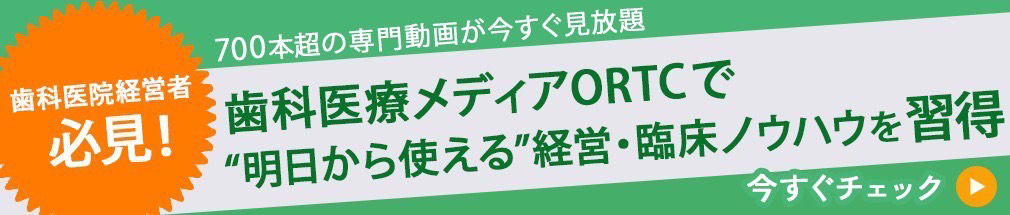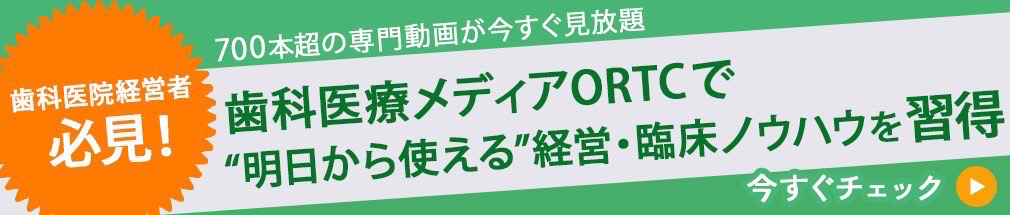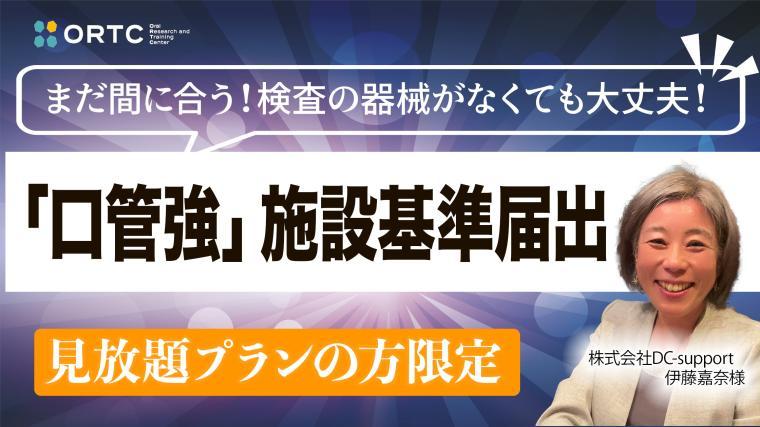「口腔の健康は全身の健康を映す鏡です。」この言葉を、日々の臨床の中で実感している先生方も少なくないでしょう。糖尿病や心疾患、誤嚥性肺炎、認知症といった生活習慣病や高齢者疾患と口腔機能の関連性は、もはやエビデンスレベルで確立されつつあります。にもかかわらず、多くの歯科医院では「重要なのはわかるが、実際にどう連携を始めれば良いのかわからない」という壁に直面しています。
日本はすでに世界でも有数の超高齢社会に突入しており、地域包括ケアシステムのもとで医療と介護が一体となった仕組みづくりが進んでいます。この中で、歯科は「治療」だけでなく「予防・管理」の担い手として役割を拡大しつつあります。口腔の健康維持が全身の健康寿命を左右することが明確になった今、医科歯科連携は「やった方が良い」ではなく「やらなければならない」テーマなのです。
なぜ今、医科歯科連携が必須なのか?

日本は75歳以上の後期高齢者が急速に増加しています。こうした中で、病院中心の医療から地域包括ケアシステムへと舵が切られています。地域包括ケアとは、住み慣れた地域で医療・介護・予防・生活支援を一体的に提供する仕組みです。その中で歯科は、食べる・話すといった生活の根幹を支える役割を担っており、医科との連携なしには機能し得ません。
糖尿病・心疾患・誤嚥性肺炎・認知症と口腔の関係
全身疾患と口腔の関係は数多くの研究で明らかになっています。歯周病は糖尿病の血糖コントロールを悪化させ、逆に歯周病治療はHbA1cの改善につながることが示されています。心疾患や脳梗塞も、歯周病菌が関与する動脈硬化と関係していることが知られています。また、高齢者の誤嚥性肺炎は口腔内の衛生状態が大きく影響し、認知症患者においても口腔ケアが病状進行を緩やかにする可能性が指摘されています。これらの疾患との関連性を考えれば、歯科は医科の「補助」ではなく「必須のパートナー」だと言えるでしょう。
「治療」から「予防・管理」へ:歯科の新しい役割
かつては「悪くなったら治す」のが歯科の役割でした。しかし医療全体が「予防・管理」へシフトしている今、歯科もまた予防と全身疾患管理の一翼を担う存在として期待されています。生活習慣病の予防、周術期の合併症回避、介護現場での口腔ケア支援――これらはすべて「予防・管理型の歯科」の新しいミッションです。
【成功事例に学ぶ】医科歯科連携の現場から

では、実際に医科歯科連携が成果を上げている現場を見てみましょう。抽象的な理念ではなく、具体的な事例にこそ明日からの実践ヒントが詰まっています。
東京科学大学病院(旧・東京医科歯科大学医学部附属病院)の取り組み
東京医科歯科大学は、2021年10月に医学部附属病院と歯学部附属病院を統合し、国内初となる「医科と歯科のシームレスな一体運営」をスタートさせました。2024年には東京科学大学病院へと改称され、さらに発展的な体制を築いています。
この病院の大きな特徴は、「Oral Health Center」を中心とした周術期口腔ケアの導入です。外科・麻酔科と歯科が協働し、手術前から患者の口腔状態を評価・改善することで、術後合併症を大幅に減少させています。歯科医師や歯科衛生士は医師と同じチームの一員として位置づけられ、情報は電子カルテを通じて双方向に共有。診療・教育・研究のすべてにおいて連携が当たり前に機能している点は、まさに「理想のモデルケース」といえるでしょう。
この事例は大規模大学病院だからこそ可能な取り組みとも言えますが、地域の中小規模医院にとっても大いに参考になります。たとえば「周術期口腔ケアのフローを地域病院と共有する」「歯科からの情報提供書を定型化する」など、規模を問わず応用できる部分が数多く存在します。
▶▶ 「歯周病と全身疾患の関係を徹底解説 命に関わるリスクと最新の検診・指導法」
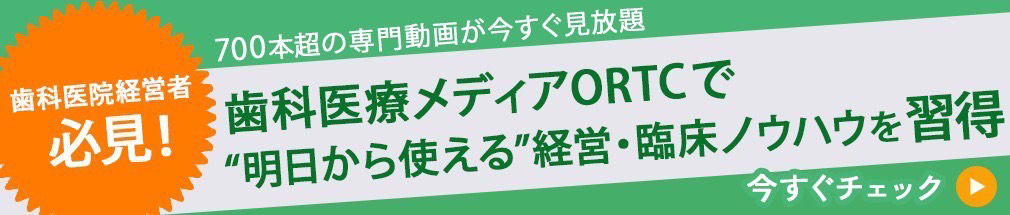
Case2:周術期口腔機能管理基幹病院(外科・麻酔科)とのネットワーク構築
術後合併症減少という客観的成果
基幹病院において、外科や麻酔科と歯科が連携し、術前の口腔機能管理を徹底するケースも増えています。術前に歯科が口腔内を清掃・調整することで、術後合併症、とりわけ誤嚥性肺炎の発生率が減少したという客観的な成果が報告されています。病院にとっては合併症リスクの低下、患者にとっては安心して手術に臨める環境が整う、そして歯科にとっては地域医療に不可欠な役割を果たせるという三方良しの結果となります。
Case3:在宅・介護施設との多職種連携:ケアマネ・訪問看護師との協働 多職種カンファレンスでの歯科の存在感
高齢化に伴い、在宅医療や介護施設での歯科の役割はますます大きくなっています。訪問看護師やケアマネジャーと協働し、口腔ケアの方法や重要性を共有することは、誤嚥性肺炎予防やQOLの維持に直結します。多職種カンファレンスに歯科が積極的に参加することで、これまで以上に存在感を発揮できるのです。
【2025年最新情報】制度・診療報酬改定と国の後押し

連携を推進するには制度と診療報酬の理解も欠かせません。2025年の診療報酬改定を見据え、今から押さえておくべきポイントを整理します。
かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(か強診)の役割
か強診に認定されると、地域包括ケアの中核的役割を担うことができ、医科からの信頼も得やすくなります。特に在宅患者の口腔ケアや多職種連携に積極的に取り組む体制を持つことで、連携の基盤が整います。
医科歯科連携加算・多職種連携加算の最新動向
周術期口腔機能管理料や歯科疾患管理料の連携加算など、歯科の医科連携を評価する項目は増加しています。これらは経営的な安定にもつながるため、算定要件を理解し積極的に活用することが重要です。
▶▶ 診療報酬制度の基本と改定の概要:医療現場で押さえるべきポイント
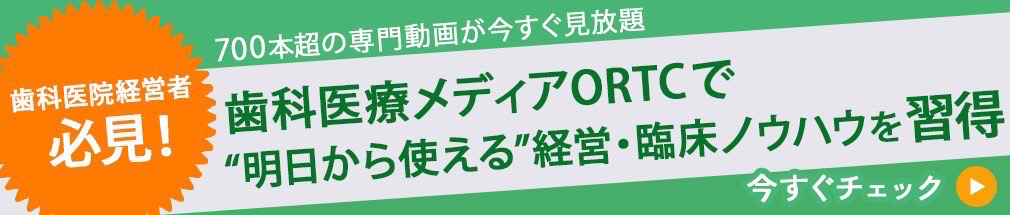
明日から始める!医科歯科連携 強化の3ステップ

「重要なのは分かるけれど、何から始めればよいのか分からない」という声に応えるべく、明日から実践できる3つのステップを紹介します。
Step1:院内体制の整備(目的共有・フォーマット準備)
まずは院内で「なぜ連携が必要なのか」を共有することが大切です。その上で紹介状や報告書のフォーマットを準備し、担当者を決めて役割を明確にしましょう。
Step2:地域医療資源へのアプローチ(医師会・病院訪問)
地域の医師会や病院の勉強会に参加し、まずは顔を知ってもらうことから始めます。近隣の医療機関を訪問し、自院の取り組みを紹介するパンフレットを渡すだけでも、第一歩となります。
H3 Step3:継続的な情報交換(紹介患者の経過報告・勉強会開催)
連携は一度きりではなく継続が大切です。紹介患者の経過報告を徹底することで信頼関係は深まり、定期的な勉強会や情報交換会を開くことで関係はさらに強固なものになります。
Q&A
Q. 医科歯科連携のメリットは?
A. 医科歯科連携の最大のメリットは、患者さんの健康寿命を延ばせることです。糖尿病や心疾患、誤嚥性肺炎といった全身疾患は、口腔環境と密接に関係しており、歯科が関与することで疾患の予防・進行抑制が可能になります。さらに医院にとっては、医科からの紹介患者が増えることで専門性を高められるだけでなく、診療報酬加算を活用することにより経営の安定にもつながります。地域の中で「連携に積極的な歯科」として認知されれば、患者さんや他職種からの信頼も格段に向上し、医院のブランド力向上にも寄与します。
Q. 糖尿病患者への歯科介入は本当に効果がある?
A. 多くの研究で、歯周病治療を行うことでHbA1c値が有意に改善することが示されています。これは単なる数値の変化ではなく、合併症のリスクを減らし、患者さんの生活の質を高める重要な成果です。医師にとっても、血糖コントロールの一助となる歯科の役割は大きな意味を持ちます。そのため、「歯科からの報告が治療計画に役立った」という声は少なくありません。歯科が積極的に介入することで、医科からの信頼を得るきっかけとなり、持続的な連携関係へと発展します。
Q. 医科との関係づくりはどう始めればいい?
A. 最初の一歩は「顔の見える関係」をつくることです。具体的には、地域の医師会や勉強会に参加し、歯科としての取り組みを紹介することから始めましょう。また、患者さんを紹介する際には紹介状や情報提供書を必ず添え、治療経過を報告することが大切です。こうした小さな積み重ねが信頼につながり、将来的には双方向の紹介や共同での勉強会開催といった形に発展します。特に「報告を欠かさない」姿勢は、医科から見たときに歯科を信頼できるパートナーと評価する大きなポイントです。
Q. 医科歯科連携加算はどんな時に算定できる?
A. 医科歯科連携加算や多職種連携加算は、条件を満たした場合に算定可能です。代表的なのは「周術期口腔機能管理計画」や「歯科疾患管理料の連携強化加算」です。例えば、基幹病院の外科・麻酔科と連携して術前の口腔管理を行うケースや、多職種カンファレンスに参加し在宅患者のケアプランに関与するケースが挙げられます。こうした算定は単なる収益確保ではなく、国が歯科の医科連携を積極的に評価しようとしている証拠でもあります。制度を正しく理解し、日常臨床に活かすことで、医院経営と社会的意義の両立が可能となります。
Q. 明日からできる取り組みは?
A. 大掛かりなことをしなくても、明日から始められる取り組みは数多くあります。まずは院内で「なぜ医科歯科連携を行うのか」という目的をスタッフ全員で共有し、紹介状や情報提供書のテンプレートを準備することが第一歩です。さらに、近隣の医療機関へ挨拶に伺い、自院の連携への意欲を伝えるだけでも十分なスタートになります。その際、パンフレットや簡単な活動紹介資料を用意すると印象が良くなります。重要なのは「完璧を目指す前に、小さな一歩を踏み出すこと」です。継続することで自然と信頼関係が深まり、連携は次のステージへと進んでいきます。
まとめ:医科歯科連携は未来の歯科を切り拓く
医科歯科連携は、患者にとっては健康寿命を延ばす力となり、医院にとっては専門性や信頼性の向上、さらには経営的な安定にもつながる「三方よし」の取り組みです。地域で選ばれる歯科医院へと成長するためには欠かせないテーマであり、今こそ一歩を踏み出すときです。
歯科衛生士ライター 西
【参考URL】構成作成・記事執筆で参考にしたURLを記載する
https://www.tmd.ac.jp/medhospital/%EF%BC%89?utm_source=chatgpt.com
歯科医療の現場で役立つ実践的な知識を届けるORTC

ORTCは「笑顔の役に立つ」を理念に、歯科界の知識を共有する場を目指しています。歯科医療の現場で役立つ最新の知識と技術を提供することで、臨床と経営の両面からクリニックの成長を支援します。最先端の技術解説や経営戦略に特化した情報を集約し、歯科医療の現場での成果を最大化。自己成長を追求するためのコンテンツをぜひご活用ください。
無料会員登録
無料動画の視聴、有料動画のレンタルが可能です。歯科業界についてのオンライン・オフラインセミナーへの参加が可能となります。
ORTCPRIME
月額5500円で、 ORTC内のすべての動画を見放題に。臨床の現場に役立つ最新の技術解説や、歯科医院経営の成功戦略を網羅した特別コンテンツをご利用いただけます。 歯科業界の方へ効率的に知識を深めていただける内容です。
ORTC動画一覧
ORTCセミナー一覧
まずは無料会員登録
こちらのリンクより会員登録ページへお進みください。
会員登録はこちら
ORTCPRIMEへのアップグレードも簡単!
登録後は「マイページ」から、ORTCPRIMEにいつでもアップグレード可能です。
 こちらの動画もおすすめです
こちらの動画もおすすめです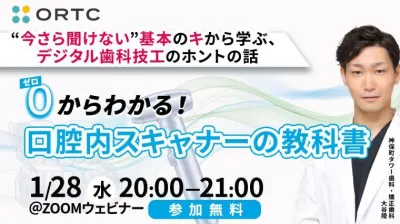 “今さら聞けない”基本のキから学ぶ、デジタル歯科技工のホントの話『ゼロからわかる、口腔内スキャナーの教科書』
“今さら聞けない”基本のキから学ぶ、デジタル歯科技工のホントの話『ゼロからわかる、口腔内スキャナーの教科書』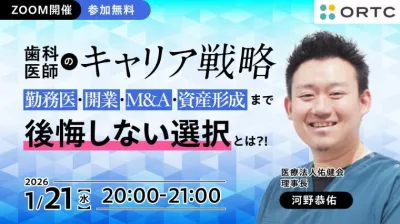 歯科医師のキャリア戦略 ― 勤務医・開業・M&A・資産形成まで、後悔しない選択とは ―
歯科医師のキャリア戦略 ― 勤務医・開業・M&A・資産形成まで、後悔しない選択とは ―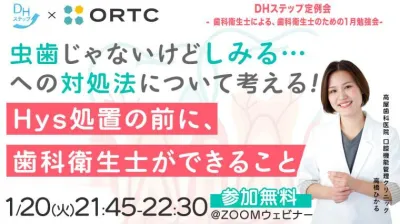 虫歯じゃないけどしみる…への対処法について考える Hys処置の前に、歯科衛生士ができること
虫歯じゃないけどしみる…への対処法について考える Hys処置の前に、歯科衛生士ができること 「TBIが変われば患者が変わる」 自費TBI成功マインド
「TBIが変われば患者が変わる」 自費TBI成功マインド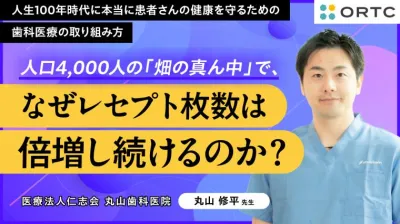 人口4,000人の「畑の真ん中」で、なぜレセプト枚数は倍増し続けるのか?
人口4,000人の「畑の真ん中」で、なぜレセプト枚数は倍増し続けるのか?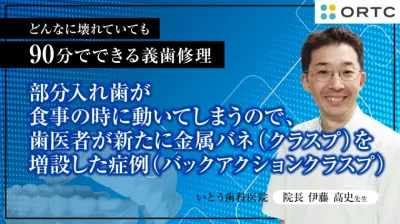 部分入れ歯が食事の時に動いてしまうので、歯医者が新たに金属バネ(クラスプ)を増設した症例(バックアクションクラスプ)
部分入れ歯が食事の時に動いてしまうので、歯医者が新たに金属バネ(クラスプ)を増設した症例(バックアクションクラスプ)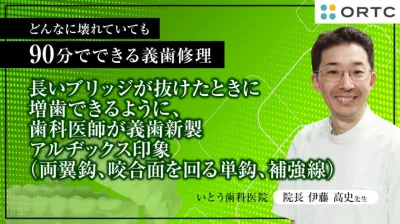 長いブリッジが抜けたときに増歯できるように、歯科医師が義歯新製 アルヂックス印象(両翼鈎、咬合面を回る単鈎、補強線)
長いブリッジが抜けたときに増歯できるように、歯科医師が義歯新製 アルヂックス印象(両翼鈎、咬合面を回る単鈎、補強線)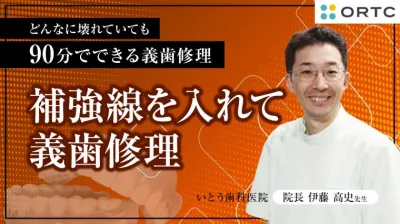 補強線を入れて義歯修理
補強線を入れて義歯修理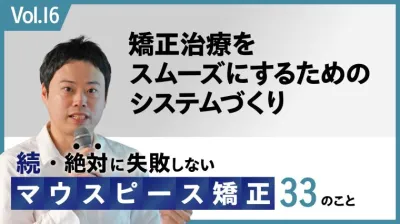 続・ 絶対に失敗しないMP矯正33の事 システムづくり
続・ 絶対に失敗しないMP矯正33の事 システムづくり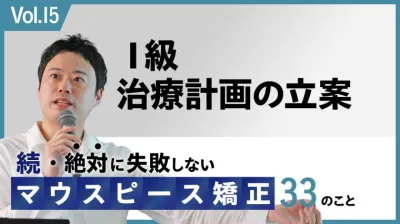 続・ 絶対に失敗しないMP矯正33の事 Ⅰ級 治療計画の立案
続・ 絶対に失敗しないMP矯正33の事 Ⅰ級 治療計画の立案