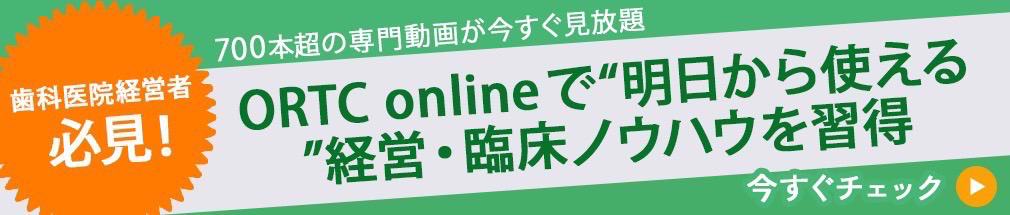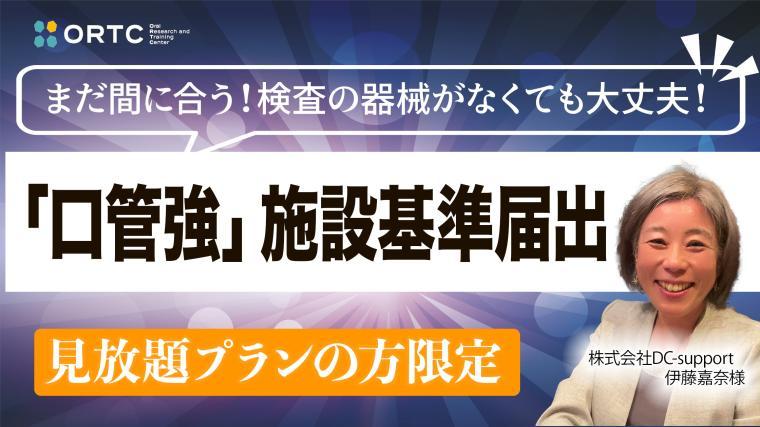昨今では一般の方々にも歯科検診の必要性が認知されており、「予防歯科」という言葉も浸透してきました。
厚生労働省が発表した内容(※1)によれば、日本の歯科定期検診受診率は、2009年の34.1%から2022年には58%へと大幅に上昇しており、この結果からも健康意識が高まっていることが分かります。
しかし一方で、歯科検診の時期やその必要性についてはまだ周知されていないことも事実です。
歯周病初期治療が終わり、虫歯の治療が終わって、さて今後はメンテナンスへ、となった段階へきて患者さんの通院が途絶えてしまっていませんか?
治療終了後、そこから定期検診を受ける必要性やその理由を説明することができず、患者さんに納得して頂けなかったり、次の定期検診につなげられなかったり、虫歯の治療だけで終わってしまうことも多いのではないでしょうか。
この記事では、患者さんに歯科定期検診がなぜ必要なのか、そのメリットや理由について解説します。
また、定期検診だけでなく、自費メニューへの誘導フローについてもお話しします。
1、歯科定期検診のエビデンス
 定期メンテナンスの効果を示す具体的な研究結果としては、2004年に発表されたスウェーデン・イエテボリ大学のAxelsson教授をはじめとする、研究グループが1970年から30年間の研究結果をまとめた論文が有名です。
定期メンテナンスの効果を示す具体的な研究結果としては、2004年に発表されたスウェーデン・イエテボリ大学のAxelsson教授をはじめとする、研究グループが1970年から30年間の研究結果をまとめた論文が有名です。
この研究内容としては、500人以上の被験者に最初の2年間は2ヶ月に1度、その後は3〜12ヶ月間隔で定期メンテナンスを受けてもらい、メンテナンス開始年齢と30年間で虫歯になった数と抜歯した数を調べるというものでした。
結果としては、メンテナンス開始年齢が20〜35歳の対称群は30年間の虫歯の本数が1.2本、30年間の抜歯数は0.4本です。
メンテナンス開始年齢が51〜65歳の対称群は30年間の虫歯の本数が2.1本、30年間の抜歯数は1.8本でした。
また、厚生労働省が2016年に行なった歯科疾患実態調査(※2)によると、日本の場合2016年時点での1人あたりの歯を失った本数の平均値は60〜65歳で4.6本となっており、この結果から見ても上記の定期メンテナンスを受けた場合の抜歯本数がいかに少ないかが分かります。
1-2、歯科定期検診の経済効果
では、歯科定期検診を受けることでどのような経済効果が見込まれるのでしょうか?
歯科定期検診を受けることのメリットとして、虫歯や歯周病の早期発見・早期治療はもちろんのこと、全身の健康の維持につながることが挙げられます。
歯周病は糖尿病や心筋梗塞、脳卒中などの全身の疾患と関連があることが知られています。
歯科定期検診を受けることで、口腔内の健康を保つことで全身疾患のリスクを軽減し、健康維持に繋ぐことができるのです。
また、健康な歯を維持することは日常生活の質にも大きな影響を与えます。
歯を健康な状態に保つことにより、噛むこと・食べることという健康状態に直結する大切な機能を維持することができ、美味しい食事を楽しめることで社会生活も充実することが見込めます。
一方で歯に問題を抱えると、その治療にかかる医療費が発生するだけでなく、噛めない・食べられないという問題が起こり、生活全体の満足度も低下してしまいます。
このように、歯科定期検診を受けることは生活全体の質にも直結するのです。
デンソー健康保険組合が発表した「歯科・医科医療費の相関分析」(※3)によれば、歯周疾患がある被験者群は、歯周疾患がない被験者群に比べて年間医療費が22,072円もの差が出ることが分かっています。
また、歯科検診を行なった事業所は年間医科歯科医療費が減少した一方、歯科検診を行なわなかった事業所では年間医科歯科医療費が大幅に増加したことが分かりました。
このように、定期的な歯科検診を受けることはお口の健康だけでなく体全体の健康に寄与することが分かっています。
ぜひこのエビデンスを患者さんにお伝えし、歯科定期検診の重要性をお伝えして下さい。
2、適切な受診頻度とは?
 多くの歯科で定期検診の時期について「3ヶ月に一度」と患者さんにお伝えされていることと思いますが、なぜ「3ヶ月に一度」なのでしょうか?
多くの歯科で定期検診の時期について「3ヶ月に一度」と患者さんにお伝えされていることと思いますが、なぜ「3ヶ月に一度」なのでしょうか?
この「3ヶ月に一度」という頻度は、虫歯や歯周病の原因である「歯垢(プラーク)」の成熟スピードと関係があります。
口の中には善玉菌や悪玉菌、そしてどちらにも移り変わる日和見菌が存在しており、その種類は400種類以上と言われています。
歯の表面には歯を保護する働きのある「ペリクル」という唾液の成分が覆っていますが、ここにまず細菌が付着し、定着・増殖することでプラークが形成されます。
ここから時間が経過するほど口の中でトラブルを起こす細菌が増えていき、バイオフィルムと呼ばれる細菌の膜ができるのです。
どんなに気をつけて磨いていても、歯磨きなどのセルフケアだけでは歯垢を完全に落としきれません。
また、お口の中から細菌を全てなくすこと、いわゆる殺菌することは出来ないため大体3〜4ヶ月でまた細菌が増殖してしまい、元の状態に戻ってしまいます。
3〜4ヶ月の期間で定期検診を受診することを進めているのはこのためです。
ただし、歯科検診の頻度に関しては、患者さんの口腔内の状態を見てその都度考えることが求められます。
虫歯になりやすい人や、歯周病の状態が安定していない場合には1〜2ヶ月、口腔内の状態がよくセルフケアも効果的に行えている人は半年に1回など状態に合わせて歯科定期検診の時期を設定しましょう。
3、歯科定期検診には保険が適用される?
歯科定期検診にはどのような種類があるのでしょうか?
以下で解説します。
歯周病の治療を目的とした歯科定期検診
歯周病治療を目的としてクリーニングを行う場合、保険適用となります。
歯肉炎の治療を目的とした歯科定期検診
軽度の歯肉炎の治療も保険適用の対象になります。
歯周病の初期段階である歯肉炎を治療することにより、歯周病への進行を防ぐことが可能です
メンテナンス治療
歯周病治療を受け、安定した歯周組織を維持し再発を防ぐためのメンテナンスも保険適用の対象となります。
これに対し、「歯を白く美しい見た目にしたい」など、審美的観点でのクリーニング は保険適用にはなりません。
また、保険適用となる回数は月に1度、または3ヶ月に1回という頻度になるため、毎週のようにクリーニング を受けたいというような場合も保険適用外となります。
4、自費メニュー化のポイント
上記で触れたように、審美的観点でのクリーニングについては保険適用がされないため、患者さんの希望に応えるためには、自費メニューを設定することが求められます。
実際に患者さんから要望があったエピソードなどを取りまとめて、今どのような内容が求められているのかを考えながら自費メニューの内容を設定していくことがポイントです。
分かりやすく保険のクリーニング と線引きをするために、使用する機材や歯磨剤を保険のクリーニングと自費のクリーニングで変えたり、「個室に案内する」、「アロマオイルでリラックスできる場作りをする」など内容だけでなくコンセプトも設定することで「特別な内容」という印象をつけることができるのでおすすめです。
\今すぐこの知識を深堀したいなら/
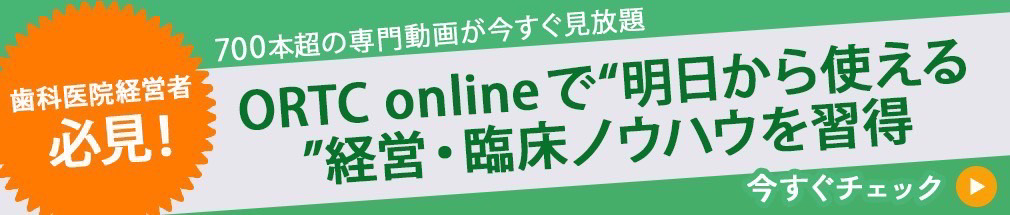
5、自費メニューのトークフロー
 自費メニューを設定するときには、患者さんの要望に沿ったメニューを選べるようにメニューを設定するだけでなく、患者さんの要望を上手に聞き出すことも重要です。
自費メニューを設定するときには、患者さんの要望に沿ったメニューを選べるようにメニューを設定するだけでなく、患者さんの要望を上手に聞き出すことも重要です。
患者さんの望みを確認する
患者さんにTBI(歯磨き指導)する際などに、「ご自身の歯の色について、白くしたいと思っておられますか?」と質問を投げかけてみましょう。
気になっておられない方でも、こうして聞いてみることで「私の歯は黄色いんですか?」と興味を持ってもらうきっかけになります。
その人の生活背景や望みに合った提案をする
自費メニューを受けることで、その方にとってどのような未来が手に入るのかその未来像を具体的に説明しましょう。さらに魅力的に感じられるようになります。
例えば春の新生活や新入学の時期で、また結婚式などのパーティがあるのであれば記念写真を撮ることも多いので、綺麗な口元で素敵な笑顔で写真に写るようにしませんか?とお声かけをしてみると「綺麗な口元で笑顔の自分」を想像しやすいでしょう。その理想的な未来に近づけるのであれば自費メニューを受けてみたい、と考えやすくなります。
ゴール設定をする
一言に「クリーニング 」と言っても、着色を落とすクリーニング、根本的に色を変えるホワイトニングなど、目的が違えばその内容も異なります。
患者さんが思い描く「こうなりたい」という姿をしっかりと聞き取り、ゴール設定をした上でメニューを決めていきましょう。
また、患者さんの要望に添えるのはどのメニューなのか、自費メニューのどこが保険と違うのか、自費メニューを受けるメリットは何か、誰でもすぐに説明できるようにします。そのために、患者さんに説明するための説明ツールを作成し、提案する時にはすぐに見せられるようにしておきましょう。
6、実体験エピソード
メニュー化のポイントの中で、自費メニューとしての場作りも大切とお話ししましたが、実際に新たな自費メニューを設定した時に私が体験したエピソードをお話しします。
「自費=高い」という心の壁から提案ができない
自費メニューを作った時に、スタッフから一番上がってきたのが「自費という高額商品を勧めにくい」というものです。
保険であれば3,000〜4,000円で済むところ、自費メニューではどうしてもそれ以上の金額になるため、お勧めしにくいと尻込んでしまい紹介に漕ぎ着けない方が多くいました。
ここで大切になるのは「お金の価値は人それぞれ」だということ、そして「提案するだけでいい」ことです。
着色が気になっておられる方にとって、自費メニューを選択することで今まで悩んでいた着色を取ってスッキリできるのであれば、その金額は気にならないかも知れません。
その方のお悩みが解決できるのであれば自費メニューは「高額なもの」ではなく、「悩みを解決できる魅力的な手段」となるのです。
また、提案するのはあくまで自費メニューがあることを紹介するだけであり、提案した上で患者さんが選択されるかどうかはその患者さん次第です。
紹介しなければ患者さんは自費メニューがあることを知らないままになってしまいますから、提案・紹介しないことはむしろ罪であるとも言えます。
どんどん積極的にお声かけしてみてくださいね。
思ってもいないところから反響があった!
新しいメニューを紹介する時には、どの患者さんにも分け隔てなくご紹介してみてください。
この人は興味ないかも…と感じても、実際にお話ししてみると興味を持ってくださる場合もあります。
また、自費メニューを受けたことで「自費メニューでお金をかけた自分の今の状態には価値がある」と感じて頂けて、保険の定期検診のリコールに繋がることもあります。
この人には伝えてこの人には伝えない、とはせずに全ての方にお話ししてみてくださいね。
7、まとめ
保険で行えるクリーニングにはその内容や期間においてどうしても制約があります。
自費メニューを組み合わせることでさらに柔軟に患者さんの希望に沿うことができるようになりますから、ぜひ自費メニューについて検討してみてくださいね。
歯科衛生士ライター:moe
\今すぐこの知識を深堀したいなら/
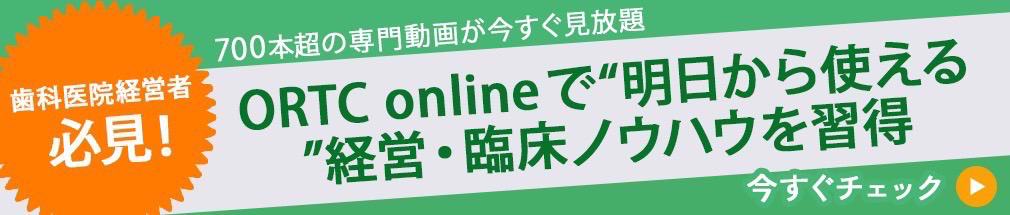
Q&A
Q.自費メニューにはどのようなものがありますか?
A.オフィスホワイトニング、自費クリーニング、着色除去などがよく設定されるメニューです。他に、口腔内マッサージを自費メニューとして設定されている所もあります。
Q.自費メニューの価格はどのくらい?
A.内容や時間にもよりますが、3,000〜10,000円程度が相場のようです。
Q.保険のクリーニングと自費のクリーニングについて違いを聞かれたら何と答えるといいですか?
A.保険は治療や予防のためのクリーニング、自費はお口をより良くするための癒しの時間、と捉えてもらうと説明や提案がしやすくなります。
Q.定期検診を受けるメリットは?
A.虫歯や歯周病の早期発見早期治療ができることです。
お口の中の異常について早くに気づくことで、早い段階で治療することができます。
虫歯も歯周病も進行してしまうと治療のために何度も通ってもらうことになってしまいます。
早くに気づくことで結果的に来院回数が減ることを説明してみてくださいね。
Q.自費メニューを提案しやすくするための方法はありますか?
A.1ヶ月など期間を決めてキャンペーンを組み、待合や診療室にPOPを貼っておくと患者さんにも知ってもらいやすく、提案しやすくなります。
【参考URL】
※1厚生労働省「平成28年国民健康・栄養調査報告」https://www.mhlw.go.jp/content/001066497.pdf
※2厚生労働省「平成28年歯科疾患実態調査」
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/62-28.html
※3デンソー健康保険組合「歯科・医科医療費の相関分析」
https://www.jda.or.jp/occupational_health/doc/poster-01.pdf
歯科医療の現場で役立つ実践的な知識を届けるORTC

ORTCは「笑顔の役に立つ」を理念に、歯科界の知識を共有する場を目指しています。歯科医療の現場で役立つ最新の知識と技術を提供することで、臨床と経営の両面からクリニックの成長を支援します。最先端の技術解説や経営戦略に特化した情報を集約し、歯科医療の現場での成果を最大化。自己成長を追求するためのコンテンツをぜひご活用ください。
無料会員登録
無料動画の視聴、有料動画のレンタルが可能です。歯科業界についてのオンライン・オフラインセミナーへの参加が可能となります。
ORTCPRIME
月額5500円で、 ORTC内のすべての動画を見放題に。臨床の現場に役立つ最新の技術解説や、歯科医院経営の成功戦略を網羅した特別コンテンツをご利用いただけます。 歯科業界の方へ効率的に知識を深めていただける内容です。
ORTC動画一覧
ORTCセミナー一覧
まずは無料会員登録
こちらのリンクより会員登録ページへお進みください。
会員登録はこちら
ORTCPRIMEへのアップグレードも簡単!
登録後は「マイページ」から、ORTCPRIMEにいつでもアップグレード可能です。
 こちらの動画もおすすめです
こちらの動画もおすすめです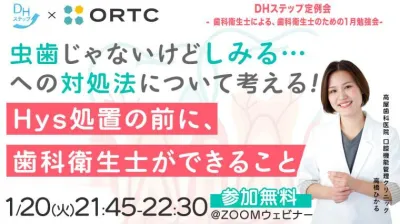 虫歯じゃないけどしみる…への対処法について考える Hys処置の前に、歯科衛生士ができること
虫歯じゃないけどしみる…への対処法について考える Hys処置の前に、歯科衛生士ができること 「TBIが変われば患者が変わる」 自費TBI成功マインド
「TBIが変われば患者が変わる」 自費TBI成功マインド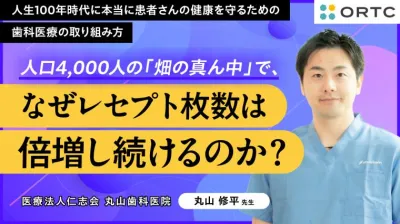 人口4,000人の「畑の真ん中」で、なぜレセプト枚数は倍増し続けるのか?
人口4,000人の「畑の真ん中」で、なぜレセプト枚数は倍増し続けるのか?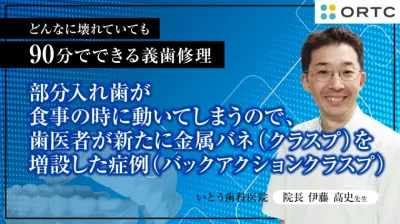 部分入れ歯が食事の時に動いてしまうので、歯医者が新たに金属バネ(クラスプ)を増設した症例(バックアクションクラスプ)
部分入れ歯が食事の時に動いてしまうので、歯医者が新たに金属バネ(クラスプ)を増設した症例(バックアクションクラスプ)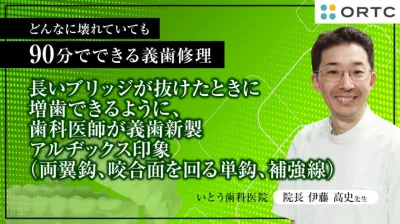 長いブリッジが抜けたときに増歯できるように、歯科医師が義歯新製 アルヂックス印象(両翼鈎、咬合面を回る単鈎、補強線)
長いブリッジが抜けたときに増歯できるように、歯科医師が義歯新製 アルヂックス印象(両翼鈎、咬合面を回る単鈎、補強線)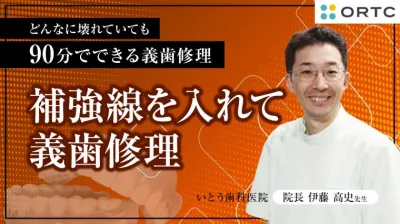 補強線を入れて義歯修理
補強線を入れて義歯修理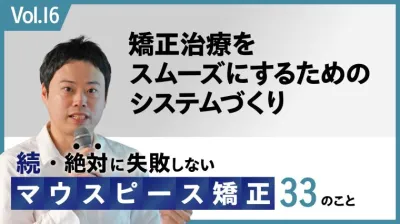 続・ 絶対に失敗しないMP矯正33の事 システムづくり
続・ 絶対に失敗しないMP矯正33の事 システムづくり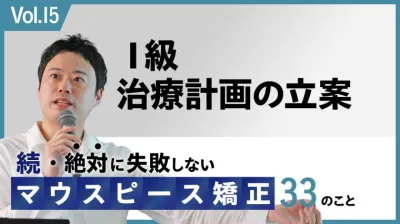 続・ 絶対に失敗しないMP矯正33の事 Ⅰ級 治療計画の立案
続・ 絶対に失敗しないMP矯正33の事 Ⅰ級 治療計画の立案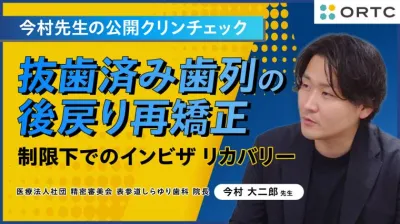 抜歯済み歯列の後戻り再矯正:制限下でのインビザ リカバリー
抜歯済み歯列の後戻り再矯正:制限下でのインビザ リカバリー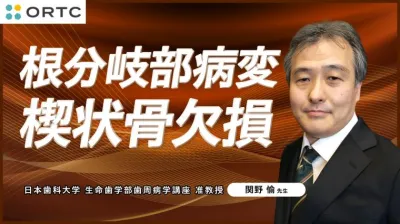 根分岐部病変 楔状骨欠損
根分岐部病変 楔状骨欠損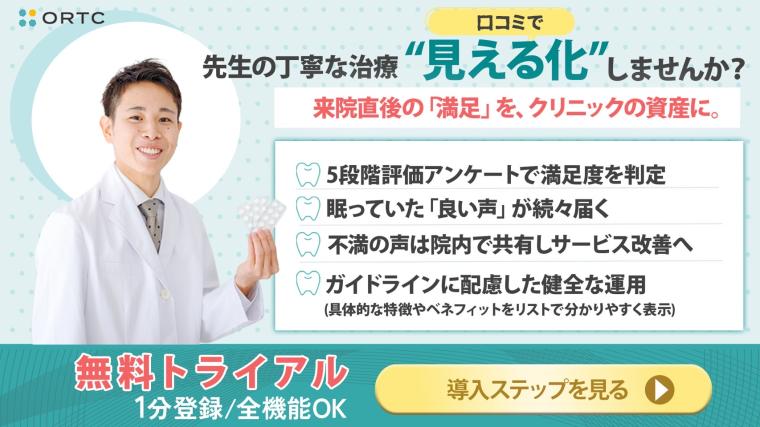
 定期メンテナンスの効果を示す具体的な研究結果としては、2004年に発表されたスウェーデン・イエテボリ大学のAxelsson教授をはじめとする、研究グループが1970年から30年間の研究結果をまとめた論文が有名です。
定期メンテナンスの効果を示す具体的な研究結果としては、2004年に発表されたスウェーデン・イエテボリ大学のAxelsson教授をはじめとする、研究グループが1970年から30年間の研究結果をまとめた論文が有名です。 多くの歯科で定期検診の時期について「3ヶ月に一度」と患者さんにお伝えされていることと思いますが、なぜ「3ヶ月に一度」なのでしょうか?
多くの歯科で定期検診の時期について「3ヶ月に一度」と患者さんにお伝えされていることと思いますが、なぜ「3ヶ月に一度」なのでしょうか?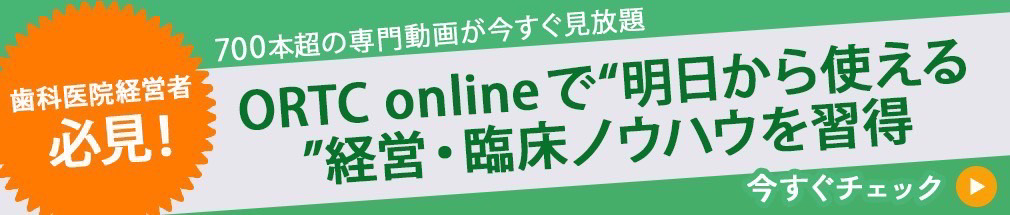
 自費メニューを設定するときには、患者さんの要望に沿ったメニューを選べるようにメニューを設定するだけでなく、患者さんの要望を上手に聞き出すことも重要です。
自費メニューを設定するときには、患者さんの要望に沿ったメニューを選べるようにメニューを設定するだけでなく、患者さんの要望を上手に聞き出すことも重要です。