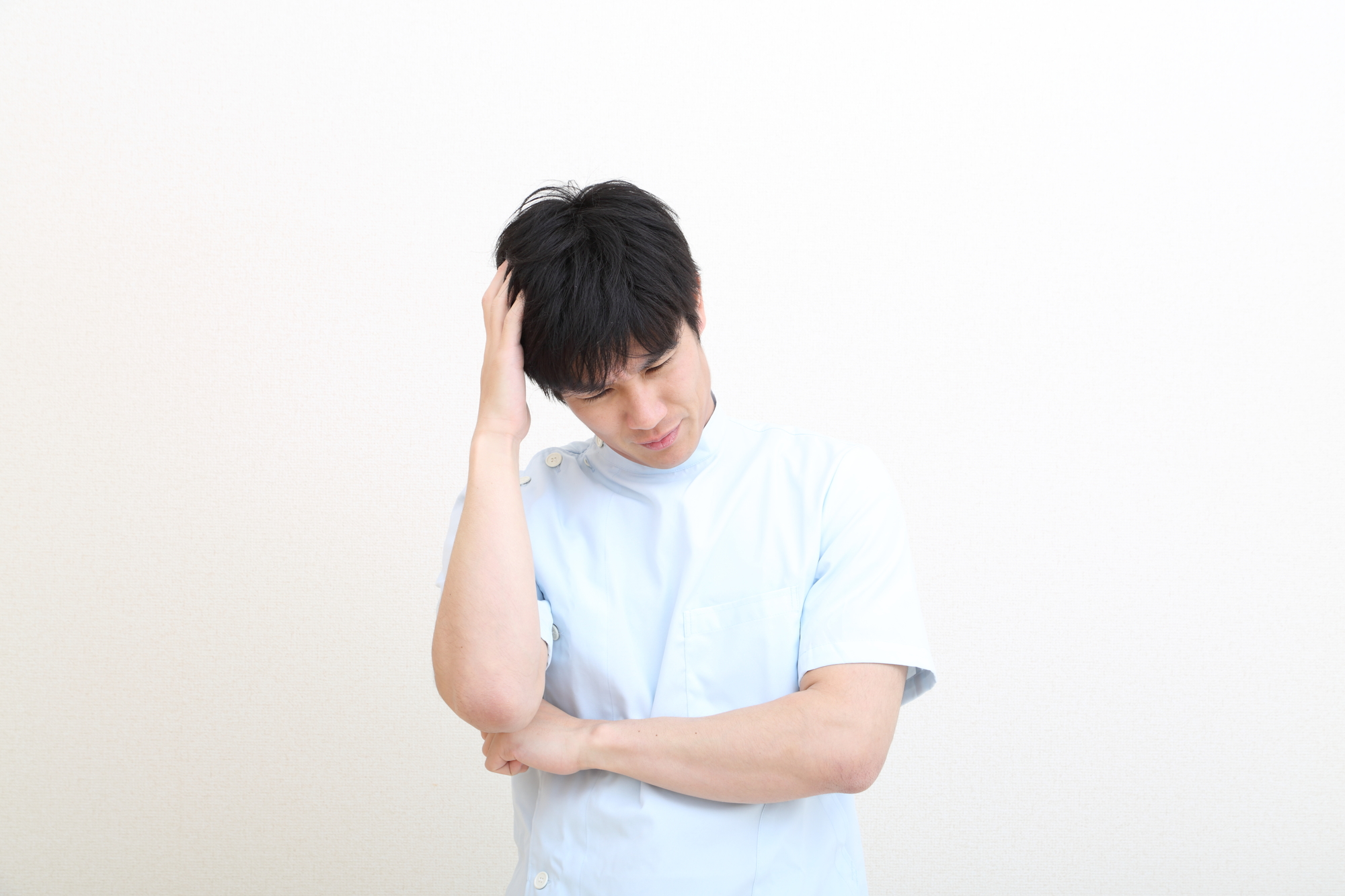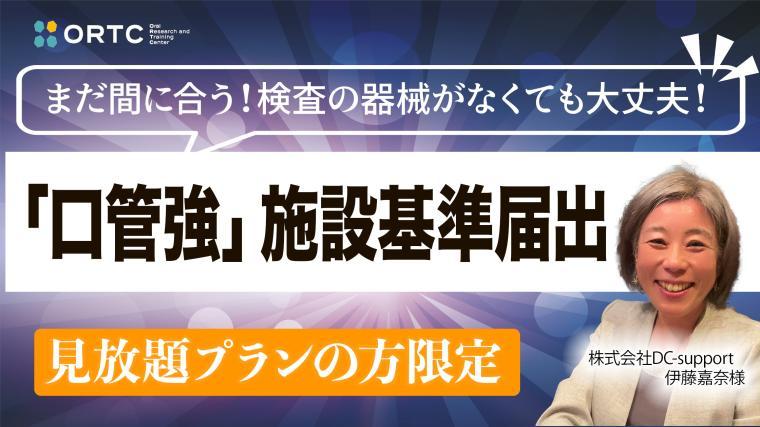口管強とは?
 なぜ今、「口管強」が必要なのか?
なぜ今、「口管強」が必要なのか?
2024年6月、歯科診療報酬の改定により「かかりつけ歯科医機能強化型診療所(か強診)」は、「口腔管理体制強化加算(口管強)」への名称変更されました。
これは、単なる名称変更ではなく、制度の本質そのものが変化した象徴でもあります。
「か強診」はこれまで、地域のかかりつけ歯科医としての役割を評価する制度でしたが、小児や障害者への評価が手薄であり、患者さんにとっても名称の分かりにくさが課題でした。
「口管強」はその点を見直し、乳幼児期から高齢期までのライフステージを通じた口腔管理と重症予防に軸足を置いた制度へ再構築されています。
つまり、「口腔管理体制強化加算」は、今後の歯科医療において、より包括的で、より質の高い医療提供を目指す医院にとって、極めて重要な制度です。
口管強認定取得の3つのメリット

本記事では、口腔管理体制強化加算認定で得る、患者さんにも医療従事者にも大きなメリットをわかりやすく説明します。
メリット①収益構造の強化と安定化
「口管強」認定を受けることで、従来の保険診療では得られなかった項目での点数加算が可能になります。
たとえば、歯周病の安定期治療(SPT)では長期管理加算120点※(厚生労働省「令和6年度診療報酬改定の概要」より)を算定可能。さらに、SPTの実施間隔も3ヶ月から1ヶ月ごとへ短縮され、算定機会も大幅に増加します。
これにより、以下のようなことが見込めます。
・定期的な来院につながる
・予防主体の継続的な医療が可能になる
・自費依存から脱却と保険収入の安定化が見込める
といった「収益の質的転換」が期待されます。
メリット②地域で選ばれる圧倒的な信頼性と差別化
「口管強」は、全国の歯科医院のうち認定率はわずか20%未満(※2025年時点での歯科関連業界の調査・報告による概算。正式な公的統計は今後の報告が待たれます)と言われており、取得には一定の基準や体制が求められます。
その認定自体が、地域住民に対する信頼の証であり、競合医院との差別化を図る大きな要因となります。
患者にとって、「口管強」認定医院とは、「制度的に認められた、より安全で質の高い医療が受けられる場所」という印象を与えることができ、医院ブランディングにもつながります。
メリット③スタッフの専門性向上とモチベーション活性化
「予防」や「口腔機能管理」など、これまで点数化されにくかった領域が明確に評価されるようになったことで、歯科衛生士やスタッフの専門性が「見える化」されます。
その結果、以下のようなことが期待されます。
・業務の意味や成果が実感できる
・モチベーションや責任感が向上
・チーム医療としての連携が強化される
つまり、「制度がスタッフの意識を変える」大きなきっかけとなるのです。
患者さんが「口管強」認定歯科医院で得られる特別な価値

口腔管理体制を強化することで、患者さんに届けられる4つの価値をご紹介します。
①予防ケアがもっと身近に(保険適用の拡大)
これまで自費の対応が多かったフッ化物歯面塗布が、月1回の保険適用内で実施できるようになります。また、SPT(歯周病安定期治療)も毎月実施可能になるため、予防的な来院のハードルが大きく下がります。
さらに、「お口ぽかん」や「飲み込みの苦手さ」など、小児期の口腔機能発達不全症、「むせやすい」「滑舌が悪い」といった高齢期の口腔機能低下症にも保険で対応可能となり、幅広いライフステージの患者さんに専門的なケアを提供できます。
②通院が難しくなっても安心(訪問診療の充実)
通院が困難な高齢者や障がい者の方でも、在宅や施設にて口腔ケアやリハビリを保険適用で受けられることが可能です。
地域包括ケアシステムとの連携が深まり、歯科が地域医療の中で果たす役割が一層重要になります。
③「もしも」の時にも安心な医療環境
「口管強」認定には、以下の緊急時対応設備が必須となります。
・AED(自動体外式除細動器)
・酸素供給装置、パルスオキシメーター
・歯科用吸引装置、血圧計、救急蘇生セット
さらに、地域の医療機関との連携体制も求められ、安全性が制度的に担保されています。これは、持病のある方やご高齢者の患者さんにとって、大きな安心材料となります。
④お口から始まる健康長寿(全身の健康への貢献)
継続的な口腔管理は、誤嚥性肺炎・認知症・脳梗塞・糖尿病といった全身疾患のリスクを抑え、健康寿命の延伸にも寄与します。
つまり、口腔を整えることは、生涯の健康を支える出発点でもあるのです。

懸念点とそのスマートな対応策とは?
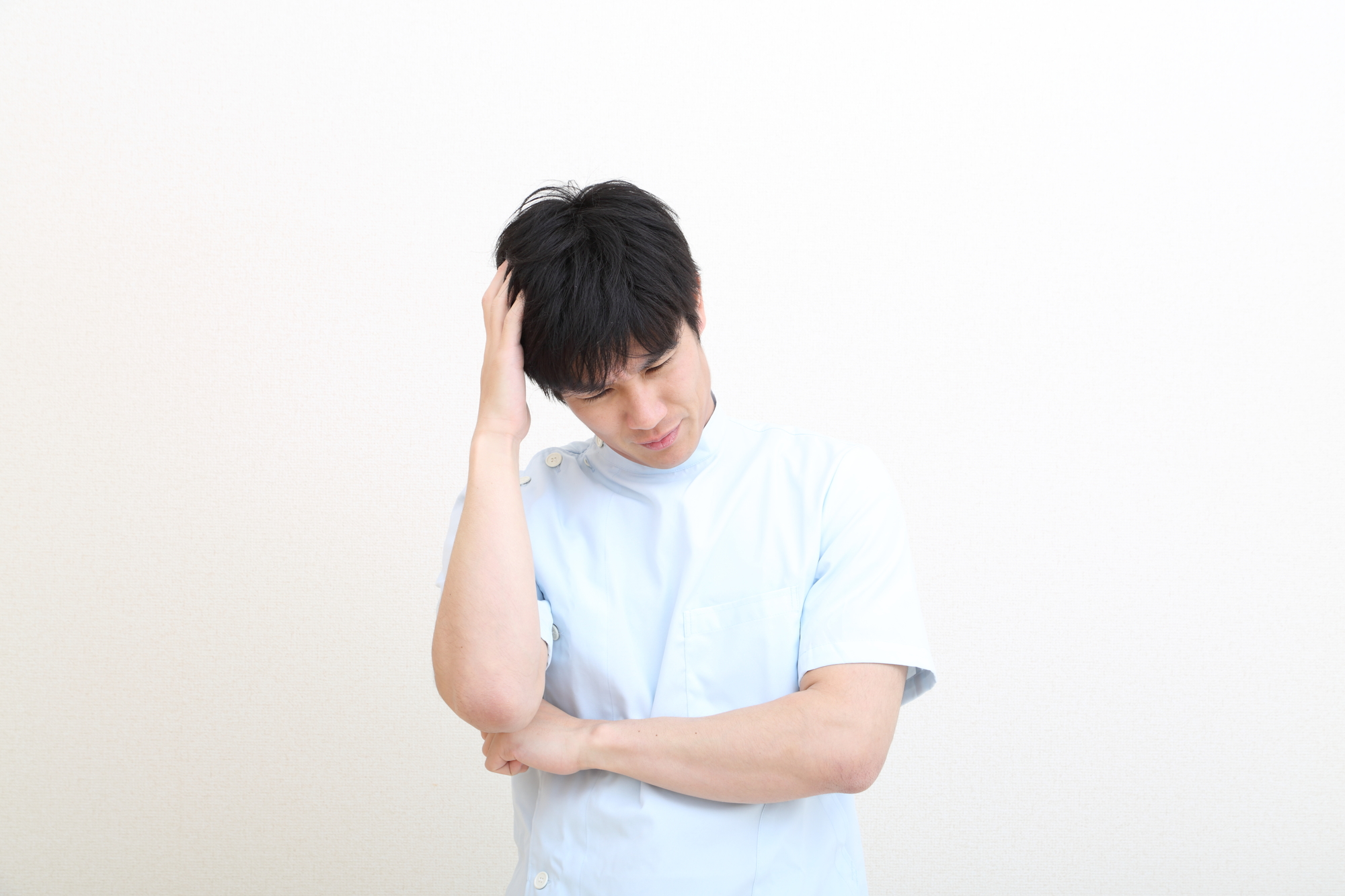
「口管強」加算によって、一部治療で患者さんの自己負担がやや増加する可能性があります。しかしこれは、提供する医療の質が高まっていることの裏返しです。
そこで重要なのが、
・ホームページや院内掲示でのわかりやすい案内
・カウンセリング時における丁寧な説明
「なぜ費用が変わるのか」「その分どんなケアが受けられるのか」を明確に伝えることで、患者さんの納得と信頼を得ることができます。
まとめ
「口管強」認定は、医院の未来を拓く戦略的な一手です。保険点数の加算にとどまらず、歯科医院の医療の質、経営の安定性、患者からの信頼を同時に高めるための、極めて重要な制度です。
収益構造の安定化、地域から選ばれるブランディング、スタッフの成長とチーム医療の活性化、地域医療・健康寿命への貢献など、こうした多方面にわたる波及効果が、医院経営にとって大きな意味を持ちます。
かかりつけ医として、地域のライフステージを支える存在となるために、ぜひ「口管強」の取得を、未来への賢明な投資として前向きにご検討ください。

よくある質問
Q1.口腔管理体制強化加算と、従来の口腔管理加算の違いはなんですか?
A.最大の違いは、医科との連携体制の強化と、地域包括ケアの一環としての評価が高まっている点です。従来の加算に比べて、歯科医師と歯科衛生士が継続的かつ計画的に、患者の状態に応じた口腔管理を実施し、さらに医療機関や施設と連携して情報共有を行っていることが求められます。
Q2.加算対象となる患者はどのような人ですか?
A.主に在宅や施設で療養している高齢者や障がい者が対象です。要介護認定を受けている方、また医科からの依頼がある場合が多く、医科歯科連携がより重視される傾向にあります。
Q3.届出や算定に必要な条件はなんですか?
A.主な条件は以下の通りです。
・医師・看護師等との連携体制の構築
・患者ごとの口腔管理計画の作成と実施
・歯科衛生士による訪問指導の体制
・医科、施設と定期的な情報共有
必要に応じて訪問歯科診療計画書の作成と同意取得も求められます。
Q4.スタッフの負担が増えるのでは?
A.一定の準備は必要ですが、役割分担を明確にすることで業務効率が向上するケースが多いです。例えば、訪問診療や連携報告は歯科医師が、計画的な口腔ケアや記録は歯科衛生士が担うことで、チーム医療としてスムーズに機能します。
Q5.具体的にどのような連携を求められるのですか?
A.例えば以下のような連携です。
・主治医やケアマネージャーとの連絡・情報提供
・訪問看護やリハビリ担当者との情報共有
・施設職員と連携して口腔衛生状態の継続的な管理
これらは「連携実績」として記録・報告しておくことが重要です。
Q6.今後、口腔管理体制強化加算はどうなると予測されますか?
A.超高齢社会が進む中で、「在宅医療」「多職種連携」「フレイル予防」に対応する歯科の役割はますます重要になります。よって、この加算の位置づけや評価は今後さらに高まる可能性が高いと考えられます。
歯科衛生士ライター 大久保
歯科医療の現場で役立つ実践的な知識を届けるORTC

ORTCは「笑顔の役に立つ」を理念に、歯科界の知識を共有する場を目指しています。歯科医療の現場で役立つ最新の知識と技術を提供することで、臨床と経営の両面からクリニックの成長を支援します。最先端の技術解説や経営戦略に特化した情報を集約し、歯科医療の現場での成果を最大化。自己成長を追求するためのコンテンツをぜひご活用ください。
無料会員登録
無料動画の視聴、有料動画のレンタルが可能です。歯科業界についてのオンライン・オフラインセミナーへの参加が可能となります。
ORTCPRIME
月額5500円で、 ORTC内のすべての動画を見放題に。臨床の現場に役立つ最新の技術解説や、歯科医院経営の成功戦略を網羅した特別コンテンツをご利用いただけます。 歯科業界の方へ効率的に知識を深めていただける内容です。
ORTC動画一覧
ORTCセミナー一覧
まずは無料会員登録
こちらのリンクより会員登録ページへお進みください。
会員登録はこちら
ORTCPRIMEへのアップグレードも簡単!
登録後は「マイページ」から、ORTCPRIMEにいつでもアップグレード可能です。
 こちらの動画もおすすめです
こちらの動画もおすすめです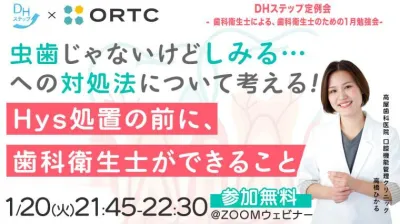 虫歯じゃないけどしみる…への対処法について考える Hys処置の前に、歯科衛生士ができること
虫歯じゃないけどしみる…への対処法について考える Hys処置の前に、歯科衛生士ができること 「TBIが変われば患者が変わる」 自費TBI成功マインド
「TBIが変われば患者が変わる」 自費TBI成功マインド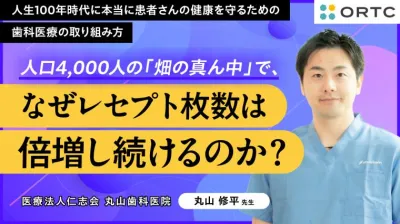 人口4,000人の「畑の真ん中」で、なぜレセプト枚数は倍増し続けるのか?
人口4,000人の「畑の真ん中」で、なぜレセプト枚数は倍増し続けるのか?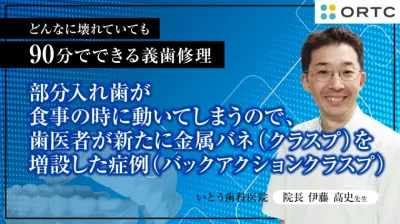 部分入れ歯が食事の時に動いてしまうので、歯医者が新たに金属バネ(クラスプ)を増設した症例(バックアクションクラスプ)
部分入れ歯が食事の時に動いてしまうので、歯医者が新たに金属バネ(クラスプ)を増設した症例(バックアクションクラスプ)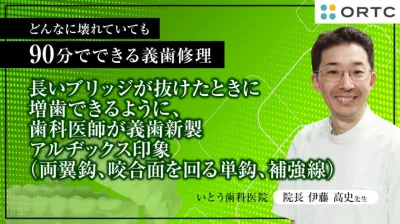 長いブリッジが抜けたときに増歯できるように、歯科医師が義歯新製 アルヂックス印象(両翼鈎、咬合面を回る単鈎、補強線)
長いブリッジが抜けたときに増歯できるように、歯科医師が義歯新製 アルヂックス印象(両翼鈎、咬合面を回る単鈎、補強線)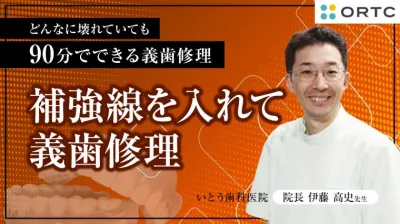 補強線を入れて義歯修理
補強線を入れて義歯修理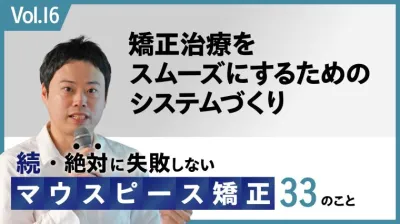 続・ 絶対に失敗しないMP矯正33の事 システムづくり
続・ 絶対に失敗しないMP矯正33の事 システムづくり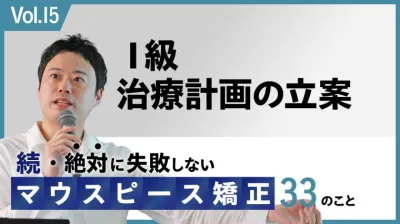 続・ 絶対に失敗しないMP矯正33の事 Ⅰ級 治療計画の立案
続・ 絶対に失敗しないMP矯正33の事 Ⅰ級 治療計画の立案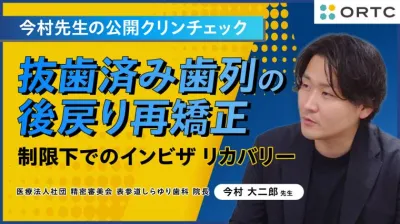 抜歯済み歯列の後戻り再矯正:制限下でのインビザ リカバリー
抜歯済み歯列の後戻り再矯正:制限下でのインビザ リカバリー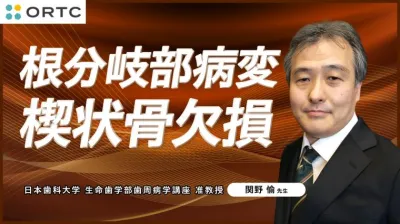 根分岐部病変 楔状骨欠損
根分岐部病変 楔状骨欠損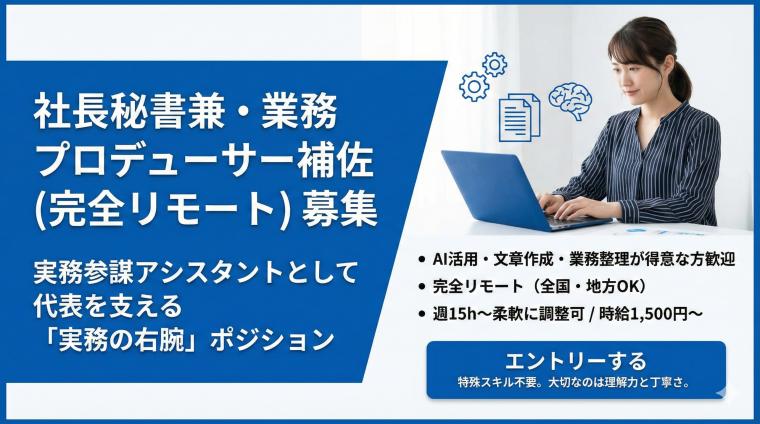
 なぜ今、「口管強」が必要なのか?
なぜ今、「口管強」が必要なのか?