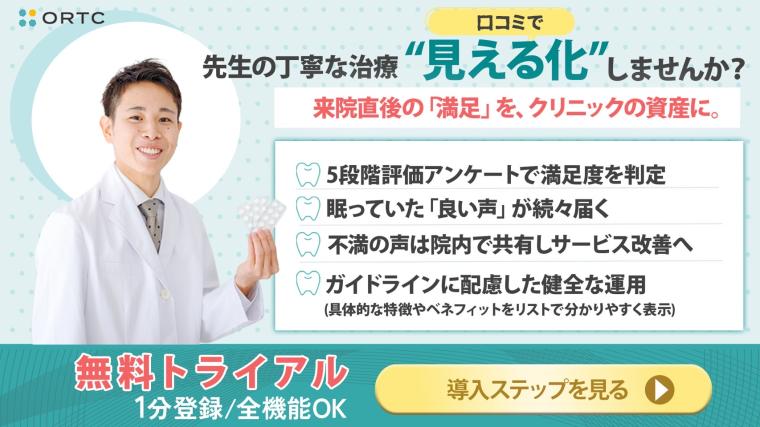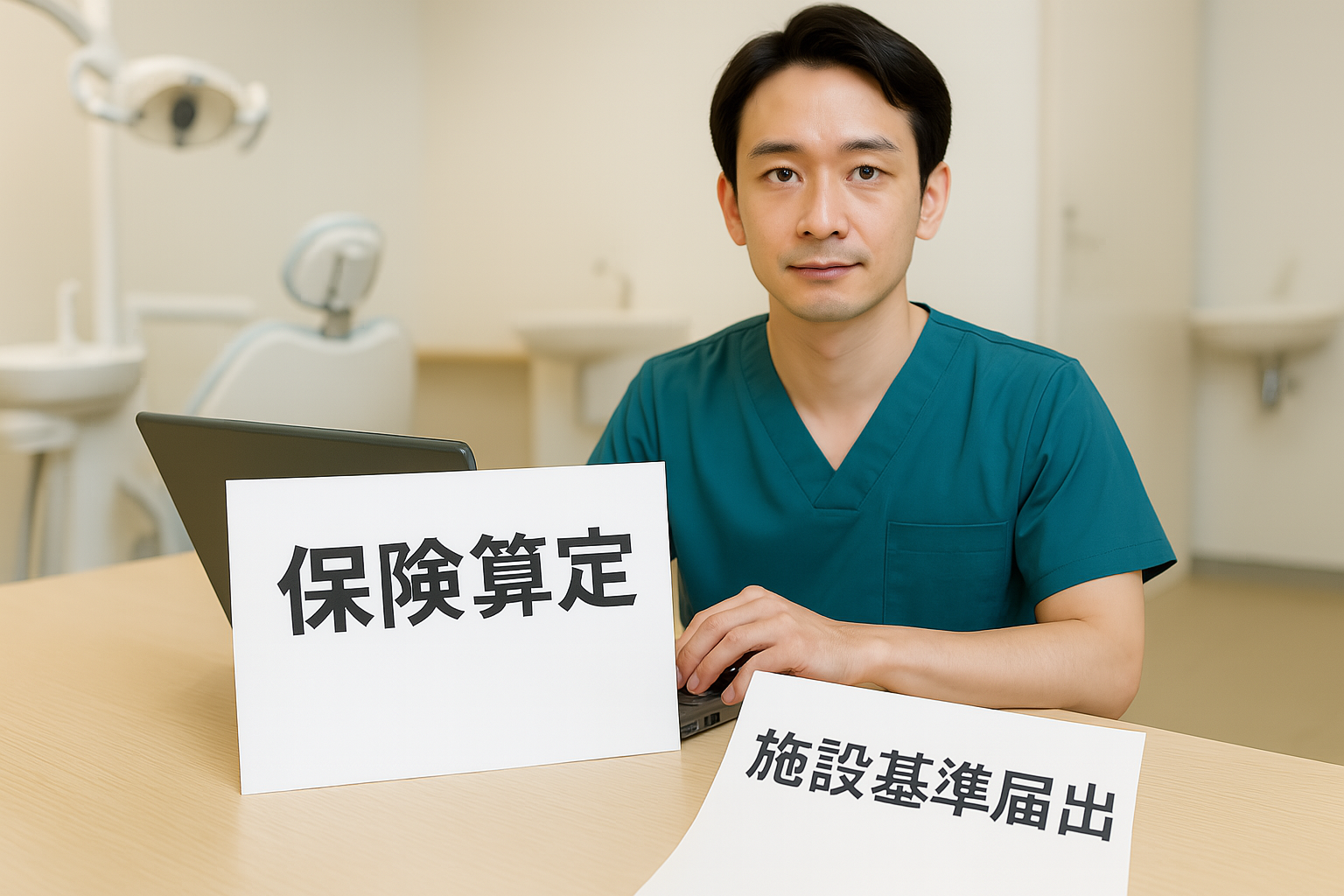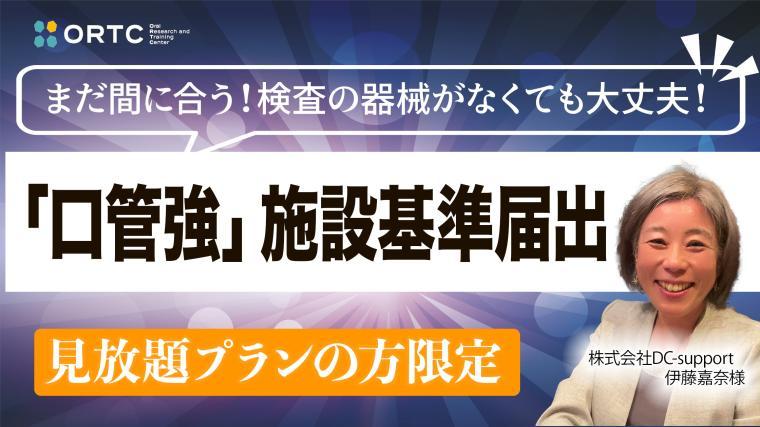先生のクリニックにも、こんなお子さんはいませんか?
診療中も常に口がぽかんと開いていたり、咀嚼がうまくできず食事に時間がかかったり…ただの“癖”ではなく「口腔機能発達不全症」のサインかもしれません。
見過ごすことで、歯列不正や顎の成長障害、さらには睡眠障害や学習意欲の低下といった全身への影響につながることもあります。
食生活の変化や社会環境の影響により、この疾患は急速に注目されるようになりました。
2024年の診療報酬改定では保険算定も拡充され、歯科医院が早期発見・指導に関与することがより重要になっています。
ORTCでは「口腔機能発達不全症」を深掘りするセミナーを開催しております。
こちらから、お申し込みください。

本記事では、その前提となる「口腔機能発達不全症」の全体像と実践ポイントをわかりやすく整理します。
第1章|そもそも「口腔機能発達不全症」とは?

口腔機能発達不全症とは、子どもの「食べる」「話す」「その他の機能(呼吸・姿勢・習癖など)」が、年齢相応に発達していない状態を指します。
厚生労働省では2018年より保険病名として認められ、病名ではなく“発達の遅れ”としての医療介入対象であることが大きな特徴です。
食生活や育児環境の変化(やわらかい食事、個食・孤食の増加)、早期のデジタル接触による口腔筋活動の低下などにより、近年は“見た目”では健康そうでも、機能が育っていない子どもが増加しています。
「ポカン口(口唇閉鎖不全)」「滑舌が悪い(構音障害)」「よく噛まずに飲み込む」といった状態は、“癖”として見過ごされがちです。
しかし、将来的には歯列不正・顎顔面の発育障害・睡眠障害・学習意欲の低下などに発展するリスクがあります。
日本歯科医学会が提示する15の評価項目は、以下の3群に分類され、複合的に現れることが多いです。
① 食べる機能の未発達
・哺乳・離乳の遅れ
・咀嚼が弱く丸呑み傾向
・食事に時間がかかる、むせる
② 話す機能の未発達
・構音が不明瞭(特にサ行・ラ行)
・滑舌が悪く、発語が遅い印象
・話すときに舌が飛び出す
③ その他の機能(呼吸・姿勢・習癖)
・口呼吸、いびき、低位舌
・指しゃぶり、歯ぎしりなどの口腔習癖
・猫背、筋緊張低下などの身体的特徴
参考:日本歯科医学会「口腔機能発達不全症に関する基本的な考え方」(2024年3月改訂)PDF
口腔機能発達不全症は、医科よりも歯科が最も早期に気づきやすい領域です。
定期検診やTBIの中で「口が閉じない」「舌が挙がらない」「発音が気になる」など、医科が見逃しやすい“微細な異変”に気づけるのが歯科の特権ではないでしょうか。
歯科衛生士が評価・指導の担い手となることで、MFTや口腔機能支援といった新たな専門性の習得につながり、医院としての差別化や保険収益の向上にも直結します。
口腔機能発達不全症を放置すると?歯列不正・睡眠障害など全身への影響も
「個性」や「一時的な癖」に思えるこれらの症状も、複数の要因が重なることで口腔機能発達不全症として保険算定の対象となります。
問題を放置することで、以下のようなリスクを引き起こす可能性があります。
第2章|明日からできる!口腔機能発達不全症の早期発見5つのポイント

「口腔機能発達不全症かもしれない」と気づく第一歩は、日常診療の中にあります。
「舌の機能不全、口呼吸、低位舌、食事に時間がかかる」それらはすべて、早期発見のチェックリストに該当する重要な所見です。
歯科医師・歯科衛生士がすぐに実践できる「口腔機能発達不全症の早期発見ポイント」を5つに整理していきます。
診断基準に沿った観察方法や問診のコツを押さえることで、保護者への説明や保険算定にもつながる“臨床力”が身につくでしょう。
「ポカン口」や猫背は要注意|姿勢・表情から見る口腔機能発達不全症の初期サイン
待合室で口がぽかんと開いていたり、猫背で座っている子どもはいませんか?
「ポカン口」は、口腔機能発達不全症の初期サインになります。
口が閉じられない原因には、唇の筋力低下や口呼吸の習慣、鼻詰まりなどの呼吸障害が隠れていることもあります。
猫背や前傾姿勢といった身体のバランスの崩れは、顎の発達や咬合(かみ合わせ)にも悪影響を及ぼす可能性も考えられるでしょう。
姿勢と口元の状態は密接に関連しているため、歯科医院の待合室や診療中の何気ない様子にも注意を向けておくことが大切です。
こうした見た目の些細な変化が、全身の機能低下と関連するケースもあるため、まずは姿勢と表情から注意深く観察しましょう。
発音が不明瞭な子どもに注目|口腔機能発達不全症の会話チェックポイント
「サ行」や「タ行」が聞き取りづらい子どもは、構音機能に問題を抱えている可能性があります。
舌の可動域や口唇の筋機能の未発達が原因となることが多く、滑舌の悪さは見逃せないチェックポイントです。
診療時のちょっとした会話の中で、音の不明瞭さや言い直しの多さに気づいたら、口腔機能評価の第一歩として記録しておきましょう。
低位舌・扁桃肥大・V字口蓋は要観察|診療中に確認すべき口腔内のチェックリスト
診療時に観察したいのは、舌の位置、口蓋の形、そして扁桃の肥大です。
舌が常に下にある「低位舌」は、正常な嚥下や発音に影響します。また、V字型の狭い口蓋や扁桃の肥大があると、呼吸や咀嚼の障害に直結するでしょう。
こうした所見は、解剖的特徴ではなく、機能面のトラブルを示す重要なサインです。
見逃さず、記録に残すことが口腔機能発達不全症の早期発見につながります。
いびき・指しゃぶり・食事時間もヒントに|問診で見抜く口腔機能発達不全症の兆候
問診では、保護者から得られる日常情報がヒントになります。
・寝ているときにいびきをかく
・食事に30分以上かかる
・指しゃぶりが3歳を過ぎても続いている
このようなポイントは、口腔機能発達不全症の兆候として見逃せません。
保護者への質問項目をテンプレート化しておくことで、再現性のあるスクリーニングが可能になります。
特別な機器は不要|あいうべ体操や水飲みテストで行うスクリーニング法
口腔機能評価に、必ずしも特別な機器は必要ありません。
「あいうべ体操」で口唇や舌の動きを確認や、水飲みテストで嚥下機能を観察などで、十分なスクリーニングが可能です。
診療室でも簡単にできるこれらの方法をマニュアルに組み込むことで、見逃しを防ぎ、早期介入のきっかけを作ることができます。
第3章|評価から指導へ。歯科医院での具体的なアプローチ法

専門的な器具がなくても、明日からできる対応はたくさんあります。
「診断・評価→トレーニング→チーム連携」の流れに沿って、歯科医院での具体的なアプローチを整理します。
診断はここから!口腔機能発達不全症の評価と検査の流れ
「口腔機能発達不全症かもしれない」と気づいたら、次に行うのが評価と診断です。
問診や視診からスタートし、必要に応じて検査へと進みます。
評価には、厚労省が定めた15項目を活用したチェックリストや、「口腔機能発達不全症評価マニュアル」などの公的資料が参考になります。
舌圧や咀嚼力の測定など、特別な機器を使う検査もあります。導入初期は「あいうべ体操」「水飲みテスト」など簡便な方法から始めていきましょう。
子どもの口腔機能を“数値化”し、継続的に記録・管理していくことが重要です。その積み重ねが、保険算定にも直結していきます。
歯科衛生士が行うMFT|口腔機能トレーニングの実践例
評価の後は、改善に向けたアプローチが必要となります。
低位舌の子どもには「舌のポッピング」「舌挙上トレーニング」、口唇の筋力が弱い子には「ボタンプル」や「リップトレーニング」が効果的です。
咀嚼や嚥下のトレーニングでは、左右でバランスよく噛ませる意識づけや、飲み込む際の姿勢・タイミングへのアドバイスもポイントになります。
MFTは一度で効果が出るものではなく、継続とフォローが欠かせません。
歯科衛生士が伴走者として子どもと保護者に寄り添いながら、実践しやすい環境を整えることが成果につながります。
チームで支える!院内での役割分担と連携のポイント
口腔機能発達不全症への対応は、歯科医師一人の業務ではありません。
院内全体でのチーム連携がカギになります。
歯科医師:診断と治療計画の立案
歯科衛生士:評価・記録・トレーニング
歯科助手:記録補助や保護者対応、物品の準備
受付や保育士スタッフ:待合室での姿勢や会話の様子を観察・共有
こうした役割分担と情報共有を仕組み化することで、スムーズな運用と質の高い支援が可能になります。
チーム全員が「子どもの成長を支える」という共通認識を持つことが、継続的な取り組みの土台になるのです。
ここでご紹介したのは、すぐに実践できるトレーニングの一例です。
より体系的な評価・指導法については、ORTCの夏季セミナーで動画や資料をもとに詳しく解説します。
現場で即実践できるスキルアップを目指すなら、ぜひご参加ください!

第4章|歯科医院の強みになる!保険算定と施設基準届出の手引き
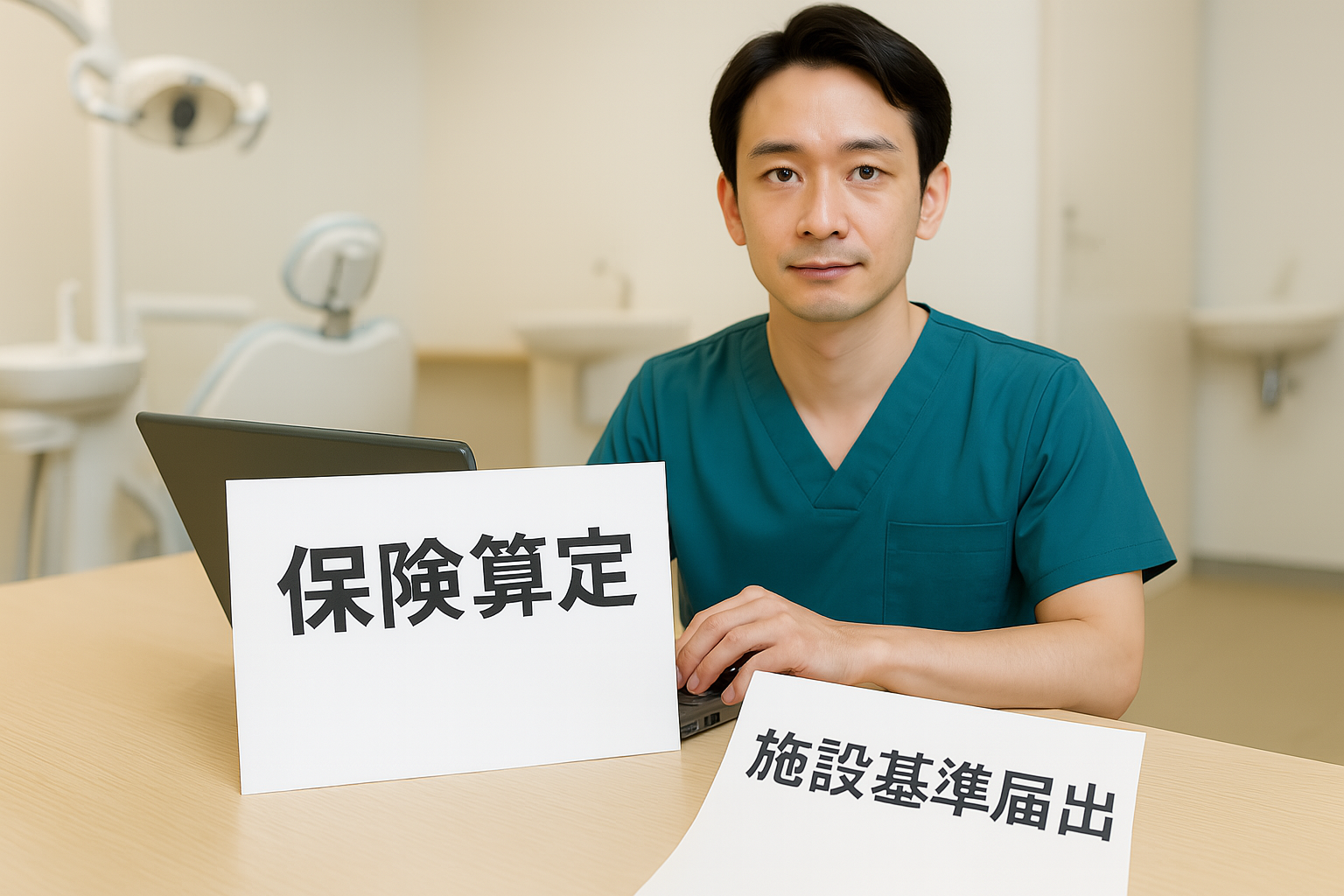
「算定したいけど、何から始めればいいのか分からない」そんな歯科医院に向けて、経営面のメリットから届出の具体的ステップまでを、わかりやすく解説します。
口腔機能発達不全症は、歯科医院の専門性と収益性を両立できる領域です。実践すれば確実に差がつきます。
基本的なステップと書類のポイントさえ押さえれば、届出は十分可能です。
口腔機能発達不全症の保険算定がもたらす3つのメリット
「口腔機能発達不全症」の算定は、単なる診療報酬の加算ではなく、医院全体にとって多くのメリットをもたらします。
① 経営の安定化
継続的な評価・管理・指導が必要な疾患であるため、患者の定着率向上と定期的な来院サイクルの確保につながります。
② 医院のブランディング
子どもの成長支援に取り組む姿勢が「地域の子育て支援拠点」としての評価にもつながり、口コミ・紹介も増加しやすくなります。
③ スタッフのやりがい
歯科衛生士が主体となって評価・トレーニングを担当することで、専門性の向上やキャリア形成にもつながり、歯科医院の職場定着率アップも期待できます。
初めてでも安心!施設基準届出のステップと必要書類
口腔機能発達不全症を保険算定するためには、施設基準の届出が必須となります。
歯科医院でもスムーズに進められるよう、以下のステップを押さえておきましょう。
① 設備・体制の確認
舌圧計などの測定機器は必須ではなく、視診や問診・体操チェックでも対応可能な点がポイントです。
② 研修の受講
歯科医師・歯科衛生士は、厚生労働省が認める研修(例:日本歯科医学会連合認定研修等)を受講し、修了証を取得・保管する必要があります。
③ 届出様式の準備
「施設基準届出書」「構造設備に関する報告書」などの様式をダウンロードし、記入ミスや漏れがないよう注意しましょう。
書類は各地域の地方厚生(支)局へ郵送もしくは窓口提出となります。
届出後の流れと注意点|審査・更新・実績管理まで
届出が受理された後も、継続的な対応が求められます。
審査支払機関によるレセプト確認時には、記載内容の整合性が見られます。
診療録には、評価項目や指導内容を明確に残すことが大切です。
実績管理として、算定件数や評価データは、施設基準の継続要件として管理・保存が求められます。
定期的な確認と帳票整備を怠らないようにしましょう。
複雑に感じることも、正しい知識と体制づくりで十分対応可能です。
初回だけでなく、継続的な運用体制が医院の信頼性につながります。
まとめ
口腔機能発達不全症への対応は、もはや一部の小児歯科医院だけのテーマではありません。
「気づく・伝える・関わる」3ステップが、今後すべての歯科医療現場に求められる知識と実践です。
歯科衛生士として、口腔機能への介入は、スケーリングやTBIに留まらない新しい専門スキルとして、歯科衛生士自身のステップアップにつながると感じています。
MFTや評価技術を習得すれば、歯科医院の診療幅も広がり、患者満足度の向上や保険算定にもつながることで、歯科医院にも返ってくる部分が大きいのではないでしょうか。
仕事をしていくうえで「口腔機能を診て指導できる人材」として、ステップアップできるのも魅力の1つとなります。
早期に介入し、子どもの健やかな発育を支援することは、私たち医療従事者にとってやりがいある使命であり、医院の強みにもつながります。
そのために必要な『知識を行動へ、行動を成果へ』そのための最短ルートをこの夏、手にしませんか?
【4回シリーズ 本当にやばい!口腔機能発達不全症】
開催日時
第1回:2025年7月7日(月)20:00〜20:30
第2回:2025年7月14日(月)20:00〜20:30
第3回:2025年8月4日(月)20:00〜20:30
第4回:2025年8月6日(水)20:00〜20:30
登壇者:堀尾 麻衣先生(THDC合同会社 代表)
主催:デンタルシステムズ株式会社

今こそ、子どもの未来を変える一歩を踏み出しましょう。
Q&A
Q1. 口腔機能発達不全症は、何歳から診断・対応が必要ですか?
A1. 基本的には1歳半〜3歳頃から着目すべきとされます。特に「離乳の進行が遅い」「「ポカン口(口唇閉鎖不全)」「滑舌が悪い(構音障害)」などの症状が見られる場合は、年齢に関係なく早期のチェックと対応が望まれます。保険算定の対象年齢は原則18歳未満です。
Q2. チェックリストはどこで入手できますか?医院で独自に作っても良いのでしょうか?
A2. 厚生労働省の「口腔機能発達不全症対応マニュアル」や日本歯科医学会などで公開されているチェックリストが基本です。独自の補足項目を加えるのは可能ですが、保険算定時は公的資料に準拠した評価項目が必要です。
Q3. 舌圧測定器や専用機器がないと、保険算定はできませんか?
A3. 舌圧測定器などの機器は必須ではありません。 問診・視診・スクリーニングテスト(例:あいうべ体操、咀嚼観察)でも評価・指導は可能です。ただし、届出施設としての信頼性や今後の対応範囲を広げるために導入を検討する価値はあります。
Q4. 歯科衛生士が中心となって行えるトレーニングには何がありますか?
A4. 舌の動きや筋力を高めるポッピング、舌挙上訓練、口唇閉鎖力を高めるボタンプル、リップトレなどがあります。また、咀嚼・嚥下トレーニングや保護者への指導も、衛生士が主導できる重要な領域です。
Q5. 指しゃぶりや口呼吸はどの程度、問題と捉えるべきですか?
A5. 指しゃぶり・口呼吸は歯列不正や低位舌、口腔乾燥の原因になることがあり、習慣の持続期間と年齢によって介入が必要か判断します。就学前に続いている場合は、MFTや生活指導を早期に行うべきです。
Q6. 届出や算定で気をつける落とし穴はありますか?
A6. 最も多いのは、評価項目の記録漏れや、研修受講の証明書未提出です。
厚生労働省の通知では、
①継続的な指導管理の要件:再評価・定期記録があるか
②診療録の個別記載が必須:判定・指導内容が症例ごとに記録されているか
③研修受講の証明書保管:スタッフが所定研修を受けているか証拠が揃っているか
書類や診療記録、研修証明書の整備を徹底すれば、算定・届出でのリスクを大幅に減らせます。チェックしておきましょう。
歯科衛生士 原田未祐
歯科医療の現場で役立つ実践的な知識を届けるORTC

ORTCは「笑顔の役に立つ」を理念に、歯科界の知識を共有する場を目指しています。歯科医療の現場で役立つ最新の知識と技術を提供することで、臨床と経営の両面からクリニックの成長を支援します。最先端の技術解説や経営戦略に特化した情報を集約し、歯科医療の現場での成果を最大化。自己成長を追求するためのコンテンツをぜひご活用ください。
無料会員登録
無料動画の視聴、有料動画のレンタルが可能です。歯科業界についてのオンライン・オフラインセミナーへの参加が可能となります。
ORTCPRIME
月額5500円で、 ORTC内のすべての動画を見放題に。臨床の現場に役立つ最新の技術解説や、歯科医院経営の成功戦略を網羅した特別コンテンツをご利用いただけます。 歯科業界の方へ効率的に知識を深めていただける内容です。
ORTC動画一覧
ORTCセミナー一覧
まずは無料会員登録
こちらのリンクより会員登録ページへお進みください。
会員登録はこちら
ORTCPRIMEへのアップグレードも簡単!
登録後は「マイページ」から、ORTCPRIMEにいつでもアップグレード可能です。
 こちらの動画もおすすめです
こちらの動画もおすすめです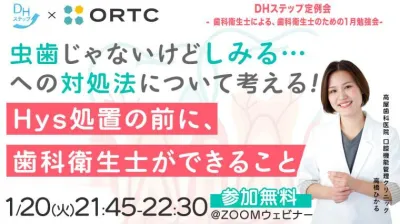 虫歯じゃないけどしみる…への対処法について考える Hys処置の前に、歯科衛生士ができること
虫歯じゃないけどしみる…への対処法について考える Hys処置の前に、歯科衛生士ができること 「TBIが変われば患者が変わる」 自費TBI成功マインド
「TBIが変われば患者が変わる」 自費TBI成功マインド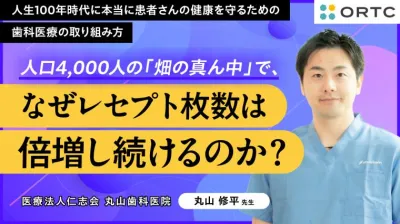 人口4,000人の「畑の真ん中」で、なぜレセプト枚数は倍増し続けるのか?
人口4,000人の「畑の真ん中」で、なぜレセプト枚数は倍増し続けるのか?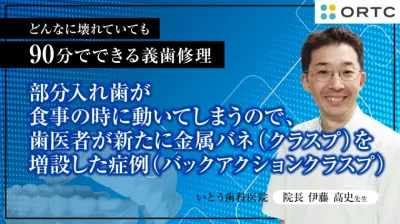 部分入れ歯が食事の時に動いてしまうので、歯医者が新たに金属バネ(クラスプ)を増設した症例(バックアクションクラスプ)
部分入れ歯が食事の時に動いてしまうので、歯医者が新たに金属バネ(クラスプ)を増設した症例(バックアクションクラスプ)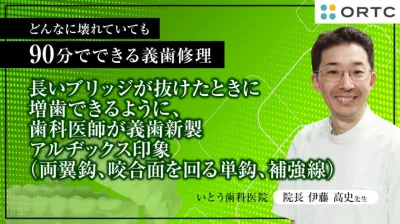 長いブリッジが抜けたときに増歯できるように、歯科医師が義歯新製 アルヂックス印象(両翼鈎、咬合面を回る単鈎、補強線)
長いブリッジが抜けたときに増歯できるように、歯科医師が義歯新製 アルヂックス印象(両翼鈎、咬合面を回る単鈎、補強線)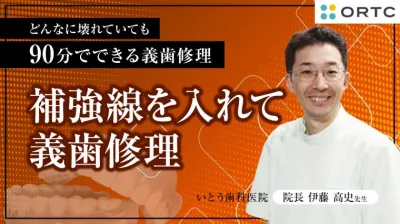 補強線を入れて義歯修理
補強線を入れて義歯修理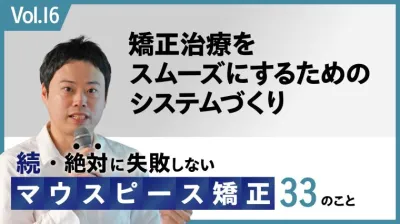 続・ 絶対に失敗しないMP矯正33の事 システムづくり
続・ 絶対に失敗しないMP矯正33の事 システムづくり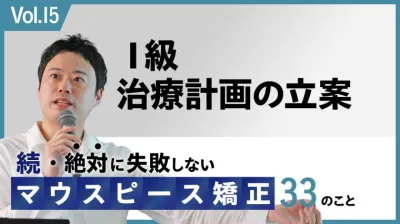 続・ 絶対に失敗しないMP矯正33の事 Ⅰ級 治療計画の立案
続・ 絶対に失敗しないMP矯正33の事 Ⅰ級 治療計画の立案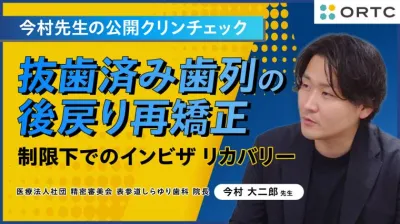 抜歯済み歯列の後戻り再矯正:制限下でのインビザ リカバリー
抜歯済み歯列の後戻り再矯正:制限下でのインビザ リカバリー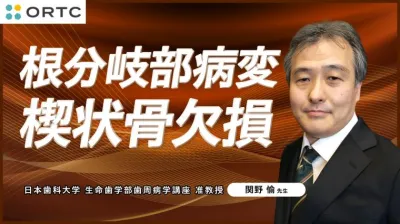 根分岐部病変 楔状骨欠損
根分岐部病変 楔状骨欠損