こんな方におすすめ
下顎前突矯正治療に苦手意識を持つ歯科医師
インビザラインにおける抜歯・非抜歯の診断基準を学びたい方
契約率を高め、症例数を増やしたい矯正歯科医・一般歯科医
動画の紹介
マウスピース矯正(インビザライン)において、多くの歯科医師が治療をためらう下顎前突(クラス3)症例に自信を持って対応するための治療計画立案戦略を解説します。
骨格性か歯槽性かの的確な診断の重要性を強調し、クリンチェック作業に入る前に必須となる審査のポイントを紹介。
不可逆的な処置(抜歯、外科手術など)を最小限に抑え、バイトランプ付与、遠心移動、顎間ゴム使用、IPRといった可逆的な治療の選択肢から優先順位を決定する論理的な思考プロセスを伝授。
これにより、患者の満足度と契約率を高め、自院の症例数増加に直結する実践的なノウハウが詰まっています。
動画内容
クラス3不正咬合の診断と治療計画立案の原則 🧠
下顎前突(クラス3不正咬合、俗にいう受け口)は、オーバージェットがマイナスを示す状態ですが、その多くはマウスピース矯正(インビザライン)での改善が可能であると論じています。重要なのは、症例が骨格性によるものか、歯槽性によるものかを正確に診断することです。
骨格的な問題がない場合、外科手術や抜歯といった不可逆的な処置を避けるべきであり、安易に専門医に紹介するのではなく、まず自院での治療の可能性を徹底的に検討する機会を提言しています。
不可逆的処置を避けたシミュレーション活用法 🚀
治療計画立案の第一原則として、「不可逆的な要素が少ない方から考える」という方針が示されます。これは、患者の心理的負担を低減し、契約率を高めるための重要な戦略です。。
具体的には、バイトランプの付与、遠心移動、側方拡大、顎間ゴムの使用(ジャンプアクションのシミュレーション)、FMCやインレー除去によるスペース確保、そしてIPR(歯間削合)といった可逆的または低侵襲な処置から順に、クリンチェック上でシミュレーションを行う手順を推奨しています。
特に、顎間ゴムによる下顎の後退(ジャンプ)の可能性をシミュレーションで確認することが、クラス3治療の鍵となります。
重度症例からの逆算思考で診断精度を向上 🔄
クリンチェック作成時のテクニックとして、重度の処置(例:上下顎4番抜歯)を先に設定し、そこから改善度を確認し、次に軽度の処置へと段階的に引き下げていく「逆算思考」の重要性を説きます。
これは、下顎4番抜歯や外科手術が必要な真の骨格性不正咬合なのか、それともIPRや遠心移動といった非抜歯処置で十分に対応できる歯槽性不正咬合なのかを効率的に見極めるための診断プロセスです。
この診断の精度と、不可逆的な処置を回避できたことによる患者の満足度(特に顔貌の変化)の高さが、口コミや紹介患者の増加につながると強調し、積極的なクラス3治療への挑戦を促しています。

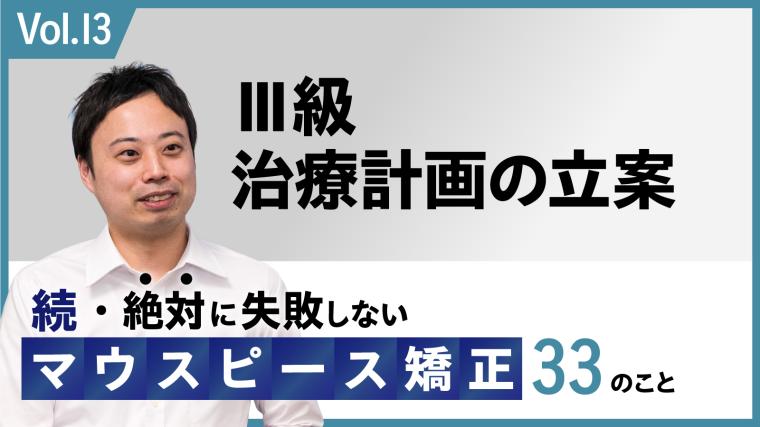
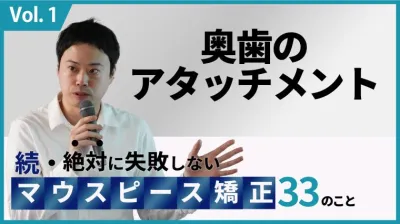
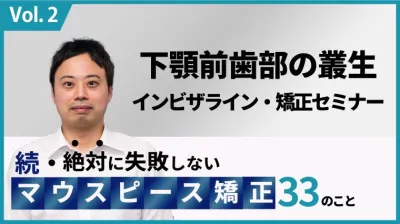
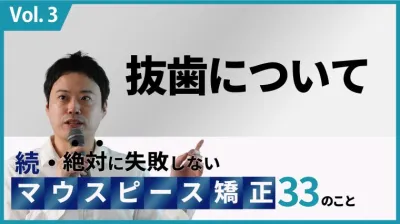
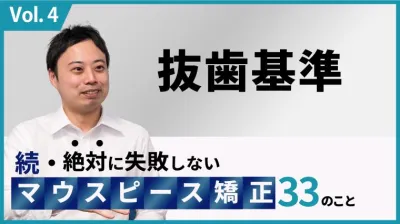
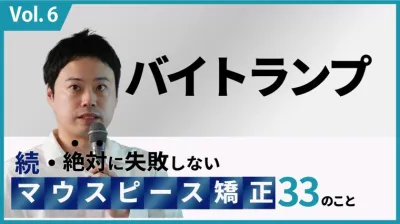
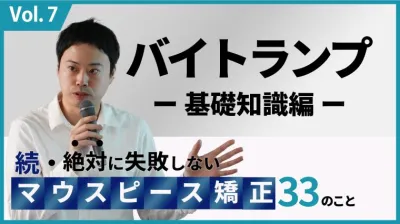
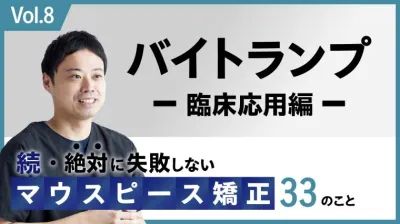
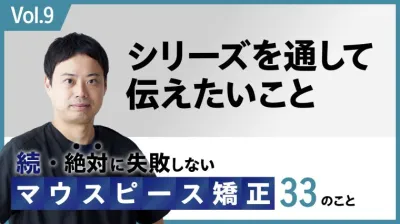
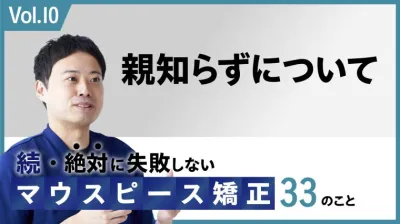
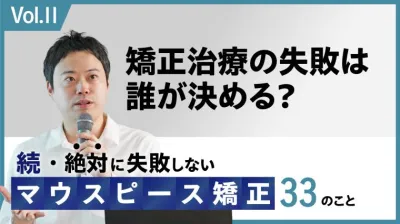
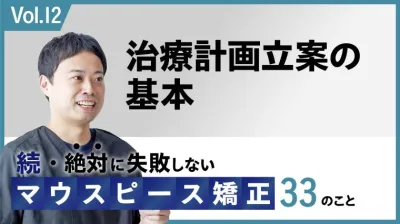
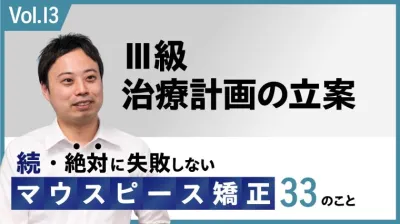
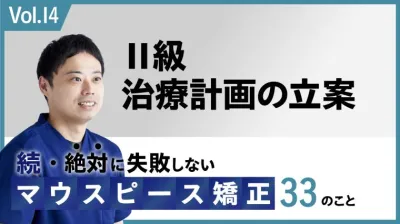




 見放題プラン PRIME会員(お勧め)
見放題プラン PRIME会員(お勧め)
 見放題対象の全作品が視聴可能
見放題対象の全作品が視聴可能 見放題プランに登録せず1本だけ視聴する
見放題プランに登録せず1本だけ視聴する