こんな方におすすめ
・一般診療と矯正治療を両立したい開業医
・短期かつ確実なアライナー矯正の習得を目指す歯科医師
・訴訟リスク回避の知識を深めたいトリートメントコーディネーター
動画の紹介
日常臨床の合間にマウスピース矯正に取り組む一般歯科医師向けに、失敗を回避する現実的な治療戦略を解説します。 非現実的な長期治療計画(99枚など)を避け、予測実現性の高い治療を行うためのポイントを紹介。
一般歯科医師は抜歯、CR充填、義歯など多岐にわたる診療を担っており、矯正治療に100%のウェイトをかけることは困難です。 本動画では、最短の治療期間で患者の満足度を高め、訴訟リスクを最小限に抑えるための基礎知識として、日本矯正歯科学会(日矯)のガイドライン遵守の重要性を強調。
また、トータルフィー制で陥りやすいコミュニケーション不足の解消法についても言及しています。安全かつ確実なアライナー矯正を目指す先生方に必見の内容です。
動画内容
一般歯科医師のための「失敗しないマウスピース矯正」戦略
本シリーズでは、根管治療、歯周外科、補綴といった一般診療とアライナー矯正を両立させる歯科医師が、失敗しないための具体的な指針を提供します。矯正治療に全精力を注ぐ専門医とは異なり、多忙な日常臨床の中で、いかに現実的かつ安全に治療を完遂させるかが焦点です。
非現実的な長期治療計画の排除
アライナー枚数が99枚といった極端に長い治療計画(約2年)は、非現実的であると強く警鐘を鳴らしています。2年間という期間は、患者の生活環境やライフステージ(結婚、進学など)が大きく変化するため、インビザラインの治療予測自体が困難になります。 そのため、基本的な考え方として、「少ない枚数で治療を終える」ことが、予測実現性を高め、成功への近道であると提唱。枚数が少ないクリンチェックこそが美しい治療計画であり、一般歯科医師が目指すべきゴールであるとしています。
訴訟リスクの最小化と法的側面
矯正治療はインプラント治療と比べても、患者が支払う金額が高額(80万〜100万円程度)になりやすいため、訴訟・裁判になるリスクが最も高い治療の一つです。この訴訟リスクを回避するための最も簡単な対策として、以下の2点を挙げています。
1. 日本矯正歯科学会(日矯)ガイドラインの遵守
裁判になった際、治療の適否を判断する際の基準となるのが、日本矯正歯科学会のガイドラインです。最低限、このガイドラインに沿った治療計画と術式を行うことで、医療紛争時の法的防御を強固にすることができます。高得点の完璧な治療(100点)を目指すよりも、まずは最低限の安全基準(60点)をクリアすることを推奨しています。
2. コミュニケーション不足の解消
トータルフィー制を採用する多くのクリニックで陥りやすいのが、患者とのコミュニケーション不足です。契約時のみ歯科医師が担当し、その後の治療の大半を歯科衛生士が担うケースでは、患者のフラストレーションが溜まり、訴訟のリスクにつながります。これを防ぐため、歯科医師だけでなく、歯科衛生士、歯科技工士、トリートメントコーディネーターなど、チーム医療として連携し、情報共有のネットワークを患者に提示することが重要であると説いています。
専門医の長期症例と現実的な臨床の切り分け
長期間(5年、10年)を要するような難症例の勉強会は、日常臨床で多忙な一般歯科医師にとっては無意味であると断言。「完璧よりも安全」、「確実な治療」を追求し、最短の治療期間で患者の満足度が高いうちに終了させる、現実的なゴール設定が求められます。一般診療と経営を両立する中で、矯正治療にかけられるウェイトは限られるため、リスクを最小限に抑え、確実に結果を出すことに集中すべきであるという強いメッセージを伝えています。

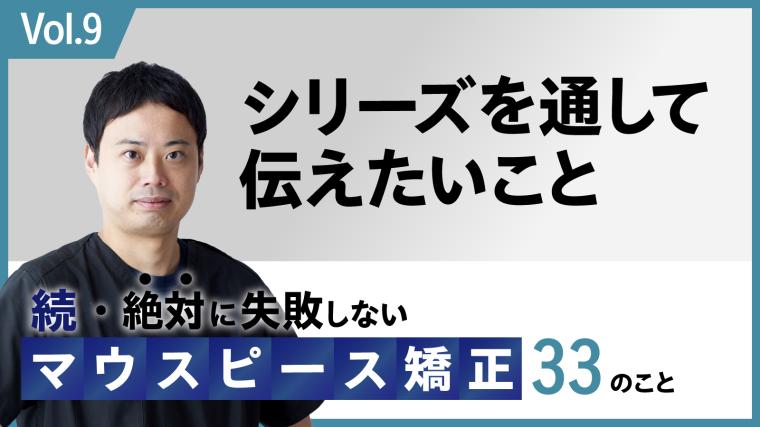
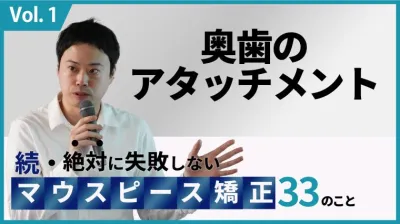
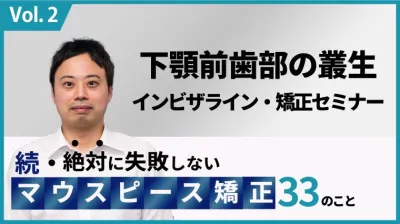
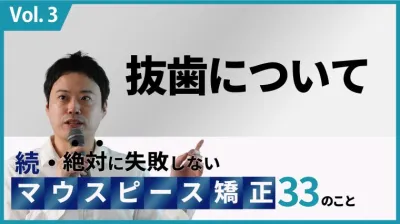
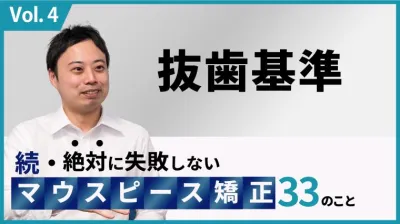
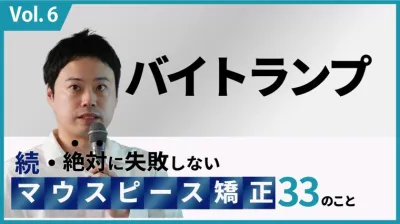
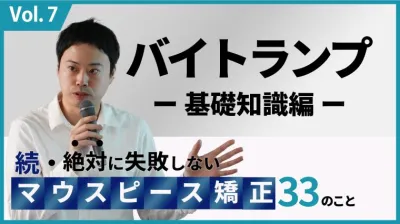
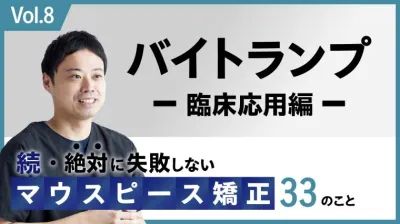
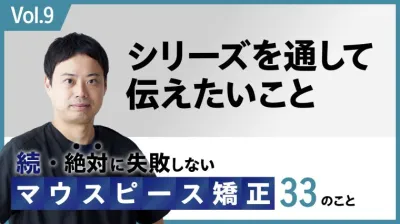
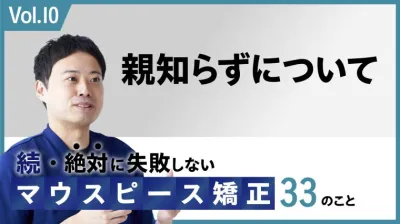
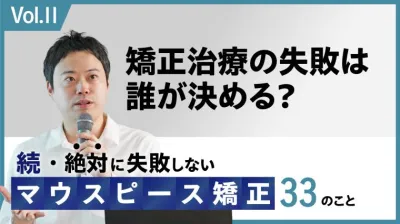
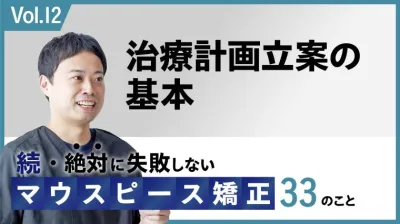
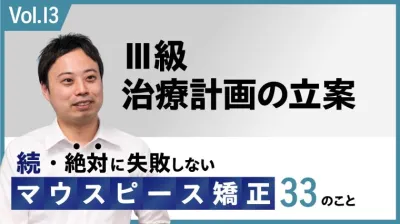
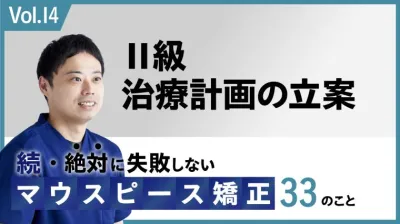




 ORTCプライム 月額 5,500円 (税込)
ORTCプライム 月額 5,500円 (税込)
 対象セミナーが見放題
対象セミナーが見放題