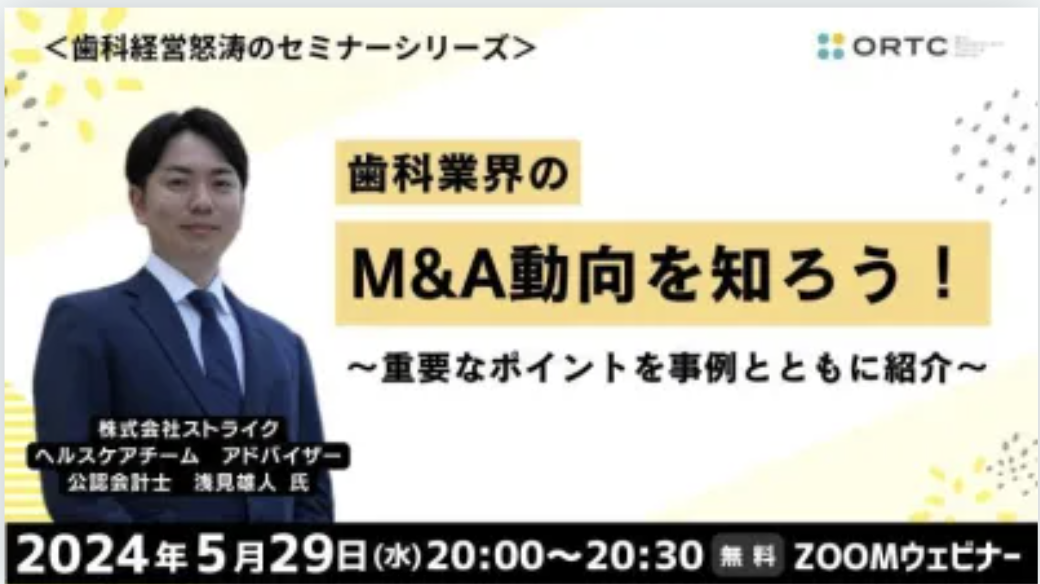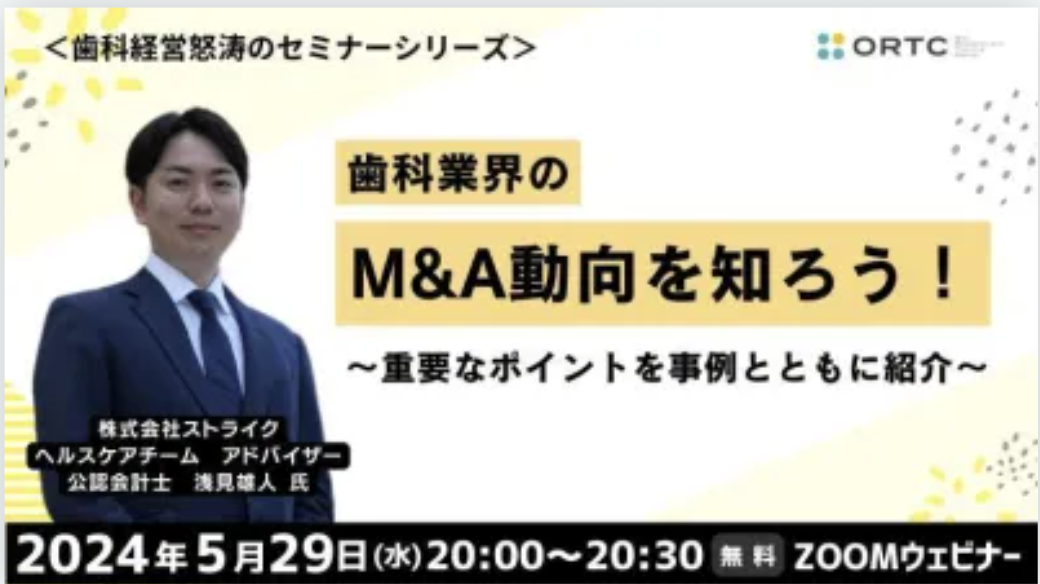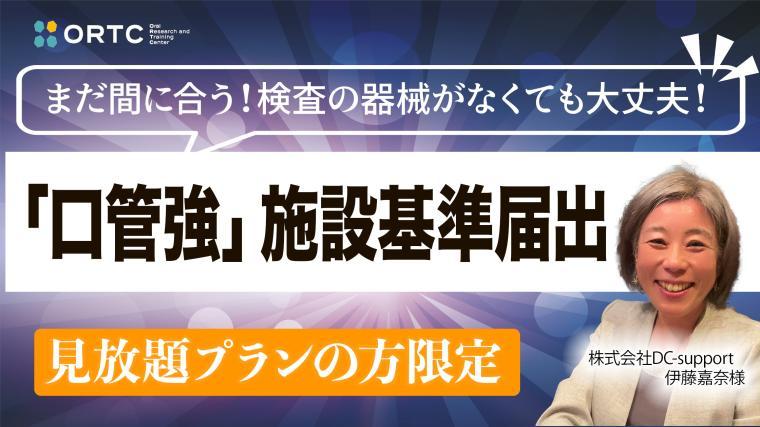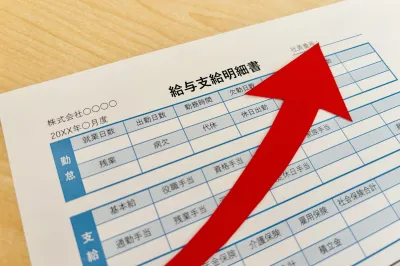「後継者が決まらない」「閉院か親族承継しか道がない」50代の歯科経営者に立ちはだかる問題ではないでしょうか。不安に感じている部分はあるのだが、実際のイメージがつかない先生に、今回は「M&A」についてお話をしていきます。
今回は、歯科医院の後継者問題の実態データを示し、第三者承継=M&Aの基本、価格の“相場”の考え方、よくある類型、譲渡側のメリットと不安解消、進め方までを要点整理します。決断は急がず、まずは情報収集から。医院を守る選択肢を一緒に見極めましょう。
歯科医院の後継者問題のいま

歯科診療所数の微減と中高年層に厚い年齢構成が確認できます。
施設数の動向では、厚生労働省「令和5(2023)年 医療施設(静態・動態)調査の概況」によると、歯科診療所は66,818施設で前年より937施設減でした。最新の月次公表でも、医療施設動態調査(令和7年3月末概数)で歯科診療所が24施設減とされています。これらは、地域単位での継続的な診療体制の維持に配慮が要ることを示唆します。(※1)
一方、年齢構成は中高年層が中心です。厚労省「令和4(2022)年 医師・歯科医師・薬剤師統計」では、医療施設に従事する歯科医師の年齢分布で「60〜69歳」が23.1%で最多、次いで「50〜59歳」が22.0%。また同統計の表では、診療所に従事する歯科医師の平均年齢は54.8歳と整理されています。近い将来に承継ニーズの波が高まることが統計上から読み取れます。(※2)
さらに、施設の開設・廃止・休止・再開は毎年(および毎月)の公的統計として公開されており、後継者不在の検討にあたっては、自院の年齢構成・地域の施設動態という“事実”をまず把握することが出発点になります。第三者承継(M&A)を含む選択肢の整理は、中小企業庁の事業承継ガイドラインでも推奨されている公的な考え方です。
①院長側の事情:家族の職業選択の多様化、勤務医のキャリア志向、人材不足などが内的に承継を難化。
②経営環境の逆風:物価・人件費等の上昇や制度・地域事情の影響下で退出が増える月が生じ、地域医療の継続性リスクが高まる。
③年齢分布の現実:中高年層が厚く、承継のピークはこれから本格化。
したがって、「閉院か親族承継か」の二択に縛られず、第三者承継(M&A)という“医院を守る選択肢”を早期から視野に入れる発想が合理的です。中小企業庁の事業承継ガイドラインでも、親族承継・従業員承継・第三者承継(M&A)を並列の選択肢として整理し、早期の準備を推奨しています。
参照
※1:厚生労働省(令和5(2023)年 医療施設(静態・動態)調査・病院報告の概況 )https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/iryosd/23/dl/11gaikyo05.pdf?utm_source=chatgpt.com
※2:厚生労働省(令和4(2022)年 医師・歯科医師・薬剤師統計の概況)https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/ishi/22/dl/R04_1gaikyo.pdf
M&Aの基本|“第三者承継”をやさしく解説

「M&A=どこかに“買われる”」そう身構える必要はありません。歯科医院の現場でのM&Aは、患者・スタッフ・医院の理念を傷つけずに“バトンを渡す”ための設計です。医療分野特有の留意点(許認可・自治体運用・契約の連続性)を押さえて、「自院ではどれが現実的か」をすぐ判断できる土台をつくっていきましょう。
ORCTでも、M&Aについてのセミナー動画があります。まずは、「M&Aって何?」というところを知るところから、始めてみませんか?
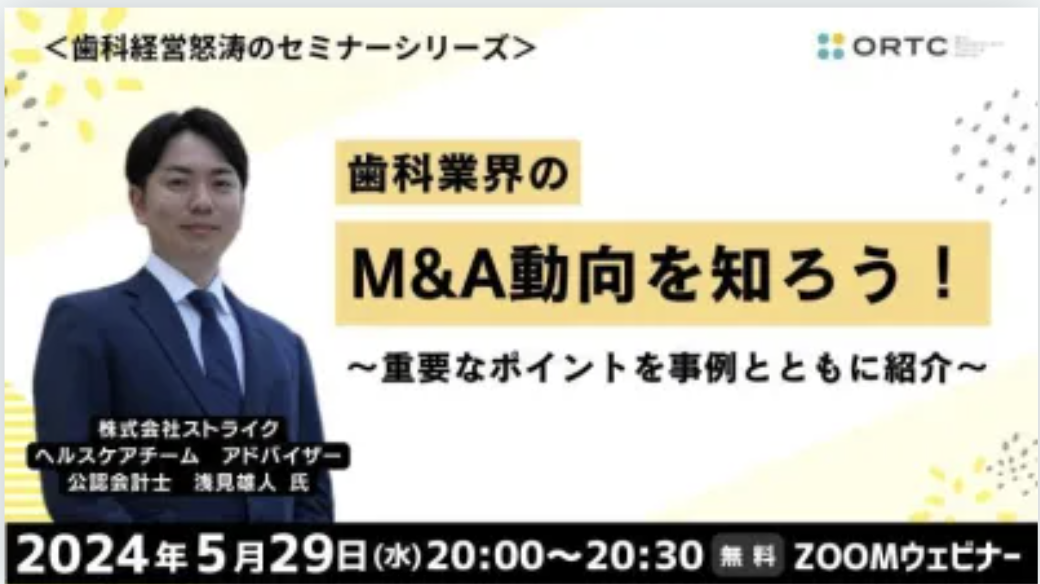
歯科業界のM&A動向を知ろう~重要なポイントを事例とともに紹介~
講師 浅見雄人(株式会社ストライク)
M&A=「買収」ではなく承継
歯科医院のM&Aは、相手に飲み込まれる出来事ではなく、「守りたいものを契約に刻んで、計画的に“渡す”プロセス」です。
・理念や診療方針
・医院名の扱い
・スタッフの雇用継続
・価格や自費の運用ルール
・どれくらい並走して引き継ぐか
こうした条件を先に言語化し、相性の合う相手と合意していくほど、移行後の離職や離患を防げます。大切なのは、数字だけで相手を選ばず、理念の相性とPMI(統合運用)を実行できる体制を見極めることが必要です。スタッフへの説明から院内掲示、患者さんへの個別案内まで周知の順番と文面を決めておけば、「買われた」ではなく「継いだ」と胸を張れる承継になります。
主なスキーム(取引の設計図)
スキーム(取引の設計図)は大きく、①株式(持分)譲渡、②事業譲渡、③吸収合併の三つに整理できます。
現状を崩さず連続性を重視するなら、法人の持分を移す株式譲渡が適しています。一方で不要資産を切り離したい、契約を選び直したいといった事情があるなら、選別移転が可能な事業譲渡が候補になります。多院展開の標準化やバックオフィスの一体化を急ぐ場面では、吸収合併が威力を発揮します。
いずれも会計・税務・許認可への影響や、賃貸・リース・保守といった契約の承継可否が変わります。早い段階で専門家と前提をそろえ、「自院にとって現実的で、リスクの少ない道筋」を描くことが肝心です。
医療分野特有の留意点
医療のM&Aは、一般事業と違って法規・届出・個人情報・運用手順まで多面的に整える必要があります。
保険医療機関の指定や各種施設基準、放射線や感染対策の記録、医療廃棄物や機器保守の契約など、許認可と運用の両面を事前に点検し、自治体ごとの運用差は所管に照会して段取りを前倒しにします。
患者情報は、秘密保持(NDA)を前提にしても個票開示を避け、匿名・集計でのKPI共有(匿名・集計データの提供)を原則とし、電子カルテやレセコンの契約・権限移管は計画的に切り替えます。賃貸借やサプライ、リース契約の承継同意を抜け漏れなく整え、医療広告ガイドラインに沿ってHPや看板、マップ情報の表示変更を段階的に実施します。
これらを落とし込み、「人(雇用・評価・教育)→患者(予約・説明・価格)→オペレーション(在庫・購買・IT)」の順に静かに統合していけば、医院の“日常”を崩さずに次の体制へ橋渡しできます。
歯科医院M&Aのよくあるケース

M&Aは、規模・診療体制・地域性・借入/賃貸条件・人員構成で変わります。
ここからは、現場で頻度の高い4類型を取り上げ、狙い(何を守るか)→向き不向き→注意点→“契約で先に決めること/PMI(統合計画)でやること”の順で要点を押さえましょう。
患者構成(外来/訪問)・スタッフ年齢/定着・法人化の有無・多院展開の意向を手元メモに照らしてみてください。自院がどの型に最も近いかが、数分で見えてきます。
①地方×地方——患者・スタッフを活かす承継
地域密着の強みは「顔なじみの継続」。院長交代は段階的な周知+並走期間で不安を最小化します。診療時間・価格・予約ルールは当面据え置きが基本となります。賃貸契約・機器保守・紹介状対応も引継計画に組み込み、退職・離患の“谷”を作らないのが肝です。
②医療法人への吸収——バックオフィス強化と理念条項
購買・人事・教育・レセ/予約など法人機能の底上げで運営が安定します。反面、“色が変わる”不安に配慮し、理念条項・医院名の扱い・投資方針をLOI(基本合意)段階で文書化をしましょう。統合は、会計/人事/IT→診療体制→ブランディングの順で段階導入が安全です。
③訪問歯科のM&A——ルート/人材/稼働率が価値ドライバー
価値のコアは、利用者ルート・人材体制・曜日別稼働により変わります。ケアマネ・施設との関係性は無形資産なので、同行引継ぎと予定表の共有で摩擦を防止しましょう。車両・機材・衛生管理、医療/介護保険の請求運用までチェックリスト化します。
④多院再編——ユニット稼働・導線再設計で“混まないのに回る”
近接院の役割分担(一般/小児/自費/訪問)を再設計し、予約導線とユニット稼働を最適化します。在庫・価格テーブル・説明資料を統一し、どの院でも同じ体験を作ります。ブランドは屋号統一 or サブブランドを選び、広告も一本化していきましょう。
譲渡側のメリット

「譲渡=お金の話だけ」じゃありません。理念の継続・スタッフの雇用維持・患者さんの通院継続・段階的リタイアまで、設計次第で“医院を守る”価値が増えます。不安になる部分は、情報漏洩・条件の食い違い・価格の下振れ・風評・税務や借入の扱いに集約されます。
この不安は、準備をすることでコントロールが可能です。NDA(秘密保持)→LOI(基本合意)→DD(デューデリ)→PMI(統合計画)の順で確認をしていきましょう。
譲渡の最大の価値は、医院の“日常”を切らさずに次へ渡せることです。
契約に理念や診療方針、医院名の扱い、スタッフの雇用継続、価格運用のルール、引継ぎ期間の役割まで織り込めば、離職や離患を最小化できます。加えて、財務・人事・主要契約・KPI(匿名・集計データの提供)で新患数、リコール率、ユニット稼働などの整理して提示できる医院は、再現性ある収益力が伝わりやすく、条件交渉でも“守りたいもの”を優先事項として位置づけやすくなります。
院長個人にとっては、非常勤や相談役を挟む段階的リタイアという選択が現実的になり、地域にとっては患者と雇用を守る承継として評価されやすいのもメリットです。
要するに、譲渡は「手放す」ではなく、契約とPMI(統合運用)で価値を“残す”行為になります。
居抜き開業とM&Aの違い

同じ「引き継ぐ」でも、居抜きは箱(内装・設備)中心、M&Aは医院そのもの(患者・スタッフ・評判・運営)を承継する手段。何を守りたいのかで選択は変わります。
比較軸 | 居抜き開業(物件承継) | M&A(第三者承継) |
|---|
承継の対象 | 内装・ユニット等の設備中心 | 患者・スタッフ ブランド・運営一式 |
|---|
連続性 | 新装扱いになりがち 患者継続はゼロから | 通院・雇用・運営の 連続性が高い |
|---|
引き継げる無形資産 | 原則なし (評判・紹介・診療データはなし) | 評判・紹介ルート・診療データ等を設計次第で承継 |
主な交渉軸 | 家賃、原状、設備状態、鍵渡し時期 | 理念・医院名・雇用条件 価格・投資方針・引継期間 |
スピード感 | 早い (手続きは比較的シンプル) | 中〜長 (買い手が医院の実態を 確認、審査や契約設計が必要) |
成功の条件 | 立地/賃料/導線、設備の状態 | PMI(統合計画)の質 周知設計、相手選定 |
主なリスク | 設備劣化、集患の立ち上がり遅延 | 条件不一致、情報管理 引継計画の甘さ |
向くケース | 「場所・賃料・箱」を重視 新ブランドで勝負 | 「患者・人・理念」を守りたい 医院を“まるごと”継ぎたい |
“医院を守る”がゴールならM&A、 “場所から作る”がゴールなら居抜きというようなイメージです。
進め方の8ステップ

ゴールは「継ぐ設計」を落とし込むことになります。ざっと、流れを知り、1つの選択肢にしておきましょう。不安の多くは、情報漏洩・条件の食い違い・価格の下振れ・風評・税務や借入の取り扱いに集約されます。しっかり情報を入れ、準備をすることで、対策をしていくことが可能です。
参考までに、以下の8ステップを順に進めれば、条件ブレや情報漏洩の不安を最小化できます。
①意向整理(守るべき条件の言語化)
まず「何を守るか」をまとめていきましょう。例:理念・医院名の扱い/スタッフ雇用継続/患者周知の方法/価格より優先する条件は何かを挙げていきます。ここが後工程の判断基準になります。
②初回相談・秘密保持(NDA)
候補探しや打診の前にNDAを締結しておきます。
③相手探索・一次打診
地域・診療方針・規模が合う先へ打診を行います。買い手の「理念相性」と「PMI力」を早めに見極めていきましょう。
④面談・条件すり合わせ
“医院を守る条件”を金額と同じテーブルに乗せ、文書メモをその場で残す運用が安全になります。
⑤基本合意(LOI)
独占交渉期間、価格レンジ、主要条件(理念条項/医院名/雇用継続/投資計画)をLOIに明記します。ここが“約束の骨格”です。後戻りを防ぎます。
⑥デューデリジェンス(DD)
財務・税務・法務・人事、そして医療特有の論点(保険指定、レセ/査定、機器・放射線、感染対策、広告規制)を確認していきます。事前に資料を整えておくほど短期化できます。
⑦最終契約・クロージング
表明保証・誓約、価格・支払方法、引継期間の役割、周知計画(院内掲示・個別案内・紹介状)、IT/アカウント移管、賃貸・保守契約の承継などを確定をしていきます。
⑧PMI(統合計画)
人(雇用・評価・教育)/患者(予約・説明・価格)/オペ(在庫・購買・IT)の順に混乱が起こらない設計をしましょう。
期間は案件規模や地域で前後しますが、「意向整理→LOI」までを急ぎ過ぎないほうが、結果的に全体は早く、きれいに進みます。
まとめ
後継者未定が当たり前になりつつある今、歯科診療所の微減傾向と中高年に厚い年齢分布という公的データが示すのは、承継ニーズの波が確実に近づいているという現実です。だからこそ「閉院か親族承継か」の二択に縛られず、第三者承継=M&Aを“買収”ではなく「理念・患者・スタッフを守って次へ渡す設計」として捉え直すことが要点になります。
歯科衛生士の立場から思うのは、これまで閉院する歯科医院のお手伝いをしてきた中で、掲示を貼った日から、患者さんに「寂しい」「どこに通えばいいの?」と何度も声をかけられたことがあります。スタッフ側も同じで、雇用や担当患者さんの行き先が見えず、不安な空気になっていました。
だからこそ、第三者承継=M&Aを「買収」ではなく、患者・スタッフ・医院の理念を傷つけずに“日常”を次へ渡す設計として捉え直す価値があると思っています。
居抜きが「箱」の承継であるのに対し、M&Aは「医院そのもの」を承継する手段です。何を守りたいのかを明確にすれば、進むべき道は自ずと定まります。
M&Aは「価格交渉」より前段の設計と合意形成に時間がかかるため、最初の一歩は情報収集です。
ORTCには、業界動向と進め方を学べるM&A関連の動画セミナーをご用意しています。
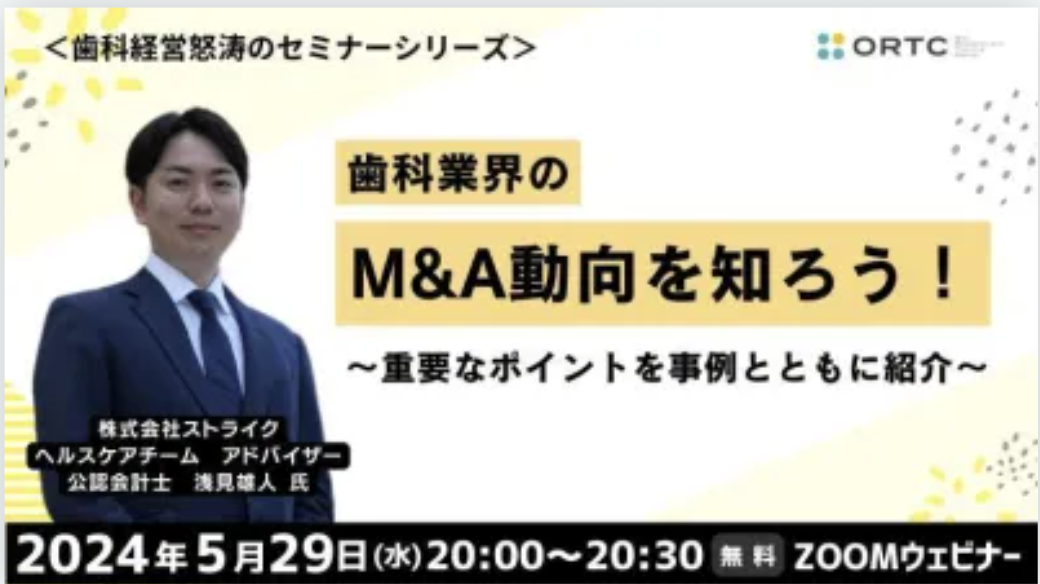
歯科業界のM&A動向を知ろう~重要なポイントを事例とともに紹介~
講師 浅見雄人(株式会社ストライク)
これからの歯科医院を考えるきっかけにしてください。
Q&A
Q1:医院名・診療方針は変わる?
A1:変えるかどうかは合意次第です。LOI(基本合意)や最終契約に「理念条項」「医院名の扱い」を明記すれば、原則は現状維持も可能となります。移行後に段階的な変更を予定する場合も、時期・範囲・周知方法まで先に決めておくと混乱を避けられます。
Q2:スタッフ雇用は継続される?
A2: 多くの案件で雇用継続を前提に設計しますが、自動ではありません。継続雇用・処遇・評価の枠組みを契約に落とし、説明会→個別面談→書面確認の順で行っていきます。
Q3:借入が残っていても譲渡できる?
A3: 可能性はありますが、金融機関の同意要否を早めに確認するのが安全です。
Q4:「相場」はどこまで参考にすれば良い?
A4:目安にはなりますが、鵜呑みは禁物です。価格は収益力(継続性)に加え、患者基盤・スタッフ定着・評判・立地・契約条件・設備更新状況などの個別要因で決まります。まずは、自院データを整えた上で、価格の決まり方を理解し、専門家に当てはめてもらうのが近道です。
Q5:居抜きと最大の違いはなんですか?
A5: 居抜き=箱(内装・設備)中心の承継、M&A=医院そのもの(患者・スタッフ・ブランド・運営)の承継です。「何を守りたいか」を先に決めると、選ぶべき手段が自然に定まります。
歯科衛生士ライター 原田
歯科医療の現場で役立つ実践的な知識を届けるORTC

ORTCは「笑顔の役に立つ」を理念に、歯科界の知識を共有する場を目指しています。歯科医療の現場で役立つ最新の知識と技術を提供することで、臨床と経営の両面からクリニックの成長を支援します。最先端の技術解説や経営戦略に特化した情報を集約し、歯科医療の現場での成果を最大化。自己成長を追求するためのコンテンツをぜひご活用ください。
無料会員登録
無料動画の視聴、有料動画のレンタルが可能です。歯科業界についてのオンライン・オフラインセミナーへの参加が可能となります。
ORTCPRIME
月額5500円で、 ORTC内のすべての動画を見放題に。臨床の現場に役立つ最新の技術解説や、歯科医院経営の成功戦略を網羅した特別コンテンツをご利用いただけます。 歯科業界の方へ効率的に知識を深めていただける内容です。
ORTC動画一覧
ORTCセミナー一覧
まずは無料会員登録
こちらのリンクより会員登録ページへお進みください。
会員登録はこちら
ORTCPRIMEへのアップグレードも簡単!
登録後は「マイページ」から、ORTCPRIMEにいつでもアップグレード可能です。
 こちらの動画もおすすめです
こちらの動画もおすすめです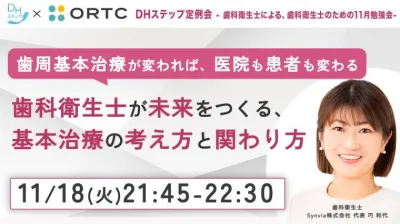 歯周基本治療が変われば、医院も患者も変わる 歯科衛生士が未来をつくる、基本治療の考え方と関わり方
歯周基本治療が変われば、医院も患者も変わる 歯科衛生士が未来をつくる、基本治療の考え方と関わり方 歯科衛生士の専門性を資産に変える!安定サロン経営
歯科衛生士の専門性を資産に変える!安定サロン経営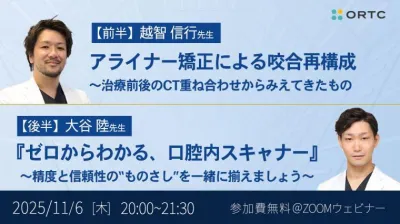 アライナー矯正による咬合再構成 〜治療前後のCT重ね合わせからみえてきたもの/『ゼロからわかる、口腔内スキャナー』 ~精度と信頼性の“ものさし”を一緒に揃えましょう~
アライナー矯正による咬合再構成 〜治療前後のCT重ね合わせからみえてきたもの/『ゼロからわかる、口腔内スキャナー』 ~精度と信頼性の“ものさし”を一緒に揃えましょう~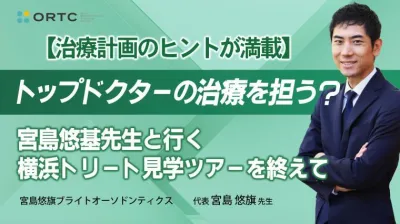 【治療計画のヒントが満載】トップドクターの治療を担う?宮島悠基先生と行く横浜トリート見学ツアーを終えて
【治療計画のヒントが満載】トップドクターの治療を担う?宮島悠基先生と行く横浜トリート見学ツアーを終えて 歯科医師の「高すぎる所得税住民税」を限りなく0円に!
歯科医師の「高すぎる所得税住民税」を限りなく0円に! 継承医院の新患数を爆増させるには? 継承前に行う患者数、スタッフ数を上げる取り組みを徹底公開
継承医院の新患数を爆増させるには? 継承前に行う患者数、スタッフ数を上げる取り組みを徹底公開 医院経営と投資に共通する成功の法則 ― 信頼と継続が生む「本物の資産形成」ー
医院経営と投資に共通する成功の法則 ― 信頼と継続が生む「本物の資産形成」ー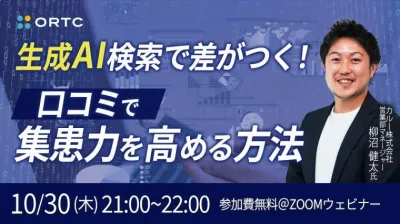 生成AI検索で差がつく!口コミで集患力を高める方法
生成AI検索で差がつく!口コミで集患力を高める方法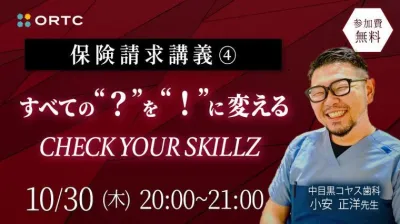 保険請求講義④すべての“?”を“!”に変える:CHECK YOUR SKILLZ
保険請求講義④すべての“?”を“!”に変える:CHECK YOUR SKILLZ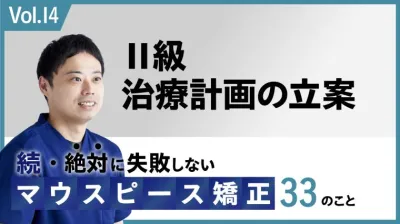 続・ 絶対に失敗しないMP矯正33の事 Ⅱ級 治療計画の立案
続・ 絶対に失敗しないMP矯正33の事 Ⅱ級 治療計画の立案