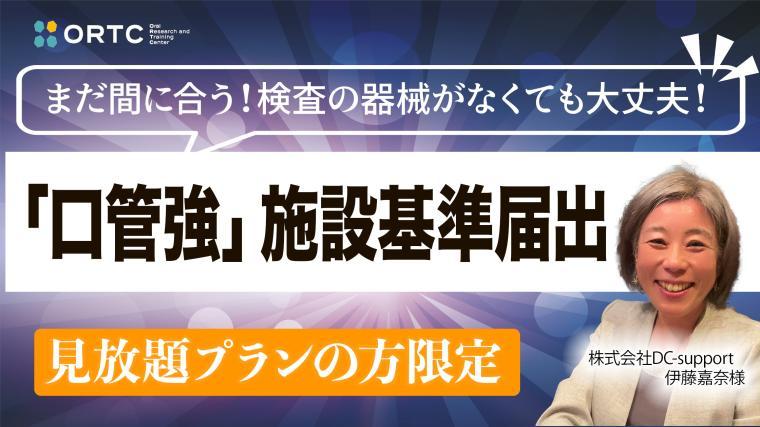歯科麻酔の時間管理:浸潤麻酔・伝達麻酔の作用時間と患者対応のポイント
歯科麻酔の時間管理:浸潤麻酔・伝達麻酔の作用時間と患者対応のポイント
はじめに
歯科治療において、「麻酔はどれくらいで効き始めて、どのくらいの時間持続するのか?」という疑問は患者さんから頻繁に寄せられます。麻酔の作用時間を正確に把握し、状況に応じて浸潤麻酔と伝達麻酔を使い分けることは、快適で安全な治療を行ううえで欠かせません。
また、検索されることの多い浸潤麻酔の時間や伝達麻酔の時間、作用時間の違いに関する情報からも、多くの人が麻酔の時間に関心を持っていることが分かります。ただし、麻酔の効き方には年齢、体重、代謝など個人差があり、画一的な対応では不十分です。
本記事では、歯科麻酔の基本と作用時間の違い、効果を持続させるポイント、麻酔が長すぎる・短すぎる場合の対応、患者への説明の工夫などをわかりやすく解説します。歯科麻酔に関する最新情報は ORTC https://ortc.jpでも随時紹介されていますので、ぜひご活用ください。
歯科麻酔とは?その種類と基本的な特徴
歯科で使われる局所麻酔は主に以下の3種類です。
| 麻酔法 | 主な使用部位 | 効果発現時間 | 持続時間 | 主な特徴 |
|---|
| 表面麻酔 | 粘膜表面 | 数十秒 | 10〜15分 | 針刺入時の不快感軽減に有効 |
| 浸潤麻酔 | 歯根膜・歯槽骨周辺 | 1〜3分 | 約30〜60分 | 一般的な歯科治療で広く使用 |
| 伝達麻酔 | 神経幹(例:下歯槽神経) | 5〜10分 | 約2〜3時間 | 広範囲の麻酔が可能、下顎臼歯部に適用 |
浸潤麻酔は短時間で即効性があり、限られた部位への治療に向いています。一方、伝達麻酔は効果が現れるまでにやや時間がかかるものの、広範囲にわたる処置や長時間の治療に適しています。
麻酔が効き始めるまでの時間と切れるまでの時間
○薬剤ごとの効果発現時間と持続時間
| 薬剤名 | 発現時間 | 持続時間(アドレナリン含有) |
|---|
| リドカイン | 2〜3分 | 約60〜90分 |
| メピバカイン | 1.5〜2分 | 約90〜120分(血管収縮剤なしでも持続) |
| アーティカイン | 1〜3分 | 約75〜90分(骨浸透性が高い) |
※参考文献:日本歯科麻酔学会ガイドライン2020、厚生労働省資料
浸潤麻酔の時間は一般的に30〜60分程度、伝達麻酔の時間は2〜3時間程度とされています。使用する薬剤や血管収縮剤の有無によっても持続時間は変わります。こうした麻酔の作用時間の違いを把握することは、治療計画を立てるうえでも重要です。
○年齢・体重・代謝による個人差
麻酔の効果や持続時間は患者ごとの体質や状態によって異なります。以下のような要因を考慮する必要があります。
①年齢:高齢者は肝臓や腎臓の代謝機能が低下していることが多く、麻酔薬の代謝・排泄に時間がかかり、効果が長く持続する傾向があります。逆に、小児は代謝が活発なため、効き目が早く出る反面、効果が早く切れることがあります。
②体重:体重が重い患者では薬剤の分布が広がるため、局所への作用が弱まりやすく、麻酔が早く切れる場合があります。逆に低体重の患者では、同じ投与量でも効果が強く現れる可能性があります。
③代謝:糖尿病、甲状腺機能異常、肝疾患などがあると、薬剤の反応に差が出ます。代謝能力が低いと、麻酔の効果が予想より長く続くことがあります。
効果が長すぎる場合の原因と対処法
○原因の例:
- 高濃度の麻酔薬の使用
- 血流不足(寒冷環境や血管収縮剤の影響)
- 高齢者や代謝機能の低下
○対処法:
- 軽く顎を動かす、咀嚼を促す
- タオルなどで温めて血流を促進
- 経過観察、必要に応じて医科と連携
効果が短すぎる場合の原因と対処法
○原因の例:
- 炎症によるpH低下(麻酔薬が効きにくくなる)
- 注入部位の不適切さ(神経から外れているなど)
- 投与量不足や代謝亢進
○対処法:
- 血管収縮剤を含む薬剤に変更
- 適切な部位への再注射
- 必要に応じて鎮静法の併用
---
患者さんへの説明例(麻酔の時間に関して)
「本日の処置では麻酔を使用します。注射してから2〜3分でしびれを感じ始め、約1時間ほど効果が続きます。体質によっては早く切れたり、逆に長く残ることもありますが、ほとんどの場合は問題ありません。気になることがあれば、すぐにお知らせください。」
このような説明をすることで、患者さんの不安を軽減し、信頼関係の構築にもつながります。浸潤麻酔と伝達麻酔の時間的な違いについても、わかりやすく伝えることが満足度向上に寄与します。
---
ORTCでさらに学ぶ:最新の麻酔技術と臨床応用
歯科麻酔の作用時間や使い分け、症例ごとのコツなどに関する知識は、ORTC https://ortc.jpでも紹介されています。臨床に役立つコンテンツが満載なので、ぜひご覧ください。
---
まとめ
- 歯科麻酔には浸潤麻酔と伝達麻酔があり、それぞれに適した時間的特性がある
- 浸潤麻酔の時間は30〜60分、伝達麻酔の時間は2〜3時間程度
- 麻酔の作用時間の違いを理解することで、安全で効率的な治療が可能になる
- 年齢・体重・代謝などの個人差を考慮して対応を調整することが重要
- 麻酔が長く効きすぎる、または短すぎる場合には原因を見極めて適切に対応
- 患者への丁寧な説明が信頼関係を築く鍵となる
麻酔の時間に関する正しい知識を身につけることで、トラブルを防ぎ、治療の質を高めることができます。日々の診療において自信をもって対応できるよう、引き続き学びを深めていきましょう。
歯科麻酔の最新情報やコラムは、ORTC https://ortc.jpにて随時更新されています。ぜひご活用ください。
歯科衛生士ライター;東雲
歯科医療の現場で役立つ実践的な知識を届けるORTC

ORTCは「笑顔の役に立つ」を理念に、歯科界の知識を共有する場を目指しています。歯科医療の現場で役立つ最新の知識と技術を提供することで、臨床と経営の両面からクリニックの成長を支援します。最先端の技術解説や経営戦略に特化した情報を集約し、歯科医療の現場での成果を最大化。自己成長を追求するためのコンテンツをぜひご活用ください。
無料会員登録
無料動画の視聴、有料動画のレンタルが可能です。歯科業界についてのオンライン・オフラインセミナーへの参加が可能となります。
ORTCPRIME
月額5500円で、 ORTC内のすべての動画を見放題に。臨床の現場に役立つ最新の技術解説や、歯科医院経営の成功戦略を網羅した特別コンテンツをご利用いただけます。 歯科業界の方へ効率的に知識を深めていただける内容です。
ORTC動画一覧
ORTCセミナー一覧
まずは無料会員登録
こちらのリンクより会員登録ページへお進みください。
会員登録はこちら
ORTCPRIMEへのアップグレードも簡単!
登録後は「マイページ」から、ORTCPRIMEにいつでもアップグレード可能です。
 こちらの動画もおすすめです
こちらの動画もおすすめです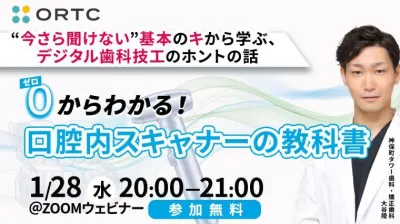 “今さら聞けない”基本のキから学ぶ、デジタル歯科技工のホントの話『ゼロからわかる、口腔内スキャナーの教科書』
“今さら聞けない”基本のキから学ぶ、デジタル歯科技工のホントの話『ゼロからわかる、口腔内スキャナーの教科書』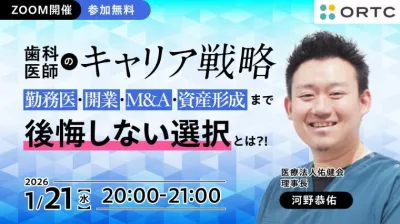 歯科医師のキャリア戦略 ― 勤務医・開業・M&A・資産形成まで、後悔しない選択とは ―
歯科医師のキャリア戦略 ― 勤務医・開業・M&A・資産形成まで、後悔しない選択とは ―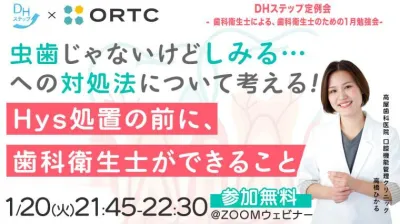 虫歯じゃないけどしみる…への対処法について考える Hys処置の前に、歯科衛生士ができること
虫歯じゃないけどしみる…への対処法について考える Hys処置の前に、歯科衛生士ができること 「TBIが変われば患者が変わる」 自費TBI成功マインド
「TBIが変われば患者が変わる」 自費TBI成功マインド 後継者不在、人材不足、競争激化を乗り切る! 歯科医院M&Aの基本と成功へのプロセス
後継者不在、人材不足、競争激化を乗り切る! 歯科医院M&Aの基本と成功へのプロセス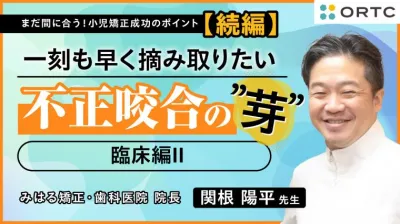 続・まだ間に合う!小児矯正のポイント 〜一刻も早く摘み取りたい 不正咬合の”芽”~ 臨床編Ⅱ
続・まだ間に合う!小児矯正のポイント 〜一刻も早く摘み取りたい 不正咬合の”芽”~ 臨床編Ⅱ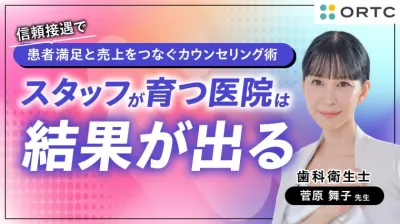 信頼接遇で患者満足と売上をつなぐカウンセリング術 〜スタッフが育つ医院は結果が出る〜
信頼接遇で患者満足と売上をつなぐカウンセリング術 〜スタッフが育つ医院は結果が出る〜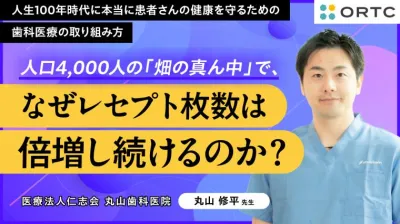 人口4,000人の「畑の真ん中」で、なぜレセプト枚数は倍増し続けるのか?
人口4,000人の「畑の真ん中」で、なぜレセプト枚数は倍増し続けるのか?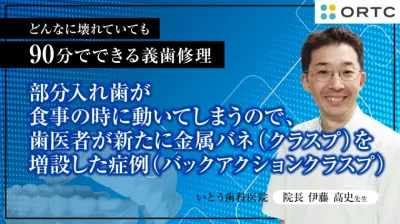 部分入れ歯が食事の時に動いてしまうので、歯医者が新たに金属バネ(クラスプ)を増設した症例(バックアクションクラスプ)
部分入れ歯が食事の時に動いてしまうので、歯医者が新たに金属バネ(クラスプ)を増設した症例(バックアクションクラスプ)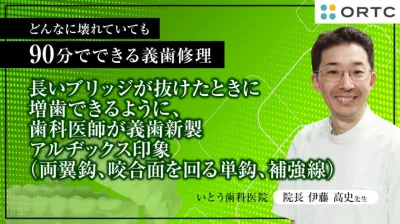 長いブリッジが抜けたときに増歯できるように、歯科医師が義歯新製 アルヂックス印象(両翼鈎、咬合面を回る単鈎、補強線)
長いブリッジが抜けたときに増歯できるように、歯科医師が義歯新製 アルヂックス印象(両翼鈎、咬合面を回る単鈎、補強線)
 歯科麻酔の時間管理:浸潤麻酔・伝達麻酔の作用時間と患者対応のポイント
歯科麻酔の時間管理:浸潤麻酔・伝達麻酔の作用時間と患者対応のポイント