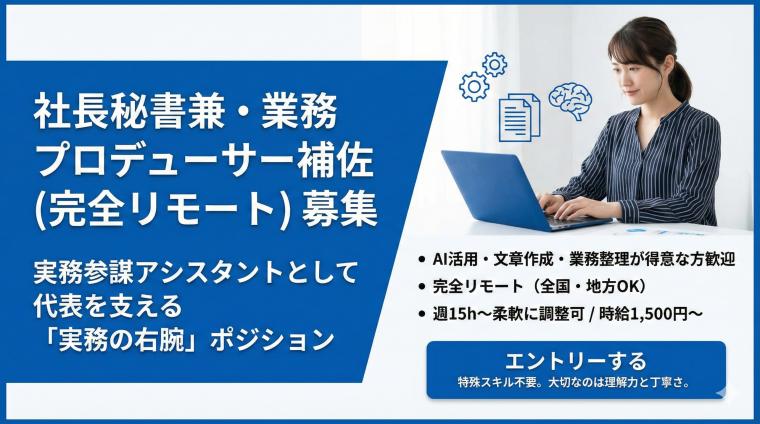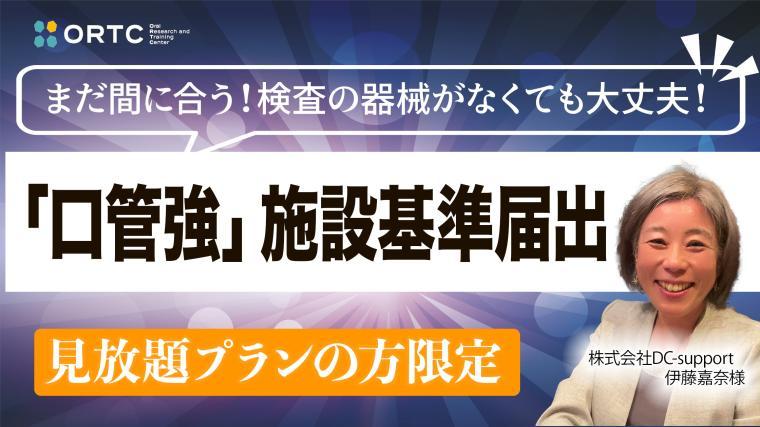風薫る5月、過ごしやすい季節となりました。青葉若葉が目にまぶしく、心地よい初夏の日差しが感じられますね。
みなさん新たな気持ちで春を迎えられていることと思いますが、そんな中でも新たに国家資格を取得し、晴れて社会人としてデビューを果たした皆さんは、今までに体験したことのないドキドキした気持ちで日々を過ごされているのではないでしょうか。
新人研修のスピードは医院にもよるため、始めはアシスト業務ばかり…というところもあれば、すでにメンテナンスを担当していたり、受付業務まで兼任しててんやわんやな毎日!という方もおられるかと思います。
入職してすぐは新たな環境に慣れることで一苦労ですよね。
学校で今までたくさんのことを学んできたつもりでも、それらはあくまでも基礎知識。
勤務がスタートしたら分からないことだらけでツライ…と感じるのは、新人の頃に誰もが通る道です。
年齢の異なる方と一緒に仕事をする緊張感や、社会人としてのプレッシャーもあり、毎日目まぐるしく過ぎていって不安な気持ちもあるかと思います。
この記事では、「入職直後の業務を効率的に覚えるヒント」として、つまずいてしまいやすいポイントへの対処法をお伝えします。
この記事で分かること
1、まずはコレから!医院のルールと環境に早く慣れる方法
2、ドキドキのアシスト業務!早く上達するための3つのポイント
3、いよいよ本番!歯科衛生士業務の基本ステップと心構え
1、まずはコレから!医院のルールと環境に早く慣れる方法
1)医院マニュアルを確認しよう!
新人教育をするにあたり、どこの医院でも「医院マニュアル」が準備されていることが多いです。
医院マニュアルは言わば「医院の知識の結晶」!
マニュアル化されていることはその医院にとって基礎的な内容であり、書かれていることは重要な部分を要点に絞って載せられているはず。
ですから、まずは医院マニュアルに関して理解を深めることが重要です。
マニュアルに目を通し、知らない用語やわからない点について自分で確認し、その上で教育担当の先輩に確認してみましょう。
確認ポイント①器材の取り扱いについて
医院によって器材の「呼び名」が決まっている場合があります。
例えば、「サスブラシ」 ではなく「ユリー」など商品名で呼ばれていたり、「黄色のブラシ」など呼称がついていたりします。
これはその医院での呼び名であり、例え間違っていなかったとしても全体の認識と違う名前で呼んでしまうと話が通じなくなりコミュニケーションが取れなくなってしまいます。
医院での呼び名を確認し、その呼び方を使うようにしましょう。
また、診療の流れや術式は分かっていても器材をどこから出すのか、どのように戻すのか分からなければ業務に支障が出てしまいます。
チェアの引き出しや消毒室など、どこに何があるのかをまずはメモしましょう。
その上で、これは滅菌するのか、拭掃して戻すのか?など戻し方についても確認しておきましょう。
確認ポイント②薬剤の取り扱いについて
薬剤についても取り扱いについて確認しておきましょう。
薬剤は冷暗所保管のものもあります。棚だけでなく、冷蔵庫なども何が入っているのか把握しておきましょう。
在庫はそれぞれどこにあり、何個必要なのか?
また、在庫がなくなった場合にはどこに注文するのかも確認しておきましょう。
2)1日の流れを確認しよう!
新人として入職してすぐは教育担当の先輩がついてくれるかと思います。一緒についていただけているうちに医院の1日の流れを確認しておきましょう。
よくある歯科医院の1日の流れとしては、
<午前>
診療前の掃除
朝礼 診療スタート
昼休憩
<午後>
午後診療
診療終了 後片付け
終礼
このような流れが一般的かと思います。
医院の特色によって午前は高齢者が多く、午後は子供が多いなどもあります。
それぞれ行われる内容や担当について確認しておきましょう。
確認ポイント①予約システムについて
医院によって予約システムはそれぞれです。ネット予約に対応したソフトを活用しているところもあれば、昔ながらの紙媒体の医院も存在します。
受付スタッフが予約を取る医院が一般的ではありますが、電話対応で予約を取らなければならないこともありますし、患者さんから予約方法について聞かれる場合もあります。
・予約システムはどのようなものを使っているのか?
・何時から何時まで予約が取れるのか?
・予約はいつでも取れるのか?(予約の混雑状況)
・一患者につき何枠まで先の予約が取れるのか?(キャンセル対策として予約は一枠のみとしている医院もあります)
など、ざっくりとでも良いので確認しておきましょう。
確認ポイント②カルテの書き方について
医療業界ではデジタル化が進み、電子カルテがベースではありますが手書きカルテも多く存在します。
手書きカルテに多いものが、
・業務内容カルテ
・自費カルテ
です。
業務内容カルテは、その日行った業務はもちろん、その時に歯科医師から説明した内容や患者とのコミュニケーションを書きとめたり、患者さんが話した主訴についてや会話内容を書き込みます。
当日行ったやり取りを記入しておくことで、もしもの時に「説明義務を怠っていなかったか」の確認ができますし、患者さんとの小さなやり取りがTBI時に役立つこともあります。
自費カルテには、その日行った自費の内容や金額について記入します。
受付への指示にもつながりますし、金銭のやり取りに使われるものになるため確実に記入できるようにしておきましょう。
また、見返したときに患者さんがどのような治療を行なってきたかを把握するヒントにもなります。
手書きカルテの書式には規定がないため、医院でのオリジナルが使われており、それぞれの特色があります。
記入する時の書き方はもちろん、ペンの色やシャーペンかマーカーかなどその種類まで決まっていることもありますから、必ず確認しておきましょう。
確認ポイント③スタッフの名前を覚えよう!
職場のスタッフの名前や役職、役割について覚えることはとても重要です。
医院によっては歯科医師、歯科衛生士、歯科助手、受付と職種によってユニフォームがしっかり分かれているところもありますが、そうでない医院も多くあります。
人数が多いと名前を覚えることも一苦労ですが、それぞれの職種で分かること・分からないこと、判断できること・できないことが違うので、職種や役割については特に優先して覚えていくようにしましょう。
私も入職直後は覚えることが多く、業務内容で手一杯で一緒に働くスタッフの名前がなかなか覚えられずに苦労しました。
私は、カルテや予約表、またロッカーの名札でまずは名前を把握して、それからどの方がどのお名前なのかを覚えていきました。
名前をまずは覚えておけば、それぞれの役職については話をするうちにだんだんと理解していくことができます。
スタッフの名前を覚えることは相手とのコミュニケーションを取るための第一歩でもありますから、早めに覚えられるよう頑張りましょう。
新人を迎えるにあたり、緊張するのは新人スタッフ側だけでなく受け入れる医院側も同じです。
どんな人が来るのか、どのように教えていけばいいのかと悩むことも多いですよね。
診療中や昼休憩でもコミュニケーションは取れますが、もちろん業務というお仕事が優先になります。
仕事から少し離れて、みんなで医院で行うイベントを考えたり、掲示物を作るなどオリエンテーションの時間もとても大切です。
また、スタッフ全員でのオリエンテーションだけでなく、院長と新人スタッフ、教育担当と新人スタッフがマンツーマンで話す時間を設けることも新人の不安を減らすことに役立つかと思います。
また、医院のマニュアルについても確認するタイミングや期間を設けておくことが重要です。
マニュアルを作成するのはとても大変で、作成したら最後そのまま見直しをしていない…という場合も多くあります。
ですが、そうすると新しい器材についての記入がなかったり、もう行われていない術式がそのままマニュアルに残ってしまったりします。
新人スタッフが入る時にはその内容を見返しておき、内容に変更点がないかどうか確認しておきましょう。
また、新人スタッフがマニュアルにメモした内容は大きな気づきです。
その職場に慣れ親しんだスタッフでは分からない大切なメモですから、次に来る新人スタッフのためにも新たに記載しておきましょう。
2、ドキドキのアシスト業務!早く上達するための3つのポイント
新人に任される初めてのお仕事はアシスト業務からのスタートが一般的です。
アシスト業務も歯科衛生士の立派なお仕事です!
歯科医師のアシストをスムーズに行い、また患者さんに不安なく診療を進めてもらえるように学んでいきましょう。
1)治療の流れを理解しよう
まずは治療の流れを理解しましょう。
学生時代に診療実習に臨んだ時にも治療の流れはもちろん理解していたこととは思いますが、医院によっては使う器材に決まりがあったり、受け渡しの順番が決まっていたりします。
治療に必要な器材をまずは準備できるようにし、そして使う順番を理解しましょう。
治療にはある程度の決まった流れがあり、これを理解しておくことで歯科医師が今何を求めていて、次にどんなことを行うのかを予測することができるようになります。
そうすると、診療がスムーズに進み、歯科医師はもちろん患者さんにとっても快適な流れで診療を終えることができます。
まずは手順を確実に理解し、そして次の一手が何であるのか考えられるようにしていきましょう。
2)先輩の動きをよく見よう
新人研修で先輩の業務を見学している時には、先輩の動きをよく観察しましょう。
どのタイミングで何を準備しているのかはもちろん、器具の受け渡し方法や片付ける時の手順についても確認しておきましょう。
バキューム操作は特に細かい角度調整が必要になります。頰粘膜を吸い込まないように角度をつけたり、前歯部では口唇を排除するために左手でどのように支えているのかなどの細かいポイントをしっかり見ておき、自分でも実践してみて、細かいポイントや気をつけていることについて質問を重ねましょう。
また、器具の受け渡しについても持つ場所や角度、持つ指の動きなど細かい部分に工夫があります。
こちらについてもしっかりと観察し、気をつけるポイントについて質問してみましょう。

3)分からないことはすぐ聞こう
一度教えてもらったことであっても、分からなくなってしまうことはあります。
「聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥」という言葉もあります。
分からないまま進めずに、必ず確認をしてミスのないように努めましょう。
質問する時にはいきなり聞くのではなく、「お聞きしたいことがあるのですが、今質問してもいいですか?」と声をかけてからにしましょう。
診療中は何かと忙しく、何かの作業中であることも多いです。必ず相手の状況を確認してから質問してみてくださいね。
また、一度確認した内容は必ずメモにして残しておきましょう。
分からないことを確認せずにミスを引き起こしてしまうことはもちろん避けるべきことですが、何度も質問を繰り返すと「やる気がない」とみなされてしまいかねません。
自分がどんなことに悩んで、その解決策と答えはなんだったのか?メモとしてまとめておいて、同じミスを繰り返すことのないよう復習しておきましょう。
私は入職直後、特にバキュームとライティングで苦労しました。
バキュームは唾液や水を吸引することはもちろんですが、吸引するためには粘膜を排除することもとても重要です。
また、患者さんに無理をさせない、痛みを与えないことも重要です。どの角度でどのように入れれば痛みなくしっかり吸引できるのか、自分の口でも実際に行ってみながら少しずつ学んでいきました。
また、入れる場所について考える時は術者の視野を確保することも重要です。
患者さんに負担なく吸引できる部位であっても、そこに術者が器具を当てようとしているのであれば診療することができません。
ライティングもまた術野を明るく照らせていたとしても、術者の視点からすると影になっていたり、患者さんには眩しかったりとそれぞれの視点に立って考えることが重要になります。
場数を踏むことで慣れていくことでもありますが、始めはどのようにすれば良かったのか、その日のうちに先輩に確認するようにしましょう。
専門学校で学んできて、実習を経験してきたとはいえ、新人の頃は慣れない環境で緊張したり萎縮したりとなかなか思うように上手くいかないことも多いものです。
また、人によって得意不得意はありますし、学ぶペースや技術を会得するスピードも人によって異なってきます。
新人として一律で捉えすぎずに、一人一人に合わせて一週間、一ヶ月などゴール設定を決めて、本人と目標を共有して振り返りが出来るようにしましょう。
そうして段階的に出来ることを確実に増やしていくことで新人さんの自信にも繋がります。
教える側からも積極的に声をかけ、出来て当たり前、ではなく、「これが出来ていて良かったよ!」「助かったよ!」など感謝の言葉を出していくようにしてみてくださいね。
3、いよいよ本番!歯科衛生士業務の基本ステップと心構え
歯科衛生士国家資格を取得し、入職して、晴れて今日から一人前!すぐにメンテナンス担当スタート!…というわけにはもちろん行きません。
「患者さんを診る」ということは、ただスケーリングをする、メンテナンスをするだけではありません。
安全に診療を行うことはもちろん、患者さんの細かなサインを感じ取って適切な行動を取ること、危険な行為を理解しそうならないよう安全対策を万全に行っておくことが最低限求められます。
このためには、自分の業務はもちろん、目の前の患者さんだけでなく他のスタッフの業務などを考慮して診療を進める、大きな視点が必要になります。
歯科衛生士として独り立ちができるよう、まずは目の前の業務を確実に行えるように学びを深めていきましょう。
標準的な新人研修の流れとしては、
| 期間 | 内容 |
|---|
| 1ヶ月目 | 先輩アシスタントとして診療を見学、検査入力の補助や器具出しを覚える
並行してスケーリングやTBIの練習 |
| 2~3ヶ月目 | スケーリングやTBIを少しずつ実践、先輩と振り返り |
| 3~6ヶ月目 | 軽度の患者から一人での診療スタート
並行してSRPの練習 |
| 6~12ヶ月目 | 軽度の患者からSRPスタート |
このように、入職して半年ほどで基本的な新人研修を終え、患者さんを担当していく場合が多いです。
新人研修で学んでいく中で、特に気をつけるポイントについて見ていきましょう。

1)患者さんとのコミュニケーションについて
まず患者さんとコミュニケーションを取る前に、できる限りその方のカルテを読み込んでおきましょう。
特に服薬内容や持病について、今まで医院とのやりとりで特筆する点がなかったか、歯ブラシのこだわりやチェアのポジショニングについての注意点がないかなどについて確認しておきましょう。
患者さんを実際にチェアに導入し、診療を始める前には自己紹介を行いましょう。
相手の正面から、「本日担当します、歯科衛生士の○○です。よろしくお願いします。」と笑顔で挨拶を行うことで、患者さんに安心感を持ってもらうことができます。
診療をスタートする時には、「痛みがあれば左手を上げて教えてください」と痛みについてのサインを決めておく、チェアを倒したら「頭や腰に痛みはないですか?」と確認するなど、声かけを行い確認しましょう。
患者さんから話を聞く時には傾聴の姿勢が大切です。
相手の話を遮らず、頷きや「そうなんですね」と相手の話を聞いていますよ、というサインを出しながらゆっくりと話を聞くようにしましょう。
2)ひとつひとつの手技を確実に身につけましょう
新人の頃は、先輩たちが何気なく行っている作業がなかなか上手くいかず落ち込んでしまうことも多いかと思います。
例えば、先輩なら10分程度で済ませてしまうスケーリングも、頰粘膜排除がうまくできなくで吸引できなかったり、スケーリング後先輩にチェックしてもらったら歯間など細かい部分にチップが当てられず残石だらけで手直しされてしまったり…なんて、新人の頃にはよくあるエピソードです。
とはいえここで腐らず、焦らず、確実にできることを増やしていくことが大切です。
例えば、粘膜の排除はそのままアシスト業務に繋がりますし、スケーリングの手技はSRPを行う時に必ず必要になります。
小さなミスと思わず、それぞれが次のステップに繋がっていますから、着実にできるように努めていきましょう。
私は初めの頃、患者さんを診るので精一杯で声かけや配慮にまで気が回らず、患者さんから「あの子暗いけど大丈夫?」と心配されてしまったことがあります。
また、先輩のように上手くできなくて、担当を外してくれ、なんて言われたことだってもちろんあります。
そんな時には、何がいけなかったのか?どうしたらもっと上手くできたのか?と自分で考え、また先輩にもアドバイスしてもらったり、実際に先輩を相手に実習したり、逆に先輩に施術してもらったりして学んできました。
自分が体感することで分かることもたくさんありますから、機会があればぜひ先輩に診てもらって自分との違いについて学んでみてくださいね。
新人さんに初めて仕事を振る時は、本人もですが医院側としてもなかなか緊張することかと思います。
患者さんにとっては新人であろうが、体験入社であろうが、医院の一人。もちろん失敗は許されません。
医院に古くから馴染んでくださっていてこちらの事情も汲んでくださる患者さんにまずは相手役をしてもらったり、重症症例の患者さんは経験を積んでからにする、気難しい患者さんや過去にトラブルに発展したことのある方はやめておくなど新人との相性も考えながらマッチングを行うことも重要かと思います。
初めの半年ほどはそのように症例配当しながら、できることを着実に増やして場数を踏み、それから誰でも診られるようにステップを作っていきましょう。
<終わりに>
新人の頃は何かとうまくいかずに悩んだり、時には涙することもあるかと思います。
誰でも初めから上手くいくことなどなく、少しずつできるように成長していきますから、焦らず一歩ずつ進んでいきましょう。
始めは社会人として日々出社するだけで、はなまるです。
体調管理をし、休まず毎日同じ時間にきちんと職場に行くこと。また、笑顔でスタッフや患者さんと話すことを目標にすることもいいでしょう。
毎日できたことをベースに考え、日々の小さな成長を大切に一歩ずつ確実に進んで行くことが大切です。
また、入職後に他の職場で働いている同級生に会ってお互いの近況を報告し合ってみると、自分とは研修の進み具合が違ったり、行っている業務内容が違っていて、焦ったり不安に感じることもあるかと思います。
大事なことは、「どれだけ早く業務をこなせるようになるか」ではなく、「歯科衛生士として確実に独り立ちできるようになること」です。
友人や同期と比べるのではなく、自分の思い描いていた「歯科衛生士」になれるよう、日々学んでいきましょう。
歯科衛生士ライター:moe
歯科医療の現場で役立つ実践的な知識を届けるORTC

ORTCは「笑顔の役に立つ」を理念に、歯科界の知識を共有する場を目指しています。歯科医療の現場で役立つ最新の知識と技術を提供することで、臨床と経営の両面からクリニックの成長を支援します。最先端の技術解説や経営戦略に特化した情報を集約し、歯科医療の現場での成果を最大化。自己成長を追求するためのコンテンツをぜひご活用ください。
無料会員登録
無料動画の視聴、有料動画のレンタルが可能です。歯科業界についてのオンライン・オフラインセミナーへの参加が可能となります。
ORTCPRIME
月額5500円で、 ORTC内のすべての動画を見放題に。臨床の現場に役立つ最新の技術解説や、歯科医院経営の成功戦略を網羅した特別コンテンツをご利用いただけます。 歯科業界の方へ効率的に知識を深めていただける内容です。
ORTC動画一覧
ORTCセミナー一覧
まずは無料会員登録
こちらのリンクより会員登録ページへお進みください。
会員登録はこちら
ORTCPRIMEへのアップグレードも簡単!
登録後は「マイページ」から、ORTCPRIMEにいつでもアップグレード可能です。
 こちらの動画もおすすめです
こちらの動画もおすすめです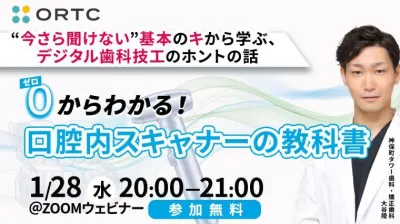 “今さら聞けない”基本のキから学ぶ、デジタル歯科技工のホントの話『ゼロからわかる、口腔内スキャナーの教科書』
“今さら聞けない”基本のキから学ぶ、デジタル歯科技工のホントの話『ゼロからわかる、口腔内スキャナーの教科書』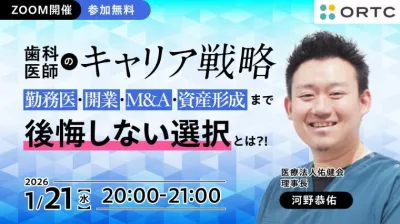 歯科医師のキャリア戦略 ― 勤務医・開業・M&A・資産形成まで、後悔しない選択とは ―
歯科医師のキャリア戦略 ― 勤務医・開業・M&A・資産形成まで、後悔しない選択とは ―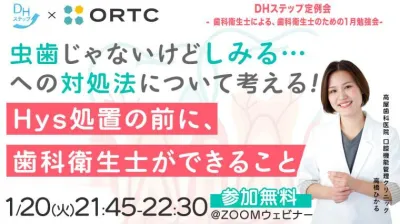 虫歯じゃないけどしみる…への対処法について考える Hys処置の前に、歯科衛生士ができること
虫歯じゃないけどしみる…への対処法について考える Hys処置の前に、歯科衛生士ができること 「TBIが変われば患者が変わる」 自費TBI成功マインド
「TBIが変われば患者が変わる」 自費TBI成功マインド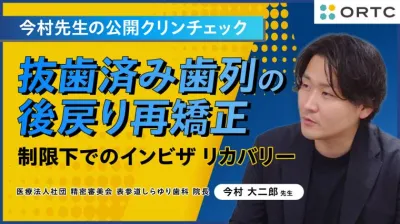 抜歯済み歯列の後戻り再矯正:制限下でのインビザ リカバリー
抜歯済み歯列の後戻り再矯正:制限下でのインビザ リカバリー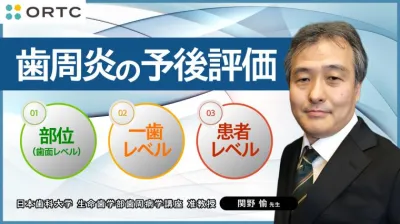 歯周炎の予後評価 1.部位(歯面レベル) 2.一歯レベル 3.患者レベル
歯周炎の予後評価 1.部位(歯面レベル) 2.一歯レベル 3.患者レベル チェアサイドでのご提案を7ステップで完全マスター Part3
チェアサイドでのご提案を7ステップで完全マスター Part3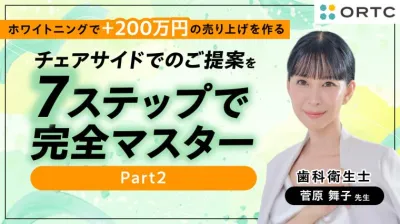 チェアサイドでのご提案を7ステップで完全マスター Part2
チェアサイドでのご提案を7ステップで完全マスター Part2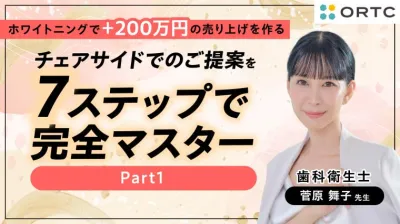 チェアサイドでのご提案を7ステップで完全マスター Part1
チェアサイドでのご提案を7ステップで完全マスター Part1 資産形成の土台を磨く ― 3年目から始まる本当の運用ー
資産形成の土台を磨く ― 3年目から始まる本当の運用ー