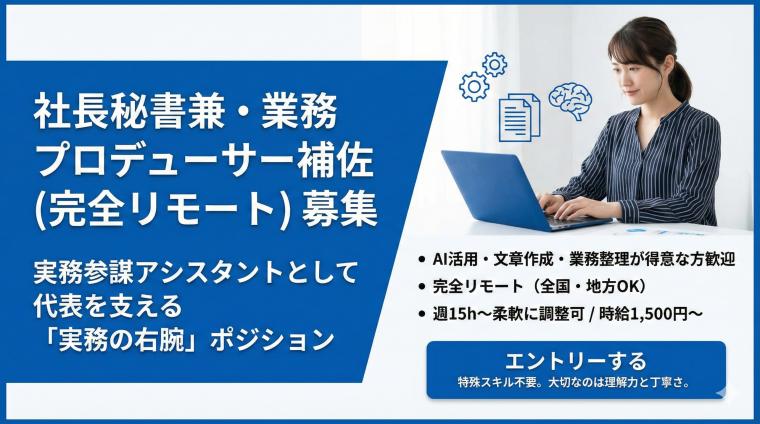歯科治療において、正確な咬合平面の設定は患者様の口腔機能と審美性を大きく左右する重要な要素です。
従来、咬合平面はカンペル平面(鼻聴道平面)と平行であるとされてきましたが、近年の研究により、必ずしもすべての症例でこの平行性が成立するわけではないことが明らかになってきました。
特に3DCTの導入は、この分野に革新的な進展をもたらしています。
従来の2次元エックス線写真では困難だった軟組織と硬組織の立体的な位置関係を、より正確に把握することが可能となったのです。
本記事では50名の成人有歯顎者を対象に、3DCTを用いて咬合平面とカンペル平面の位置関係を詳細に分析した資料を参考にし、顔面頭蓋の側貌形態が両平面の関係性に及ぼす影響について、新たな知見を解説します。
はじめに

歯科治療において、咬合平面の設定は患者様の口腔機能と審美性に大きく影響を与える重要な要素です。
咬合平面は、上下の歯が接触する平面として定義され、補綴治療の基準となります。
一方、カンペル平面(鼻聴道平面)は、鼻翼下端と外耳道上縁を結ぶ平面であり、解剖学的な指標として広く用いられています。
これまでの研究では、咬合平面とカンペル平面は平行であるとされてきました。
この認識は、多くの臨床現場にて共有され、特に全床義歯の製作などにおいて重要な指標となっています。
しかし、実際の臨床では、必ずしもすべての症例でこの平行性が成立するわけではないことが経験的に知られてきています。
3DCTの導入により、軟組織と硬組織の立体的な位置関係をより正確に把握することが可能となったおかげで、従来の2次元エックス線写真では困難だった詳細な解析が実現し、両平面の関係性について新たな知見が得られつつあります。
このアプローチにより、より精密な治療計画の立案が可能となってきているのが現状です。
咬合平面とカンペル平面の関係性を理解する重要性

補綴治療において、適切な咬合平面の設定は、咀嚼機能の回復、発音の明瞭性、および顔貌の審美性を左右する重要な要素です。
特に、全床義歯の製作や大規模な補綴処置では、患者様の解剖学的特徴に調和した咬合平面の決定が治療の成否を決定づけます。
カンペル平面を基準とする利点は、解剖学的指標として明確で再現性が高く、多くの臨床家に広く認識されている点です。
しかし、個々の患者様の顔面形態の違いによって、必ずしもカンペル平面と咬合平面が平行関係にならない場合があるという課題も存在します。
これまで用いられてきた2Dエックス線セファログラムでは、軟組織と硬組織の重なりにより、正確な計測点の設定が困難でした。
また、立体構造を平面に投影することで生じる歪みや、撮影時の頭位の違いによる誤差など、様々な技術的限界が存在していたため、より精密な診断と治療計画の立案には新たな手法が求められていたのです。
3DCTを用いた最新研究の知見
本研究(参考元:顔面頭蓋の側貌形態による 咬合平面とカンペル平面の位置関係に関する考察)では、3DCTを用いて咬合平面とカンペル平面の位置関係を、顔面頭蓋の側貌形態の違いによる影響も含めて詳細に分析しました。
成人有歯顎者50名を対象とし、3DCTで得られた正中矢状面投影像に対して、SN平面を基準としたセファロ分析を実施しています。
分析では、側貌の前後的形態をN-Me角度(対SN)、上下的形態を下顎下縁平面角度(対SN)で評価し、これらの値と咬合平面-カンペル平面のなす角度との関連を線形重回帰分析で検討しました。
その結果、N-Me角度と下顎下縁平面角度の両方が、咬合平面とカンペル平面のなす角度に有意に関連することが示されました。
この研究結果は、顔面頭蓋の側貌形態によって、咬合平面とカンペル平面の位置関係が影響を受けることを統計学的に実証しています。
これにより、個々の患者様の顔貌形態に応じた、より精密な咬合平面の設定が可能となることが示唆されました。
臨床への応用

症例1:標準的な顔貌における咬合再構成
患者様情報
・ 45歳女性
・主訴:総義歯の不適合による咀嚼困難
・顔貌所見:N-Me角度 83度(標準範囲内)、下顎下縁平面角度 32度(標準範囲内)
治療経過
1. 3DCT撮影による詳細な顔貌分析の実施
2. カンペル平面と平行な咬合平面を基準とした人工歯排列
3. ゴシックアーチ描記法による下顎位の決定
4. 試適時の咬合平面評価:カンペル平面との平行性を確認
治療結果
・咀嚼機能の回復:咀嚼効率80%以上を達成
・審美性:患者様の顔貌に調和した自然な表情を獲得
・経過観察:6ヶ月後も安定した咬合関係を維持
症例2:N-Me角度が大きい症例での対応
患者様情報
・52歳男性
・主訴:部分床義歯の咬合不調和
・顔貌所見:N-Me角度 88度(標準より5度大)、下顎下縁平面角度 34度
特徴的な所見
・咬合平面が前方に開く傾向
・従来の平行基準では、後方臼歯部で早期接触が発生
治療アプローチ
1. カンペル平面に対して約3度の前方傾斜を付与
2. 人工歯排列時の咬合平面修正
3. 咬合器上での慎重な咬合調整
4. 試適段階での咀嚼機能評価
治療結果
・咬合の安定性が向上
・患者様の顔貌に調和した咬合平面を実現
・咀嚼効率の改善を確認
症例3:下顎下縁平面角度が特徴的な症例
患者様情報
・38歳女性
・主訴:臼歯部の咬合崩壊による全顎的治療希望
・顔貌所見:N-Me角度 82度、下顎下縁平面角度 38度(急峻)
特徴的な所見
・咬合平面が後方に開く傾向
・前歯部での早期接触リスク
・下顎の回転角が大きい
治療アプローチ
1. カンペル平面に対して約2度の後方傾斜を付与
2. 前歯部ガイダンスの慎重な設定
3. 臼歯部咬合接触の均等化
4. 段階的な咬合挙上による調整
治療結果
・安定した前歯部ガイダンスの獲得
・臼歯部での均等な咬合接触
・ 顔貌の調和改善
臨床的考察

これら3症例から得られた知見は以下の3つです。
・個別化の重要性
・3DCT活用の利点
・経過観察の重要性
それぞれ詳しく解説していきます。
個別化の重要性
補綴治療において、個々の患者様の特徴を考慮した個別化アプローチは極めて重要です。
たとえ標準的な顔貌を持つ患者様であっても、細かな解剖学的特徴や機能的要件は一人ひとり異なります。
3DCTによる詳細な分析により、これまで見過ごされてきた微細な形態的特徴を把握することが可能となりました。
顔貌形態、特にN-Me角度と下顎下縁平面角度の違いによって、適切な咬合平面の設定位置は変化します。
従来のように、すべての症例でカンペル平面と平行に咬合平面を設定する画一的なアプローチでは、理想的な治療結果を得られない可能性があります。
そのため、3DCTデータに基づく詳細な診断と、それに応じた咬合平面の個別化された修正が必要不可欠です。
この個別化アプローチにより、より安定した咬合関係の確立と、患者様満足度の向上が期待できます。
3DCT活用の利点
3DCTの活用は、補綴治療における診断と治療計画の精度を大きく向上させました。
従来の2次元エックス線撮影では困難だった軟組織と硬組織の立体的な位置関係を、より正確に把握することが可能となりました。
特に、咬合平面とカンペル平面の関係性について、個々の患者様の顔貌形態を考慮した詳細な分析が実現しています。
治療計画においては、3DCTデータに基づく精密なシミュレーションが可能となり、術前の予測精度が向上しました。この技術により、咬合平面の設定や人工歯排列位置の決定において、より確実な判断が可能となっています。
また、治療結果の予測性も大幅に向上し、患者様との治療計画の共有や説明がより具体的になりました。
これにより、治療の透明性が高まり、患者様の理解と同意を得やすくなったことも、3DCT活用の重要な利点として挙げられます。
経過観察の重要性
補綴治療後の経過観察は、治療の長期的な成功を確保する上で極めて重要な要素です。
特に、個々の顔貌形態に応じて咬合平面を設定した症例では、定期的な咬合確認が不可欠です。
初期の段階では月1回、その後は3ヶ月ごとの経過観察を実施し、咬合状態の変化を注意深く観察します。
長期的な安定性の評価においては、咬合接触の均等性、顎運動の円滑性、咀嚼効率の維持などを総合的に確認しましょう。
また、患者の主観的評価として、咀嚼時の違和感や疲労感、顎関節症状の有無なども重要な評価項目となります。
必要に応じた微調整の実施も重要です。わずかな咬合の変化でも、放置すると大きな問題に発展する可能性があるのです。
そのため、定期的な咬合調整を行い、早期に問題を発見し対応することで、長期的な治療の安定性を確保することができます。
新しい咬合平面設定の提案

本研究の結果から、咬合平面の設定において、「平行」「前開き」「後開き」の3つの基準を提案したいと思います。
理由は、3DCTによる顔貌形態の分析結果に基づく、より精密な治療アプローチです。
従来のカンペル平面との平行性だけでなく、患者様個々の形態的特徴を考慮した新しい基準となるからです。
「平行」基準は標準的な顔貌形態の患者様に適用され、「前開き」基準はN-Me角度が大きい症例に、「後開き」基準は下顎下縁平面角度が急峻な症例に適用されます。
この個別化アプローチにより、より自然で安定した咬合関係の確立の可能性が上がります。
治療計画立案時には、3DCTによる詳細な形態分析、咀嚼筋の走行、顎運動パターン、さらには患者様の年齢や生活習慣なども考慮する必要があるでしょう。
これらの要素を総合的に評価することで、より高い補綴治療が可能となります。
まとめ
本研究により、咬合平面とカンペル平面の関係性が顔面頭蓋の形態によって影響を受けることが統計学的に実証されました。
3DCTを用いた詳細な分析により、N-Me角度と下顎下縁平面角度が両平面の位置関係に有意に関連することが明らかとなり、この知見は補綴治療の精度向上に大きく貢献すると考えられます。
今後の課題として、より多くの症例データの蓄積と長期的な経過観察による検証が必要です。
また、年齢層や性別による違い、顎関節症状との関連性など、さらなる研究の展開が期待されるでしょう。
参考資料文献:顔面頭蓋の側貌形態による 咬合平面とカンペル平面の位置関係に関する考察
執筆:歯科専門ライター 萩原すう
歯科医療の現場で役立つ実践的な知識を届けるORTC

ORTCは「笑顔の役に立つ」を理念に、歯科界の知識を共有する場を目指しています。歯科医療の現場で役立つ最新の知識と技術を提供することで、臨床と経営の両面からクリニックの成長を支援します。最先端の技術解説や経営戦略に特化した情報を集約し、歯科医療の現場での成果を最大化。自己成長を追求するためのコンテンツをぜひご活用ください。
無料会員登録
無料動画の視聴、有料動画のレンタルが可能です。歯科業界についてのオンライン・オフラインセミナーへの参加が可能となります。
ORTCPRIME
月額5500円で、 ORTC内のすべての動画を見放題に。臨床の現場に役立つ最新の技術解説や、歯科医院経営の成功戦略を網羅した特別コンテンツをご利用いただけます。 歯科業界の方へ効率的に知識を深めていただける内容です。
ORTC動画一覧
ORTCセミナー一覧
まずは無料会員登録
こちらのリンクより会員登録ページへお進みください。
会員登録はこちら
ORTCPRIMEへのアップグレードも簡単!
登録後は「マイページ」から、ORTCPRIMEにいつでもアップグレード可能です。
 こちらの動画もおすすめです
こちらの動画もおすすめです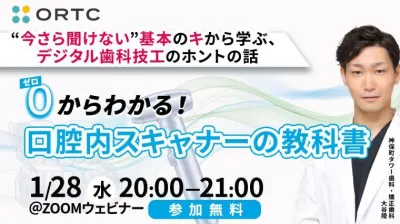 “今さら聞けない”基本のキから学ぶ、デジタル歯科技工のホントの話『ゼロからわかる、口腔内スキャナーの教科書』
“今さら聞けない”基本のキから学ぶ、デジタル歯科技工のホントの話『ゼロからわかる、口腔内スキャナーの教科書』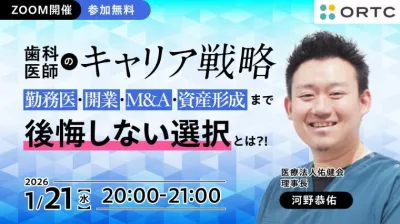 歯科医師のキャリア戦略 ― 勤務医・開業・M&A・資産形成まで、後悔しない選択とは ―
歯科医師のキャリア戦略 ― 勤務医・開業・M&A・資産形成まで、後悔しない選択とは ―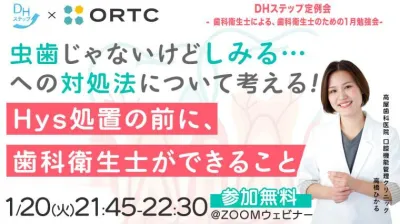 虫歯じゃないけどしみる…への対処法について考える Hys処置の前に、歯科衛生士ができること
虫歯じゃないけどしみる…への対処法について考える Hys処置の前に、歯科衛生士ができること 「TBIが変われば患者が変わる」 自費TBI成功マインド
「TBIが変われば患者が変わる」 自費TBI成功マインド Implant Guide Course | インプラント・ガイデッドサージェリー徹底解説|静的・動的ガイドの使い分けとAll-on-4への応用
Implant Guide Course | インプラント・ガイデッドサージェリー徹底解説|静的・動的ガイドの使い分けとAll-on-4への応用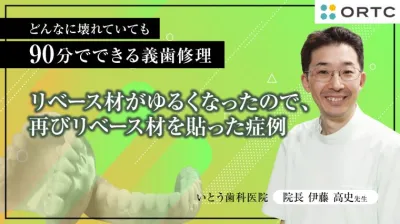 リベース材がゆるくなったので、再びリベース材を貼った症例
リベース材がゆるくなったので、再びリベース材を貼った症例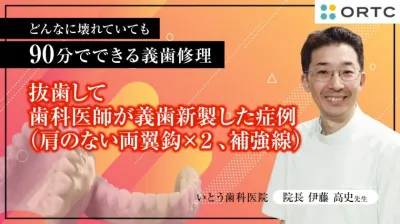 抜歯して歯科医師が義歯新製した症例(肩のない両翼鈎×2、補強線)
抜歯して歯科医師が義歯新製した症例(肩のない両翼鈎×2、補強線) 後継者不在、人材不足、競争激化を乗り切る! 歯科医院M&Aの基本と成功へのプロセス
後継者不在、人材不足、競争激化を乗り切る! 歯科医院M&Aの基本と成功へのプロセス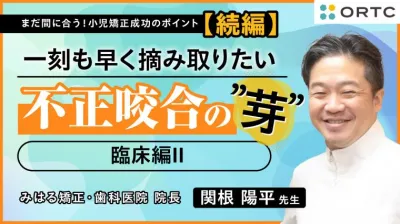 続・まだ間に合う!小児矯正のポイント 〜一刻も早く摘み取りたい 不正咬合の”芽”~ 臨床編Ⅱ
続・まだ間に合う!小児矯正のポイント 〜一刻も早く摘み取りたい 不正咬合の”芽”~ 臨床編Ⅱ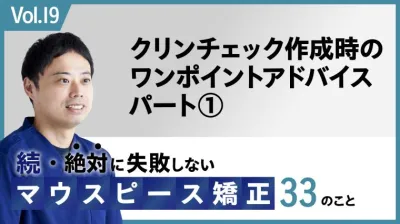 続・ 絶対に失敗しないMP矯正33の事 クリンチェック作成時のワンポイントアドバイス パート①スーパーインポーズ機能
続・ 絶対に失敗しないMP矯正33の事 クリンチェック作成時のワンポイントアドバイス パート①スーパーインポーズ機能