こんな方におすすめ
【歯科衛生士向け】
口呼吸や舌位不正が歯並びや顎顔面成長に大きく関与している事実は、歯科衛生管理の観点からも見逃せません。本動画ではMFT(筋機能療法)のポイントが詳述されており、患者さんへの口腔ケア指導をより効果的に行うための具体的アドバイスが得られます。特に、舌や唇の筋肉の訓練法はブラッシング指導にも応用可能です。
【歯科助手向け】
日々の歯科診療アシストに携わる歯科助手の方々にとっても、本動画の内容は重要です。患者さんが訴える「息苦しさ」や「口呼吸」の背景を理解しておくと、治療の補助や患者対応が円滑になります。特に、拡大床やバイオネーターなどの装置装着時に生じる疑問に対して、適切な連携や案内ができるため、院内のチームワーク向上に寄与します。
【歯科医師(一般開業医)向け】
一般歯科の領域でも、子どもから成人まで、さまざまな年齢層で口呼吸や歯列不正の問題が深刻化しています。本動画は、ジビカでの鼻疾患治療を含めた多角的なアプローチや、MFT・機能装置の選択基準を整理してくれるため、日常臨床での治療計画立案に大いに役立ちます。また、患者・保護者とのコミュニケーションにも有用な情報が満載です。
【歯科矯正専門医向け】
矯正専門医にとっても、MFTや機能装置(プレオルソ、マイオブレース、ムーシールドなど)を活用した新たな治療展開は興味深いテーマです。本動画では、いわゆるワイヤー矯正だけでは解消しにくい口呼吸や舌位の乱れを、基本的な機能療法によって改善するプロセスを示唆しています。すでに高度な矯正技術を有するからこそ、根本原因へのアプローチと装置の併用で、より長期安定が期待できる治療計画を組み立てられるでしょう。
【歯科技工士・その他スタッフ向け】
拡大床やバイオネーターなどの矯正装置は、歯科技工士の精巧な製作技術によって最適化されます。本動画を通じて装置のコンセプトや目的を理解することで、歯科医師との情報共有がスムーズになり、患者さんの歯列や航空機能を踏まえたオーダーメイドのアプローチが可能になります。また、院内スタッフ全体が動画の情報を共有することで、より一貫性のある歯科診療を提供できる点も大きなメリットです。
動画の紹介
はじめに:口呼吸が引き起こす歯科的問題とは?
口呼吸が長期的に続くと、歯並びを含む顎顔面の成長に影響を及ぼすだけでなく、
口腔内の乾燥やむし歯リスクの増大など、多角的なトラブルが生じやすくなります。
本動画では、歯列不正の原因として注目される「口呼吸」に焦点を当て、
耳鼻科と連携した治療やMFT(筋機能療法)などの手段を体系的に解説しています。
ジビカ受診の必要性
最初に強調されるのが、鼻づまりやアレルギー性鼻炎などの耳鼻科的疾患を放置しないことの重要性です。
歯科診療でMFTを進めても、鼻の閉塞が解消されなければ、トレーニングが十分に機能しないケースが多々あります。
そのため、鼻腔の通りを確保するために耳鼻科を受診し、根本的な治療を行うことが不可欠です。
MFT(筋機能療法)の基礎
本動画の中心テーマであるMFTは、舌や唇、頬の筋肉を正しく使うことで歯列への過剰な圧力を緩和し、
歯並びの悪化を抑えるアプローチです。
成長期に適切なMFTを導入することで、矯正治療の負担を軽減できる可能性があります。
機能装置とその役割
本動画では、プレオルソ・マイオブレース・ムーシールドといったマウスピース型装置が紹介されています。
これらは、単に歯を動かすだけでなく、口腔機能を改善するトレーニング器具としての役割を持ちます。
舌の正しい位置を習得し、上下顎のバランスを整えるための重要なツールです。
本動画では、使用期間の目安や保護者とのコミュニケーションの大切さについても解説されています。
拡大床によるアーチ拡大
歯列が狭い場合に有効な装置として「拡大床」が紹介されています。
成長期の子どもに適用することで、上顎骨の横幅を広げ、歯の萌出スペースを確保しやすくなります。
特に、MFTや機能装置と併用することで、歯列の調整と機能改善を同時に行える点が強調されています。
バイオネーターの魅力
下顎の成長が遅れがちな症例には「バイオネーター」が有効です。
この装置は、下顎を前方へ誘導し、呼吸路を広げることで、
高呼吸や開咬の悪循環を断ち切る効果が期待されます。
本動画では、使用前後の症例写真を通じ、実際の治療成果が示されています。
まとめ:総合的な歯科診療の実践へ
この動画は、口呼吸が歯列不正を引き起こすプロセスから、
具体的に使用できる治療・管理法までを包括的にカバーしています。
耳鼻科診療・MFT・機能装置・拡大床・バイオネーターといった手段を適切に組み合わせることで、
患者の口腔環境を根本から改善することが可能になります。
チーム医療としての取り組み
歯科医師だけでなく、歯科衛生士・歯科助手・歯科技工士など、
院内スタッフ全員が動画の内容を共有することで、一貫した治療方針を確立できます。
動画では、専門用語だけでなく、実際の症例を交えた具体的なアプローチが解説されているため、
実践的な歯科診療に役立つ内容となっています。
患者教育とモチベーション管理
特にMFTは、短期間で劇的な変化が出にくいため、患者と保護者のモチベーション管理が重要です。
本動画では、トレーニング期間の明確化・定期的な計測・写真撮影による変化の可視化など、
継続支援の方法についても具体的な提案がされています。
未来の歯科診療への提案
これからの歯科医療では、口呼吸・姿勢・顎顔面形態といった要因を総合的に捉え、
チーム医療としての対応が求められます。
本動画の情報を参考に、患者の将来にわたる口腔ケアと健康管理を強化していきましょう。
動画内容
序章:歯並びの乱れと口呼吸の密接な関係
本動画は「歯並びの乱れが生じる原因」として口呼吸を大きなキーワードに位置づけています。
歯科医療現場では、不正咬合の原因を単純な遺伝要素だけでなく、生活習慣や口腔機能の問題として捉える傾向が強まっています。
特に口呼吸は、鼻腔がうまく通らないために口を開けて呼吸する場合と、習慣化して口を閉じる意識が薄れている場合の両方が考えられます。
本動画では、口呼吸による歯列や顎顔面への圧力バランスの変化が歯並びに大きく影響する点を具体的な症例を交えて解説しています。
ステップ1:ジビカとの連携で鼻疾患を除外する意義
最初に強調されるのは、鼻詰まりやアレルギー性鼻炎の可能性を耳鼻科専門医に診断してもらうことの大切さです。
歯科側でいくら筋機能療法(MFT)を行っても、鼻からの呼吸が困難であれば根本的な改善にはつながりにくいと指摘されています。
鼻腔が閉塞していると、口呼吸が続くことで歯列アーチに余計な前後左右の力が加わり、不正咬合の進行を助長するため、
本動画では医科連携の必要性を強調し、患者さんに適切なタイミングで耳鼻科を紹介する重要性を解説しています。
ステップ2:MFT(筋機能療法)の概要と可能性
次に、口呼吸や舌突出癖、唇閉鎖不全などの機能異常を修正する具体策としてMFTが挙げられます。
MFTでは、舌や唇、頬の筋肉を正しい位置や動きに導くトレーニングを行い、
歯列にかかる不均衡な圧力を是正することを目的としています。
また、MFTだけで歯並びが劇的に改善するかどうかは症例により異なるため、
矯正装置の併用が必要なケースについても解説がなされています。
ステップ3:機能装置(プレオルソ、マイオブレース、ムーシールドなど)の活用
本動画では、機能装置と総称されるプレオルソやマイオブレース、ムーシールドなどが紹介されています。
これらの装置は、単に歯を動かすのではなく、口腔機能の訓練器具としての側面があります。
また、「ただ装置をはめているだけでは十分な効果が得られない」という実践的なポイントも強調されています。
ステップ4:拡大床による歯列アーチの広げ方
歯列が狭く、永久歯が正しい位置に萌出するスペースが不足している場合には、拡大床が有効な選択肢として紹介されます。
成長期の子どもに適用することで、ワイヤー矯正などの本格的治療を軽減できる可能性があります。
ただし、拡大床単独では口呼吸や舌位異常といった根本原因を改善できないため、
MFTや機能装置との併用が重要であることが解説されています。
ステップ5:バイオネーターで下顎の成長をサポート
本動画後半では、下顎の成長が追いつかない症例に効果的とされるバイオネーターが取り上げられます。
この装置は、下顎を前方へ誘導し、顔貌や気道の空間を改善する効果が期待されます。
特に、あごが小さく後退傾向の子どもに適用すると、短期間で目に見える変化が得られるケースが示されています。
ステップ6:対症療法と根本原因の同時アプローチ
本動画では、「口呼吸をはじめとする根本原因を無視したままでは、いくら装置を使っても理想的な歯並びは維持できない」と繰り返し強調されています。
鼻疾患を耳鼻科で治療し、MFTで口腔機能を改善しながら、拡大床やバイオネーターを併用することで、
歯列不正の再発リスクを大幅に低減できることが解説されています。
ステップ7:スタッフ全員で取り組む歯科衛生管理
歯科医師だけでなく、歯科衛生士、歯科助手、歯科技工士など、
院内スタッフが本動画の内容を共有することで、患者への説明の統一が可能になります。
患者さんにとっても、「なぜ鼻呼吸を意識すべきなのか」、
「舌や唇の筋肉の訓練が必要な理由」が明確になることで、モチベーション維持につながるとされています。
ステップ8:日常臨床への落とし込みと今後の展望
本動画の最後では、それぞれの装置について詳細な解説を行う予定が示唆されています。
また、ワイヤー矯正の必要がある症例との住み分けについても解説され、
「最適な装置選択が治療の成否を大きく左右する」ことが強調されています。
結論:今後に活かすポイント
本動画は、診断・機能療法・装置活用・医科連携という視点で包括的に解説されています。
歯科医師、歯科衛生士、歯科助手、歯科技工士など、歯科に携わるすべての人が理解しやすい内容です。
この動画で得た情報を活かし、総合的な歯科診療を実践することで、
患者の将来的な歯科医療負担を大幅に軽減できる可能性があります。
【お知らせ】

詳細ページは右リンクより:https://minoakajp.com/


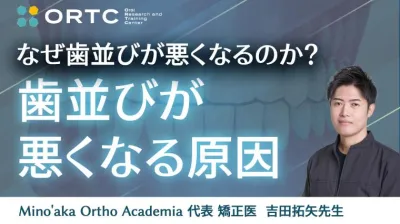



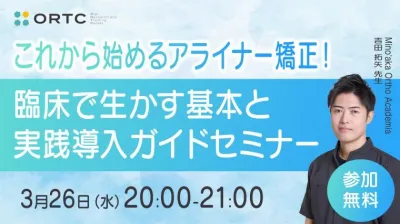
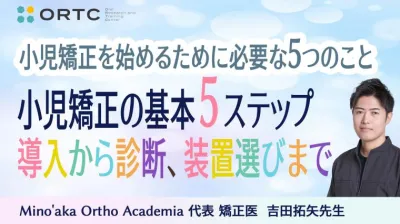


 ORTCプライム 月額 5,500円 (税込)
ORTCプライム 月額 5,500円 (税込)
 対象セミナーが見放題
対象セミナーが見放題