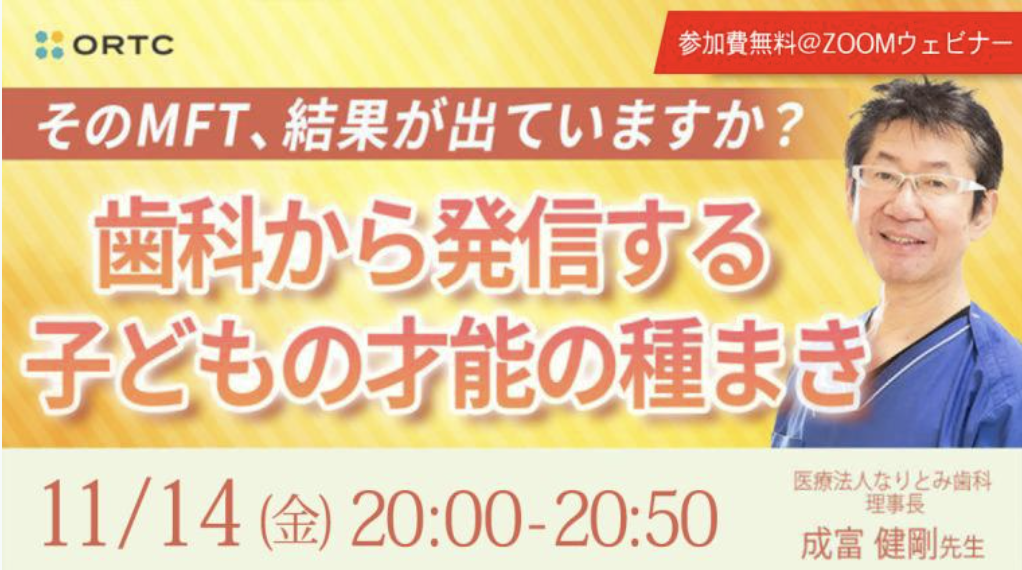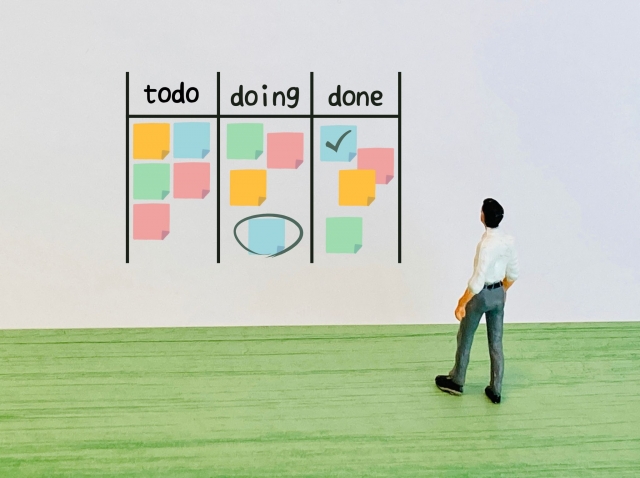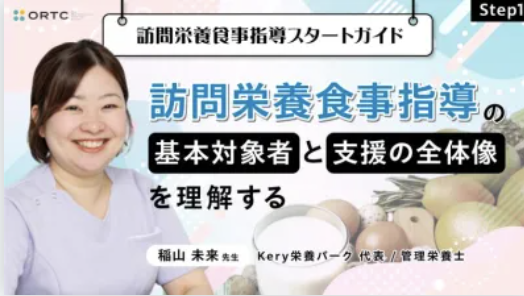歯科医院の経営を安定させるうえで、「自由診療の拡大」だけが答えではありません。
診療報酬改定を重ねる今、保険診療の中で確実に収益を積み上げ、継続的な患者信頼を築くことが重要になっています。
中でも注目されているのが「小児口腔機能管理料」です。
小児期からの口腔機能の発達を支援しながら、予防歯科やMFT(口腔筋機能療法)との連携にもつながるこの管理料は、“医療の質向上”と“経営基盤の強化”を同時に実現できる制度です。
本記事では、歯科経営者の立場から
・なぜ今、小児の口腔機能管理が重要なのか
・算定の具体的プロセスと体制づくり
・経営・ブランディングへの効果
を分かりやすく解説します。
院内での導入判断に役立つ実践的なヒントとして、ぜひ参考にしてください。
子どもたちの口腔の発達不全が及ぼす未来への影響や説得力のある「口腔機能発達不全」対応への説明へのアドバイスなど、ORTC onlineでセミナーを行なっております。子どもの発達の知識を理解しMFTを取り入れ、治療をスタートさせ継続に繋げる秘訣セミナーです。
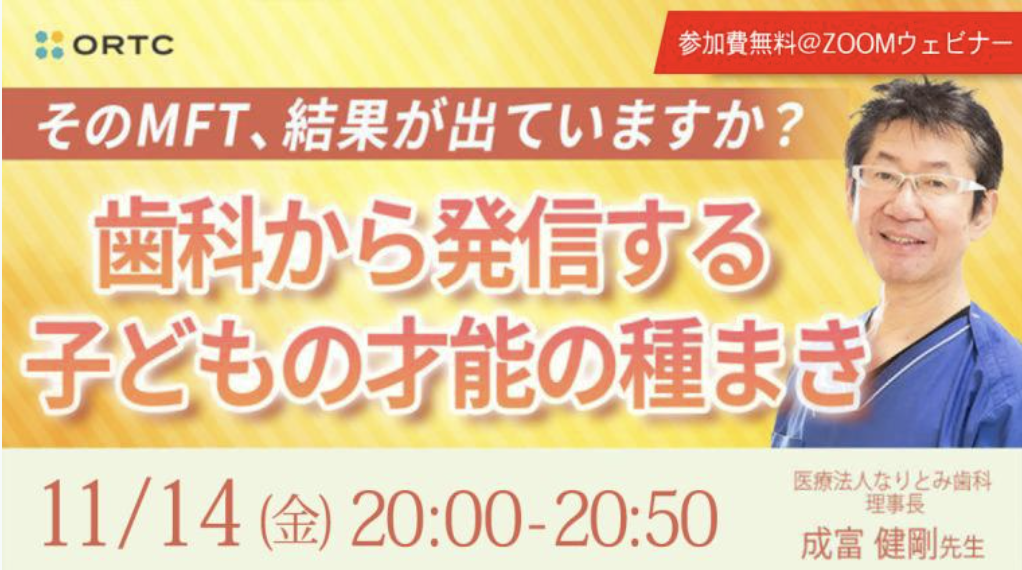
そのMFT、結果が出ていますか?~歯科から発信する子どもの才能の種まき~
講師 医療法人なりとみ歯科 理事長 成富健剛
(11/14開催 参加無料@zoomウェビナー)
https://ortc.jp/seminar/new/MFT1114
なぜ今「小児の口腔機能管理」が重要なのか

近年、「口を閉じられない」「よく噛めない」といった子どもの口腔機能発達不全は、いまや珍しい問題ではありません。スマホや軟食など生活環境の変化が影響しています。歯並びや咬合だけでなく、呼吸・姿勢・全身の成長にも影響することが分かっており、早期発見と介入が不可欠です。
そのなかで歯科医院が担うべき役割は、単なる“虫歯治療”ではなく、“機能発達の伴走者”へと変化しています。
小児口腔機能管理料は、その体制を整えるための制度的な枠組みであり、医療の質と経営の安定を両立させるチャンスでもあります。この管理料を適切に活用できるかどうかが、これからの小児歯科経営を左右すると言っても過言ではありません。
経営面でも、予防型診療・リコール強化の基盤として、医院の信頼と持続的収益を支える重要な領域となっています。
口腔機能の発達不全が増加している背景
子どもの口腔機能発達不全は、生活習慣の変化とともに年々増えています。
軟食傾向・咀嚼回数の低下・長時間のスマホ姿勢・口呼吸などが重なり、十分に噛めない・正しい嚥下ができないなどの機能不全を引き起こします。
これは歯並びや咬合だけでなく、全身の成長や心身発達にも影響するため、歯科が早期から関わる重要性が高まっています。
現場でも“食べ方・話し方・呼吸のクセ”に気づく機会が増えています。早期に関われる体制がある医院は、本当に保護者から感謝されます。
診療報酬改定で注目が高まる「小児口腔機能管理料」
2024年の診療報酬改定では、小児口腔機能管理料の対象年齢が拡大され、国として“成長期からの口腔機能支援”を後押しする姿勢が明確になりました。
単なる加算ではなく、評価・管理・計画的支援までを求める仕組みとなっているため、医院として体制整備が必要です。
今後は、この管理料を活用できるかどうかが、小児歯科領域での競争力と専門性の差につながっていきます。
制度が整った“今”がスタートのタイミングです。始める医院と始めない医院で、数年後の差は確実に広がります。
予防中心の小児歯科が医院の信頼を高める理由
小児期から機能発達を支援する診療は、保護者にとって「治療の場」ではなく「子どもの成長をサポートしてくれる場所」として映ります。
むし歯治療中心の医院より、予防・教育型の小児歯科は信頼性が高く、継続的な受診や家族での来院につながりやすいのが特徴です。
口腔機能管理を軸にした診療は、医院のブランド価値を高め、地域で“選ばれる存在”になる大きな強みとなります。
制度が整った“今”がスタートのタイミングです。始める医院と始めない医院で、数年後の差は確実に広がります。
近年、“治す歯科”から“育てる歯科”と聞くことが増えました。ここに力を入れている医院は、保護者の紹介や口コミの広がり方が違います。
小児口腔機能管理料の算定要件とプロセス
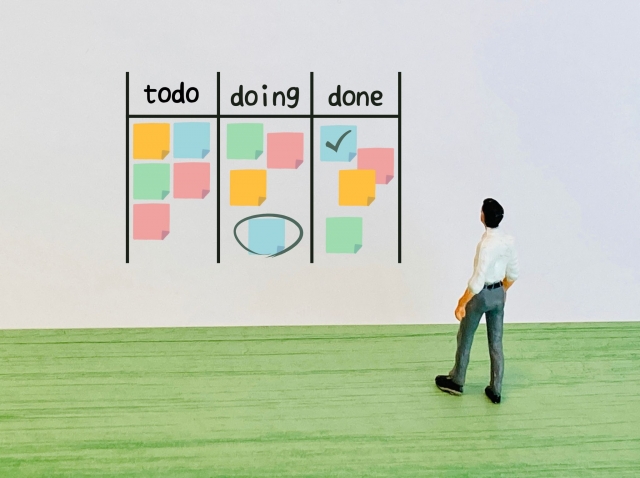
小児口腔機能管理料は、単に“算定できるかどうか”ではなく、どのように評価・記録・管理していくかが問われる制度です。
対象となるのは、口腔機能の発達に問題がみられる18歳未満の小児です。診断・検査・訓練の3段階で、機能の状態を科学的に評価し、保護者の同意を得たうえで計画的に支援を行うことが求められます。
算定には、チェックリスト・評価票・写真記録・管理計画書といった書類整備が欠かせません。
一見ハードルが高く感じられるものの、一度院内フローを構築すれば、衛生士主導で運用できる仕組みです。
ここでは、算定の要件と流れを整理し、スムーズに取り入れるための実務ポイントを解説します。
対象患者と年齢条件
小児口腔機能管理料の対象は、18歳未満で、口腔機能の発達に課題がみられる小児です。
診断は、問診・視診(口腔内所見)・機能検査を総合的に行い、必要な評価項目が一定数該当した場合に、口腔機能発達不全症と診断されます。機能検査には、リップフォースメーター(口唇閉鎖力)、舌圧計、咀嚼・嚥下状態の確認などが含まれ、日本歯科医学会が示す診断基準のチェックリストを参考にします。
https://www.jads.jp/assets/pdf/basic/r06/document-240402-2.pdf
口腔機能発達不全症に関する基本的な考え方(日本歯科医学会)
“気になるサインがある子ども”のうちに評価できる体制が、保護者の強い味方になれます。
必要な評価・検査(口唇閉鎖力・舌圧・問診・写真など)
小児口腔機能管理料を算定するためには、口腔機能の状態を客観的に評価し、根拠が残る形で記録する必要があります。
評価の基本項目は以下の通りです。
評価項目 | 内容・目的 | 実施タイミング |
問診 | 食習慣、姿勢、呼吸、発音、生活状況などを確認 | 初回+再評価時 |
視診(口腔内・全身) | 口唇閉鎖、舌位置、歯列、嚥下時の口元、姿勢などを観察 | 初回+再評価時 |
機能検査 | 口唇閉鎖力(リップフォースメーター)、舌圧(舌圧計)、咀嚼・嚥下状態の確認 | 初回+必要に応じて |
写真撮影 | 口唇閉鎖、舌位置、姿勢、口腔内などの記録として保存 | ※算定要件として必須(下記参照) |
写真撮影の必須要件
・初回算定時は必ずカラー写真を撮影し、診療録に添付または電子保存
・その後は、3回算定するごとに1回以上の写真撮影が必要
評価は、初回評価だけで終わらせず「初回 → 計画 → 再評価 → 継続支援」という流れで行うことで、改善度が明確になり保護者への説明・協力も得やすくなります。
算定に必要な書類(管理計画書・同意書・記録・写真保存)
保険算定をする上で、必要になってくる書類は5つあります。これらは「算定の根拠」と「支援の継続性」を示す重要な資料であり、院内で形式を統一して運用することで算定の安定化につながります。
①同意書
小児口腔機能管理を行うことに対して、保護者の理解と同意を得るための文書です。初回算定前に必ず取得し、保管します。後々の説明不足トラブルを防ぐ役割もあります。
②管理計画書
初回評価に基づき、「どの課題に対して、どのような支援を、どの期間行うのか」を明確にした計画書です。作成後は保護者へ説明し、文書で提供します。継続算定の根拠になるため内容はわかりやすく簡潔にまとめることがポイントです。
③カルテ記録
毎回の指導内容・支援内容・経過を記録します。「口頭指導した」という表現だけでは不十分で、指導内容や保護者への説明内容まで記載しておくことが望ましいです。管理計画書の写しも添付しておくと、流れが一目で確認できます。
④カラー写真
初回算定時には必ずカラー写真の保存が必要です。また、3回算定するごとに1回を目安に、状態の変化がわかる写真を撮影し、保存します。口唇閉鎖、舌位、口腔内所見など、変化が比較しやすい部位を記録することが大切です。
⑤初回評価シート(※実質必須)
診断の根拠となる評価項目を記録したシートです。口腔機能発達不全症に該当した根拠が残るため、監査対策としても極めて重要です。初回評価だけでなく、再評価時にも同じシートで比較できる形式にしておくと運用がスムーズです。
これらの書類は、作成することが目的ではなく、支援の経過が一目で追える状態にすることが最も大切です。
フォーマット化して院内で統一することで、どのスタッフでも同じ水準で対応でき、算定漏れや記録不足を防ぐことができます。
歯科経営者が整えるべき“算定促進体制”

小児口腔機能管理料は、院長ひとりの理解だけでは機能しません。評価・記録・書類作成・保護者対応など、複数の工程をチームで分担し、“仕組みとして回す”ことが算定の継続につながります。
一度フローを作れば、衛生士主導で自然に算定が進む体制を築けるため、結果として院長の負担も軽減されます。また、この取り組みは単なる保険算定の効率化にとどまらず、スタッフ教育・院内の一体感・地域からの信頼といった無形資産の強化にも直結します。
経営者として求められるのは、“現場が動ける環境づくり”と“成果が見える運用設計”です。
算定を促進するための実践的な体制構築のポイント
・役割分担を決める(評価・計画書作成・説明・記録・再評価)
・院内フローを統一(属人化させず、誰でも回せる形に)
・衛生士が主導できる環境を用意(研修・任せる姿勢・相談ルート)
・保護者説明の型を作る(スクリプト+見える化資料)
・成果を共有し、院内で成功体験を積む(改善事例をスタッフ間で共有)
仕組み化されている医院は、スタッフが動きやすいです。任せてもらえる環境があるほど、DHは成長し、自走します。
算定がもたらす経営効果とブランディング価値

小児口腔機能管理料の導入は、単に点数を積み上げるための取り組みではありません。子どもの発達を支える姿勢そのものが、医院の信頼とブランドを形成します。
「口腔機能を育てる歯科」として地域から認識されることは、保護者の共感を生み、リコール率や家族での受診率を高める結果につながります。
また、管理料の算定を通してスタッフの専門性向上・医院の社会的評価・自由診療への波及効果といった経営的リターンも期待できます。目の前の算定1件が、将来の医院価値を積み上げていくことになります。
ここでは、算定体制の定着が生み出す“経営的・ブランディング的メリット”を具体的に掘り下げます。
リコール率・再来率の向上
口腔機能の経過を継続的に見守る診療スタイルは、保護者の安心感につながり、定期的な通院の習慣化を促します。「診てもらいたい理由」が生まれるため、リコール率が自然と向上し、家族ぐるみの受診にも発展しやすくなります。
地域での小児口腔機能支援の実績が医院の信用に
小児の成長を支える取り組みを行う医院は、地域から「子どものお口を任せられる場所」として選ばれやすくなります。実績が積み重なるほど紹介も生まれ、医院の専門性と社会的信用が確立されます。
自由診療への波及(矯正・MFT・メンテナンス)
小児口腔機能支援を通じて保護者の理解が深まると、矯正相談やMFT、メンテナンスなどの自由診療への導線がスムーズになります。「必要性を感じてもらえる状態」が作れるため、押し売りにならず自然に受診が広がります。
経営安定化とスタッフモチベーションの好循環
算定体制が定着すると、医院収益の安定化だけでなく、スタッフの役割拡大や成長実感にもつながります。やりがいと結果が見える診療はチームの士気を高め、良い循環で医院力を底上げします。
まとめ

小児口腔機能管理料は、制度としての複雑さよりも、取り組む姿勢と体制づくりが成果を左右します。単なる保険算定の枠を超え、子どもの発達支援を軸にした診療スタイルを築くことは、医院の信頼を高め、安定した経営基盤を育てることにもつながります。
現場で子どもたちと向き合う歯科衛生士から見ても、口腔機能の評価やトレーニングは、“治療”よりも“成長を支えるケア”としてやりがいの大きい領域です。
「食べる・話す・呼吸する」を支える支援を継続することで、子どもの変化を間近で感じられ、保護者からの信頼も深まります。だからこそ経営者には、算定体制を整えるだけでなく、衛生士が主体的に関われる環境づくりを意識することが重要です。
歯科衛生士の専門性が最大限に発揮される現場こそ、医院のブランド価値を高め、長期的なリピートと紹介につながっていきます。
まずはスタッフと共に、「評価・記録・説明」の流れを作ることから始めていきましょう。その一歩が、地域に根ざした“教育型・予防型歯科医院”への始まりになります。
さらに深く学びたい方は、ORTC onlineでのセミナーもあわせてご覧ください。
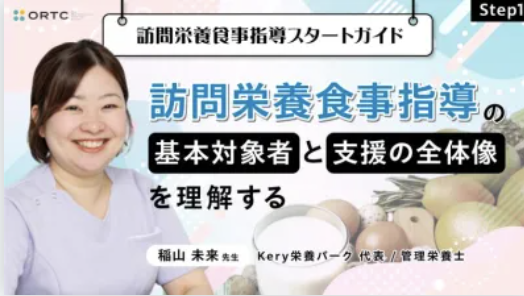
講師:Kery栄養パーク 代表 管理栄養士 稲山未来
Step1 訪問栄養食事指導の基本 対象者と支援の全体像を理解する
https://ortc.jp/movie/new/dental-rd-home-nutrition-care-guide
Q&A
Q1. 小児口腔機能管理料は、どんな医院でも算定できますか?
A1. 対象となるのは、施設基準を満たし届出を行っている歯科医院です。算定には、評価・記録・同意書・管理計画書などの整備が必要で、スタッフ教育体制も求められます。基準をクリアすれば、小児歯科を標榜していない一般歯科でも算定可能です。
Q2. 算定の手間に見合うメリットはありますか?
A2. あります。小児口腔機能管理料は単なる加算ではなく、「予防・教育型診療」を形にできる仕組みです。継続的な評価を通じてリコール率が上がり、自由診療(矯正・MFT)への導線にもつながります。経営的にもブランディング的にも費用対効果の高い取り組みです。
Q3. スタッフにどうやって算定体制を浸透させればよいですか?
A3. 衛生士主導の「チェック→記録→報告」の流れを作ることがポイントです。評価票や口唇閉鎖力検査などをルーチン化し、マニュアルを整備しましょう。研修や院内勉強会を行い、「自分たちの仕事が子どもの将来を支える」意識を共有すると、自然と算定率が上がります。
Q4. 算定を継続的に運用していくためのコツは?
A4. “初回で終わらせない”こと。再評価やトレーニングの継続が算定の鍵です。
リコール時にチェックリストや再撮影をルーチン化することで、継続加算につながります。衛生士主導での「再評価→説明→管理計画書更新」をサイクル化しましょう。
Q5. 算定ミスや指摘を避けるために気をつける点は?
A5. よくある誤算定は、対象年齢外の算定・記録不備・同意書未取得などです。診療記録、評価票、写真保存を徹底することが重要です。診断・検査・訓練のそれぞれで「根拠が残る書類」を整えることで安心して算定できます。
歯科衛生士ライター 原田
歯科医療の現場で役立つ実践的な知識を届けるORTC

ORTCは「笑顔の役に立つ」を理念に、歯科界の知識を共有する場を目指しています。歯科医療の現場で役立つ最新の知識と技術を提供することで、臨床と経営の両面からクリニックの成長を支援します。最先端の技術解説や経営戦略に特化した情報を集約し、歯科医療の現場での成果を最大化。自己成長を追求するためのコンテンツをぜひご活用ください。
無料会員登録
無料動画の視聴、有料動画のレンタルが可能です。歯科業界についてのオンライン・オフラインセミナーへの参加が可能となります。
ORTCPRIME
月額5500円で、 ORTC内のすべての動画を見放題に。臨床の現場に役立つ最新の技術解説や、歯科医院経営の成功戦略を網羅した特別コンテンツをご利用いただけます。 歯科業界の方へ効率的に知識を深めていただける内容です。
ORTC動画一覧
ORTCセミナー一覧
まずは無料会員登録
こちらのリンクより会員登録ページへお進みください。
会員登録はこちら
ORTCPRIMEへのアップグレードも簡単!
登録後は「マイページ」から、ORTCPRIMEにいつでもアップグレード可能です。
 こちらの動画もおすすめです
こちらの動画もおすすめです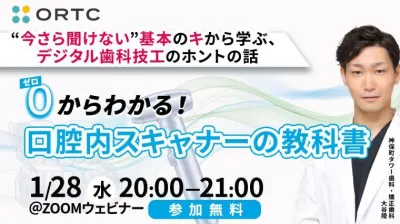 “今さら聞けない”基本のキから学ぶ、デジタル歯科技工のホントの話『ゼロからわかる、口腔内スキャナーの教科書』
“今さら聞けない”基本のキから学ぶ、デジタル歯科技工のホントの話『ゼロからわかる、口腔内スキャナーの教科書』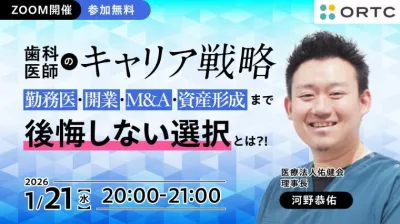 歯科医師のキャリア戦略 ― 勤務医・開業・M&A・資産形成まで、後悔しない選択とは ―
歯科医師のキャリア戦略 ― 勤務医・開業・M&A・資産形成まで、後悔しない選択とは ―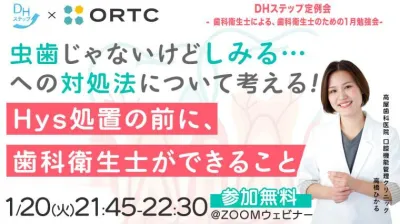 虫歯じゃないけどしみる…への対処法について考える Hys処置の前に、歯科衛生士ができること
虫歯じゃないけどしみる…への対処法について考える Hys処置の前に、歯科衛生士ができること 「TBIが変われば患者が変わる」 自費TBI成功マインド
「TBIが変われば患者が変わる」 自費TBI成功マインド Implant Guide Course | インプラント・ガイデッドサージェリー徹底解説|静的・動的ガイドの使い分けとAll-on-4への応用
Implant Guide Course | インプラント・ガイデッドサージェリー徹底解説|静的・動的ガイドの使い分けとAll-on-4への応用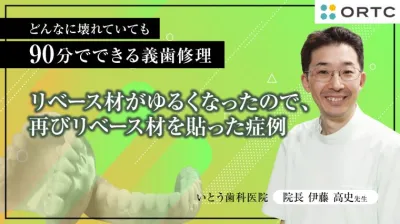 リベース材がゆるくなったので、再びリベース材を貼った症例
リベース材がゆるくなったので、再びリベース材を貼った症例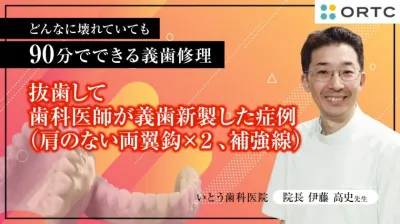 抜歯して歯科医師が義歯新製した症例(肩のない両翼鈎×2、補強線)
抜歯して歯科医師が義歯新製した症例(肩のない両翼鈎×2、補強線) 後継者不在、人材不足、競争激化を乗り切る! 歯科医院M&Aの基本と成功へのプロセス
後継者不在、人材不足、競争激化を乗り切る! 歯科医院M&Aの基本と成功へのプロセス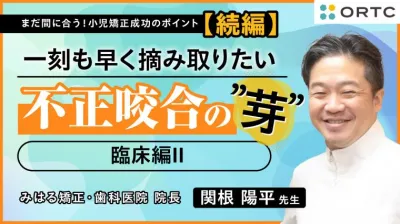 続・まだ間に合う!小児矯正のポイント 〜一刻も早く摘み取りたい 不正咬合の”芽”~ 臨床編Ⅱ
続・まだ間に合う!小児矯正のポイント 〜一刻も早く摘み取りたい 不正咬合の”芽”~ 臨床編Ⅱ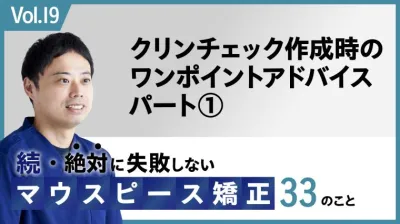 続・ 絶対に失敗しないMP矯正33の事 クリンチェック作成時のワンポイントアドバイス パート①スーパーインポーズ機能
続・ 絶対に失敗しないMP矯正33の事 クリンチェック作成時のワンポイントアドバイス パート①スーパーインポーズ機能