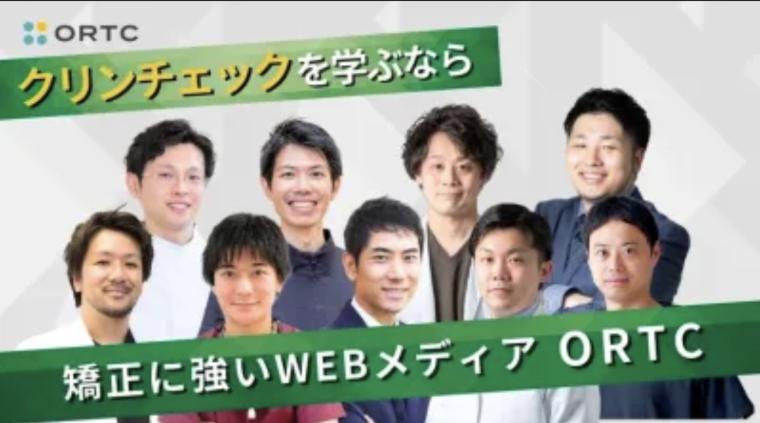フラップ手術は、歯周治療において重要な外科的アプローチの一つです。
深い歯周ポケットや複雑な骨欠損に対して、直視下での確実な処置を可能にし、歯周組織の再生を促進するこの術式は、多くの歯科医療現場で実施されています。
本記事では、フラップ手術の基本的概念から実践的な手技、さらには術後管理まで、臨床現場で必要となる知識を体系的に解説します。
特に、歯科医師と歯科衛生士の連携に焦点を当て、治療の成功率を高めるためのポイントを詳細に紹介していきますので、ご参考くださいね。
フラップ手術の基礎理解

フラップ手術の基礎理解として押さえておきたいのが以下の点です。
・
・適応症と術前評価
それぞれ詳しく解説します。
定義と目的
フラップ手術は、歯周治療における外科的アプローチの代表的な術式です。
その主な目的は、深い歯周ポケット内部の病的組織を確実に除去し、歯根面の徹底的なデブライドメントを行うことにあります。
歯肉を剥離することから展開することで、通常のSRP(スケーリング・ルートプレーニング)では到達困難な深部歯周ポケットや複雑な骨欠損部位に直接アプローチすることが可能となります。
直視下での処置により、歯石や壊死組織の完全な除去、さらには歯根面の徹底的な清掃と平滑化を実現できます。
また、適切な歯肉弁の形成と縫合により、歯周組織の再生を促進し、新たな付着の獲得を図ることができます。
これにより、歯周ポケットの減少、付着の獲得、そして長期的な歯周組織の安定性が期待できるでしょう。
適応症と術前評価
フラップ手術の適応を判断する際、最も重要な基準は歯周ポケットの深さと骨欠損のパターンです。
一般的に、非外科的治療で改善が見られない6mm以上の歯周ポケットや、垂直性骨欠損を伴う中等度~重度の歯周炎症例が主な適応となります。
術前の全身状態評価では、糖尿病、高血圧、心疾患、骨粗鬆症などの基礎疾患や服用薬剤(特に抗凝固薬)の確認が不可欠です。
また、喫煙習慣も治療予後に大きく影響するため、詳細な問診が必要となります。
出血傾向や感染性がある場合は、手術の延期や代替治療の検討が必要です。
さらに、術前の口腔衛生状態とプラークコントロールレベルは治療成功の鍵となります。
PCR(プラークコントロールレコード)20%以下を目標とし、患者のモチベーションと口腔清掃技術の向上を確認してから手術に臨むことが推奨されています。
手術の実際

実際にフラップ手術を行う際には、以下の準備が必要になります。
こちらもそれぞれ確認していきましょう。
術前準備
フラップ手術の成功には、入念な術前準備が不可欠です。
まず、FOPセットの準備では、メス(15号、15C号)、剥離子、鋭匙鉗子、持針器、縫合針(4-0シルク)などの基本器具に加え、タービン、コントラアングル、超音波スケーラーなどの動的器具も滅菌のうえセットアップします。
また、生理食塩水、消毒剤、軟膏類も使用順に配置しておきましょう。
術者とアシスタントの連携では、内回り(直接介助)と外回り(間接介助)の2名体制が理想的です。
内回りは清潔操作を維持しながら器具の受け渡しを担当し、外回りは照明調整、バキューム操作、物品の補充を行います。
感染防止対策として、術者・アシスタントともにマスク、ゴーグル、ガウン、グローブを適切に装着します。
特に清潔野の確保には細心の注意を払い、器具の受け渡しや操作時の汚染防止に努めます。
これらの準備を術式の流れに沿って体系的に行うことで、円滑な手術進行が可能です。
手術手技のステップ確認

フラップ手術における手技は、適切な局所麻酔から始まります。
浸潤麻酔に加え、必要に応じて伝達麻酔を併用し、十分な麻酔深度を確保しましょう。
切開デザインは、歯間乳頭部を保存する内斜切開を基本とし、骨欠損の形態や術野の展開を考慮して設計します。
続いて、粘膜骨膜弁の剥離では、骨膜剥離子を用いて愛護的に全層弁を形成します。
この際、周囲組織の損傷を避けながら、十分な視野が得られるまで慎重に剥離を進めます。
術野が展開されたら、肉芽組織の除去、歯石のデブライドメント、そして根面のルートプレーニングを徹底的に行います。
最後の縫合では、4-0シルク糸を用いた単純縫合あるいはマットレス縫合です。
創の閉鎖時は、歯間乳頭部の適切な位置付けと緊密な縫合により、一次治癒を促進します。
また、必要に応じて歯周パックを装着し、創部の保護を図ります。
術後管理とフォローアップ

無事フラップ手術を終えたら、今後はフォローアップに努めます。
留意したい点は以下のとおりです。
それぞれ見ていきましょう。
術直後の管理
フラップ手術後の管理は、患者の早期回復と合併症予防のために極めて重要です。
術直後から24時間は、ガーゼ圧迫による止血確認と、冷罨法による腫脹の抑制を指示します。
疼痛に対しては、術後の痛みのピークが48時間後であることを説明したうえで、適切な鎮痛剤を処方します。
投薬については、抗菌薬(通常3-5日分)と消炎鎮痛剤を基本とし、必要に応じて含嗽剤を追加します。
生活指導では、術後24時間は歯磨きを控え、その後も手術部位を避けた優しいブラッシングを指導しましょう。
また、禁煙、過度な運動の回避、アルコール制限などの注意事項も具体的に説明します。
緊急時の対応として、異常出血や強い疼痛、発熱などの症状出現時の連絡方法を明確に伝えておきます。
診療時間内外での連絡先を明記した術後指導書を渡し、患者様に安心していただけるよう備えがあることを伝えましょう。
長期的な経過観察
フラップ手術後の長期的な経過観察は、治療成功の鍵です。
リコールスケジュールは、術後1週間での抜糸を起点とし、2週間後、1ヶ月後、3ヶ月後と段階的に設定します。
特に術後3ヶ月までは慎重な経過観察が必要で、その後は患者の治癒状態に応じて3-4ヶ月ごとのメインテナンスに移行します。
プラークコントロールの再評価では、術後の回復に合わせてブラッシング方法を段階的に調整します。
PCRを用いた客観的評価と、歯間ブラシやフロスの使用状況を確認し、必要に応じて清掃指導を行います。
治癒経過の評価は、以下の項目を基準とします。
- プロービング値の改善(3mm以下を目標)
- 歯肉の性状(発赤・腫脹の消失)
- 付着の獲得状態
- エックス線写真による骨レベルの変化
これらの項目を総合的に評価し、治療効果の判定と長期的な予後予測を行います。
チーム医療としての取り組み

フラップ手術はもちろんですが、歯科医療は基本的にチーム医療が重要になります。
ここでは、歯科衛生士の役割と知っておきたい留意事項をまとめました。
歯科衛生士の役割
フラップ手術における歯科衛生士の役割は、治療の全過程で重要な位置を占めます。
術前では、徹底的なプラークコントロール指導を行い、PCR20%以下を目標とした口腔衛生状態の改善が重要です。
患者の口腔清掃技術とモチベーションを向上させることで、手術の予後を大きく左右する基盤を整えます。
手術時には、内回り・外回りのアシスタントとして重要な役割を担います。
器具の準備・受け渡し、バキューム操作、術野の確保など、術者との緊密な連携により手術の円滑な進行をサポートします。
特に清潔操作の維持と術野の的確な視認性確保は、アシスタントの技量が直接影響する重要な要素です。
術後は、個々の患者の回復状態や生活環境を考慮した、きめ細かなメインテナンスプログラムを立案しましょう。
定期的な専門的歯面清掃(PMTC)、口腔衛生指導の継続、そして長期的な予後管理を通じて、治療結果の安定性を確保します。
治療成功のための要件
フラップ手術の成功には、術式の完遂だけでなく、包括的な治療管理体制の確立が不可欠です。
まず、患者教育においては、治療の必要性と術後の自己管理の重要性を十分に説明し、術前からのモチベーション構築が重要です。
視覚資料や症例写真を用いた分かりやすい説明により、患者の治療への理解と協力を得ることが治療成功の基盤となります。
スタッフ間の情報共有では、術前カンファレンスによる治療計画の確認、術中の注意点、術後管理の要点などを、歯科医師、歯科衛生士間で明確に共有しましょう。
特に患者の全身状態や服薬情報、不安要素などは確実な申し送りが必要です。
症例記録の管理では、術前・術中・術後の写真記録、プロービング値、エックス線写真などの客観的データを経時的に記録します。
これらの記録は、治療効果の評価だけでなく、類似症例への対応や若手スタッフの教育にも活用され、チーム全体の技術向上に貢献します。
合併症への対応と予防

ここでは合併症の対応や予防、禁忌事項を解説します。
以下の2項目で解説しているので、参考にしてください。
早期合併症
フラップ手術後の早期合併症には、適切な予防と迅速な対応が求められます。
最も注意すべき術後出血は、通常24時間以内に発生し、基礎疾患や服薬状況が影響します。
過度な出血に対しては、ガーゼ圧迫や局所止血剤の使用、必要に応じて縫合の追加を行いましょう。
感染兆候(疼痛増強、腫脹、発熱)が認められた場合は、抗菌薬の投与と創部の洗浄を実施します。
歯肉退縮は、特に審美領域で問題となりやすく、不適切な切開デザインや過度な組織操作が原因となります。
これに伴う知覚過敏に対しては、知覚過敏抑制材の塗布や露出根面のコーティングなどで対応します。
創傷治癒不全は、局所因子(プラークコントロール不良、喫煙)や全身因子(糖尿病、免疫不全)が関与します。早期発見のため、術後の定期的な経過観察を徹底し、治癒遅延が認められた場合は、原因の特定と適切な対応策の実施が必要です。
予防的アプローチ
フラップ手術の合併症予防には、包括的なリスク管理と適切な術前評価が重要です。
リスク因子として、喫煙、糖尿病、高血圧、骨粗鬆症などの全身疾患、抗凝固薬の服用、不良な口腔衛生状態などが挙げられます。
これらのリスクを術前に特定し、必要に応じて医科との連携や術前の口腔衛生管理を徹底します。
術式選択では、骨欠損の形態、歯周ポケットの深さ、角化歯肉の幅、根分岐部病変の有無などを総合的に評価しましょう。
過度な侵襲を避けつつ、十分な視野確保が可能な切開デザインを選択し、愛護的な組織操作を心がけます。
術後管理プロトコルは、創傷治癒のステージに応じて段階的に設定します。
術直後の止血確認から始まり、抜糸までの創部管理、その後の口腔衛生指導まで、明確な基準とタイムラインを設定します。
特に感染予防と早期発見のため、定期的な経過観察と適切な指導を組み込んだプロトコルを確立します。
まとめ
フラップ手術は、深い歯周ポケットや複雑な骨欠損に対する重要な外科的アプローチです。
手術の適応には、6mm以上の歯周ポケットや垂直性骨欠損を伴う中等度~重度の歯周炎が含まれ、術前の全身状態評価とプラークコントロール(PCR20%以下)が必須となります。
手術では、適切な局所麻酔後、内斜切開による粘膜骨膜弁の形成、デブライドメント、縫合という基本ステップを踏みます。
術後管理では、24時間以内の出血管理、抗菌薬投与、段階的な口腔衛生指導が重要です。
治療成功には、歯科医師と歯科衛生士の緊密な連携が不可欠で、特に術前のプラークコントロール指導から術後のメインテナンスまで、チームとしての一貫した取り組みが求められます。
また、合併症予防のため、リスク因子の特定と適切な術式選択、そして体系的な術後管理プロトコルの確立が重要となることを覚えておきましょう。
参考資料:知っておきたい歯科外科資料3
編集・執筆
歯科専門ライター 萩原 すう
歯科医療の現場で役立つ実践的な知識を届けるORTC

ORTCは「笑顔の役に立つ」を理念に、歯科界の知識を共有する場を目指しています。歯科医療の現場で役立つ最新の知識と技術を提供することで、臨床と経営の両面からクリニックの成長を支援します。最先端の技術解説や経営戦略に特化した情報を集約し、歯科医療の現場での成果を最大化。自己成長を追求するためのコンテンツをぜひご活用ください。
無料会員登録
無料動画の視聴、有料動画のレンタルが可能です。歯科業界についてのオンライン・オフラインセミナーへの参加が可能となります。
ORTCPRIME
月額5500円で、 ORTC内のすべての動画を見放題に。臨床の現場に役立つ最新の技術解説や、歯科医院経営の成功戦略を網羅した特別コンテンツをご利用いただけます。 歯科業界の方へ効率的に知識を深めていただける内容です。
ORTC動画一覧
ORTCセミナー一覧
まずは無料会員登録
こちらのリンクより会員登録ページへお進みください。
会員登録はこちら
ORTCPRIMEへのアップグレードも簡単!
登録後は「マイページ」から、ORTCPRIMEにいつでもアップグレード可能です。
 こちらの動画もおすすめです
こちらの動画もおすすめです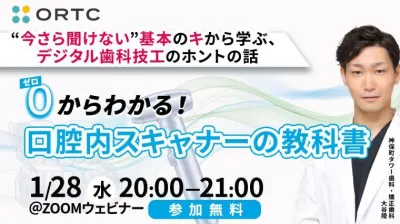 “今さら聞けない”基本のキから学ぶ、デジタル歯科技工のホントの話『ゼロからわかる、口腔内スキャナーの教科書』
“今さら聞けない”基本のキから学ぶ、デジタル歯科技工のホントの話『ゼロからわかる、口腔内スキャナーの教科書』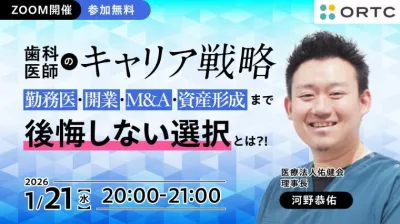 歯科医師のキャリア戦略 ― 勤務医・開業・M&A・資産形成まで、後悔しない選択とは ―
歯科医師のキャリア戦略 ― 勤務医・開業・M&A・資産形成まで、後悔しない選択とは ―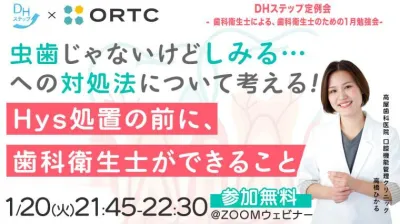 虫歯じゃないけどしみる…への対処法について考える Hys処置の前に、歯科衛生士ができること
虫歯じゃないけどしみる…への対処法について考える Hys処置の前に、歯科衛生士ができること 「TBIが変われば患者が変わる」 自費TBI成功マインド
「TBIが変われば患者が変わる」 自費TBI成功マインド Implant Guide Course | インプラント・ガイデッドサージェリー徹底解説|静的・動的ガイドの使い分けとAll-on-4への応用
Implant Guide Course | インプラント・ガイデッドサージェリー徹底解説|静的・動的ガイドの使い分けとAll-on-4への応用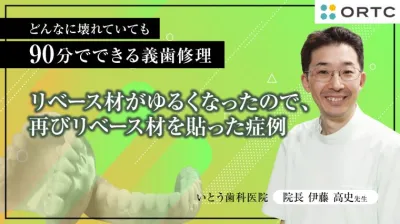 リベース材がゆるくなったので、再びリベース材を貼った症例
リベース材がゆるくなったので、再びリベース材を貼った症例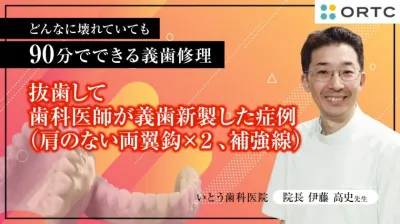 抜歯して歯科医師が義歯新製した症例(肩のない両翼鈎×2、補強線)
抜歯して歯科医師が義歯新製した症例(肩のない両翼鈎×2、補強線) 後継者不在、人材不足、競争激化を乗り切る! 歯科医院M&Aの基本と成功へのプロセス
後継者不在、人材不足、競争激化を乗り切る! 歯科医院M&Aの基本と成功へのプロセス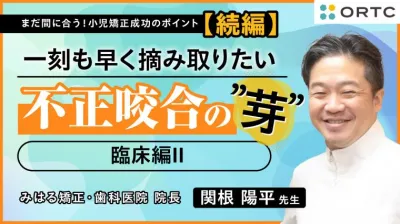 続・まだ間に合う!小児矯正のポイント 〜一刻も早く摘み取りたい 不正咬合の”芽”~ 臨床編Ⅱ
続・まだ間に合う!小児矯正のポイント 〜一刻も早く摘み取りたい 不正咬合の”芽”~ 臨床編Ⅱ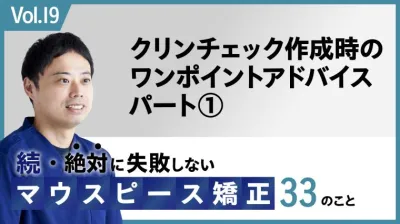 続・ 絶対に失敗しないMP矯正33の事 クリンチェック作成時のワンポイントアドバイス パート①スーパーインポーズ機能
続・ 絶対に失敗しないMP矯正33の事 クリンチェック作成時のワンポイントアドバイス パート①スーパーインポーズ機能