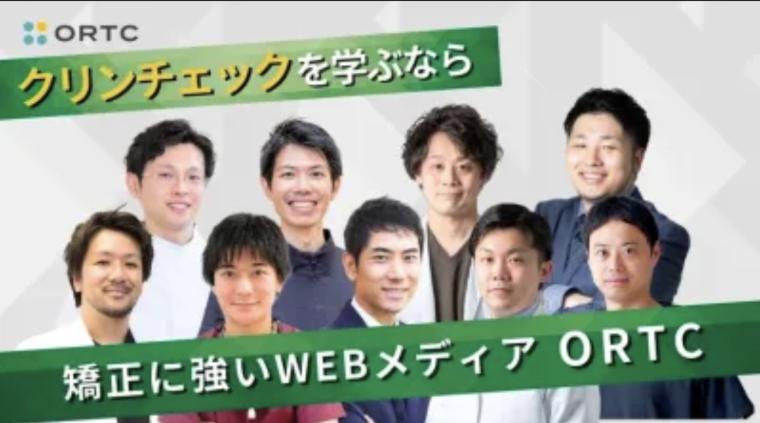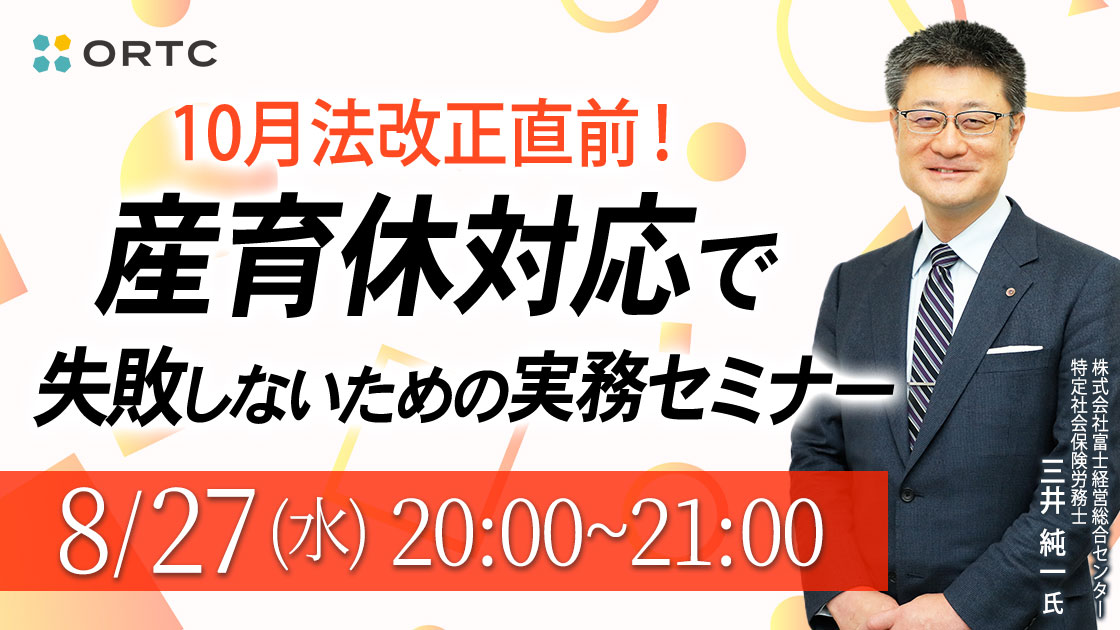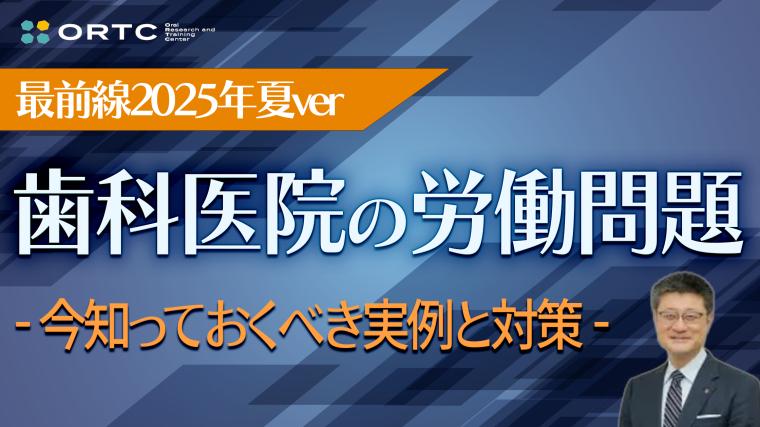歯科医院経営者が押さえる「育児・介護休業法改正2025」ポイントと実務対応
歯科経営
2025年4月と10月にかけて、育児・介護休業法の改正が段階的に施行されます。改正内容は、子育てや介護を行う従業員の働き方をより柔軟に支援する方向にシフトしており、歯科医院にとっても就業規則や勤務体制の見直しが必須となります。
とくに中小規模の医院が多い歯科業界では、非常勤やパート職員も対象になるため、「うちは小規模だから関係ない」とは言えません。むしろ、限られた人員で診療を回す現場だからこそ、早めの準備が経営リスクを防ぎ、職場定着や採用力向上につながります。
本記事では、2025年4月・10月の改正ポイントを整理し、歯科医院がどのような対応を進めるべきかを解説します。
1.2025年4月施行の改正ポイント

①子の看護休暇の対象/拡大と取得事由の追加
これまで小学校就学前までが対象だった「子の看護休暇」が、小学3年生までの子に拡大されます。また、取得事由として「感染症予防のための登校・登園自粛」や「学級閉鎖への対応」なども追加。近年の感染症流行や学級閉鎖の増加を踏まえた対応です。
歯科医院への影響
小学生の子を持つスタッフは珍しくありません。突然の学級閉鎖などで休暇を希望するケースが増える可能性があり、急な人員不足に備える代替体制の整備が求められます。
②所定外労働制限対象拡大
時間外労働や深夜労働の制限が「就学前までの子」を持つ従業員に拡大されます。これにより、子育て中のスタッフから「残業免除申請」が増えることが想定されます。
歯科医院への影響
夕方以降の残業が難しいスタッフが増えるため、シフト作成において「早番・遅番のバランス」を工夫する必要があります。勤務調整を無理に押し付けると離職につながるため、公平性のあるシフト運用ルールを就業規則に明記しておくことが大切です
③育児・介護のためのテレワーク努力義務
従業員が育児や介護を理由に通勤困難となる場合、テレワークを検討する努力義務が課されます。歯科医院では直接診療業務のテレワークは難しいものの、事務作業やリモート会議、資料作成など一部業務は在宅対応可能です。
歯科医院への影響
「診療補助以外の仕事は在宅でもできる」という視点を持ち、受付業務の一部やSNS更新、院内広報資料の作成などを切り出してみましょう。院内で全て抱え込むよりも、柔軟に役割分担することで離職防止につながります。
④介護休暇の取得要件緩和と環境整備義務化
これまで細かい条件があった介護休暇について、取得要件が緩和され、環境整備が義務化されます。介護離職を防ぐための改正であり、歯科医院でも職員の親世代の高齢化に伴い、利用希望が増えることが予測されます。
歯科医院への影響
「介護休暇は特別な制度」という位置づけではなく、育児と同じく「あり得ること」と認識して体制を整えておく必要があります。具体的には、代理業務の割り振りや臨時パートの登録制度を検討しておくと安心です。
⑤育休所得状況の公表義務拡大
これまでは「従業員1,000人超の企業」に限られていた育休取得状況の公表義務が、「従業員300人超」に拡大されます。多くの歯科医院は該当しませんが、業界全体として「取得率を見られる時代」に入ったことを意味します。
歯科医院への影響
小規模医院であっても、採用ページや求人広告で「育休取得実績あり」「短時間勤務実績あり」と明示することで信頼度が増し、採用力向上につながります。形式的な義務がなくても、自院の取り組みを可視化することが重要です。
2.2025年10月施行の改正ポイント

①3歳〜就学前の子を持つ従業員への制度義務化
従業員に対して「始終業の変更」「テレワーク」「短時間勤務」「養育両立支援休暇」などの制度から、少なくとも2つ以上を整備する義務が課されます。
歯科医院への影響
小規模な歯科医院にとって「短時間勤務制度」や「シフトの柔軟対応」は必須となります。例えば、午前診療のみ勤務可能なスタッフを積極的に採用したり、保育園送迎に合わせた始業時間調整を行うなど、柔軟な選択肢を就業規則に明記しておきましょう。
②個別ヒアリング義務の導入
子が3歳になる前の1年間に、事業主が従業員と個別に面談し、今後の働き方や育児と仕事の両立希望を確認する義務が新設されます。
歯科医院への影響
「忙しいから話す時間がない」と後回しにせず、短い面談を年1回でも設けておくことが必要です。このヒアリングを通じて「退職を考えていたが相談できて安心した」というケースも生まれます。採用難の歯科業界において、離職防止の大きな一手となるでしょう。
3.歯科医院が準備すべき事務対応

①就業規則の改訂
・子の看護休暇対象年齢の拡大を反映する
・時間外労働免除や短時間勤務制度の対象を明記する
・育児・介護を理由としたシフト調整ルールを整備する
・在宅業務や代替業務の範囲を明確にする
②運用フローの見直し
・急な休暇発生時の代替シフト作成手順を共有
・パート・非常勤スタッフを含めた連絡網を整備
・介護・育児理由による勤務希望を定期的にヒアリング
③採用・定着戦略への活用
・子育てと介護を両立できる職場として求人に明記
・面接時に柔軟勤務の選択肢を提示し安心感を与える
・院内で実際の利用事例を共有し、働きやすさを可視化する
4.制度は「コスト」ではなく「投資」
 改正育児・介護休業法は、一見すると「小規模医院には負担が大きい」と感じられるかもしれません。しかし視点を変えると、これは優秀な人材を確保し、長期的に定着させるための投資です。スタッフが安心して働ける環境を整えることは、結果として患者さんへのサービス品質や医院の経営安定につながります。
改正育児・介護休業法は、一見すると「小規模医院には負担が大きい」と感じられるかもしれません。しかし視点を変えると、これは優秀な人材を確保し、長期的に定着させるための投資です。スタッフが安心して働ける環境を整えることは、結果として患者さんへのサービス品質や医院の経営安定につながります。
「法律だから仕方なく対応する」ではなく、「働きやすい職場づくりの一環」と前向きに取り組むことが、これからの歯科医院経営に求められます。
まとめ
育児・介護休業法改正は、歯科医院にとって小規模だからこそ影響が大きい内容です。とくにパートや非常勤スタッフの働き方にも関わるため、就業規則や勤務フローの整備は早めに着手すべきです。制度を「負担」ではなく「魅力」として打ち出せれば、採用力・定着力の向上という大きなメリットを得ることができます。
2025年10月施行分は特に「制度設計」と「従業員との対話」が大きな鍵になります。具体的な制度設計や人事労務の実務対応については、以下の専門動画も参考になりますので、ぜひチェックしてみてください。
よくある質問
Qパートやアルバイトも今回の改正の対象になりますか?
A.はい。雇用形態に関わらず労働者であれば対象となります。歯科医院で多い非常勤スタッフも例外ではないため、就業規則やシフト運用において配慮が必要です。
Q.テレワークは歯科医院に実装可能ですか?
A.診療業務自体は難しいですが、事務作業・広報・在庫管理などは一部在宅対応が可能です。「どの業務なら可能か」を院内で整理しておくことが大切です。
Q.小規模歯科医院でも個別ヒアリングは必要ですか?
A.必要です。義務化されるものは全て事業者であり、従業員数が少なくても例外はありません。むしろ小規模歯科医院だからこそ、日常的な対話を制度化することが安心につながります。
Q.就業規則改訂は必ず社会保険労務士に依頼すべきですか?
A.法改正に伴う条文変更は専門家に確認してもらうのが望ましいです。院長自身で修正できる部分もありますが、誤りがあるとトラブルにつながるため、社労士への相談をおすすめします。
歯科衛生士ライター大久保
歯科医療の現場で役立つ実践的な知識を届けるORTC

ORTCは「笑顔の役に立つ」を理念に、歯科界の知識を共有する場を目指しています。歯科医療の現場で役立つ最新の知識と技術を提供することで、臨床と経営の両面からクリニックの成長を支援します。最先端の技術解説や経営戦略に特化した情報を集約し、歯科医療の現場での成果を最大化。自己成長を追求するためのコンテンツをぜひご活用ください。
無料会員登録
無料動画の視聴、有料動画のレンタルが可能です。歯科業界についてのオンライン・オフラインセミナーへの参加が可能となります。
ORTCPRIME
月額5500円で、 ORTC内のすべての動画を見放題に。臨床の現場に役立つ最新の技術解説や、歯科医院経営の成功戦略を網羅した特別コンテンツをご利用いただけます。 歯科業界の方へ効率的に知識を深めていただける内容です。
まずは無料会員登録
こちらのリンクより会員登録ページへお進みください。
ORTCPRIMEへのアップグレードも簡単!
登録後は「マイページ」から、ORTCPRIMEにいつでもアップグレード可能です。