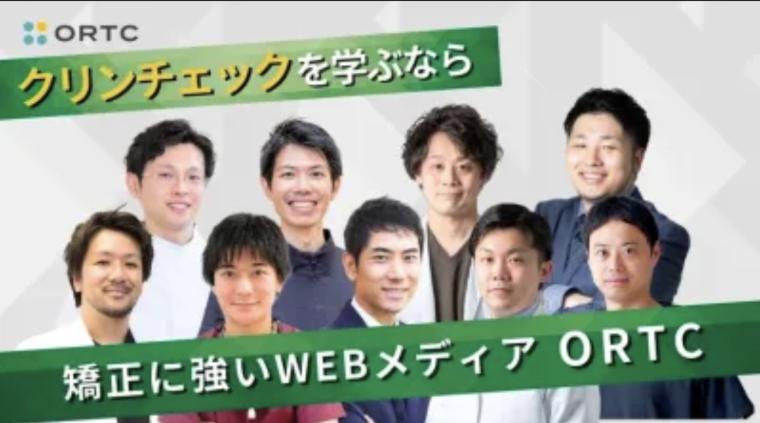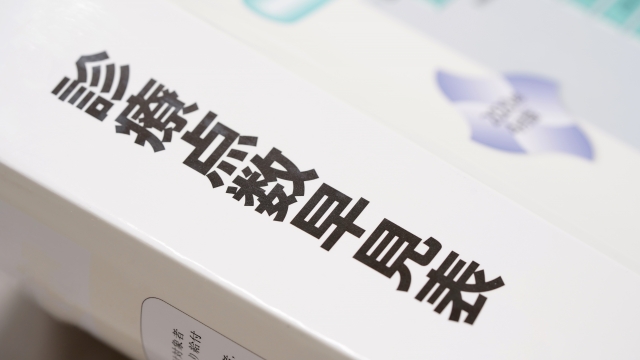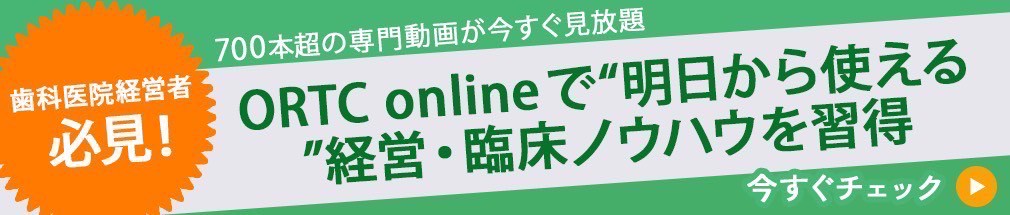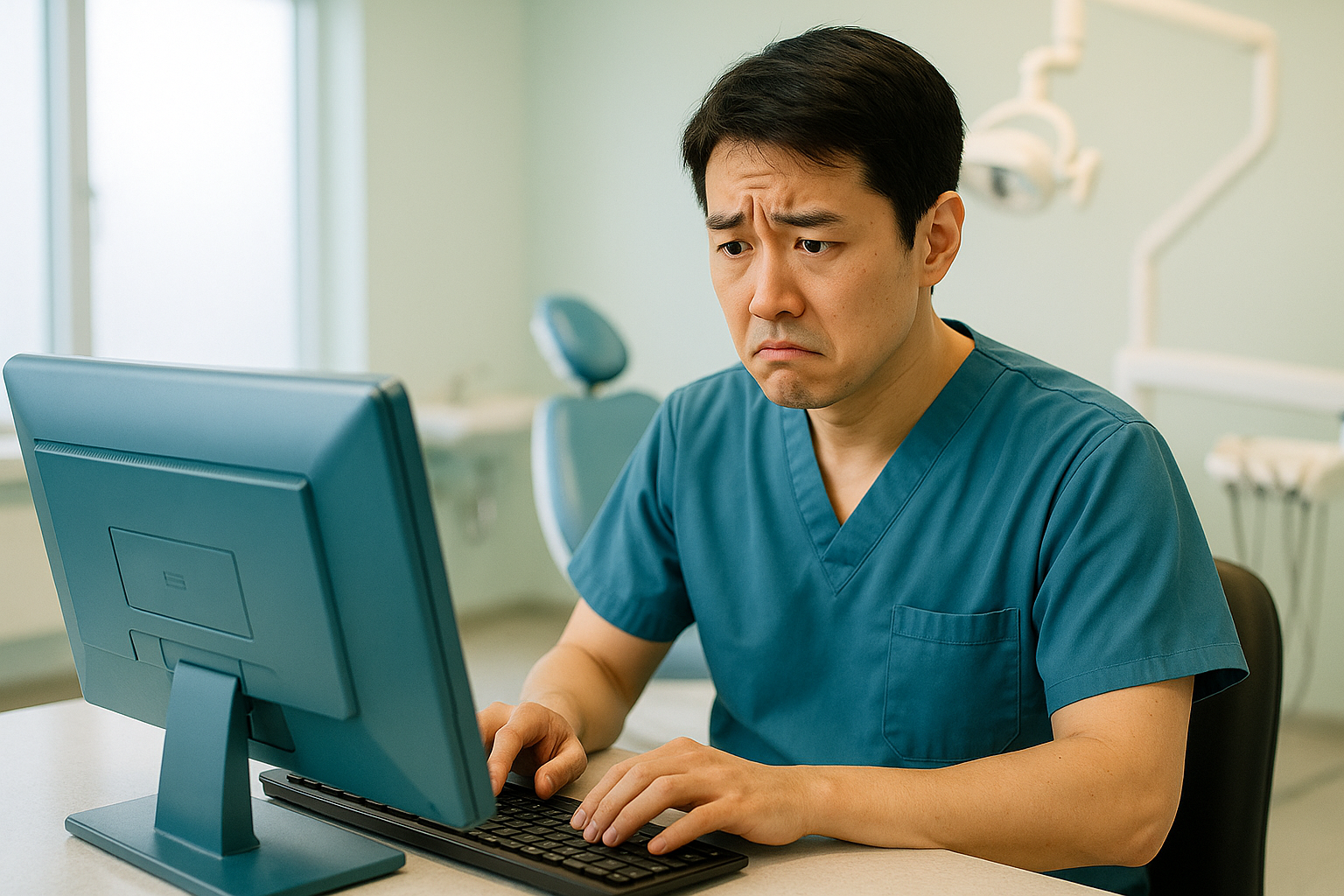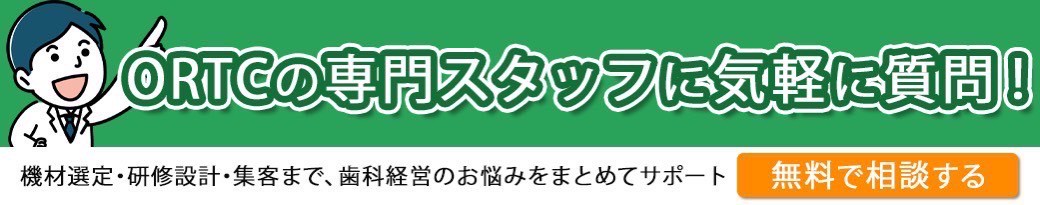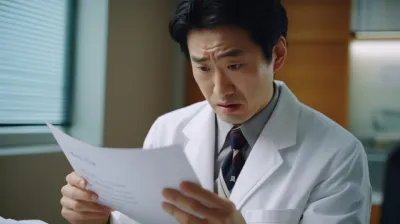2024年6月の診療報酬改定により、「か強診」は新たに「口腔管理体制強化加算(口管強)」へ移行しました。これに伴い、再届出が必要になったことは知っているけれど、まだ手をつけられていないという歯科医院も多いのではないでしょうか。
口管強の届出には、複雑な施設基準や小児研修・訪問診療の実績など、これまで以上に厳格な要件が求められます。「やらなきゃ」と思いながらも、後回しになってしまう理由もよくわかります。
この記事では、制度の要点や届出の流れ、メリット、そして今からでも間に合う対応策をわかりやすく整理しました。「忙しくても損はしたくない」先生のために、書類作成支援や解説動画といった解決策もご紹介します。
2024年診療報酬改定、「か強診」から「口管強」へ
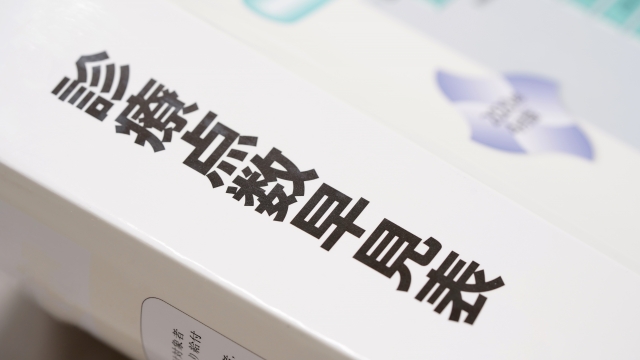
2024年の診療報酬改定で、「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(か強診)」は、「口腔管理体制強化加算(口管強)」へと移行しました。単なる名称変更ではなく、制度の背景や評価の軸も変化しています。
ここではまず、新制度の全体像と、か強診との違いを整理していきましょう。
そもそも「口腔管理体制強化加算(口管強)」とは
「口管強」は、2024年6月に新設された診療報酬上の加算項目です。「かかりつけ歯科医機能強化型診療所(か強診)」から進化し、一生涯を通じた口腔の健康管理に重点を置いた新しい評価制度です。
小児期から重症化予防、高齢者までの継続的な管理の実績が重視され、単なる単発治療ではなくライフコース全体でのケア体制構築が求められるようになっています。
従来の要件に加え、小児口腔機能への対応研修の受講や、訪問診療実績・他医療機関との連携といった項目も加わり、施設基準がかなり複雑化しています。
「か強診の名称変更」ではなく、医院としての取り組み姿勢や体制そのものが改めて問われる制度改革といえます。
今後も患者が“かかりつけ”として選び続けるためには、口腔管理体制だけでなく、医療連携や感染対策まで視野に入れた包括的な取り組みが不可欠です。
「口管強」の全体像と、今すぐ取り組むべき理由をしっかり整理していきましょう。
「か強診」からの変更点|「口管強」が名称変更ではない理由
2024年6月の診療報酬改定で、「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(か強診)」は「口腔管理体制強化加算(口管強)」として新たに制度設計が見直されました。
一見、名称が変わっただけのようにも見えますが、実は制度の“中身”も大きく変わっており、再度の届出が必要です。
なかでも大きな変更点は、以下の3つです。
① 小児口腔機能に関する研修・実績が要件に追加
新制度では、これまで高齢者中心だった評価軸に加え、小児期からの継続管理が強く求められています。
具体的には、小児に関する口腔機能管理の研修受講や、実績要件施設基準に新たに加えられました。
② 医療・福祉機関との連携体制をより厳格に評価
これまでも連携実績は要件のひとつでしたが、地域包括ケアや他職種との関係強化がより明確に求められるようになりました。
例えば、診療情報提供料や連携共有料の算定実績など、点数評価の裏付けが必要です。
③ 外来環・外来感染・歯初診など、他の施設基準との“同時見直し”が前提
「口管強」だけを見直せばいい…というわけではありません。
「外安全(外来環)」「外感染」「歯初診」「医療DX」など、他の届出との関連が深く、まとめて対応する必要があります。
なぜ今、再届出が必要なのか
「か強診は、すでに届出してるから大丈夫」だと思っていませんか?
2024年の診療報酬改定では、「か強診」から「口管強」への移行に伴い、すべての歯科医院で“再届出”が必須になっています。
加算名の変更ではなく、評価基準そのものの見直しが行われたためです。
小児口腔機能への対応や、訪問診療の実績、他機関との連携要件などが追加・拡充されており、以前の届出内容では不十分なケースがほとんどです。
「口管強」だけでなく、外来環(外安全)・外来感染(外感染)・歯初診など他の関連基準も同時に見直しが必要なため、対応の遅れはそのまま算定漏れや機会損失につながりかねません。
再届出の受付は始まっており、対応が遅れるほど、損をする医院と動いた医院の差が開く一方です。
だからこそ、「今」届出対応に動き出すことが、医院の安定経営と信頼獲得の第一歩になります。
口管強を分かりやすく解説した動画はこちら https://ortc.jp/movie/Delivery/movie-1420
これだけは押さえたい!「口管強」の施設基準一覧

「口管強」の届出には、さまざまな施設基準を満たす必要があります。実績や人員体制、研修の受講、小児対応まで、多岐にわたる要件が設定されています。
厚生労働省が定めた基準を項目ごとに整理してご紹介します。
実績要件(重症化予防・口腔機能管理・訪問診療など)
「口管強」では、単に制度に申請するだけでなく、実績として裏付けられる診療活動が求められます。
以下の3つが主要な実績項目です。
① 歯周病・う蝕の重症化予防管理の実績(例:重症化予防治療、周病安定期治療などの算定回数)
② 口腔機能管理の実績(例:オーラルフレイルや摂食嚥下リスクの管理等)
③ 訪問診療・連携診療の実績(例:訪問診療1〜3、支援依頼、診療情報提供など)
届出前1年間での算定回数や対応実績が求められ、感覚的な「やっている」では届出要件を満たせません。
レセプト確認・症例数の整理など、客観的な数値の把握が必須です。
小児口腔機能への対応|研修や診療実績の求められ方
今回の改定で大きなポイントのひとつが、小児に対する口腔機能管理への対応が明確に組み込まれたことです。
これにより、以下2つが新たに要件として加わっています。
① 小児に関する口腔機能管理の研修受講(指定された内容・所定時間数)
② 小児患者への診療実績(例えばフッ化物塗布や管理指導など)
「高齢者対応だけでなく、子どもの口腔発達段階も視野に入れた管理体制が整っているか」が評価対象となるということです。これまで高齢者中心で届出していた歯科医院では、体制や診療方針の見直しが必要になるケースも出てきています。
人員配置・装置基準・緊急時連携体制のチェックポイント
「口管強」のもう一つの大きな柱は、受け入れ体制に関する施設要件です。
以下のようなチェックポイントが求められます。
・歯科医師・歯科衛生士の配置状況
・必要な診療装置・器具の常備(滅菌機器、緊急時対応機器など)
・緊急時の連携体制(医科との連携や協定書の有無)
・「地域の医療・介護・福祉機関との連携」も評価対象となり、学校歯科医や介護会議の参加実績など、地域貢献度も加点要素
見落としがちなのが、設備や書類は整っていても、「実際に活用されているか」が評価されるという点です。
形式だけでは届出が通らないケースもあるため、実績と照らし合わせた見直しが重要です。
口管強を分かりやすく解説した動画はこちら https://ortc.jp/movie/Delivery/movie-1420
「口管強」だけでは不十分? 同時に見直すべき施設基準

「口管強」の届出を検討する際に、見落としがちなのが関連する複数の施設基準です。実際には、「外来環(外安全)」「外来感染(外感染)」「歯初診」なども再届出が必要となっています。
申請の手間を最小限に抑えるために、併せて見直すべき基準とその注意点を解説します。
「外来環(外安全)」「外来感染(外感染)」のポイント
「口管強」を算定するには、外来環(外来診療環境体制加算/通称:外安全)や外来感染対策向上加算(外感染)などの関連基準にも目を向ける必要があります。
・外安全(外来環):AEDや酸素ボンベなどの緊急時設備、スタッフの緊急時対応研修、感染症マニュアルの整備など
・外感染:感染対策の責任者配置、マスク・グローブの使用徹底、院内感染対策の実施体制など
設備基準にとどまらず、院内体制や教育体制そのものが評価される加算となります。
ポイントは、「過去に届出済でも要件が強化されている場合がある」という点です。以前のままでは要件未達の可能性もあるため、改定後の基準に沿って再確認&再届出が必要になります。
「歯初診」「歯援診」「医療DX」など再届出が必要な基準
「口管強」だけでなく、制度改定と同時に他の届出基準も見直されているため、連動してチェックすることが重要です。
以下のような基準が再届出対象になるケースが多く見られます。
・歯初診(歯科初診料の注1):特に口管強の要件に含まれているため、未届出では不可
・歯援診(在宅療養支援歯科診療所):訪問診療実績と連動しており、こちらも要確認
・医療DX推進体制整備加算:マイナ保険証、電子処方、ICT連携などが評価対象となる新設加算
これらの施設基準は、「提出していない=点数が取れない」だけでなく、「他の加算(例:口管強)の算定資格も失う」という連動制約があるため、医院全体での確認が必要不可欠です。
申請様式がバラバラ? 書類作成の落とし穴と注意点
「届出しよう」と思っても、そこで立ちはだかるのが申請書類の複雑さです。
各施設基準ごとに提出様式が異なり、必要書類もまったく統一されていません。
・様式名が類似していて紛らわしい(例:様式17-2、別添1-3 など)
・押印や日付の記載ミス、体制欄の未記入で差し戻しに
・一部基準は“根拠となる診療実績の添付”が必要になる
再届出だからといって「前回と同じで出せばいい」というわけではないのが落とし穴なのです。
2024年改定で様式自体が変更されていたり、記載項目が増えていたりするため、最新版で再作成が必要となります。
口管強を分かりやすく解説した動画はこちら https://ortc.jp/movie/Delivery/movie-1420
口管強取得によるメリットとは?

制度変更や届出は“負担”と感じるかもしれませんが、その先には大きなメリットがあります。経営・患者・スタッフ、それぞれの面において、医院にとってのプラスになる点を以下で詳しく見ていきましょう。
経営面|算定点数UPによる増収と安定経営
口管強の最大の魅力のひとつが、診療報酬点数の上乗せによる増収効果です。
歯周病の重症化予防治療や周病安定期治療において、口管強を届出済の歯科医院と未届出の歯科医院とでは算定できる点数が大きく異なります。
再診料や管理加算なども上乗せされることで、1回の診療単価が安定化しやすくなります。
日々の診療において「点数の積み上げ」が収益に直結する今の制度設計においては、届け出ているかどうかがそのまま経営の強さに反映されると言っても過言ではありません。
患者面|継続管理で定着率・信頼感が向上
口管強では、ただ治療するのではなく、患者の生涯を通じた“口腔の健康管理”を評価します。
「かかりつけ歯科医」として患者と長期的に関わる体制を整えることができ、リコール・定期受診の定着率向上が期待できます。
「きちんと見てもらえている」という安心感は、患者の信頼感にもつながります。
高齢者や小児の保護者にとっては、“この歯科医院に任せて大丈夫”という心理的な信頼の積み重ねが医院選びの決め手にもなり得ます。
組織面|スタッフ意識改革・チーム医療への強化
届出に向けて研修や体制を整備していく過程で、スタッフの意識やスキルにも前向きな変化が生まれるのが口管強のもうひとつのメリットです。
歯科衛生士が「ただの予防処置担当」ではなく、“生涯を通じた口腔管理の担い手”としての視点を持つようになることで、スタッフのモチベーションや自信にもつながります。
地域の医科や福祉施設との連携が強化されることで、チーム医療・地域包括ケアの一員としての医院の存在感が高まることも期待できます。
「口管強、うちも取った方がいいかも…」そう思った今こそ、動くタイミングです。
そんな先生のために、制度を理解できる【解説動画】をご用意しております。
まだ間に合う!検査の器械がなくても大丈夫‼︎ 「口管強」施設基準届出
講師:株式会社DC-support 伊藤嘉奈
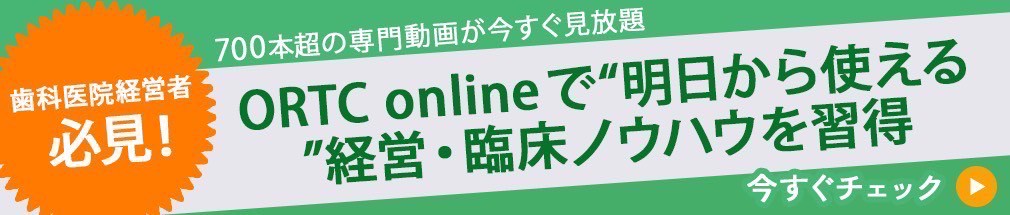
実はハードルが高い? 現場の“負担とリアル”
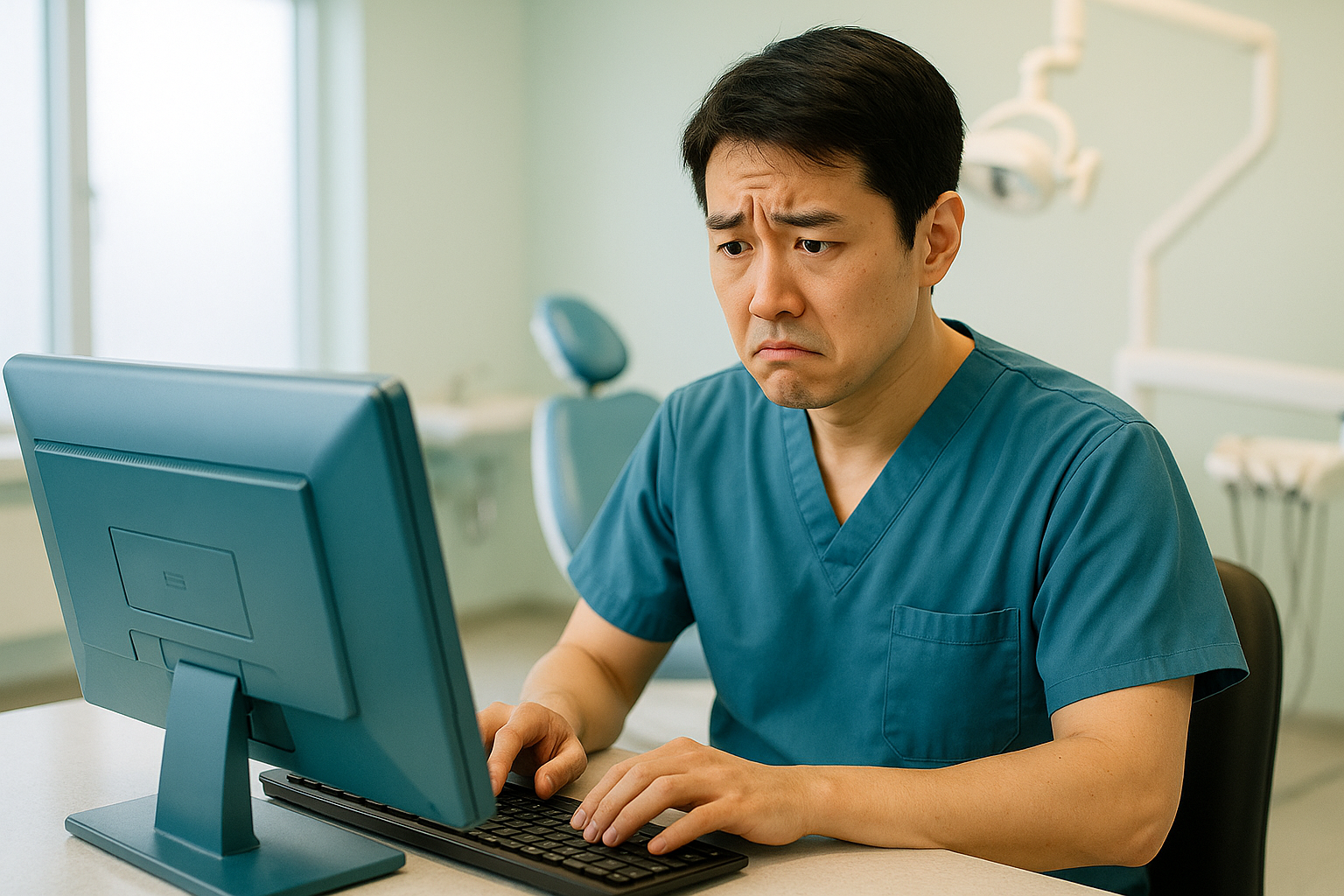
制度の理解が進む一方で、「実際に届出しようとすると準備が大変だった」という声も多く聞かれます。研修・人員・連携体制の整備など、実務上の課題は想像以上にハードルが高いものです。
現場目線での「大変さ」や「つまずきポイント」を取り上げ、具体的に解説します。
人員・研修・訪問体制… 院内体制に求められる整備
「口管強」を取得するには、制度的な要件だけでなく、医院の中身=“体制の土台”そのものを整えることが求められます。
・小児・高齢者の口腔機能管理に関する研修の受講
・歯科医師・歯科衛生士の複数名配置
・訪問診療の実績と支援体制(記録付きで算定されたもの)
・他医療機関・地域施設との連携実績
ただ項目を揃えるだけでなく、日々の診療に落とし込まれていることが重要になります。
実際にこの制度をクリアするためには、時間・人手・意識改革のいずれも必要であり、「やってみようかな」でなんとなく通るものではありません。
歯科医院全体で“やる”と決めて取り組む体制づくりが重要です。
「やったほうがいい」と「やるべき」を分ける基準
とはいえ、「すべての歯科医院が、今すぐ届出すべきか?」と言われれば、必ずしもそうとは限りません。
ポイントになるのは、以下のような視点です。
・すでに高齢者・小児の診療が一定数あるか?
・訪問診療や多職種連携に力を入れているか?
・地域医療への“信頼構築”が経営方針に合っているか?
これらに該当する歯科医院は、口管強を届出することで制度的にも評価され、点数的にも実入りが大きくなる可能性が高いです。
一方で、患者層や歯科医院の規模・方向性によっては、“今は備えるフェーズ”という選択もありです。
制度が進むにつれて「届出しているのが当たり前」の時代が来る可能性も見据えて、今のうちに体制を見直し、準備だけでも進めておくことが医院のリスクヘッジになります。
口管強を分かりやすく解説した動画はこちら https://ortc.jp/movie/Delivery/movie-1420
まとめ
ここまでお読みいただき、「口管強」の届出が重要だということはご理解いただけたと思います。
でも実際には…
・様式が多くて、どれが必要かわからない
・記入ミスや書き漏れが不安
・日々の診療で、とても対応する時間がない
そんな声も、現場のスタッフとしてよく耳にします。
私自身も歯科衛生士として、制度や届出の内容を把握するたびに、「これ、本当に院長ひとりでやるのは大変だよな…」と感じています。
そんな場合は、無理してご自身で対応しなくても大丈夫です。
医院ごとの状況に合わせて、必要な様式の選定から記入サポートまで、届出に詳しい専門スタッフが対応します。
・「うち、どれに該当するの?」という初期相談からOK
・「実績が足りているか不安…」というご相談も大歓迎
まずは、お気軽にご相談ください。
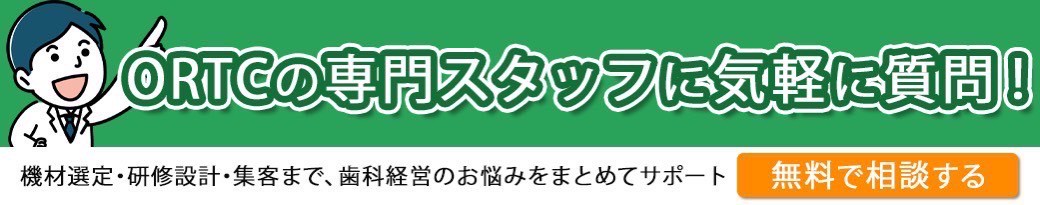
よくある質問(Q&A)
Q1:うちは届出済だけど、再届出は本当に必要?
A1:はい、すでに「か強診」で届出済の医院も、再届出が必須です。
2024年6月の診療報酬改定により、「口腔管理体制強化加算(口管強)」として制度内容が大きく見直されたため、これまでの届出では算定できなくなります。
未対応の場合、加算対象外となり減収リスクもあるため、早めの見直しをおすすめします。
Q2:実績は何を見れば足りているか判断できる?
A2:口管強では、直近1年間の診療実績が届出要件になります。
以下のような算定回数が基準です。
・周病安定期治療や重症化予防治療:30回以上
・根面う蝕やエナメル質初期う蝕の管理:12回以上
・口腔機能管理:12回以上
・訪問診療1〜3:4回以上 + 支援依頼:1回以上(または他機関との連携)
レセプトを確認しながら、厚生局指定の様式に沿ってカウントする必要があります。
Q3:小児の研修って、誰が・いつ受ければいい?
A3:歯科医師または歯科衛生士のいずれか1名以上が、小児口腔機能に関する研修を受講している必要があります。
研修内容や実施機関は地域や時期により異なるため、地方厚生局の指定を確認のうえ、受講済証明が届出時に求められます。
「いつ受ければいいのか」という点については、届出前の準備段階での受講が必須です。未受講のままだと届出が認められないので注意しましょう。
Q4:施設基準が一部だけ足りない場合はどうすれば?
A4:基準を一部でも満たせない場合、口管強としての届出はできません。
「あと少しで基準に届きそう」「書類の書き方がわからないだけかも」という医院も多いのが実情です。
そうしたケースでは、個別に相談しながら、届出可能な状態まで整備・準備を進めることができます。無理に独力で進めるより、一度プロに状況を見てもらうのが確実です。
Q5:他院との差をつけるためには何を強化すべき?
A5:ポイントは“制度対応力”と“地域連携”の2軸です。
・制度対応力:新しい加算や研修の情報に早期対応し、届出・体制を整える
・地域連携:医科・福祉施設・学校などとの連携実績を積み上げておく
口管強は、ただの点数加算ではなく、“地域のかかりつけ医”としての信頼度や体制の証明でもあります。「口管強の届出=医院ブランディング」にもつながります。
歯科衛生士ライター 原田未祐
歯科医療の現場で役立つ実践的な知識を届けるORTC

ORTCは「笑顔の役に立つ」を理念に、歯科界の知識を共有する場を目指しています。歯科医療の現場で役立つ最新の知識と技術を提供することで、臨床と経営の両面からクリニックの成長を支援します。最先端の技術解説や経営戦略に特化した情報を集約し、歯科医療の現場での成果を最大化。自己成長を追求するためのコンテンツをぜひご活用ください。
無料会員登録
無料動画の視聴、有料動画のレンタルが可能です。歯科業界についてのオンライン・オフラインセミナーへの参加が可能となります。
ORTCPRIME
月額5500円で、 ORTC内のすべての動画を見放題に。臨床の現場に役立つ最新の技術解説や、歯科医院経営の成功戦略を網羅した特別コンテンツをご利用いただけます。 歯科業界の方へ効率的に知識を深めていただける内容です。
ORTC動画一覧
ORTCセミナー一覧
まずは無料会員登録
こちらのリンクより会員登録ページへお進みください。
会員登録はこちら
ORTCPRIMEへのアップグレードも簡単!
登録後は「マイページ」から、ORTCPRIMEにいつでもアップグレード可能です。
 こちらの動画もおすすめです
こちらの動画もおすすめです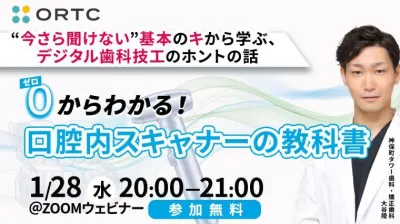 “今さら聞けない”基本のキから学ぶ、デジタル歯科技工のホントの話『ゼロからわかる、口腔内スキャナーの教科書』
“今さら聞けない”基本のキから学ぶ、デジタル歯科技工のホントの話『ゼロからわかる、口腔内スキャナーの教科書』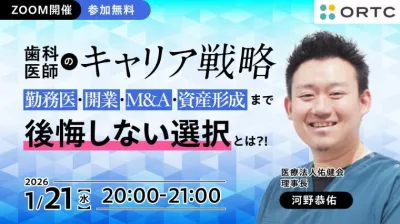 歯科医師のキャリア戦略 ― 勤務医・開業・M&A・資産形成まで、後悔しない選択とは ―
歯科医師のキャリア戦略 ― 勤務医・開業・M&A・資産形成まで、後悔しない選択とは ―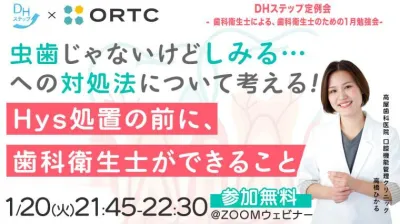 虫歯じゃないけどしみる…への対処法について考える Hys処置の前に、歯科衛生士ができること
虫歯じゃないけどしみる…への対処法について考える Hys処置の前に、歯科衛生士ができること 「TBIが変われば患者が変わる」 自費TBI成功マインド
「TBIが変われば患者が変わる」 自費TBI成功マインド Implant Guide Course | インプラント・ガイデッドサージェリー徹底解説|静的・動的ガイドの使い分けとAll-on-4への応用
Implant Guide Course | インプラント・ガイデッドサージェリー徹底解説|静的・動的ガイドの使い分けとAll-on-4への応用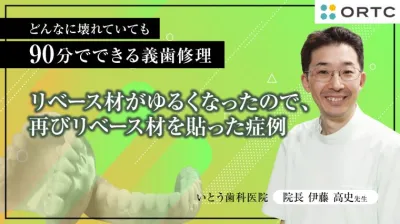 リベース材がゆるくなったので、再びリベース材を貼った症例
リベース材がゆるくなったので、再びリベース材を貼った症例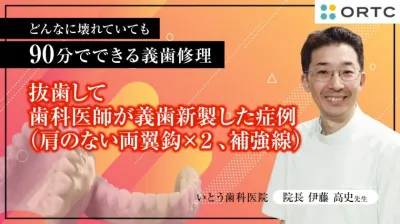 抜歯して歯科医師が義歯新製した症例(肩のない両翼鈎×2、補強線)
抜歯して歯科医師が義歯新製した症例(肩のない両翼鈎×2、補強線) 後継者不在、人材不足、競争激化を乗り切る! 歯科医院M&Aの基本と成功へのプロセス
後継者不在、人材不足、競争激化を乗り切る! 歯科医院M&Aの基本と成功へのプロセス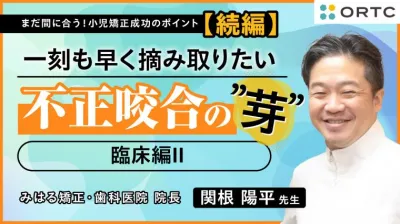 続・まだ間に合う!小児矯正のポイント 〜一刻も早く摘み取りたい 不正咬合の”芽”~ 臨床編Ⅱ
続・まだ間に合う!小児矯正のポイント 〜一刻も早く摘み取りたい 不正咬合の”芽”~ 臨床編Ⅱ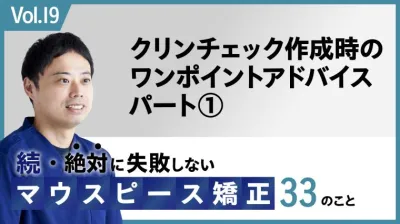 続・ 絶対に失敗しないMP矯正33の事 クリンチェック作成時のワンポイントアドバイス パート①スーパーインポーズ機能
続・ 絶対に失敗しないMP矯正33の事 クリンチェック作成時のワンポイントアドバイス パート①スーパーインポーズ機能