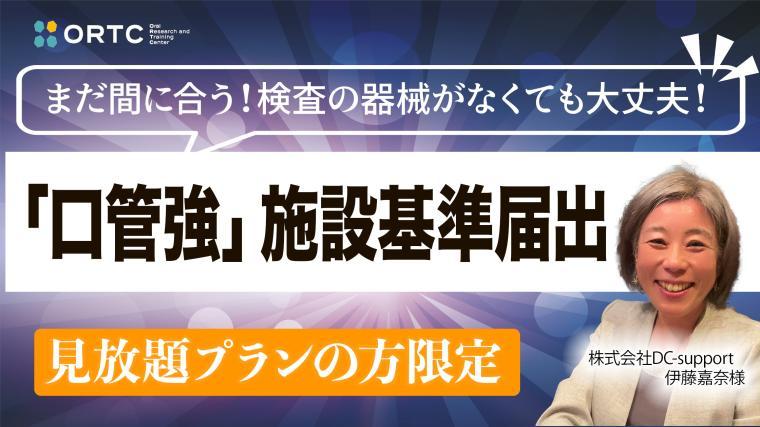「歯科でのサージセル使用と保険算定ガイド」
歯科経営
「サージセル(一般名:酸化セルロース製の吸収性局所止血材)」は、吸収性止血材です。診療報酬上は「吸収性局所止血材」と位置付けられていますが、一般的には「サージセル」という名称で知られています。
主に抜歯や歯科口腔外科の手術で使用されます。材質は酸化セルロースで、体内で自然に吸収されるため、取り出す必要がありません。これにより、術後の止血は容易になり、患者の負担が軽減できます。
1.「サージセル」とは?歯科臨床での役割
 歯科臨床では、一般的な抜歯後の止血だけでなく、難抜歯や親知らずの抜歯、小手術の際にも活用されます。特に血管の豊富な部位や出血リスクの高い症例では、「サージセル」を用いることで術後合併症の予防が可能です。
歯科臨床では、一般的な抜歯後の止血だけでなく、難抜歯や親知らずの抜歯、小手術の際にも活用されます。特に血管の豊富な部位や出血リスクの高い症例では、「サージセル」を用いることで術後合併症の予防が可能です。
また、操作が簡便であることから、手術時間の短縮や術者の負担軽減にもつながります。吸収するまでの時間は一般的に1〜2週間程度で、使用部位や患者の状態によって変動します。
サージセルは代表的な製品名ですが、同様の酸化セルロース製止血材は複数あり、いずれも保険算定の考え方は共通です。
使用される臨床場面
「サージセル」は、以下のような場面で活用されます。
・抜歯後の止血
一般的な抜歯後でも、出血が多い場合や血流が豊富な部位で使用されます。
・難抜歯症例での応用
親知らずや埋伏歯など、抜歯が複雑で出血リスクが高い症例に適しています。
・歯科口腔外科での使用例
切開を伴う歯周外科処置や、歯肉切除・歯根端切除などの処置でも止血剤として活用されます。
歯科医療現場でのメリット
「サージセル」を使用することで、以下のようなメリットがあります。
・出血量の軽減を効果的にできる
・術後合併症の予防ができる
・挿入が容易で、手術時間の短縮につながる
・縫合の妨げになりにくい
・患者の負担が少なく、安心して治療を受けられる
2.吸収性局所止血材が保険算定できるケース
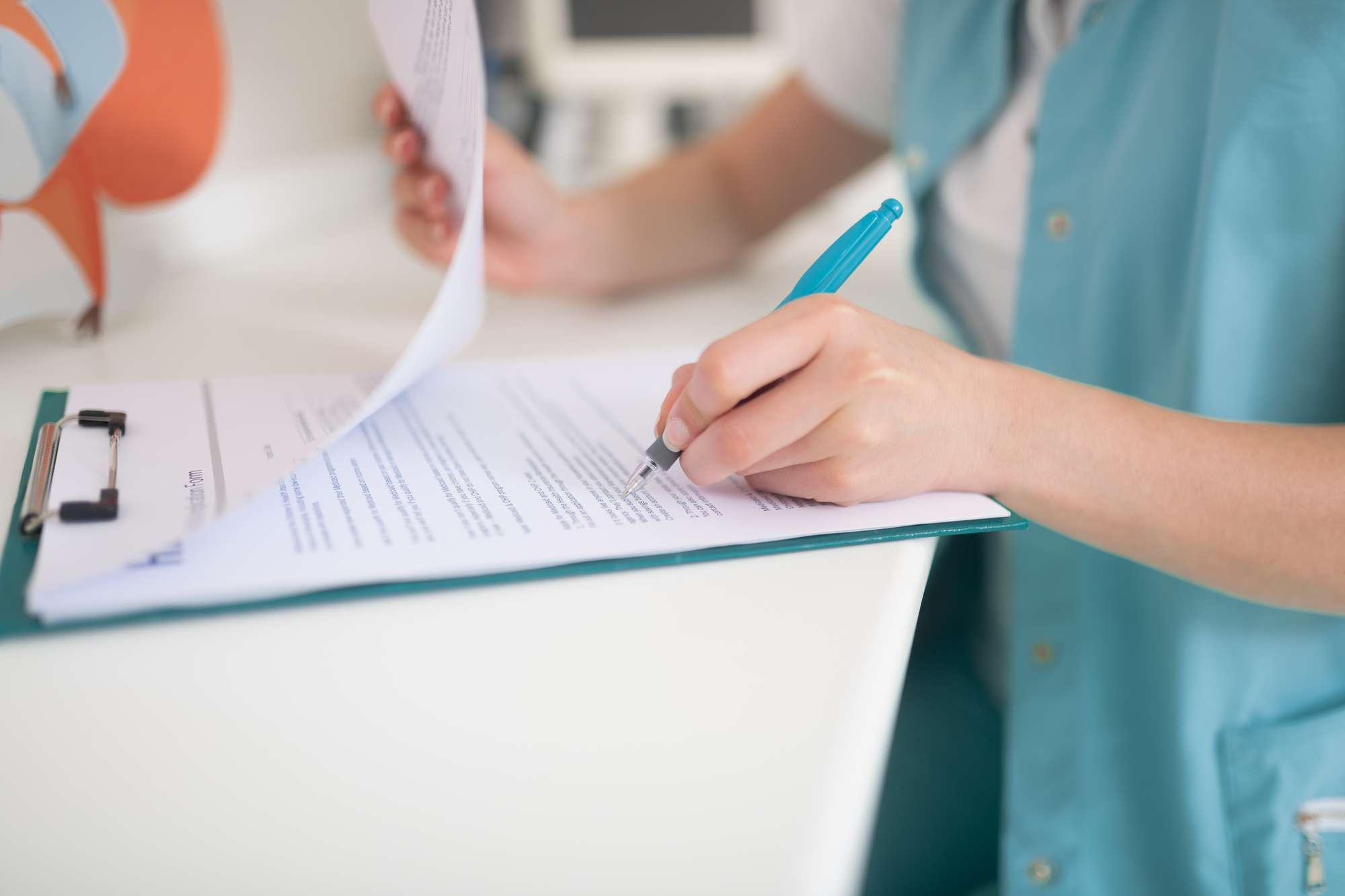 条件を満たす場合に限り、保険算定が可能です。具体的には、医師の手術の一環として必要と判断した場合が対象となります。
条件を満たす場合に限り、保険算定が可能です。具体的には、医師の手術の一環として必要と判断した場合が対象となります。
・難抜歯症例
出血量が多く、止血目的で複数枚の吸収性局所止血材が必要な抜歯。
・歯科口腔外科手術
歯根端切除術などの切開操作を伴う手術で、術中止血のために使用する場合。
・複数部位の手術
同時に複数箇所で止血材を使用する必要がある場合。
・医師が必要と判断した場合
単なる出血防止目的ではなく、手術の一環として医師が必要性を判断した場合。
3.吸収性局所止血材の算定区分
 算定は、使用量や手技内容によって処置料に含まれる場合と別途算定できる場合に分かれます。
算定は、使用量や手技内容によって処置料に含まれる場合と別途算定できる場合に分かれます。
処置料に含まれる場合
通常抜歯で1枚程度使用する場合は、処置料に含まれるとみなされ、別途算定はできません。この場合は、止血材の使用は術式の一部として扱われます。
別途算定できる場合
難抜歯などで複数枚使用した場合、算定可能なケースがあります。加算点数として扱われ、使用枚数に応じて点数が設定されます。複数枚の算定には上限が設定される場合もあるため、医療機関のガイドラインを確認することが大切です。
4.算定時の注意点

・記録に残すべき内容
→使用枚数、使用理由、手術内容
・複数使用時の扱い
→1枚あたりの点数を積算できる場合と、加算上限がある場合がある
・算定できないケース
→過剰使用や記録不十分、医師判断の必要性が不明確な場合。カルテへの記録を徹底することで、査定時の算定ミスを防ぐことができます。
5.実際に算定した場合の収益インパクトと経営効果
 「サージセル(一般名:酸化セルロース製の吸収性局所止血材)」は、単に止血効果を得るための医療材料というだけではなく、歯科医院経営における収益性の改善に直結する材料です。
「サージセル(一般名:酸化セルロース製の吸収性局所止血材)」は、単に止血効果を得るための医療材料というだけではなく、歯科医院経営における収益性の改善に直結する材料です。
診療報酬上は「吸収性局所止血材」として位置付けられており、適切に算定することで歯科医院の経営にプラス効果をもたらします。
1件あたりの収益増加イメージ
・吸収性局所止血材の加算点数は1枚あたり約30〜50点(=約300~500円)
・難抜歯や小手術で2枚使用すれば600〜1000円程度の収益増が見込める
・1ヶ月に50件の算定を行えば、3〜5万円程度の増収効果となり、年間に換算すると36~60万円の収益アップが期待できる
材料コストとの比較
サージセルの材料費は1枚あたり約100円前後。例えば、1枚使用した場合は収益300円-材料費で、100円=粗利200円になります。
複数枚使用しても収益性は十分に確保でき、利益率が高い保険材料といえます。
経営視点での効果
・収益構造の改善
保険診療中心の歯科医院にとって、1件ごとの加算が積み重なれば固定費を補う安定収益源となります。
・患者満足度の向上とリピート強化
出血や術後合併症を減らせることで患者の安心感が高まり、「この歯科医院なら安心」というリピートや紹介に直結します。
・スタッフ教育による効率化
全てのスタッフが算定について理解をしていれば、カルテ記載や請求漏れが減り、歯科医院の経営管理が効率化します。
まとめ
サージセル(吸収性局所止血材)は、歯科医院での抜歯や小手術における有効な止血材であり、条件を満たせば保険算定が可能です。算定ポイントを正しく理解し、記録を適切に残すことで、患者安全と歯科医院収益の両立が可能です。
経営視点でも、材料費を抑えつつ算定による収益を確保することは、歯科医院の持続的な成長に直結します。
近年の歯科医院経営では、診療報酬の正しい算定がますます重要になっています。特に「サージセル」のように「処置料に含まれる場合」と「別途算定できる場合」がわかれる材料は、スタッフ間で認識に差が出やすいポイントです。
算定ルールを全員が理解していれば、歯科医院としての収益を守るだけでなく、査定リスクを未然に防ぐことにもつながります。
特に複数歯科医院を展開している場合、算定ルールをマニュアル化して全院で共有することが、経営安定の大きな鍵となります。
今こそ体制強化に取り組みましょう。
本記事でご紹介した内容をさらに深く知りたい方は、こちらの動画でも詳しく解説しています。ぜひご覧ください。
よくある質問
Q.サージセルはどの手術まで保険算定できる?
A.出血リスクの高い抜歯や小手術、歯科口腔外科手術で医師が必要と判断した場合に算定可能です。
Q.止血のみの場合は算定可能?
A.単純な止血目的だけでは算定できない場合が多く、必ず手術の一環として使用する必要があります。
Q.算定ミスを防ぐ簡単な方法は?
A.使用枚数、理由、手術内容を必ずカルテに記録し、スタッフ全員で共有することが基本です。
Q.査定リスクを避ける工夫は?
A.「サージセル(吸収性局所止血材)」の使用目的を明確にカルテに記録することが最も重要です。使用枚数・手術内容・止血必要性を具体的に記載することで、保険査定時に算定理由が明確になり、査定リスクを最小化できます。
Q.複数歯科医院展開での管理方法は?
A.複数歯科医院で「サージセル」を使用する場合、マニュアル化と統一ルールの徹底が鍵です。使用条件・記録方法・算定基準を全員共通化することで、算定ミスや査定リスクを防止できます。また、定期的にカルテ・算定チェックを行うことで、全歯科医院のコンプライアンス維持と収益管理が可能になります。
歯科衛生士ライター大久保
歯科医療の現場で役立つ実践的な知識を届けるORTC

ORTCは「笑顔の役に立つ」を理念に、歯科界の知識を共有する場を目指しています。歯科医療の現場で役立つ最新の知識と技術を提供することで、臨床と経営の両面からクリニックの成長を支援します。最先端の技術解説や経営戦略に特化した情報を集約し、歯科医療の現場での成果を最大化。自己成長を追求するためのコンテンツをぜひご活用ください。
無料会員登録
無料動画の視聴、有料動画のレンタルが可能です。歯科業界についてのオンライン・オフラインセミナーへの参加が可能となります。
ORTCPRIME
月額5500円で、 ORTC内のすべての動画を見放題に。臨床の現場に役立つ最新の技術解説や、歯科医院経営の成功戦略を網羅した特別コンテンツをご利用いただけます。 歯科業界の方へ効率的に知識を深めていただける内容です。
まずは無料会員登録
こちらのリンクより会員登録ページへお進みください。
ORTCPRIMEへのアップグレードも簡単!
登録後は「マイページ」から、ORTCPRIMEにいつでもアップグレード可能です。