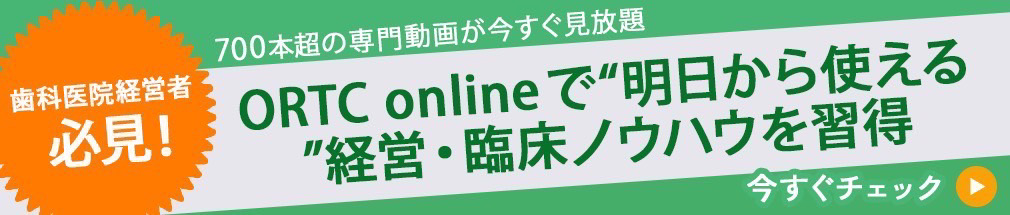患者数が伸びない理由は?歯科医院の集患を成功に導く実践ロードマップ
歯科経営
歯科医院やクリニックの経営において、「集患」は避けて通れない課題です。
「開業しても患者が来ない」「ネットで検索しても見つけてもらえない」そんな悩みを抱える院長先生は少なくありません。
競合がひしめく都市部では、ただ診療を続けるだけでは生き残れない時代です。
本記事では、「集患とは何か」から始まり、患者数が伸びない理由や成功する集患戦略、歯科・医療機関におけるオンライン・オフラインの具体的な集患方法、効果的な対策、マーケティングの視点を交えた戦略の立て方まで、網羅的に解説します。
これからの歯科医院経営を安定させたい方にとって、必ず押さえておきたい集患の基本と実践ポイントを抑えていきましょう。
「集患」とは?

「集患」という言葉は医療業界で広く使われていますが、その意味や重要性を正しく理解している人は意外と少ないかもしれません。
歯科医院経営を安定させるうえで、集患は単なる“患者数の確保”ではなく、戦略的な取り組みです。
ここではまず、医療現場における「集患」の定義と、似た言葉である「増患」との違いについて整理しておきましょう。
医療現場における集患の定義
「集患」とは、歯科医院やクリニックなどの医療機関が新規患者や再来患者を安定的に“集める”ための取り組みになります。
単なる「患者数の増加」ではなく、認知・信頼・来院までの導線を設計し、継続的に通ってもらう仕組みをつくることが目的です。
開業すれば患者が来る時代もありましたが、現在は医院数の増加や地域間競争の激化、患者ニーズの多様化により、戦略的な集患対策が不可欠になっています。
歯科医院は「コンビニより多い」とも言われ、他院との差別化なしに生き残るのは難しくなっていくでしょう。
増患との違いと使い分け
「集患」と似た言葉に「増患」がありますが、意味合いには違いがあります。
- 集患=患者を集めるための活動や手段
- 増患=患者数が実際に増加した状態や結果
単純に新患数を増やすことだけでなく、リコール(予防や経過観察のための定期的な再来院)や定期メンテナンスの強化による再来率アップも、定期メンテナンスの強化による再来率アップも、集患戦略の一部として含まれる点は見落とされがちです。
これからの医療機関には、「質」と「量」の両方を意識した集患が求められています。
なぜ「集患対策」が必要なのか
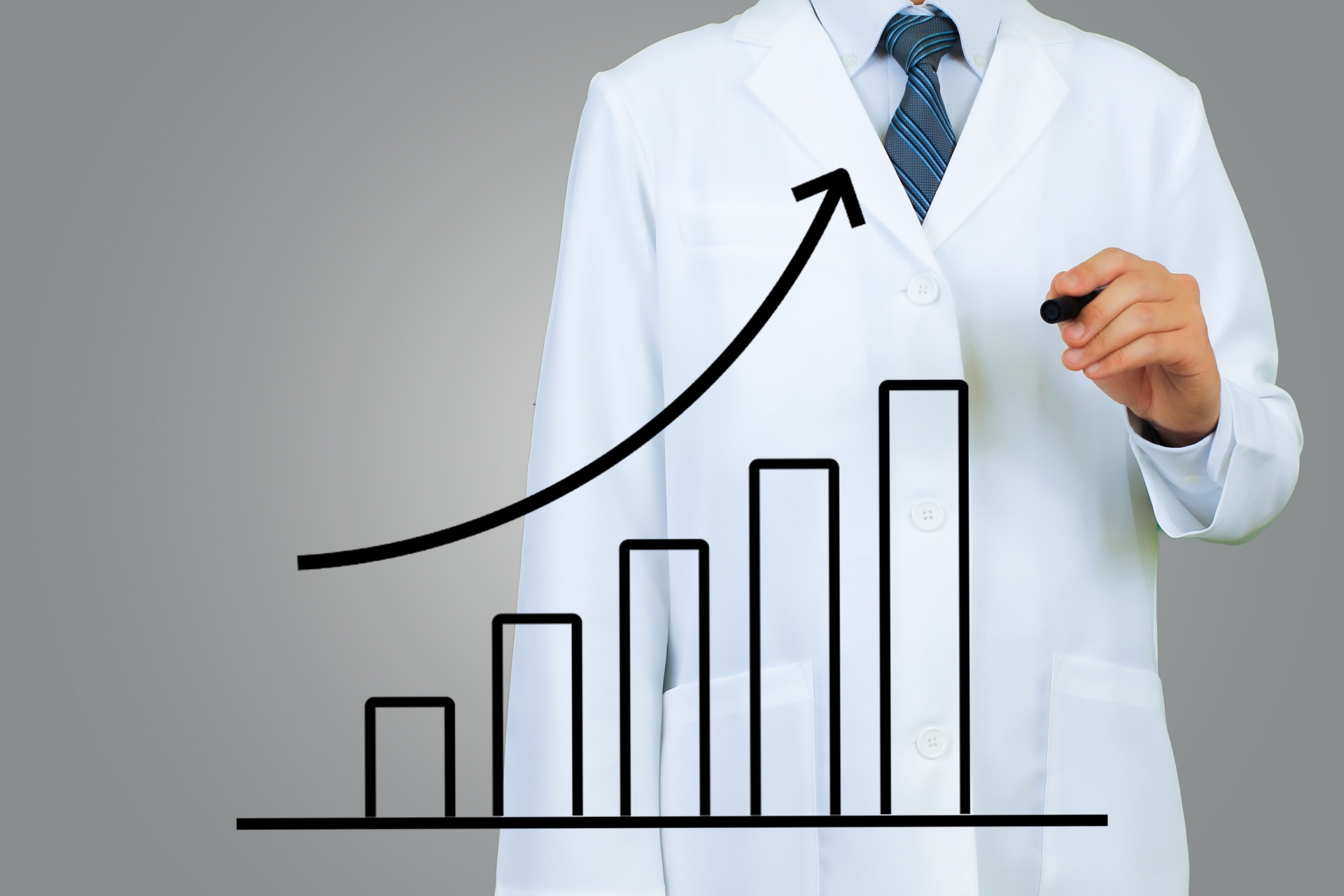
「集患」が重要なのは今に始まったことではありませんが、今このタイミングで改めて本気で取り組むべき理由があります。 現代の歯科医院・クリニックが置かれている背景を整理し、なぜ“集患戦略”が経営のカギになるのかを理解しておきましょう。
人口減少と医院数増加による競争激化
日本では少子高齢化に伴い、国全体の人口は減少傾向にあります。
子どもや働き盛りの世代が少なくなることで、患者となる層も確実に減ってきています。
歯科医院の数はほぼ横ばい~微増で推移しており、「コンビニより多い」と言われる状況に変わりはありません。
患者数が減っているのに、ライバル医院は増えているというギャップが、集患における最大の危機ポイントです。
地域によっては、半径500m以内に5軒以上の歯科医院が存在するケースもあり、従来の待ちの姿勢では患者に選ばれにくい時代になっています。
集患が経営安定に直結する理由
集患対策が必要なのは、「予約が空いているから」だけではありません。
安定した経営のためには、継続的な新患・リピーターの流入が不可欠です。
新規患者が増えれば、診療の幅が広がり、売上も伸びやすくなります。
定期検診・メンテナンスで通ってもらうことで、患者との信頼関係が深まり、長期的なリピートと紹介にもつながります。
「集患できる医院」は、採用や人材定着の面でも有利です。
活気ある医院にはスタッフが集まりやすく、医院のブランディングやチーム力の向上にもつながります。
集患は単なる「数の問題」ではなく、経営・人材・地域医療への影響まで含めた戦略の起点となるでしょう。
歯科医院で行う集患方法

「集患」といっても、その方法はさまざまです。
近年は、インターネットの活用が当たり前になったことで、オンラインとオフラインの境界が曖昧になりつつあります。
歯科医院が実践できる集患手段を、「オンライン」「オフライン」「ハイブリッド」の3つに分けて紹介します。
オンラインで行うWeb集患(グーグルGoogleビジネスプロフィール、ローカルSEO活用、MEO対策)
まず注目すべきは、Webを活用したオンライン集患です。近年は「歯医者 地域名」「歯科医院 口コミ」といった検索を通じて、患者が医院を探す時代になりました。
オンライン集患の主な手段は以下の通りです。
- SEO対策(検索エンジン最適化):Googleで上位表示を目指す施策です。「歯医者+エリア」などローカルSEOの効果は大きいでしょう。
- ホームページ改善:診療内容、アクセス、料金などを分かりやすく表示します。スマホ最適化も必須です。
- SNS活用(Instagram・LINEなど):医院の日常や雰囲気を伝え、共感・信頼を得ることができます。
- Googleビジネスプロフィールの運用:口コミ管理や写真投稿などで検索時の印象を高めていけます。
こうしたWebマーケティングによる集患方法は、費用対効果が高く、エリアを限定せずにアプローチできるのが強みです。
オフラインの口コミ対策
昔ながらのオフライン集患方法も、地域密着型医院にとっては非常に重要です。
- 外看板・駅看板などの視認性向上
- 患者からの紹介促進(家族・友人)
- 地域イベントや健康講座への参加
- 学校・高齢者施設・地域包括支援センターとの連携
こうした施策は、特に高齢層やネットを使わない層への集患対策として有効であり、「通いやすい」「信頼できそう」と感じてもらうことで来院につながります。
口コミ促進×Web連動のハイブリッド集患
今もっとも注目されているのが、オンラインとオフラインを組み合わせたハイブリッド型集患です。
- 来院した患者の声をWebに掲載(口コミ・インタビュー形式)
- SNSやGoogleで口コミを見た患者が「近所でいい歯医者を探していた」と来院
- 地域イベントで接点を持ち、その後LINE公式アカウントで定期配信 → 来院へ
こうしたクロスメディア的な集患戦略は、「知った→調べた→行ってみた」という自然な流れをつくり、患者の信頼をより強く引き出していきましょう。
歯科医療メディアORTCは、Googleビジネスプロフィールの設定から、MEO対策、運用代行含めて、月々4万円税別という非常にお安い価格で歯科医院の集患支援も行っています。
集患を成功に導く3つの戦略

集患方法を実践するだけでは、期待通りの結果は得られません。
集患を戦略的に成功させるには、3つの柱を意識して取り組むことが重要です。
ただ情報を発信するのではなく「誰に、何を、どう届けるか」を設計することが、継続的な患者獲得と歯科医院ブランディングの鍵になります。
ターゲット明確化と患者像のペルソナ設計
集患の第一歩は、「誰に来てほしいのか」を明確にしていきましょう。
地域・年齢・性別だけでなく、「どんな悩みを持ち、何を求めているか」まで掘り下げたペルソナ設計が不可欠です。
「仕事が忙しくて通院に時間を割けない30代男性」なら、土日診療・ネット予約の訴求が刺さります。
他にも「子育て中のママ層」であれば、キッズスペースや保育士常駐といった価値が響くでしょう。
このように患者のニーズを言語化することで、適切な打ち手(広告・SNS・LP内容など)も明確化され、無駄な集患コストを削減できます。
歯科医院の強みを活かしたブランディング
他院と差別化できるUSP(Unique Selling Proposition)=医院の強みです。
患者は「どの医院でもいい」と思っていません。「自分に合う」「安心できそう」な医院を選びます。
- 予防歯科に特化
- マイクロスコープ完備
- 痛みの少ない治療
- 子ども好きなスタッフ多数
- 女性院長によるきめ細かい対応
- 駅から徒歩2分
- 完全予約制で待ち時間ゼロ
このように、明確な魅力を打ち出すことで、WebサイトやSNS、広告などすべての集患チャネルが一貫性を持ち、選ばれる医院へと近づきます。
継続的な改善とデータ分析
集患は「やって終わり」ではなく、分析と改善を繰り返すことが成功のカギです。
Google AnalyticsやSearch Console、SNSのインサイト、予約管理システムなどを活用すれば、どの施策が来院につながっているかを可視化できます。
ホームページのアクセスはあるのに予約が少ない場合には、 予約への導線や訴求の改善をしていきます。
特定のキーワードからの流入が多い場合には、SEO強化・関連記事の追加などが重要です。
Instagram経由の問い合わせが多い場合には、投稿頻度や内容を最適化の見極めをしていきましょう。
こうした数字に基づく意思決定が、集患の再現性と持続性を高めるポイントになります。
ORTCでは、集患や医院経営の成功事例や予防歯科経営のノウハウを紹介する無料セミナーも配信中です。ぜひご覧ください。
注意したい集患の落とし穴

集患に力を入れる歯科医院が増えている一方で、意図せず逆効果になる施策を行ってしまうケースも後を絶ちません。
歯科医療のように信頼が求められる業界では、広告の表現や伝え方ひとつで、医院の印象が大きく変わってしまいます。
集患活動において陥りがちな注意点を2つ紹介します。
医療広告ガイドライン違反リスク
歯科医院の集患活動において、まず押さえておきたいのが厚生労働省が定める「医療広告ガイドライン」です。
これに違反した内容で広告・発信を行ってしまうと、指導や罰則の対象になることがあります。
- 「絶対に痛くない」「100%治る」などの根拠なき断定表現
- 「他院より優れている」「一番安い」などの比較優良広告
- ビフォーアフター写真や体験談を事実として掲載(規制あり)
SNS投稿、ホームページの文章、チラシの文言など、すべてが規制対象になり得るため、“集患マーケティング=自由な広告”ではないという前提を理解しておくことが大切です。
売り込み感のある訴求による逆効果
集患に力を入れるあまり、つい“集めること”だけを目的にした強い売り込み表現をしてしまうケースもあります。
患者さんは「治療の押し売り」ではなく、「信頼できる情報」と「自分に合った医院」を求めています。
「怪しい」「なんか胡散臭い」と距離を取られる原因にならないよう気をつけていきましょう。
集患で最も重要なのは、何よりも患者さんに信用してもらうことが重要です。
信頼を損なうような訴求は、どんな手法を使っても成果にはつながりません。
患者目線を忘れず、誠実な情報発信を心がけることが、長く愛される医院への近道となります。
集患支援の外部パートナーも活用しよう

「集患をしなければ…」と思っていても、診療と並行してすべてを自力でこなすのは限界があります。
専門的な知識が求められるWeb施策やSNS運用、分析・改善までをひとりで抱え込んでしまうと非効率になりがちです。
そんなとき頼りになるのが、歯科医院の集患支援をする外部パートナーになります。
マーケティング会社の活用メリット
医療マーケティングに精通した会社やコンサルタントを活用することで、プロの知見に基づいた集患戦略を構築できるでしょう。
マーケティング会社を利用する4つのメリットがあります。
- 自院に合った集患戦略の設計と実行支援
- SEO・広告・SNS運用など各チャネルの最適化
- データ分析や改善提案によるPDCAサイクルの強化
- 法令遵守(医療広告ガイドライン)のチェック体制
歯科医院専門の集患支援サービスも増えており、業界特有の事情に詳しいパートナーを選ぶことで、より効果的な施策が可能になります。
集患支援サービス選びのポイント
外部パートナーを選ぶ際には、「どこと組むか」が結果に大きく影響します。
以下の点をチェックすると安心です。
- 歯科業界への理解がある(医療広告ガイドライン対応など)
- “実績”や“事例”を具体的に提示がある
- 契約内容が明瞭である(初期費用/月額/成果報酬など)
- 一方的な提案ではなく、医院の方針に寄り添った提案がある
すべて外注するのではなく、自院でできる部分+プロに任せる部分をバランスよく分担することで、費用対効果の高い集患体制が整うでしょう。
まとめ
歯科医院における集患は、単に“患者を増やす”ための手段ではなく、歯科医院の方向性や在り方を問う戦略となります。
歯科医院の数も多く、患者さんが選ぶ時代です。
「どう見つけてもらうか」「どう信頼してもらうか」は、現場スタッフにとっても重要なテーマだと感じています。
現場で感じるのは、患者さんに選ばれる歯科医院には、必ず理由があるということです。
院内の雰囲気、スタッフの人柄、情報発信の誠実さなど、細かな積み重ねが集患に確実に繋がっていきます。
これから集患に取り組みたい方は、まず「どんな患者さんに来てほしいか?」を明確にすることが第一歩です。
歯科医院の魅力を、きちんと「伝わる形」に落とし込むことで、集患につながる“信頼の土台”を築くことができるのではないでしょうか。
ORTCでは、貴院の現状に合わせた集患・経営安定化戦略を無料でご提案します。
お問い合わせフォームから、ご連絡お待ちしております。
歯科衛生士ライター 原田
Q&A
Q1. そもそも「集患」とは何ですか?どんな意味がありますか?
A.「集患」とは、歯科医院やクリニックが新しい患者さんや再来患者さんに来てもらうために行う活動全般を指します。
広告やSNS、口コミの活用など、来院につなげる仕組みを戦略的に整えることが目的です。
Q2. 歯科医院でオンライン集患に取り組むなら何から始めるべき?
A.まずは、自院のホームページの見直しと、Googleビジネスプロフィールの整備が効果的です。
Q3. 医療広告ガイドラインに違反しないための注意点は?
A.「絶対に治る」「他院より優れている」といった断定的・比較的表現はNGです。
体験談やビフォーアフターの掲載も条件付きとなりますので、気をつけていきましょう。
Q4. 集患支援サービスはどんな歯科医院に向いていますか?
A.「集患のノウハウがない」「スタッフの手が回らない」など、集患を仕組み化したい歯科医院に向いています。
Web施策やSNS運用を任せることで、院長やスタッフが診療に集中できるのも大きな利点です。
Q5. 患者さんに選ばれる歯科医院になるために現場スタッフができることは?
A.丁寧な対応や笑顔、分かりやすい説明といった日々の積み重ねが信頼を生みます。
自院の魅力をSNSや口コミで発信する力も重要です。
歯科医療の現場で役立つ実践的な知識を届けるORTC

ORTCは「笑顔の役に立つ」を理念に、歯科界の知識を共有する場を目指しています。歯科医療の現場で役立つ最新の知識と技術を提供することで、臨床と経営の両面からクリニックの成長を支援します。最先端の技術解説や経営戦略に特化した情報を集約し、歯科医療の現場での成果を最大化。自己成長を追求するためのコンテンツをぜひご活用ください。
無料会員登録
無料動画の視聴、有料動画のレンタルが可能です。歯科業界についてのオンライン・オフラインセミナーへの参加が可能となります。
ORTCPRIME
月額5500円で、 ORTC内のすべての動画を見放題に。臨床の現場に役立つ最新の技術解説や、歯科医院経営の成功戦略を網羅した特別コンテンツをご利用いただけます。 歯科業界の方へ効率的に知識を深めていただける内容です。
まずは無料会員登録
こちらのリンクより会員登録ページへお進みください。
ORTCPRIMEへのアップグレードも簡単!
登録後は「マイページ」から、ORTCPRIMEにいつでもアップグレード可能です。