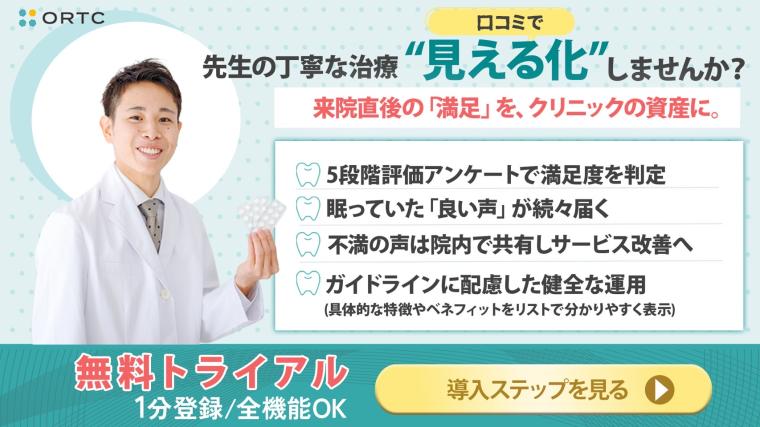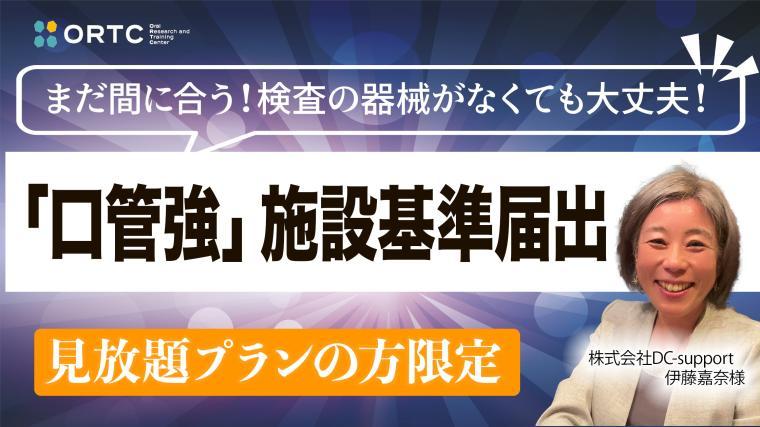CEJ(cemento-enamel junction)
CEJとは、Cemento-Enamel Junctionの頭文字を取った略語です。
日本語では「セメントエナメル境」と表記するのが一般的で、「セメント・エナメル境」と書かれることもあります。一言でいうと、歯の「歯冠(しかん)」と「歯根(しこん)」の境界線のことです。歯の頭の部分(歯冠)は硬いエナメル質で覆われ、根の部分(歯根)はセメント質という組織で覆われています。この2つの組織が出会うラインがCEJです。ちょうど歯の”ウエストライン”のようなイメージですね。
CEJは臨床の「ものさしのゼロ地点」
CEJは、単なる解剖学的な線ではありません。日々の臨床において、非常に重要な「基準点(ランドマーク)」として機能します。
1. 歯周治療での超重要ランドマーク ?
CEJが最も重要視されるのが歯周治療です。
臨床的アタッチメントレベル(CAL)の測定基準 歯周ポケットの深さ(PD)を測るだけでは、歯肉の腫れ(偽性ポケット)に惑わされて、歯を支える骨(歯槽骨)がどれだけ失われたかを正確に把握できません。
そこで、CEJを基準(ゼロ地点)としてプローブの先端までの距離を測る「臨床的アタッチメントレベル(Clinical Attachment Level, CAL)」を測定します。これにより、歯肉の状態に左右されず、歯周組織の破壊の程度を客観的に評価することができます。
先輩や先生から「CAL測って」と言われたら、このCEJを正確に探り当てることが求められます。
2. 修復治療(詰め物・被せ物)のゴールライン ?
う蝕(虫歯)の治療で詰め物(CR充填)をしたり、被せ物(クラウン)を作ったりする際にも、CEJは重要な目標となります。
マージン(修復物の辺縁)設定の目安 特に歯頸部(歯の根元)のう蝕を治療する際、どこまで削るか、どこに修復物の端を持ってくるかというマージンを設定する上で、CEJが解剖学的な目安となります。健康な状態ではCEJは歯肉に隠れているため、その位置を正確にイメージしながら治療を進めることが、適合の良い修復物を作る上で大切です。
3. 知覚過敏の原因にも ?
歯肉が退縮(歯茎が下がる)すると、本来は隠れているはずのCEJが露出します。CEJ付近ではエナメル質が薄い、もしくは存在しないため、その下にある象牙質が露出しやすい部位です。象牙質には神経につながる無数の管(象牙細管)があるため、ここに冷たいものなどが触れると「しみる」といった知覚過敏の症状が出やすくなります。
【臨床の豆知識】CEJの3つのパターン
実は、CEJのエナメル質とセメント質の接合部には、主に3つの解剖学的なバリエーションがあります。
セメント質がエナメル質を覆う(約60%):最も多いパターン。セメント質がエナメル質の上にわずかに重なっています。
エナメル質とセメント質が鋭端で接する(約30%):両者がぴったりと合わさっています。
両者の間に隙間があり、象牙質が露出している(約10%):エナメル質とセメント質が接しておらず、もともと象牙質が露出しているパターンです。このタイプの歯は、歯肉が少し退縮しただけでも知覚過敏が出やすい傾向があります。
このバリエーションを知っておくと、知覚過敏の原因を探る際などに役立ちます。
まとめ
CEJは、歯の解剖学的な境界線であると同時に、歯周病の進行度を測ったり、精度の高い修復治療を行ったりするための「絶対的な基準点」です。
このCEJの位置と、その解剖学的バリエーションを常に意識できるようになると、日々の臨床での診断力や技術が格段に向上します。ぜひ、模型やレントゲン写真を見るときにも「CEJはどこかな?」と探す癖をつけてみてください。
![]() キーワード:CEJ(cemento-enamel junction)
キーワード:CEJ(cemento-enamel junction)
CEJ(cemento-enamel junction)
CEJとは、Cemento-Enamel Junctionの頭文字を取った略語です。 日本語では「セメントエナメル境」と表記するのが一般的で、「セメント・エナメル境」と書かれることもあります。一言でいうと、歯の「歯冠(...