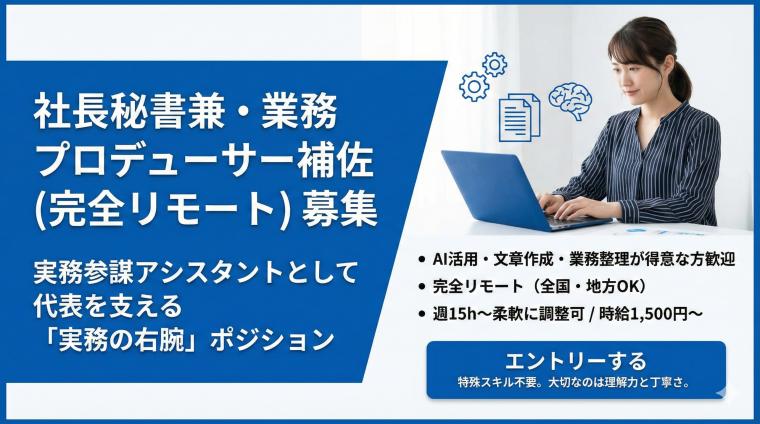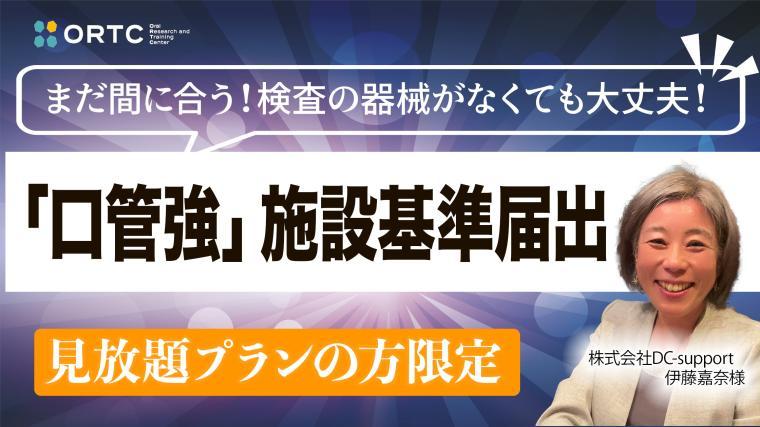補綴治療において、患者固有の機能運動に調和した咬合面形態を再現することは、長期的な予後の成功を左右する重要な要素です。
しかし、従来の静的な咬合採得法では、患者個々の下顎運動を正確に反映することが困難でした。
FGPテクニック(Functionally Generated Path)は、この課題を解決する画期的な手法として注目されています。
1959年にMeyerによって確立されたこの技術は、動的な下顎運動を直接記録することで、より生理的な咬合の再現を可能にしました。
本記事では、FGPテクニックの基本概念から実践的な手順、さらには最新のデジタル技術との統合まで、臨床に即した形で解説していきます。
FGPテクニックの基本概念と歴史

FGPテクニックを知るには、まず心得ておきたい基礎があります。
そのうえで、FGPテクニックに関してと従来の咬合採得のテクニックに関して、ここで解説しておきますのでご参考ください。
FGPテクニックとは
FGPテクニック(Functionally Generated Path)は、1959年にMeyerによって確立された機能的咬合採得法です。
従来の静的な咬合採得では捉えきれない、患者固有の下顎運動路を直接記録することを可能にした画期的な手法として注目されています。
開発の背景には、補綴物の咬合面形態を患者の機能運動に調和させることで、より生理的な咬合を再現したいというMeyerの臨床的な課題意識がありました。
特に臼歯部における側方運動時の干渉や、中心咬合位からの滑走運動の再現性向上が重要視されていました(参考文献:機能的に最適な臼歯部の歯冠修復方法を考える)。
動的な下顎運動を記録する意義は、患者個々の機能運動を立体的に捉えられる点にあります。
咀嚼時や側方運動時における歯牙接触の軌跡を直接採得することで、補綴物に理想的な咬合面形態を付与することが可能となります。
これにより、補綴装置装着後の咬合調整量を最小限に抑え、より確実な咬合の安定性を得ることができます。
従来法との比較
FGPテクニックと従来法のもっとも大きな違いは、動的な下顎運動を直接記録できる点にあります。
チェックバイト法が特定の顎位での静的な記録のみを採得するのに対し、FGPテクニックでは側方運動や前方運動などの機能運動全体を連続的に記録することができます。
パントグラフが下顎全体の運動経路を記録するのに対し、FGPテクニックは修復対象となる歯牙周辺の限局的な記録に特化しているため、単冠やブリッジなどの部分的な補綴処置において、より効率的かつ正確な咬合面形態の再現が可能です。
咬合器調整における優位性としては、患者固有の機能運動を直接的に反映できることが挙げられます。
従来の咬合器設定では平均的な値を用いることが多く、個々の症例での微細な違いを再現することは困難でした。
FGPテクニックを用いることで、より正確な咬合接触関係を再現し、補綴物装着時の調整量を大幅に削減することが可能となります。
臨床的意義と適応症

基礎を踏まえたうえで、ここでは臨床的意義と適応症に関して触れていきます。
特に適応症を理解していないとFGPテクニックは駆使できませんので、きちんと把握しておくことが重要です。
適応となるケース
FGPテクニックは、さまざまな補綴治療ケースに適応可能な咬合採得法です。
特に臼歯部単冠修復では、隣在歯との調和のとれた咬合接触を実現し、天然歯の機能的な咬合面形態を正確に再現することができます。
ブリッジ症例においては、複数歯に渡る連続的な咬合面形態の付与が求められますが、FGPテクニックを用いることで、支台歯間の滑走運動を含めた機能的な咬合面形態を一体的に採得することが可能です。
フルマウスリコンストラクションでは、咬合高径の設定から始まり、前方・側方運動時の誘導を含めた包括的な咬合再構成が必要です。
FGPテクニックは、患者固有の下顎運動を反映した咬合面形態を提供し、生理的な咬合の確立に寄与します。
インプラント上部構造においては、特に天然歯との混在症例で、インプラント周囲の生体力学的な配慮が重要となりますが、FGPテクニックを用いることで、より的確な咬合接触の付与が可能です。
導入による臨床的メリット
FGPテクニックの導入による最大の臨床的メリットは、患者様固有の下顎運動を反映した生理的な咬合面形態を再現できることです。
従来の平均値的な咬合面形態付与と異なり、個々の患者の機能運動に調和した理想的な咬合接触が実現可能となります。
このように精密な咬合面形態が得られることで、補綴物装着時の咬合調整時間が大幅に短縮されます。
特に多数歯補綴では、チェアタイムの効率化による患者負担の軽減にもつながることが予想できるのです。
長期的な補綴物の安定性においても、FGPテクニックは優れた効果を発揮します。
機能的な咬合接触により、補綴物への過度な応力集中が防止され、破折や脱離などのトラブルリスクの提言が可能となるでしょう。
結果として、咀嚼効率の向上や違和感の少ない装着感覚により、患者満足度の向上が期待できます。
補綴物の長期的な予後の安定性は、患者との信頼関係構築にも寄与します。
実践的テクニック

実践的なテクニックに移ります。
ここからは以下の内容を学んでいきましょう。
・必要な材料と器具
・ステップバイステップの手順
それぞれ詳しく解説します。
必要な材料と器具
FGPテクニックの実施には、専用のFGPトレーが必要不可欠です。
このトレーは、機能運動を正確に記録できるよう設計された特殊な形状を持ち、対象歯の咬合面を確実に採得できる構造となっています。
記録材としては、温度による変形が少なく、正確な記録が可能なワックスや、硬化時の寸法安定性に優れたレジンを選択します。
咬合器は、半調節性以上のものを使用し、適切な顆路角の設定が可能なものを準備しましょう。
ステップバイステップの手順
FGPテクニックの手順は、まず作業模型を咬合器に装着し、既存の補綴物や対合歯との関係を確認することから始まります。
次に、FGPトレーに記録材を適量填入し、患者の機能運動(前方・側方運動)を記録しましょう。
得られた陰型から、咬合面形態を読み取り、補綴物製作に反映させます。
技工操作では、この陰型を参考に咬合面形態を形成し、FGPトレーで採得した動的な下顎運動路に調和した補綴物を製作していきます。
臨床での注意点

以下は臨床での注意点です。
教科書や文献上には記載がないイレギュラーが起こるのが臨床現場ですので、この点は把握しておきましょう。
精度に影響を与える要因
FGPテクニックの精度は、患者の理解と協力が大きく影響します。
術者は患者様に対して、必要な顎運動の範囲や速度を明確に説明し、実際の運動を練習させることが重要です。特に側方運動時の誘導には注意が必要です。
記録材の選択においては、患者様の顎運動の特徴を考慮する必要があります。
大きな側方運動を伴う症例では変形抵抗の強い記録材を、繊細な動きを記録する場合は流動性の高い記録材を選択しましょう。
また、記録材の温度管理は精度を左右する重要な要因となります。
特にワックスを使用する場合は、適切な軟化温度の維持と、硬化までの作業時間の管理が不可欠です。
急激な温度変化は記録材の変形を招く可能性があります。
トラブルシューティング
FGPテクニックにおけるトラブルへの対応として、まず記録材の変形・破損に関しては、採得直後の取り扱いに特に注意が必要です。
変形が生じた場合は、同じ条件下で再度採得を行い、複数回の記録を比較検証することが推奨されます。
再現性が低い場合は、患者の顎運動の安定性を再評価する必要があります。
必要に応じて筋弛緩法や運動訓練を行い、安定した下顎位が得られてから再度記録を行います。
顎機能障害を有する患者では、負担の少ない範囲で段階的に記録を行うことが重要です。
過度な顎運動は症状を悪化させる可能性があるため、患者の状態を慎重に観察しながら、必要に応じて治療計画の変更を検討します。
長期的展望と発展性

ここでは前述した治療を行ったうえでの長期的展望と、FGPクリニックの発展性について触れていきます。是非参考にしてください。
デジタル技術との統合
FGPテクニックとデジタル技術の統合は、補綴治療の精度と効率性をさらに向上させる可能性を持っています。
従来のアナログ的なFGP記録を、最新のCAD/CAMシステムに活用する手法が開発されつつあります。
具体的には、FGPテクニックで得られた機能運動の記録を、3Dスキャナーでデジタル化し、CADソフトウェア上で補綴物設計に反映させることが可能です。
これにより、患者固有の下顎運動データをデジタルワークフローに組み込むことができます。
デジタルスキャンとの併用では、口腔内スキャナーで得られた3次元データと、FGPテクニックによる機能運動記録を統合することで、より精密な補綴物設計が実現可能です。
特に、咬合接触点の位置や接触圧の分散を、デジタル上でシミュレーションできる利点があります。
このようなデジタル技術との統合により、FGPテクニックの精度向上と作業効率の改善が期待でき、より確実な補綴治療の実現につながっています。
臨床評価とエビデンス
FGPテクニックの長期予後に関する研究データでは、従来の咬合採得法と比較して、補綴物の生存率や患者満足度が高いことが報告されています。
特に臼歯部における咬合の安定性と、補綴物の破折・脱離の発生率の低さが注目されています。
多数の症例報告からは、特にインプラント上部構造やブリッジにおいて、天然歯との調和のとれた咬合接触が得られやすく、長期的な予後が良好に続くとされています。
また、顎機能障害を有する患者への応用でも、症状の改善に寄与する可能性が高まりつつあるのです。
今後の技術的展開としては、デジタルワークフローとの融合による精度向上や、AI技術を活用した咬合分析システムの開発など、さらなる発展が期待されています。
まとめ
FGPテクニックは、患者固有の下顎運動を正確に記録し、生理的な咬合面形態を再現できる有用な手法です。
特に臼歯部の補綴治療やインプラント上部構造において、長期的な安定性と高い患者満足度が期待できます。
導入時は、適切な器材の選択と正確な手技の習得が不可欠です。
また、患者の協力度や顎機能の状態を適切に評価し、症例に応じた対応が必要となります。
記録材の温度管理や作業時間にも十分な注意が必要です。
臨床実践においては、デジタル技術との統合による精度向上も視野に入れつつ、基本的な術式の確実な実施を心がけることが重要です。
継続的な症例の蓄積と評価を通じて、さらなる技術向上を目指すことが推奨されるでしょう。
参考文献:機能的に最適な臼歯部の歯冠修復方法を考える
編集・執筆
歯科専門ライター 萩原 すう
歯科医療の現場で役立つ実践的な知識を届けるORTC

ORTCは「笑顔の役に立つ」を理念に、歯科界の知識を共有する場を目指しています。歯科医療の現場で役立つ最新の知識と技術を提供することで、臨床と経営の両面からクリニックの成長を支援します。最先端の技術解説や経営戦略に特化した情報を集約し、歯科医療の現場での成果を最大化。自己成長を追求するためのコンテンツをぜひご活用ください。
無料会員登録
無料動画の視聴、有料動画のレンタルが可能です。歯科業界についてのオンライン・オフラインセミナーへの参加が可能となります。
ORTCPRIME
月額5500円で、 ORTC内のすべての動画を見放題に。臨床の現場に役立つ最新の技術解説や、歯科医院経営の成功戦略を網羅した特別コンテンツをご利用いただけます。 歯科業界の方へ効率的に知識を深めていただける内容です。
ORTC動画一覧
ORTCセミナー一覧
まずは無料会員登録
こちらのリンクより会員登録ページへお進みください。
会員登録はこちら
ORTCPRIMEへのアップグレードも簡単!
登録後は「マイページ」から、ORTCPRIMEにいつでもアップグレード可能です。
 こちらの動画もおすすめです
こちらの動画もおすすめです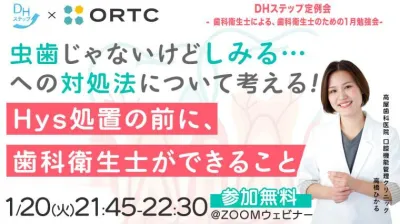 虫歯じゃないけどしみる…への対処法について考える Hys処置の前に、歯科衛生士ができること
虫歯じゃないけどしみる…への対処法について考える Hys処置の前に、歯科衛生士ができること 「TBIが変われば患者が変わる」 自費TBI成功マインド
「TBIが変われば患者が変わる」 自費TBI成功マインド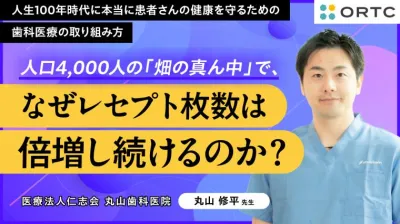 人口4,000人の「畑の真ん中」で、なぜレセプト枚数は倍増し続けるのか?
人口4,000人の「畑の真ん中」で、なぜレセプト枚数は倍増し続けるのか?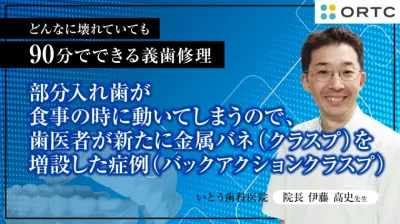 部分入れ歯が食事の時に動いてしまうので、歯医者が新たに金属バネ(クラスプ)を増設した症例(バックアクションクラスプ)
部分入れ歯が食事の時に動いてしまうので、歯医者が新たに金属バネ(クラスプ)を増設した症例(バックアクションクラスプ)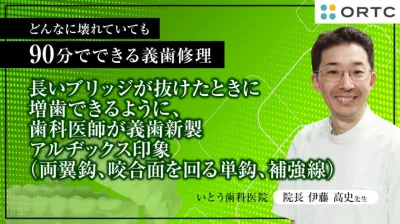 長いブリッジが抜けたときに増歯できるように、歯科医師が義歯新製 アルヂックス印象(両翼鈎、咬合面を回る単鈎、補強線)
長いブリッジが抜けたときに増歯できるように、歯科医師が義歯新製 アルヂックス印象(両翼鈎、咬合面を回る単鈎、補強線)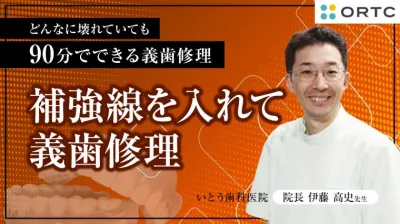 補強線を入れて義歯修理
補強線を入れて義歯修理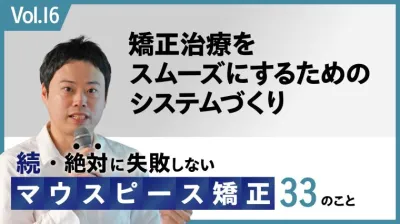 続・ 絶対に失敗しないMP矯正33の事 システムづくり
続・ 絶対に失敗しないMP矯正33の事 システムづくり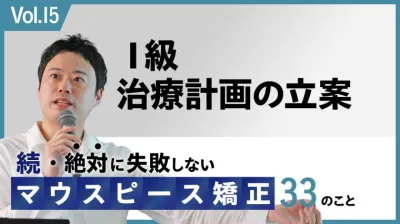 続・ 絶対に失敗しないMP矯正33の事 Ⅰ級 治療計画の立案
続・ 絶対に失敗しないMP矯正33の事 Ⅰ級 治療計画の立案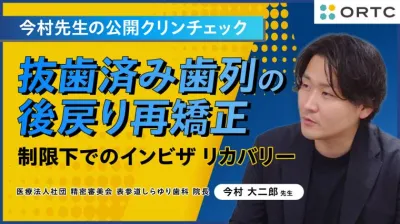 抜歯済み歯列の後戻り再矯正:制限下でのインビザ リカバリー
抜歯済み歯列の後戻り再矯正:制限下でのインビザ リカバリー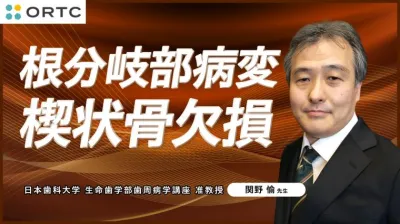 根分岐部病変 楔状骨欠損
根分岐部病変 楔状骨欠損